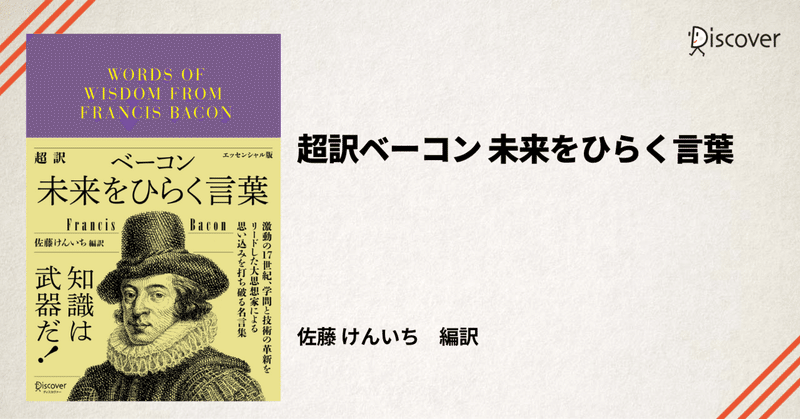
【「はじめに」公開】佐藤けんいち 編訳『超訳ベーコン 未来をひらく言葉』
10月発売の佐藤けんいち 編訳『超訳ベーコン 未来をひらく言葉』。
本書は、「知は力なり」というフレーズが有名で、学問と技術の革新をリードした大思想家フランシス・ベーコンによる思い込みを打ち破る名言集。
このnoteでは、本書の「はじめに」をご紹介します。
はじめに
なぜいまフランシス・ベーコンなのか?
フランシス・ベーコンといえば、「知は力なり」というフレーズで有名な哲学者で、実験と観察による「帰納法」を主張した「イギリス経験主義」の祖というのが、教科書的な理解であろう。一世代下のフランスの哲学者デカルトとならんで、「17世紀科学革命」を語る際にはかならず引き合いに出される、きわめて大きな存在である。
ベーコンの名句は、英語圏では引用されることが多い。英国を中心とした英語圏では現在でもよく知られた存在だ。2026年は、ベーコン没後400年になる。
ところが、現在の日本では、どうも一般には忘れられた存在となってしまっているようだ。夏目漱石の青春小説『三四郎』(1908年)の冒頭には、東京帝大文科に合格した主人公の三四郎(当時23 歳)が、「読んでも解らないベーコンの論文集」を英語で読むシーンがある。九州から上京する際の汽車のなかという設定だが、現代小説ではそんなシーンは考えにくい。ちなみに、「ベーコンの論文集」とは、日本では『随想集』と訳されてきた『エッセイズ』のことを指しているようだ。
ベーコンの主要著作は日本語訳されていて、文庫でも入手可能だが(といっても品切れになっていることが多い)、三四郎にとってもそうであったように、正直いって読みにくい。たしかに、『エッセイズ』に収録された文章は、嚙みしめれば味が出るが、嚙みしめなければ味わえないのでは、多忙な現代人をベーコンから遠ざけてしまうのは無理もないだろう。
だが、それではあまりにも、もったいないのではないか? 激動期の現在だからこそ、おなじように激動の時代を生きたベーコンの「人生訓」にあらためて注目する必要があるのではないか? 今回ベーコンを「超訳シリーズ」の一冊として取り上げることになったのは、そんな問題意識が背景にある。
二人のベーコン 哲学者と政治家の「二刀流」を生き抜いた賢人
フランシス・ベーコンをネット検索すると、たいへん紛らわしいことに、同姓同名のフランシス・ベーコンがでてくる。20世紀を代表する画家の一人である。美術愛好家なら、哲学者よりもアーティストのほうが真っ先に想起されることだろう。
じつは20世紀の画家フランシス・ベーコンは、17世紀の哲学者フランシス・ベーコンの一族の出身である。あえて区別すれば、17世紀のベーコンは、「サー」のつく貴族であったことだ。サー・フランシス・ベーコン。ベーコン卿である。
二人のベーコンというテーマで、ここで注目したいのは、17世紀のフランシス・ベーコン自身が、哲学者と政治家という二つの顔をもっていたことだ。「哲学者ベーコン」と「政治家ベーコン」である。この「二人のベーコン」が、同一人物のなかでせめぎ合いながらも、密接不可分で一心同体として同居していたのだ。「知」と「力」はベーコンにおいて一体化していた。ベーコンは、理想を説いた哲学者だけでなく、現実世界のなかで生き抜いた政治家でもあったのだ。
ベーコンといえば、かならず引き合いに出される「知は力なり」というフレーズに注目してみよう。「知は力なり」(Knowledge is power)は、正確にいうと「知識は力である」となるが、「知」は哲学者ベーコン、「力」は政治家ベーコンを象徴していると考えることも可能だろう。力(パワー)は、物理的な力だけではない。人間の力量でもあり、また政治的な権力も意味している。人間の知識と人間の力が一体となることではじめて意味をもつと、主著『ノーヴム・オルガヌム』で主張している。
まずは、比較的知られている「知」(ナレッジ)の側面、すなわち哲学者としての側面から見ていくことにしよう。
「17世紀科学革命」のプロモーターとして
ベーコンは、「17世紀科学革命」を推進した一人とされている。
16世紀から17世紀にかけては、地球規模の大転換期であった。「第1次グローバリゼーション」が引き起こした地球規模の大激動によって、西欧社会は中世ルネサンスから近世へと移行、この時代に21世紀の現在につながる「近代科学」が誕生したのである。別の言い方をすれば、この時代は「魔術から科学」への過渡期でもあった。
「17世紀科学革命」を推進した人物は、ベーコン、デカルト、ガリレオ、ニュートンの4人の知の巨人たちに集約することが可能だ。ガリレオがイタリアで進めていた天文学と力学における革命、ガリレオと同時代に生きた英国人ベーコンが提起した問題意識、それを前提にしたフランス人デカルトの数学方法論が結合し、英国人ニュートンの「万有引力の法則」において完成したのである。
ただし、ここにあげた4人のうち、ベーコンだけが、狭い意味での科学者ではない。
ベーコンは、実験と観察による科学の重要性を説き、帰納法による推論を主張したが、科学者ではなく技術者でもなかった。また、数学の重要性は説いたものの、みずから数学を駆使して天文学や力学などを推進したわけではない。あくまでも科学革命への道を準備し、プロモートした先駆者的役割にある。
ベーコンが、現在の日本であまり取り上げられることがないのも、そこに理由の一つがあるのだろう。ただし、ベーコンはデカルトやニュートンとは異なり、科学や技術のもつ正負の二面性に気がついていたことが重要だ。
「大学衰退の時代」の「新しい知」の担い手として
激動期にある21世紀の現在、大学はすでに新たな知を生み出す中心ではなくなっている。16世紀から17世紀にかけての西欧もまた、状況は似たようなものであった。
中世以来、西欧の大学で講義されていたのは、学術面では古代ギリシアの哲学者アリストテレスの体系であり、それが権威化され君臨しつづけていた。この状況は近世に入ってからも17世紀いっぱいつづいていたのである。そんな旧態依然とした状況に公然と〝NO〟をつきつけたのがベーコンであり、デカルトであった。
半自叙伝でもある『方法序説』(1637年)に書いているように、デカルトは既存の学問世界に見切りをつけ、放浪の旅のなか、数学専門家としてオランダ軍に入隊している。ある冬の日に自分が進むべき方向を直観的に確信したデカルトは、その後は在野の「独立研究者」として生涯を貫くことになる。
一世代上のベーコンもまた、ケンブリッジ大学には入学したが卒業はしていない。大学ではギリシア・ローマの古典的教養を身につけたが、アリストテレスの学説には強く反発、父親の教育方針でケンブリッジを中退して、激動のさなかにあったフランスで外交官のはしくれとして3年間を過ごしている。この実体験は大きな意味をもっているようだ。(ベーコンの生涯については巻末の「ベーコン年譜」を参照)。
父親の急死が理由となって帰国、その後は政治家としてキャリアを構築すべく、法学院で実学としての法律学を勉強している。このほかスキマ時間を利用して、独学でさまざまな学問を習得したベーコンは、法律学をベースに政治家として自己実現しただけでなく、哲学における「大革新」を志し、多方面にわたってマルチな才能を発揮したのである。だが、生涯をつうじて大学人ではなかった。
変化のスピードが速く、あっという間に技術も学問も陳腐化してしまう21世紀現在の状況では、「独学者」であったベーコンに学ぶべきものは少なくないのではないだろうか。しかも、それは「教養」の裏付けをともなったものであり、豊富な実体験から「帰納」した「経験主義的」なものであったことを強調しておくべきだろう。
ベーコンの「知の体系」は21世紀の現在につながっている
「人間の、人間による、人間のための国」。これこそが、ベーコンの理想であり、自然の解明もそのためになされるべきだと主張したのであった。人類全体が視野に入っていたのである。
狭い意味の科学者ではなかったが、ベーコンが強調した技術重視の科学は、遺著『ニュー・アトランティス』(1627年)でその構想が示されており、死後の1660年には実質的な英国の学士院である「ロンドン王立協会」(ロイヤル・ソサエティ)として結実している。産業科学志向は、18世紀後半の英国で始まった「産業革命」につながっていく。
18世紀フランスにおいては、とくに思想家ディドロがベーコンの心酔者であった。ベーコンが17世紀初頭の「学問の現在地」を見える化したものが『学問の進歩』(1605年)であるが、ディドロなど「百科全書派」は、ベーコンが体系化した「学問分類」をさらに精緻化し、その成果を膨大な『百科全書』に結実させている。
当時の産業技術知識の集大成ともいうべき『百科全書』は、学問を一般社会に開放するうえで大きな役割を果たすことになった。
「革命の世紀である18世紀は、なによりもベーコンの世紀なのである」(エウジェニオ・ガレン、澤井繁男訳『ルネサンス文化史』、平凡社ライブラリー、2011)という評価もある。だが、19世紀以降の近代においては、ベーコンの影響力は小さくなっていく。ディドロの同時代人であったフランスの哲学者ヴォルテールが『哲学書簡』(1734年)で辛辣に指摘しているように、「あたらしい哲学にとっての足場」となった『ノーヴム・オルガヌム』(1620年)に代表されるベーコン哲学は、乗り越えられたとみなされたからであろう。
とはいえ、世界中の「知識」を収集して「一元化」し、インターネット上に公開することで、誰もが検索でアクセスできるようにしたグーグルやウィキペディアなどの試みは、ベーコンが切り拓き、『百科全書』が推進した動きの延長線上にあるという言い方も可能だろう。ふだんは意識することなどまずないだろうが、21世紀の現在も、じつは4世紀前にベーコンが敷いたレールの上を走っているといっていいのである。現在つかわれている「図書分類」もまた、ベーコンの「学問分類」をベースに考案されたものだ。
「ナンバー2」まで上り詰めた「政治家ベーコン」
では、ここから先は、「二人のベーコン」のうち「政治家としてのベーコン」について見ておこう。ベーコンは自分の哲学上の理想を実現するためには、自分自身が政治家として影響力を行使できるポジションにつくことが重要だと考えていた。政府高官の息子として生まれ育ったことが、政治上のキャリア構築を目指す原点になっている。
ベーコンは、最終的に、イングランド国王ジェームズ1世のもと、もっとも重要な国王の補佐役として、実質的な「ナンバー2」のポジションまで上り詰めている。しかも、42歳から50歳代にかけての超多忙な時期に、集中的に哲学上の著作を執筆しているのは、公私ともに脂がのりきった時期だったからだろう。
ジェームズ1世(スコットランド国王をジェームズ6世として兼任)のスコットランド巡幸中の1617年には、1ヶ月にわたって「臨時摂政」として外国使節の接遇も行っている。1618年には顧問官としては最高位の大法官(ロード・チャンセラー)に任命され、また「サー」のつく貴族になっている。イングランドとスコットランドとの「ブリテン統合問題」などでも、知恵袋として大いに活躍している。
45年間もつづいたエリザベス女王の時代が終わり、王位継承にともなう環境変化にチャンスを見いだしたベーコンは、確実にゲットすることに成功したわけだ。いわゆる「二世政治家」だったベーコンだが、若き日に庇護者としての父親を失い、しかも財産もなかったため、出世の糸口を見つけるまでは、かなりの苦労を重ねている。
キャリアと人生を設計し、建設するという発想と実践である「運命の建築術」の実践が行われたのは、この時期のことだ。21世紀の現在でも、経営学者が書いた『「権力」を握る人の法則』(ジェフリー・フェファー、村井章子訳、日経ビジネス人文庫、2014年)のような本があるが、『君主論』のマキアヴェッリの後継者でもあるベーコンの説くところも、大いに説得力があるというべきだろう。
ベーコンにとっては、政治の世界におけるキャリア構築もまた「実験」であり、政治家ベーコンの「観察」から「帰納」された処世術は傾聴に値するものだ。政治に限らず、ビジネスでも非営利組織でも応用可能だろう。
専制君主の宮廷で生き抜いた政治家が発揮した処世術
ベーコンが仕えたジェームズ1世は、大陸流の「王権神授説」を唱えた専制君主であったが、権力よりも言論の力で統治することを試みた博識なインテリでもあった。近代英語の基礎をつくった源泉の一つとされる、『欽定訳聖書』(King JamesVersion、1611年)の編纂を命じて、実現させたのがこの国王である。だからこそ、ベーコンを重用したのであろう。また、ベーコンもよくそれに応えて『学問の進歩』(1605年)を英語で執筆し、国王に献呈している。
だが一方では、ジェームズ1世は、思い込みと猜疑心がつよく、偏執狂的性格がつよい人物でもあった。イングランドの国王を兼任する以前には、すでに『悪魔学』(デモノロジー、1597年)という著書も出しており、魔女の存在を信じて心底から恐れ、タバコの煙を極度に嫌っていた。そんな国王に、ベーコンは高官として仕えていたのである。
さらに、スコットランドからやって来た国王は、イングランドではあまり好まれていなかったこともあり、バラマキによって人心をつかもうと試みている。『消費社会の誕生 近世イギリスの新プロジェクト』(ちくま学芸文庫、2021年)の著者ジョオン・サースクのように、ジェームズ1世が統治した時代を「腐敗の時代」と表現する経済史家もいる。「腐敗の時代」は、エリザベス時代の「経済成長の時代」が生み出したものだ。
派手好みの宮廷生活で出費がかさみ財政難となっていたため、1618年から始まった大陸の「三十年戦争」に介入しなかったのは、結果としては賢明であった。だが、国王による経済的独占に対する反対論は国内で強かった。北米植民地は順調に成長していたが、1613年に始まった日本貿易は、オランダとの競争に敗れ去り、わずか10年で日本市場から撤退することを余儀なくされている。1614年から景気後退が始まり、17世紀のイングランドは「停滞の世紀」となった。
17世紀は全般的に寒冷期であり、ジェームズ1世の治世は厳しい不況(1620年〜1626年)で幕を閉じている。1625年にはロンドンで腺ペストが流行している。17世紀イングランドの時代精神は「メランコリー」(憂鬱)でもあった。
ちなみに、「血液循環説」を唱えて近代医学の父となったウィリアム・ハーヴィーは、ジェームズ1世の侍医であり、またベーコンのかかりつけ医でもあった。
絶頂からの転落 酸いも甘いも嚙み分けた人生
理想を説いた哲学者は、同時に権謀術数渦巻く宮廷政治を生き抜いた「中の人」でもあった。
まさに好事魔多しというべきか、「60歳の誕生日」を盛大に祝った絶頂期から1ヶ月もたたずに、天国から地獄にまっさかさまに転落することになる。1621年のことだ。政敵からの激しい攻撃にさらされていたベーコンだが、脇が甘かったというべきか、収賄容疑で糾弾され失脚し、4日間だけであったが投獄という屈辱を味わうことになったのだ。スケープゴートになったという説が有力だが、専制君主の宮廷においては、いつおこっても不思議ではない事態だったともいえるかもしれない。
ベーコンもまた、おなじく政治家であったが失脚した古代ローマのキケロやセネカにみずからをなぞらえて、晩年の5年間を著作活動に専念している。だが、キケロのように暗殺されたり、セネカのように自死を強いられずに済んだのは、ベーコンにとっては幸いだったというべきだろう。
これは余談であるが、ベーコンの人生は、日本でいえば、ちょうどベーコンの1世紀後に生きた儒者で政治家の新井白石(1657年〜1725年)と奇妙なまでによく似ている。「日本の百科全書家」(桑原武夫)という評もある白石だが、「60歳の還暦祝い」の2ヶ月後に失脚したのは、将軍の代替わりで八代将軍吉宗の治世になったためだ。白石もまたベーコンと同様、失脚後には著作活動に専念している。ベーコンにとっては5年間、白石にとっては9年間の晩年であった。
仕事が多忙であればあるほど、哲学に癒しを見いだす人もいる。『自省録』のローマ皇帝マルクス・アウレリウスがそうだった。「政治家ベーコン」にとっても、精神のバランスを保つうえでは、「哲学者ベーコン」としての学問研究が必要不可欠だったのだろう。仕事以外に熱中できるものがあったからこそ、政治的失脚という失意のなかにあっても、充実した晩年を過ごすことができたといえるのではないだろうか。
ベーコンは、雪をつかった鶏肉の冷凍保存実験中に悪寒を発し、気管支炎をこじらせて65歳で亡くなっている(1626年)。加工食品のベーコンが、ブタ肉の塩漬け燻製保存法であることを考えると(つづりはおなじbacon だ)、エピソードとして面白い。とはいえ、本人も死の床でみずからをなぞらえたように、ヴェスヴィオ山の噴火を観察中に亡くなった、『博物誌』の大プリニウスのような死を迎えることができたのは、実験と観察を重視した「哲学者ベーコン」としては本望だったかもしれない。
編集方針について
編集にあたっては、「政治家ベーコン」による人生訓と処世訓を中心に、「哲学者ベーコン」による学問論をあわせて全部で162編を選出した。あまりにも簡潔でわかりにくい場合はことばを補い、長い文章の場合は編集を加えて短縮してある。
全8章で構成しているが、時代を超えて現代でも通用する内容で、かつ基本的に実践的な処世術にかんするものを選び出した。
政府高官であったため、国家にかんする言及が少なくないが、営利と非営利を問わず、組織人ならある程度は体験するところではないかと思う。自分の立場に置き換えて読めば、納得いくものもあるのではないだろうか。
ルネサンス時代に生きたベーコンもまた、共和制から帝政移行期の古代ローマ史を「先行事例」として学んでいる。ベーコン流の解釈を通じたものではあるが、古代のギリシア人やローマ人の知恵を「教養」として学ぶことも本書で可能となるだろう。
Ⅲ章には「イドラ論」を含めた「哲学者ベーコン」の発言を収録した。やや理解しにくいかもしれないが、ベーコン自身が実際にどう発言しているかの参考にしていただけると幸いだ。「イドラ論」とは、現代では「認知バイアス」として知られているものだ。人間が人間である限り、そして人間がことばをつかう限り、先入観や固定観念といったバイアスから逃れることはできないのである。
400年前のベーコンには想像すらできなかっただろうが、デジタル時代の21 世紀の現在、「知識の量」を誇ることは、あまり意味はなくなっている。「知は力なり」ではあるが、むしろ「知識の質」を向上させることが重要だ。「再魔術化」が進んでいるとさえいわれる現代、陰謀論やフェイクニュースに足をすくわれないためにも、「魔術から科学へ」の過渡期を生きたベーコンの忠告には大いに耳を傾けたいものだ。
とはいえ、ベーコン自身による人生論や処世術も、もちろんバイアスを免れているわけではない。必ずしも同意しかねる発言も、なかにはあるだろう。このことを十分に意識して読み進めてほしいと思う。
「超訳シリーズ」の一冊として今回ベーコンをとりあげることになったのは、編集担当の藤田浩芳氏からの提案があったからだ。
昨年2020年12月に出版した拙著『世界史から読み解く「コロナ後」の現代』(ディスカヴァー携書)では、16世紀から17世紀にかけての大転換期を扱っている。
ベーコンについても、遺作となったユートピア小説『ニュー・アトランティス』について日本とのからみで言及している。そんな折りの藤田氏による提案は、まさに渡りに船であった。
ただし、その時点では、ベーコンの17 世紀英語が想像以上に難物であることは気がついておらず、訳出にあたっては、日本の真夏の猛暑もあいまっておおいに苦労させられることになった。このことは正直に告白しておきたい。ベーコンは、シェイクスピアの同時代人でもあった。
目次
はじめに なぜいまフランシス・ベーコンなのか?
I 成功の極意
001 チャンスを逃すな
002 変化を恐れるな
003 過去にとらわれるな
004 流れには逆らわないほうがいい 他
II 仕事の極意
021 もっとも重要なのは仕事が速いこと
022 議論を省略してはいけない
023 業務分担は細かくしすぎない
024 行動はスピードが勝負だ
025 成功事例にも失敗事例にも学べる
026 つねに代替案を用意する 他
III 知性を磨く極意
048 4つの思い込みに気をつけよ
049 思い込みその1
人間本性にねざした「種族のイドラ」
050 思い込みその2
経験がもたらす「洞窟のイドラ」
051 思い込みその3
ことばがもたらす「広場のイドラ」 他
IV 心を磨く極意
056 習慣だけが人間の本性を変えられる
057 自分の本性に合ったことをせよ
058 悪しき本性を克服する
059 悪しき本性を直すための段階 他
V 人とつきあう極意
087 傲慢でも卑屈でもいけない
088 秘密を守る人に秘密は集まる
089 礼儀は自然体がいい
090 礼儀正しくすれば相手もそうせざるを得なくなる 他
VI うまく立ち回る極意
117 相手の顔を読む
118 関係のない話題を持ち出す
119 重要なことほど付け足しのように見せる
120 不意打ちをかける 他
VII リーダーの極意
127 リーダーはみずから計画しチャンスを活かす
128 一人の人間を重用しない
129 アドバイスは喜んで受け入れる
130 アドバイスに耳を傾けよ
131 大胆な人物は指揮官には向かない 他
VIII 学びの極意
141 哲学や基礎研究があらゆる学問を育てる養分となる
142 学ぶとは自分の成長を実感すること
143 学問は実際に役立つ
144 学問は心の処方箋
145 歴史上の事例は実用性が高い 他
ベーコン年譜
ベーコンと同時代の人物たち
主要参考文献
著者
著者 フランシス・ベーコン (Francis Bacon)
イギリスの哲学者で政治家。「イギリス経験主義の祖」と称される。1561年、ロンドン郊外に生まれ、ケンブリッジ大学に学ぶ(中退)。1581年、下院議員に選出されて政界に入り、エリザベス1世の特別顧問官、ジェームズ1世の学識顧問官、枢密顧問官、国璽尚書、大法官等を歴任。その一方『学問の進歩』『エッセイズ』などの著書を執筆。60歳のとき収賄容疑で失脚、その後は著作に専念する。1626年、鶏肉の冷凍保存実験がもとで気管支炎にかかり、65歳で死去。
編訳者 佐藤けんいち
ケン・マネジメント代表。1962年京都府生まれ。一橋大学社会学部で歴史学を専攻、米国レンセラー工科大学(RPI)でMBAを取得(専攻は技術経営)。銀行系と広告代理店系のコンサル会社勤務を経て、中小機械メーカーで取締役経営企画室長、タイ王国では現地法人を立ち上げて代表をつとめた。編訳書に『超訳 自省録』『ガンディー 強く生きる言葉』(いずれも小社刊)がある。
***
どの言葉も、生活や仕事で大切にしたいと思うものばかりだった。その中で、「IV 心を磨く極意」にある嫉妬に関する言葉が印象的だ。ぼく自身も嫉妬の感情との付き合い方で苦しむときがある。
そんなときに「嫉妬は暇から生まれる」という言葉は、ハッと自分がいま集中すべきことは何であるかを再発見させてくれる刺激的なお守りになりそうだ。
読者のみなさまも、ぴったりな言葉がきっと見つかるはず!
ぜひ手にとってみてください。
(営業部 伊東)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
