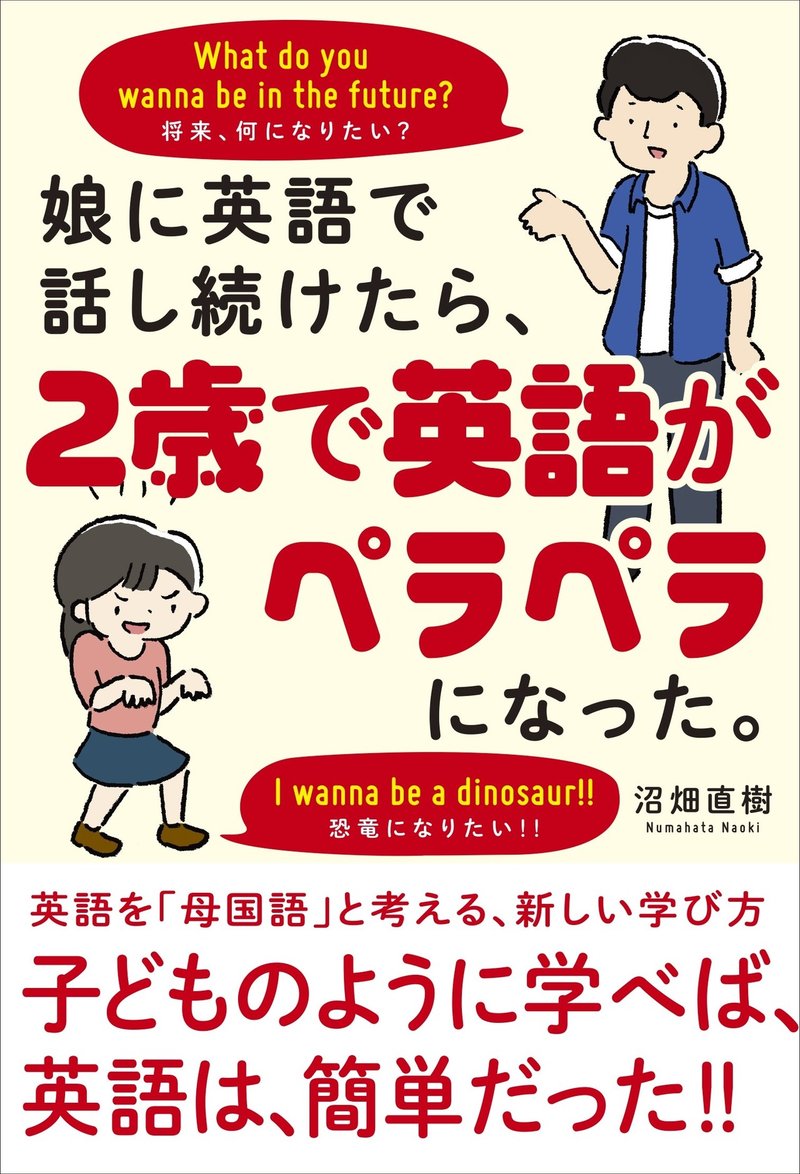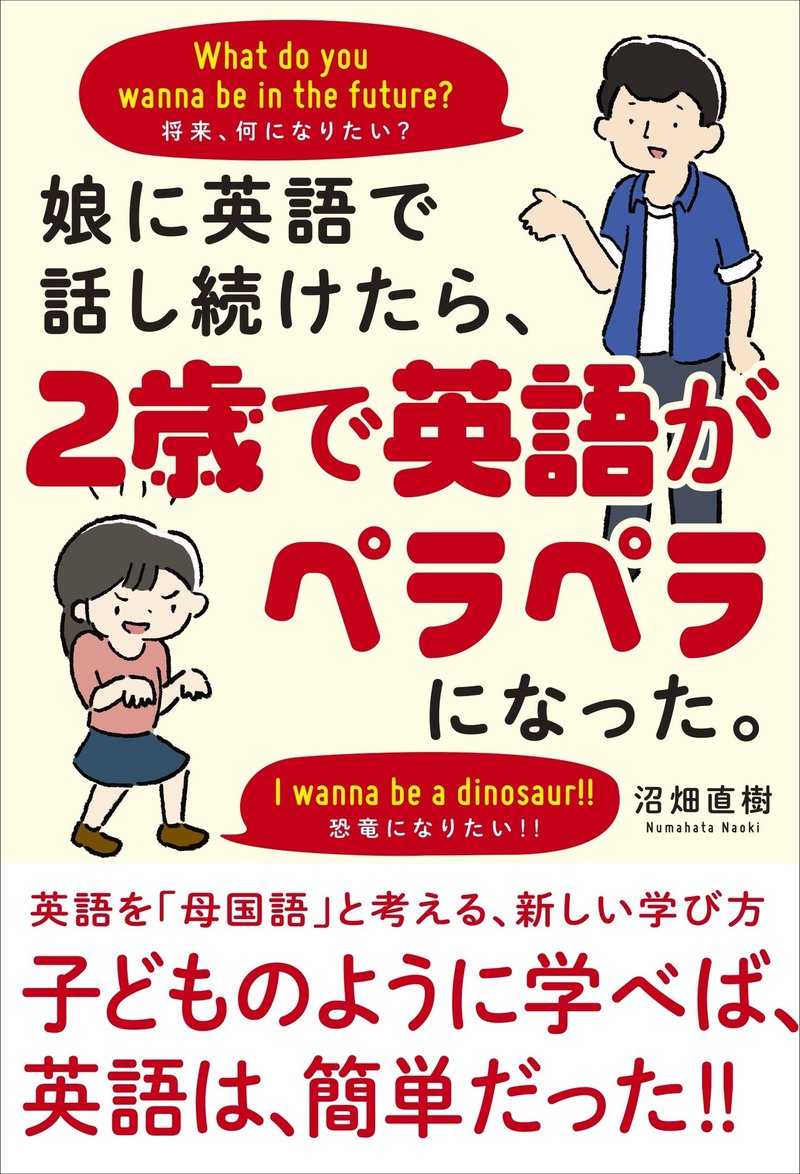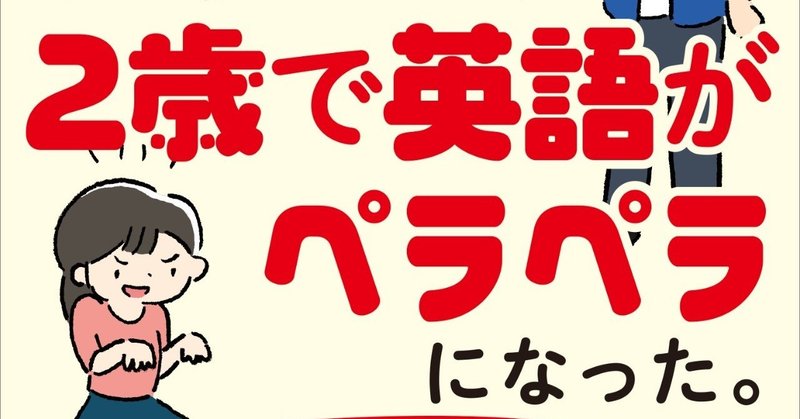
ただ聴くだけ!「何もしない」英会話勉強法のススメ
まだ暑かった昨年9月頭、『娘に英語で話し続けたら、2歳で英語がペラペラになった。』(著:沼畑直樹)の本文試し読みを公開しました。
好評につき、今回第2弾を公開できることになりました!
昨年のラグビーワールドカップ2019の時も、海外のサポーターさんたちで街が賑わっていました。
今年は東京2020オリンピック・パラリンピックが開催されます。
開会式までついに200日を切りました!
街や公共交通機関で、海外からのお客様に話しかけられる機会も増えると思います。
今から英会話を学び始めても遅いんじゃない?と思ったそこのあなた。
大丈夫、今から間に合う英会話メソッドを伝授しちゃいます!
ぜひこの書籍を通して、大人も子供も英会話習得の第一歩を踏み出しましょう!
第1弾の記事はこちら↓
本書の概要
1章では、母国語とは何か? ということについて解説します。
そして「母国語」として英語を学ぶことと、今までの英語学習法の違いについて説明します。
2章では、母国語の習得の秘密である、リスニングについて迫ります。
大人でも、子どものように聴き、子どものように言語を身につけられる方法に迫ります。
3章は、大人が英語を習得するときの実践法、スピーキング、発音のポイントについてです。日本にいながらにして、英語を使い続けるコツや、「母国語」英語を学ぶ心構えについて、そして日本人の盲点になりがちな発音のポイントについても記しています。
4章では、大人が英語を習得するときの実践法。こちらはリーディング、文法に関した内容です。英語の語順や、文法についてのシンプルな考え方を記しています。
5章では、私が子どもに英語を教えた、具体的な方法を紹介しています。
教えるうえでの10の方法や、気をつけるべき5つのポイントについて説明します。
6章では、娘が英語を覚えていった過程を記録した日記を公開します。これから子どもが生まれる人、これから子どもに英語を習得させたい親御さんの参考になればと思います。
巻末には、娘が3歳までによく使っていた英語、私が娘によく使っていた英会話をリスト化しています。英語が苦手な方でも、子どもに英語で話しかける際にお役に立てるかと思います。
***
2章 母国語の秘密は、リスニングにあり!
子どもはリスニングだけで話し始める
■ただ音だけを聴く子ども
「母国語とは何なのか」「なぜ日本人は英語を話せないのか」というテーマについて第1章で解明してきました。では、その母国語を習得するための、もっとも基本的なメソッドとは何でしょう?
これまで見てきたように、子どもはスペルや文法を知らなくても、母国語を「音」を通して覚えます。だから子どもにとっては、リーディングもライティングもなく、リスニングがすべてです。極端に言えば、英語は音だけ聴いていれば、話せるようになるのです。 しかし、条件があります。第1章でも触れたように、「その言語の勉強をしていないこと」が条件です。この部分が、音以外も勉強してきてしまった大人と子どもの決定的な違いを生みます。つまり音以外を排除した 「子どものようなリスニング法」 ができれば、大人も英語を母国語としてスムーズに習得できるのです。
■子どもは聴き取れない言葉を使う
たとえば子どもが母国語を学ぶときの動詞のイメージは、親の動きや、使っている状況から生まれてきます。娘はちょうど言語の爆発期の前に、やさしい英語のアニメドラマである『Peppa Pig(ペッパ・ピッグ)』を夢中になって見始めました。そこには、絵があり、動きがあり、音としての言葉があります。娘はそこからイメージとして音の使い方を捉えていったようです。日本人の親だけでは不足する部分を、アニメを通して補っていったのです。
アニメの中で、Abrakadabra, turn into a frog!
(アブラカタブラ〜、カエルになあれ!)
という台詞が出てきました。それを娘はまねをするのですが、アブラカタブラーの部分を、ユーキャントゥアゼィーブラー!と発音していて、私はてっきりアニメの台詞も、You can to a zebra!なのかと思いました。実際は大人なら知っている「アブラカタブラ」という単純なおまじないの言葉だったのですが、彼女なりに音を聴いて、You can to a zebra! と解釈したのです。間違ってはいますが、棒を振りながらその言葉を唱えたら、相手がカエルになるという状況を観て、「アブラカタブラー、ターンイントゥアフロッグ!」と言えばカエルになるのだ……と娘は推測し、そのイメージで使っていました。
これが大人だったらどうでしょう。映画を字幕なしで観て、たとえば「フィギュアリラウ」と音が聞こえたとしても、聴き間違っている可能性もあるし、そのままでは大人は自信がなくて使えません。正確なスペルがわからないので、辞書で調べることもできない。(Figure it out=理解する)
「自分にはそう聞こえたけど、きっと正確な発音は違うのだろう……」
そんな不安だらけの状況で、覚えていいはずがない。それが大人の心理です。
娘だって同じような状況なのに、どんどん覚えていく。そして的確に使うのです。考えてみると、娘のアプローチの仕方と大人のそれでは、根本的な違いがありました。
子どもは意味を、「想像」で覚える
■大人は辞書を使いたがる
リスニングをして、音は聴き取れたけど意味がわからなかった単語があったとします。そのときの心情はどういうものになるでしょうか?
きっとほとんどの人が辞書で調べたいと思うはずです。ですが辞書で調べることには「キリがない」と思います。リスニングするたびに辞書で調べるのは、面倒だし時間がかかります。母国語としてナチュラルに英語を聴いているシチュエーションは、勉強などではなく、ただ楽しんで聴いているだけなのです。
それは日常生活の一部として存在しています。大人は日本語訳の答えという最短距離を求めるので、辞書を使いたくなります。でも、2歳の子どもは辞書を使えません。つまり、子どもが単語を学ぶときには「想像する」しかないのです。
■想像で覚えるのは、自然なこと
大人も日本語訳を求めるよりもすべて想像力で勝負するくらいの心構えでいるべきです。前に述べたように、想像力で使い続けることが、柔軟性を生みます。もちろんときどき勘違いは起こりますが、そのほうが話せるようになります。
こんなことがありました。
娘はアニメでJoke(ジョーク)という言葉を聴いて、大喜びでI'm joking.(ジョークを言ったよ)と何度も言っていました。状況としてはただふざけているだけだったので、
I'm kidding.(ふざけているよ)
なのですが、
私がそう言ってもお構いなしにふざけてはI'm joking.と言い続けて大笑いしていました。アニメのキャラクターの行動を見て、ジョークを言っているところが「ふざけている」行動に見えたのでしょう。
大人なら「間違えて覚えてしまっている」と思うところですが、子どもが母国語を覚える過程では自然のことなのです。
■辞書を使うのは、もっと後でいい
わからない単語の意味を「辞書を使わず、想像する」というのは、今までの英語学習と正反対の行為です。だから抵抗があるかもしれません。ですが、これは後述するように、リーディングでも、この心構えでスピードはぐっと増します。読み飛ばしてしまうのではなく、あくまで意味を想像し続けるのです。
想像力を中心に理解していけば、スピーキングでも想像した意味で勝負することができます。大人は答えがないまま前に進むのは苦しいかもしれません。でも、2歳、3歳の子どもはそれでもどんどん前に進んでいきます。辞書を使うのはもっともっと後でいいのです。
■こんなふうに意味を想像しよう
1つの英文を聞いて、わからない単語の意味を想像するのは当然難しいです。ただ、その単語がまた出てくるのを繰り返すうちに、想像の精度があがり、推測ができるようになっていきます。
たとえば、捕鯨反対のニュースを英語で聞いていたとします。
「アブスラクリブ アクティヴィリィ」という言葉が聞こえたけれども、activities(活動)はわかっても、アブスラクリブの部分の意味がわからない。
ニュースを続けて聞いていくと、
「ストップ アブストラクティング ジャパニーズ〜」という言葉で再び聞こえてきました。
映像から捕鯨反対についての内容だとヒントがあると、ここで「アブスラクリブ、アブストラクティング=反対、抗議、妨害」あたりがぼんやりと想像されます。
このとき浮かんだ、この3つのイメージ以上の意味を詳しく詮索しないことです。 イメージをイメージのまま、大事に記憶することが母国語英語です。
アブスラクリブ アクティヴィリィ
=Obstructive activities
ストップ アブストラクティング ジャパニーズ〜
=Stop obstructing Japanese〜
■想像で覚えた単語のほうが「話せる」
このように、Obstructという言葉を辞書を引かず、
「反対、抗議、妨害」あたりでぼんやりと意味を覚えていたとします。その場合、「反対するぞ」と言いたくなったときに、I will obstruct you! と言えそうです。Obstructは厳密に言うと「妨害するぞ」になりますが、言いたいことはまずこれで通じるのです。
これをネイティブに話すと「ずいぶん攻撃的だな」と捉えられるので、後述するように母国語として英語を学んでいる2、3年はネイティブと話さないほうがいいかもしれません。子どもの言い方が間違っていると親は「かわいい」と言って笑ってくれますが、大人がネイティブに笑われると、間違った側は赤面し、ショック状態になったりします。留学中にそうして自信を失った人がたくさんいるはずです。
それでも、辞書を使ってひとつだけの意味を覚えるより、英語の意味をぼんやりとしたイメージで想像して、たくさん間違え、たくさん勘違いしながらも、より多様なシチュエーションで勝手に使い倒したほうが、英語が反射的に出てくるようになるのです。
「リスニング」は答え合わせじゃない
■自分が知らない単語を聴く
私が子ども向け英語アニメである『ペッパ・ピッグ』を娘と一緒に見始めたとき、自分が知っている英語を「聴き取りたい」と思いました。「知っている英語が聴き取れたら、娘に教えてやろう」という気分でした。それは英語の映画を観ていても、英語のニュースを観ていても同じ。
自分がスペルで知っている英語を聴き取れるかどうか、スペルと音の答え合わせのテストのようなものだったのです。
リスニングに関する私のヒストリーは、
(1) 字幕を観ながら、音を聴く
(2) 字幕を観ないで、音を聴く(字幕を読んでいると聴き取りがうまくできないから)
(3) 日本語に翻訳しない(翻訳しながら聴くと追いつかないから)
(4) 単語ひとつひとつを丁寧に聴いていく
こんな感じでした。
「翻訳しない」というのは以前にも意識するテーマではありましたが、言葉ひとつひとつを正確にひろっていきたいともいつも思っていて、やはり「聴き取れた!」という歓びを得るために英語を聴いていたような感覚がありました。
■聞こえた音を、そのまま使ってみる
でも、知っている英語ではなく「知らない英語はどれだ」という気分で聴くと、聴こえ方はまったく変わります。そして 「今聴こえた知らない言葉を、今度そのまま使ってみよう」という姿勢です。何か言ったその音を辞書で調べたり、スペルを知ろうとせず、そのまま使う。間違っているかもしれないけど、使うのです。私はこの方法で劇的に聴き取りが変わりました。
それを、「聴き取れない言葉こそを探し、今度使ってやろう」という気持ちで聴くことで、素直に次の音に集中できるようになりました。
ところで、ある日アメリカの旅番組の食事シーンを観ていて、そばにいた娘がGnocchi(ニョッキ)を聴き取って発音を楽しんでいました。大人向けの速く、連続する英語の渦の中で、食べ物の名前をしっかり聴き取っているのです。
子ども用アニメの英語も、大人向けの英語も、発音している基本部分は同じ。It isだとか、I thinkだとか、there was、can、to、for、withなど、名詞以外の部分は同じ単語の繰り返しで、その上に多くの名詞や形容詞が登場しているだけ。
だから、英語を聴いていて、自分が知らない名詞や形容詞などの単語がわかるのです。
そして子どもは「聴き取れなかった……」ではなく、「○○って何?」と言います。○○は子どもなりに聴いたままの音です。そうして、知らない言葉も覚えていきます。
娘は名詞も大好きなアニメから覚えていることが多いです。あるとき和食料亭の庭に竹があったので「バンブーって知ってる?」と英語で訊ねると、「知ってるよ。バンブーでしょ、『ペッパ・ピッグ』の」と英語で言っていました。
大人が子どものように「聴く」ためには?
■リスニングで混乱するのはなぜ?
ネイティブの日常会話や子ども用アニメの音は聴き取れるようになったとします。でも難しいニュースだと突然聴き取れなくなる……という場合もあると思います。まず、リスニングで混乱するパターンを見てみます。
(1) 文・単語を聴く→意味がわからない→考えてしまう時間がある→次の言葉が聴き取れなくなる
(2) 文・単語を聴く→意味がわかるけど、日本語に訳すのに時間がかかる→次の言葉が聴き取れない
これを繰り返すと、早口で進むニュースにどんどん遅れが出てきます。結果キャスターが何を言っているのかさっぱりわからないという状況になってしまいます。
この状況を打破するには、どうしたらいいでしょう? それは 「理解していようがいまいが、次の言葉を集中して聴く」という方法しかありません。
「次の言葉に集中する」ということだけならば、先ほどの「聴き取れない言葉こそを探し、今度使ってやろう」という方法が有効です。でも、ニュースのように聴き取れない言葉だらけのときは、言葉の渦に呑み込まれてしまうかもしれません。もっといい方法はないのでしょうか?
■シャドウイングにも欠点がある
たとえば、シャドウイングは有効です。相手が話した直後から、それを口に出してまねていく方法です。そのとき意味はまったく考えず、ただ音をまねて、声に出すようにします。しかしシャドウイングにも欠点があります。自分で声を出すので、次の言葉が聴き取りにくくなってしまいます。それに、子どももシャドウイングをして母国語を覚えるわけではありません。
では、どうしたらもっと子どもが母国語を覚えるのに近い方法で、大人もリスニングができるようになるでしょうか?
母国語習得の謎を解く
■子どもは口に出して覚えない?
子どもが母国語を覚える方法を考えたときに、まず疑問に思ったことがあります。娘は実際に口に出して練習してから、話せるようになったわけではないということです。
たとえば娘は英語のアニメから多くの単語や言い回しを学びましたが、そのアニメを観ているときは、じっと黙っているか、ケラケラ笑っているだけです。決して、聴いた言葉を口にして練習したりしません。でも、アニメに出てきた言葉はそのうち口に出して使い出します。
■練習せずに歌い始めた娘
こんなこともありました。ある日、難しい英語の曲を突然歌い出したのです。[日記]でも書いていますが、半年以上前に聴いていただけの『アナと雪の女王』曲を練習することなく急に、歌い始めたのです。これは一体どういう現象なのでしょう?
この曲以外にも、『Sofia the First(ちいさなプリンセスソフィア)』というアニメの劇中歌を突然歌い出したことがありました。娘がずっと前に聴いていたときには、練習していたわけでもなく、その後はしばらく聴いてさえいませんでした。それなのに、ある日突然歌い始めたのです。一体、いつ声に出して練習をしたというのでしょうか?
これは、親の赴任で海外の小学校に入った子どもが、しばらく黙っていたのに、突然現地の言葉を話し始めるという現象に似ていると思います。大人は何度も声に出して練習をするのに、子どもは黙っている期間を経て、急にペラペラと話し始めるのです。
■大人が英語を学べる唯一の秘訣!
一体なぜ、こんなことができるようになるのでしょう?
私が考えた仮説は、子どもは話すようになる前、ずっと「自分が話すように聴いている」 のではないかということです。
これは私がたどり着いた母国語習得のカギであり、大人も母国語のように英語を学ぶことができる、唯一の秘訣だと考えています。
大人が英語を学ぶ秘訣「自分が話すように聴く」とは?
■母国語とミラーニューロン
人間の脳にはミラーニューロン(共感ニューロン)という仕組みがあります。ミラーニューロンは相手の痛みや辛さを感じ取るもので、ものまねの能力にも関わっています。
相手がしていることを、自分がしていることのように感じるミラーニューロン、それにはこんなものまね能力があります。
大人の我々も、ドラマを観て感動したとき、主人公に感情移入し、自分のことのように涙を流しますが、それがミラーニューロンのものまね能力です。
これが母国語習得の基礎になっているのではないかと、私は考えています。子どもが話せるようになる前、まわりの人が話す様子を見て、ミラーニューロンをフル活動させ 「自分が話すように聴いている」 のではないかと。
■ものまねというインプット&アウトプット
現に、娘はアニメに出てくるキャラクターをものまねするかのように、まったく同じ声質・口調で話します。相手が話すことを、自分が話すように聴くということは、心の中で話すように相手の声を聴いているということです。こんなふうにものまねというインプットとアウトプットを続けた言葉が、ある日突然、口から出てくるのではないでしょうか。
先に挙げた歌も同じで、一見声に出して練習はしていないようだけれども、心の中でものまねするように何度も歌っていたために、覚えてしまっていたのです。
聴きながら同時にものまねをすることで、英語を母国語として身につけることができるのです。
「話すように聴く」メリットは?
ポイント① まねをして集中力、記憶力もアップする
まず、自分が話しているかのように、相手の発する言葉を頭の中で発することで、次の言葉に対する集中力が高まります。普段、英語を聴くという作業は、聴き流している状態に近いと思います。BGMのようなものです。わからない音や単語に対して、積極的になれないからです。
これを、「自分が話すように、相手のまねをするのだ」という心理状況で聴き取ることで、すべての音を素直に聴いて、覚えていく作業へと変わります。
これは「聴き取れない言葉こそを探し、今度使ってやろう」という方法に加えて、ミラーニューロンを刺激することで「覚える作業」をし、同時に「話す練習」までもしていることになります。
ポイント② ネイティブのタイミングやリズムが学べる
ニュースを聴いていたとして相手の発している「音」がだいたい把握できたとしても、意味がわからない、という状況はしばらく続くと思います。しかし、それでも「話すように聴く」を続けることが、英語力の向上になります。まず、英語を話すネイティブのタイミングやリズムを、身をもって学ぶことができます。次に、知らない単語の音を聴き取れるようになっていきます。
ポイント③ 「聴き取れない」という問題自体がなくなる
意味のわからない単語が「わかる」ので、スペルや辞書からではなく、生の音から単語の意味を想像できることになります。これは母国語の習得法と同じ現場主義で、辞書や例文のCDから聴くのではなく、実際に今話されている現場から聴き取るものなので、非常に強力です。
もし英語をスペルではなく、実際に話されている音から覚えたのであれば、そもそも 「聴き取れない」という問題自体が生まれないはずです。 私たちはスペルを通して言葉を覚え、スペルと音の答え合わせのようにリスニングをしているから「聴き取る」という行為をし、「聴き取れない」という問題が起こるのです。
娘は多くの言葉を、父親である私が発する音と、アニメで初めて聴き、覚えました。だからアニメや私が話している英語が聴き取れない、なんてことは当然起こりません。
ポイント④ 子どもと同じように学べる
「話すように聴く」ことですべての単語を一語一語しっかり聴き取る。スペルではなく、聴き取ったまま単語を音で覚えれば、次に別のニュースで出てきても同じ単語だとわかるでしょう。
音が聴き取れるだけで、スペルがわからなくても、気にしないでください。むしろ、スペルがわかった途端、発音がスペルに引きずられて、矯正されてしまうかもしれません。
そうして英語の会話をずっと聴いていると、意味がわかるものもあれば、わからないものもあります。それでも音は聴こえているし、毎日繰り返しているうちに進化していきます。自分が言葉を出さなくても、相手の顔を見ながら、頭の中でまねをしていると、どんどん自分が話しているような感覚になっていきます。
そしてそれが、そのうち口から出てくるようになります。ここでは、子どもが「母国語」を話すようになるのと、同じ道を辿っているのです。 この方法を続けることができたら、子どもと同じようにあなたも英語を母国語として習得できるでしょう。
ポイント⑤ 英語で感情移入できる
やがて面白い感情の変化も感じることができるかもしれません。たとえば私の場合、今までアメリカのニュースを聴いていたときとは、「話すように聴く」ようになってから、大きな感情的な違いを感じています。
私たちは日本語のニュースを聴くとき、大きな共感を持って聴いています。酷いニュースには心を痛め、嬉しいニュースは歓びとともに聴いています。アメリカのニュースで「聴き取り」を頑張っていたときは、あくまで外国のニュースという、少し距離感を感じながら聴いていました。
それが、「話すように聴く」ようになってから、自国のニュースのように感情が入ってきたのです。 まるで自分が今、アメリカの家でニュースを聴いているような、不思議な気分になるのです。
■ただ聴くだけ 「何もしない」勉強法
「自分が話すように聴く」を大人がやると、最初は新鮮かもしれません。しかし、わからなかった言葉は無視し、ひたすら次の言葉だけに集中するというのは、簡単なことではありません。
どうしたって、「今の言葉はなんだったか」「今の文は時間をかければ理解できるかもしれない」といった感情に引きずられ、次の言葉を聴き逃してしまうからです。
それに、自分が話すようにただ聴くと言われても、相手が言っている言葉がわからなければ続けられない……。もっと意味が知りたい、理解したい……という気持ちになるはずです。でも、その気持ちをぐっとこらえて、話すように、次の言葉を聴き続けてください。
なぜなら、子どもがそうしているからです。 幼児にとっては、英語にしても、日本語にしても、他の言語を介して理解することはできません。なので、決して振り返らず、何も理解できない言葉を、ただ聴くしかないのです。
■リスニングを日常の行為に
心の中で感情を込めて、相手の表情を見ながらまねしていく。本当だったらわからない言葉を調べたいのに、無視していく。ただひたすら前へ。
そのうち、「わからない言葉は無視していい」という気分が、リスニングを苦しいものではない、「日常の普通の行為」 にしてくれます。自然な気分で英語を聴き、「母国語」のように聴く気分でもあります。
英語を「母国語だと思うこと」というのは、別の言い方をすると、「訳さない」ということかもしれません。ただ素直に、感情を込めながら音を聴いていく。
そうしていると、何か文法なんて、本当にどうでもいいのではないかと思えてきます。
もっと、ひとつひとつ聴こえてくる英単語が、生き生きとしているように感じて、そこから伝わってくるもののほうが大きいと思えてきます。
それでもはじめてやってみると、「理解したい」という気持ちが勝るでしょう。理解しないまま、先に進むのは苦痛に感じるかもしれません。ただし、続けるうちに、そのスピード、ペースでも、理解できる部分が少しずつ増えていくはずです。推測、想像といった母国的な理解のメソッドが、自然とできるようになってくるのです。
ゴールは「日本語訳」じゃない
■日本語で訳をまとめない
こういった方法を使ううち、自分の実力があがったと思う瞬間が訪れると思います。「聴き取れた!」「わかった!」という感じです。そして最終的に、相手が何を言いたかったのか、まとめようとします。そのときに、日本語に訳し、理解のゴールとするでしょう。そうしないと、何かしっかり理解していないような、気持ちが悪いようにも感じるかもしれません。
でも、やはりそのままでいいです。日本語で理解する必要はありません。誰かに説明する必要はないからです。「話すように聴く」で英語を聴き続けていると、自然と「理解」していくようになります。それは日本語で訳せた理解ではありません。
英語を英語のまま、理解しているのです。
これは、体験してみないと理解できない部分かもしれません。しかし、続けるうちに、気持ち悪く感じることもなくなり、より自然な行為になっていきます。
人が話せるようになる過程のまとめ
■聴く→理解する→話す
人が話せるようになるまでの過程をまとめます。
まず、「話すように聴く」ことでミラーニューロンが働き、感情を込めながら、まねをします。ここでインプットが盛んにされます。
このインプットは、具体的に言うと音の記憶であり、発音の仕方の記憶です。黙って聴いている期間はインプットであり、準備段階ですが、まねをすることで、話すことのアウトプットの準備も実はしています。
日本語に訳さず聴くことを続けていけば、やがて英語を英語のまま理解することができるようになります。そうして直接理解を重ねていくことで、英語の言語野が作られ始めます。
そうしていつしか反射的に、
口から言葉が「産まれる」のです。
■臨界期を超える
世の中には言語習得の「臨界期」が存在するという説があります。
「○○歳までにしか言語を習得することができない」と言われたり、年齢を重ねれば重ねるほど、外国語習得が難しくなるという説です。
それはもしかしたら、確率的には正しいかもしれません。今まで書いてきたように、1つの言語を習得してしまうことで、2つめの言語を邪魔し、覚えるのが難しくなるからです。
1つの言語を理解してしまうと、「理解できないもの」に弱くなり、その言語に訳したくなったり、ただ1つの答えを探したくなったりします。これこそが、臨界期が存在する理由だと思います。
■完璧主義をやめてみる
物事をしっかり調べたくなる完璧主義者ほど子どものように学ぶのが難しくなり、勉強する人ほど話せなくなるとも言えます。リスニングでも、ついつい後戻りをしてしまうのは、完璧主義者です。勉強すればするほど、「話すように聴く」は難しいのです。これは、「勉強すればするほど、スポンジ脳の外側に硬い皮ができる」と表現することもできます。
この本でここまで述べてきたのは、大人の脳がより柔軟に、吸収力を高めていくために、蓄えた英語の知識という硬い皮を取り除いていく方法です。新しい水がどんどん入ってくるように、母国語という考え方を導入したのです。
■子どもと一緒に最初の100メートルを走る
大人は、硬い皮を剥がすのに苦労します。この本に書かれたことをすぐに実行するのは難しい人もいるかもしれません。なぜなら、たくさん勉強してきたからです。それは誇りでもあるからです。でも、この蓄積された知識は、捨てるわけではありません。まずは子どものように母国語の最初の100メートルをもう一度しっかり走り、スポンジに水をいっぱいに含ませる。そのときこそ知識は役に立つはずです。
■英語の覚悟を決める
アメリカのニュースを観ていたら、印象的な映像がありました。シリア難民の家族がカンザス州にやってきたのですが、そこでどう過ごしているのかというニュースです。
小学校低学年の女の子が学校に行くのですが、英語はわかりません。学校での初日に先生が色の紙を指さして「これは黄色、これは赤」と彼女に説明するのですが、彼女はただうなずくばかり。先生は諦めて別の席に行ってしまいます。そのときの女の子の不安そうな顔が印象的でした。彼女はこれからここで生きていく限り、英語を母国語として習得しなくてはならないのです。
数ヶ月後、彼女はクラスメートと楽しそうに英語の歌を歌い、コミュニケーションをとっていました。親はまったく英語を話せないままですが、子どもは「英語でこの教室を生き抜く」と覚悟し、黙ってまわりの英語を聴き、観察し、簡単な言葉から使い始め、まわりの子どもと遊びはじめたのです。そこには、「英語は難しい」という発想も言い訳もなく、ただ英語を母国語だと思う覚悟のもと、じっと音を聴いていたのだと思います。
そして、自分の言葉として、英語を「産んだ」のです。
■日本語は英語の邪魔になる?
彼女は硬い皮が作られる前に英語を話せるようになったのでしょう。娘は英語と日本語を同時に覚えました。娘を見ていると、英語と日本語のそれぞれのスポンジ脳に硬い皮がないという感じです。ペンやノートを使った勉強で硬い皮を作らず、ただ音という水を(他の言語を介さずに直接的に)注げば、2つの言語習得は可能だと言えます。シリアの彼女も、スポンジは柔らかいままでした。だから、日本語を習得している大人も、母国語というツールで硬い皮を剥がせば、子どもと同じようなインプットはできるのです。
***
以降の章では、大人が母国語英語を学ぶ方法や、著者の娘さんが実際に使っていた英会話リストなどを詳しく解説しています。
<収録内容>
はじめに
1章 「母国語」として学べば、英語はもっと楽しい
2章 母国語の秘密は、リスニングにあり!
3章 大人が母国語英語を学ぶ方法1(スピーキング/発音)
4章 大人が母国語英語を学ぶ方法2(リーディング/文法)
5章 子どもに「母国語」英語を教える方法
6章 2歳で英語を話しはじめた、娘の英会話日記
子どもに英語を教えるときのQ&A
2歳半ごろまでに親が本当によく使う英会話
娘がよく使っていた英会話リスト(3歳まで)
私が娘に使っていた英語(娘が3歳まで)
おわりに
著:沼畑直樹『娘に英語で話し続けたら、2歳で英語がペラペラになった。』
紙書籍定価 ¥1,300+税 / 電子書籍価格 ¥1,000+税
(書影はAmazon Kindleにリンクしています)
全国の書店・インターネット書店・電子書店にて好評発売中!
【主なインターネット書店】
Amazon・honto・紀伊國屋書店・楽天ブックス・オンライン書店e-hon・
セブンネットショッピング・ヨドバシドットコム ほか
【主な電子書店】
Amazon Kindle・honto・紀伊國屋kinoppy・楽天Kobo・BOOKWALKER・
ebookjapan・GooglePlayブックス・SonyReaderStore・DMM電子書籍 ほか
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?