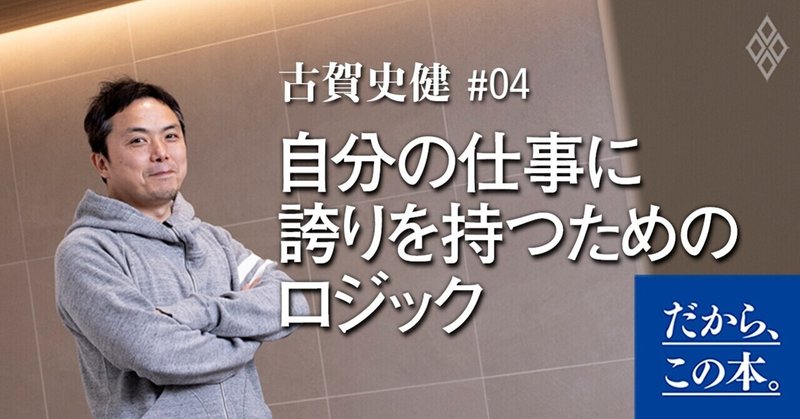
日本トップクラスのライターが、無料note記事を1500日以上更新し続ける理由
『取材・執筆・推敲』著者・古賀史健インタビュー(4)
もっとはやく、この本に出合いたかった。ライターとして、そう思わずにはいられない本が刊行された。『取材・執筆・推敲 ── 書く人の教科書』。ずっしりと重みのあるA5判の分厚い本書のボリュームは、476ページ。じつに21万字をかけて語られた「書くことの本質」に、ライターや編集者だけでなく、起業家やビジネスパーソンからも驚愕の声があがっている。それもそのはず、上梓したのは、日本では252万部、中国、韓国でもそれぞれ100万部を突破した世界的ベストセラー『嫌われる勇気』の共著者であり、日本トップクラスのライター・古賀史健氏だ。編著書の累計部数は1100万部を超え、編集者からの信頼も厚い彼の「プロライターとしての覚悟」が込められた本書は、まさに「文章本の決定版」である。
今回は、本書の刊行を記念し、「ライターの仕事術」をテーマに特別インタビューをおこなった。多忙ななかでのスケジュール管理法やnoteを1500日以上更新し続けている理由など、古賀氏のストイックな姿勢にせまる。 (取材・構成/川代紗生、撮影/疋田千里)

古賀史健(こが・ふみたけ)
ライター
1973年福岡県生まれ。九州産業大学芸術学部卒。メガネ店勤務、出版社勤務を経て1998年にライターとして独立。著書に『取材・執筆・推敲』のほか、31言語で翻訳され世界的ベストセラーとなった『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』(岸見一郎共著)、『古賀史健がまとめた糸井重里のこと。』(糸井重里共著)、『20歳の自分に受けさせたい文章講義』など。構成・ライティングに『ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。』(幡野広志著)、『ミライの授業』(瀧本哲史著)、『ゼロ』(堀江貴文著)など。編著書の累計部数は1100万部を超える。2014年、ビジネス書ライターの地位向上に大きく寄与したとして、「ビジネス書大賞・審査員特別賞」受賞。翌2015年、「書くこと」に特化したライターズ・カンパニー、株式会社バトンズを設立。次代のライターを育成し、たしかな技術のバトンを引き継ぐことに心血を注いでいる。その一環として2021年7月よりライターのための学校「batons writing college」を開校する。
「迷いの時間」がスケジュールを遅らせる
── わたし、出版業界で働きはじめたころから「古賀さん伝説」のようなものをよく耳にしていたんです。古賀さんほどやる人はいない、と。「『嫌われる勇気』は22回推敲した」という噂を聞いたのですが、ほんとうですか?
古賀史健(以下、古賀):22回推敲じゃなくて、「第22稿」ですね(笑)。ゲラのかたちで出力し直してもらったのが22回。推敲だけでいったら、22回どころじゃないです。
── えええ!
古賀:まあ、DTPのディレクターさんを巻き込んだ特殊なやり方だったので、あまりおすすめはできませんが(笑)。
── いまも昔も、ご多忙ななかで結果を出してきたと思うのですが、どうやってスケジュール管理しているのでしょう。
古賀:いや、えーと、自著についてのスケジュール管理はできてないですよ(笑)。この『取材・執筆・推敲』もほんとうは3ヵ月くらいで書き上げるつもりが、結局3年かかっちゃったし。
ただ、それとはべつに、この本を書いているあいだも雑誌やウェブの仕事をしたり、別の本をつくったりはしていて、そういう仕事の締切はかならず守ります。
── だいたい、年に10冊くらいのペースでつくってこられたんですよね。
古賀:いちばん多いときは年間18冊やっていましたね。
── 18冊!
古賀:いつも同時進行で4冊くらいの企画が動いていたんです。最短だと44時間、不眠不休で1冊、10万字くらいの本を仕上げたことがあります。
── えええ! 脳みそ、へろへろになりませんか?
古賀:もう、寝ながら書いてましたよ(笑)。でも、なんとか書き上げて、いちおう重版にはなりました。
締切を守らなきゃいけない仕事をするうえで気をつけているのは、ふたつ。
まず、「迷いの時間」をつくらないこと。スタートする前に原稿をしっかり練る。原稿制作の過程が1から10まであるとすれば、うまく文体がつかめないとか、構成が思いつかないとか、いちばん苦労するのは1から3くらいまでの「入口」なんです。だから、1から3までのスタートダッシュでつまずいてスケジュールが遅れることがないように、スタートする前にしっかりと考える。
そのときに大事なのが、「迷いの時間」をつくらずに「決める」こと。 ぼーっと、ただもやもやして迷っているだけの時間をつくらない。箇条書きで内容を洗い出したり、構成を考えたり、「どうしようかなあ」って考えたりしているつもりのときって、考えているようで考えていないことが多いんです。
「考えること」と「迷うこと」は全然違うので、迷わずにまずは決める。最初の1行を書く。決めて・書いて・読み返す。ダメだったら潔く捨てる。そのくり返しで、「原稿を考えている」状態から「原稿を書いている」状態に持っていく。「迷いの時間」がスケジュールを遅らせるんですよ。
あとは、雑誌やウェブなどの仕事に関しては、締切の2日前までには編集者に送る、という目安を持っています。というのも、ぼくは編集者にもしっかりと読み込む時間を与えたいんですよね。ギリギリのスケジュールで送ると、向こうも時間がないから「とりあえずこれで入稿しておきますね!」みたいなかたちになる。でも、そんなふうに右から左に流すだけの作業だったら、編集者がそこにいる意味がなくなっちゃいますよね。
編集者にもちゃんと仕事をしてもらいたいから、締切の1、2日前には提出して、まる1日かけてじっくりと考える時間をつくってもらう。これは自分のなかでルール化しているところです。
「それでも書く」をキーワードに、
とりあえず10年続けたい
── それだけ真剣に取り組んでいたら、寝る時間もないんじゃないか、と思うのですが……。でも、さらに驚くべきことに、通常のお仕事以外に、noteを2015年から毎日、更新されていますよね。
古賀:そうですね。いま1500本を超えています。
── 継続できている理由は何だと思いますか?
古賀:うーん、なんでしょうね。やめるとしたら、きれいにやめたいんです。エヴァンゲリオンみたいに、テレビシリーズがあって、劇場版があって、新劇場版があって、というように、自分のなかで「終わった」と思えるまでは続けたい。1年やったらとか5年やったらとか、区切りをつけようと思えばつけられるんですけど、まだ「書いた」っていえないな、という気持ちがあって、ずるずる続けています。
── いや、5年も続けているのに、「まだ書いたと言えない」ってすごいですね。
古賀:うん、あんまり公言したくはないけど、とりあえず10年やってみたいな、という気持ちがあるんです。昔、「ほぼ日」のなかで思想家の吉本隆明さんが「どんな仕事でも、10年間休まずに続けたら、必ずいっちょまえになれる」とおっしゃっていて。だから、それを自分で実感するためにも、10年間というのをひとつの区切りにしようかな、とは思っています。
── ある種、時間をかけた実験のようなものをしている、ということでしょうか。
古賀:そうですね。そもそもnoteを書きはじめたきっかけは、糸井重里さんに会いにいく方便だったんです。糸井さんが「ほぼ日」のなかで毎日「今日のダーリン」というエッセイを書いているから、「ぼくも1年間毎日やりましたが、たった1年でこんなに苦しかったです。糸井さんが20年も続けられているのは、なぜでしょうか?」という話のとっかかりをつくるために、1年やってみたんです。
それで実際に1年noteを続けて、糸井さんに会いに行って、受け入れてもらえて、当初の考えからすると、そこで更新やめてもいい。だけど、いまでも糸井さんと交流がありますからね。糸井さんに堂々と会いにいくためには、やっぱり続けている必要がある。糸井さんはいまでも毎日書かれていますしね。
ぼくもせめて10年経ったら「何かわかったことがある」と言えるのかもしれないし。いまの段階でやめても、「5年、6年やってこうでした」と言えることは何もないので。
── noteを毎日書くことが、仕事においていいリズムになっているとか、そういうことは……。
古賀:ぜんぜんなってないですよ(笑)。雑な場にしないようには心がけていますし、それなりに時間かかるんですよね。書く前も、書いた後も、頭の切り替えが必要なので、1日あたり合計2時間くらいはロスするんです。あのnoteをやめられたらなんてラクだろうって毎日思ってますよ(笑)。
── ええっ!
古賀:だって、仕事をするうえでは邪魔だもん(笑)。ただ、そんなときに思い出したい言葉があるとしたら、「それでも、書く」ですよね。この5、6年だけでも公私それぞれに大変な日もあって、「今日も書くの、おれ?」と思うこともたくさんあったんですけど。「それでも、書く」のひと言で続けていけば、何かが見えるのかもしれないと思って。
── なにか、仕事に生きているとか、効果は?
古賀:いまのところは何の効果もないです(笑)。書くのが楽しくなったとか、文章がうまくなったとか、あらたな自分を発見したとか、何もない。申し訳ないくらいに何もない(笑)。noteの人たちには悪いですけど。
自分の仕事を蔑んだまま
仕事をしたくない
── ライターの仕事にせよ、noteにせよ、なぜ、そこまでストイックに仕事と向き合えるのだと思いますか。
古賀:ぼくは、自分の仕事に誇りを持ちたいんです。自分の仕事を蔑んだまま、生きていたくない。もしぼくがライターではなく、たとえばカスタネットの営業についていたとしても同じで、自分の仕事に誇りを持つためにいろいろ考えると思います。カスタネットが児童教育に果たしている役割とか、打楽器の原点としてのカスタネットとか、カスタネットこそが最強の情操教育楽器なのだ! とか、わからないけど(笑)。自分の仕事に誇りを持つためのロジックを何かしら考えるはずです。
── ああ、誇りを持つためのロジック。
古賀:あとは、やっぱり文章自体、ずっと残るものですから。とくに紙の本で印刷されると、一回印刷されたら取り返しがつかないでしょう。だから、印刷されるぎりぎりまで全精力を傾けたい。自分の実力がなくて70点の原稿になるんだったらしょうがないけど、実力が発揮できなくて、つまりサボったせいで65点になったんだとしたら、猛烈な後悔におそわれてしまいますからね。
とにかく、サボりの余地を少しでも埋めたいんです。自分で自分のことを嫌いになりたくない。それが理由だと思います。
著者・古賀史健からのメッセージ
足かけ三年にわたって取り組んできた本が、ようやく完成しました。タイトルは『取材・執筆・推敲』。サブタイトルは「書く人の教科書」。これからの時代を担う、若い書き手たちに向けた一冊です。
書名に「教科書」の三文字を入れているとおり、本書は小手先のテクニックを集めた参考書ではありません。本書で一貫して語られているのは、書くことの大前提にある「考える技術」、もしくは「考えるためのフレームワーク」です。
考え、考え、考えて、さらにしつこく考え抜いてようやく、ライターは対象を理解し、それを誰にでもわかることばに「翻訳する=書く」ことができます。もちろん本書の執筆にあたっても、三年間ひたすら考え尽くしました。執筆中、編集者に『最後の文章論』というタイトルを提案したほど、覚悟をもった三年間でした。
あらゆるクリエイティブは、深く鋭い思考に支えられています。その意味で「考える技術」を中核とする本書は、書く人(ライター)だけでなく、すべての「つくる人=クリエイター」の精読に耐えうるものだと確信しています。
ぜひ、ご高覧ください。これまでになかった、渾身の一冊です。
※以下の記事で『取材・執筆・推敲』の「ガイダンス:ライターとはなにか」全文をお読み頂けます。
(1)ライターは「書く人」である以前に、「つくる人」なのだ!
(2)コンテンツに不可欠な「エンターテインの精神」とは?
(3)編集者とライターが「編集」するものの違いとは?
(4)価値あるコンテンツを生むための3つの要素
(5)ライターとは何者で、何を書く人のことを指すのか?
■ 書籍のご案内
編著書累計93冊、1100万部超! 世界的ベストセラー『嫌われる勇気』をはじめ数々の名著、ロングセラーを執筆してきたライター・古賀史健が、「取材」「執筆」「推敲」の三部構成・全10章、21万文字、約500ページをかけて「ほんとうの核心」だけを教える、書く技術・伝える心得の永久決定版。
現役のライターや編集者はもちろん、これからその道をめざす人、そして「書くこと」「伝えること」で自分と世界を変えようとするすべての人たちに向けた“教科書”である本書には、小手先のテクニックは一つも掲載されていません。
どうすれば、プロの「書く人」になれるのか? どうすれば、ひとりでも多くの人に届く「原稿(コンテンツ)」をつくることができるのか? この本と徹底的に格闘して、思考し、実践した先に、必ずやその「答え」はあるはずです ──。

『取材・執筆・推敲 ── 書く人の教科書』(ダイヤモンド社)
【目次】
ガイダンス ライターとはなにか
ライターは「書く人」なのか/書くのではなく、コンテンツをつくる/編集者はなにを「編集」するのか?/ライターが「編集」するもの/ふたたびライターの定義について
── 第1部 取材 ──
第1章 すべては「読む」からはじまる
一冊の本を読むように「世界」を読む/なぜ、あなたの文章はつまらないのか/情報をキャッチせず「ジャッジ」せよ/インタビューするように読む/多読よりも大切な乱読/ヒントは悪文のなかにある/わたしという人間を読むために/読書体力と自分を変える勇気
第2章 なにを訊き、どう聴くのか
なぜ取材はむずかしいのか/取材を「面接」にしてはいけない/「きく」ということばを分解する/聴くための土台はどうつくられるのか/ライターの自分を切り離す/相手の話を「評価」しない/質問の主語を切り替える/「いつもの話」のおそろしさ/本音と秘密を混同しない/質問力を鍛える「つなぎことば」/いかにして自分のこころを動かすか
第3章 調べること、考えること
取材には3つの段階がある/わかりにくい文章が生まれる理由/自分のことばで考える/自由の範囲を拡張するために/その人固有の文体をつかむ/憑依型の執筆はありえるのか/最後に残された取材相手とは/理解と感情の4ステップを追う/最良の反対意見を探す/取材という名の知的冒険
── 第2部 執筆 ──
第4章 文章の基本構造
ライターの機能を考える/書くのではなく、翻訳する/言文一致の果たされていない世界で/ことばにとっての遠近法/論理をつくる「主張」「理由」「事実」/なにを論拠に語っていくか/説得から納得へ/人はなにが揃えば納得するのか/わかりにくい日本語と起承転結/起承転結から「起転承結」へ/ふたたび翻訳について
第5章 構成をどう考えるか
ことばを外気に触れさせる前に/なにを捨て、なにを残すか/構成力を鍛える絵本思考/桃太郎を10枚の絵で説明する/構造の頑強性を考える/情報の希少性を考える/課題の鏡面性を考える/構成を絵で考える理由/バスの行き先を提示せよ
第6章 原稿のスタイルを知る
ビル・ゲイツの告白/最強のオウンドメディアとしての本/本の構成(1)いかにして「体験」を設計するか/本の構成(2)各章は、どう設計されるべきか/本の構成(3)読後感を設計するために/インタビュー原稿(1)情報よりも「人」を描く/インタビュー原稿(2)話しことばの「わたし」を描く/対談原稿(1)対談とインタビューの違いとは/対談原稿(2)現場のなにを再現するのか/エッセイ(1)コラムとエッセイはどう違うのか/エッセイ(2)感情的文章から感覚的文章へ/コンテンツの賞味期限をどう考えるか/ジャンルよりもスタイルの確立を
第7章 原稿をつくる
原稿に必要な3つの要素/リズム(1)音読と筆写が必要な理由/リズム(2)「ふたつのB」を意識せよ/リズム(3)見た目の読みやすさをつくる/レトリック(1)想像力に補助線を引く/レトリック(2)比喩とはどうつくられるのか/レトリック(3)ますます重要になる「類似を見てとる力」/レトリック(4)文章力の筋力トレーニング/ストーリー(1)論文的ストーリーとはなにか/ストーリー(2)時間の流れではなく「論の流れ」を描く/ストーリー(3)起伏より大切な「距離」/ストーリー(4)起承転結は「承」で決まる/自分の文体をつかむために
── 第3部 推敲 ──
第8章 推敲という名の取材
推敲とは「自分への取材」である/自分の原稿をどう読むか/音読、異読、ペン読の3ステップを/書き手と読み手の優先順位/最強の読者を降臨させる/論理の矛盾をどう見つけるか/すべての原稿には過不足がある/「迷ったら捨てる」の原則/読まれたくない文章を書かないために/書き上げるとはどういうことか
第9章 原稿を「書き上げる」ために
プロフェッショナルの条件/編集者とは何者なのか/ライターに編集者が必要な理由/フィードバックもまた取材である/推敲に「if」はある/やる気が出ないほんとうの理由とは/推敲の最終段階でなにを見るか/よき自信家であれ/原稿はどこで書き上がるのか
あとがきにかえて
————————————————————————————
【取り上げられた本】
『取材・執筆・推敲 ── 書く人の教科書』
古賀史健 著
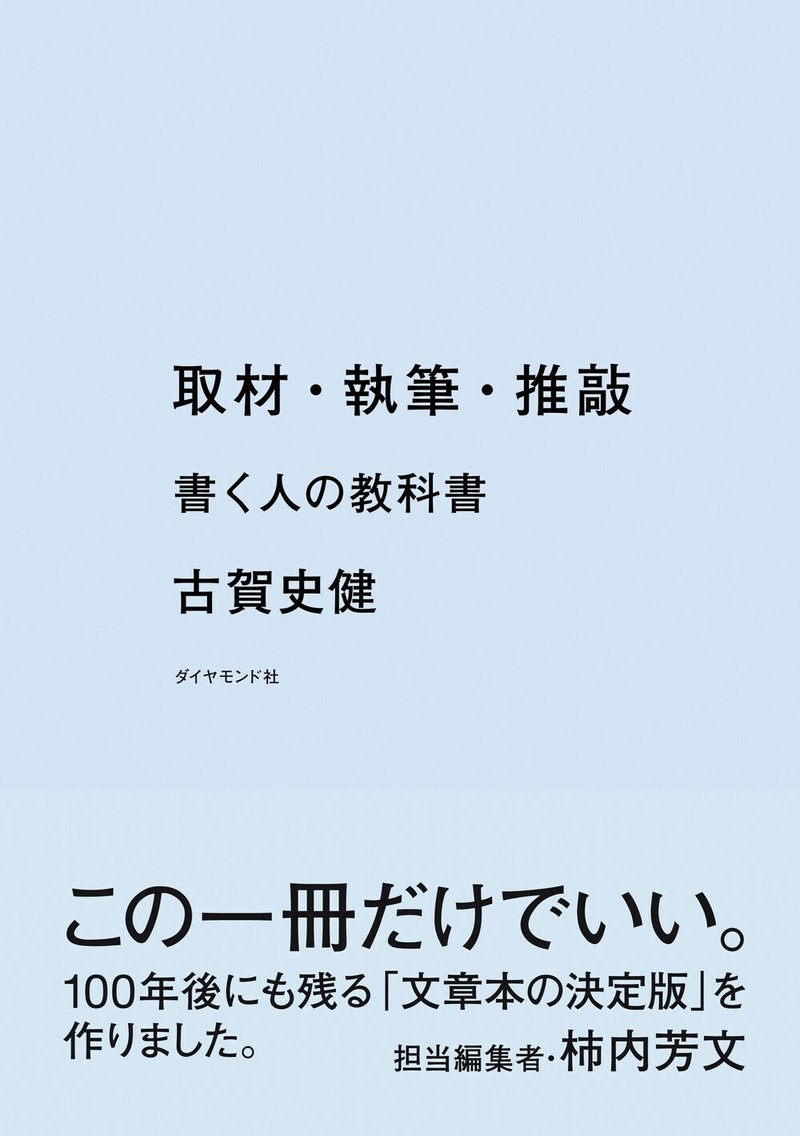
<内容紹介>
編著書累計93冊、1100万部超! 世界的ベストセラー『嫌われる勇気』をはじめ数々の名著、ロングセラーを執筆してきたライター・古賀史健が、「取材」「執筆」「推敲」の三部構成・全10章、21万文字、約500ページをかけて「ほんとうの核心」だけを教える、書く技術・伝える心得の永久決定版。————————————————————————————
