
リンチのDUNEと、ヴィルヌーヴのDUNE。
ヴィルヌーヴ監督版の『DUNE/デューン 砂の惑星』。
いや〜没入感すごかったですね!・・・完全に砂漠の惑星に連れて行かれてましたからねー。大画面&大音響で見ないと!な映画です。
ボクは1984年のデイヴィッド・リンチ版『デューン/砂の惑星』も大好きで、しかも2013年のドキュメンタリー映画『ホドロフスキーのDUNE』も大興奮で観て、両方ともBlu-rayボックス買ったくらいのファン。そしてヴィルヌーヴ監督作品の大ファンでもあるので、期待に胸をパンパンに膨らませて見に行ったのでした・・・さあヴィルヌーヴ版は???。
同点!
ヴィルヌーヴもリンチもホドロフスキーも頑張った!どれも傑作!
ホドロフスキーの『DUNE』は結局撮影すらされてないけど(笑)
いや〜どれも面白かった。
公開当初、朝のワイドショーとかでヴィルヌーヴ版の宣伝のために、リンチ版がいかに失敗作だったか!ホドロフスキーがいかに映画化を失敗したか!を特集してる番組とかがあってびっくりしたんですが(笑)・・・比べるのとか無理でしょ。

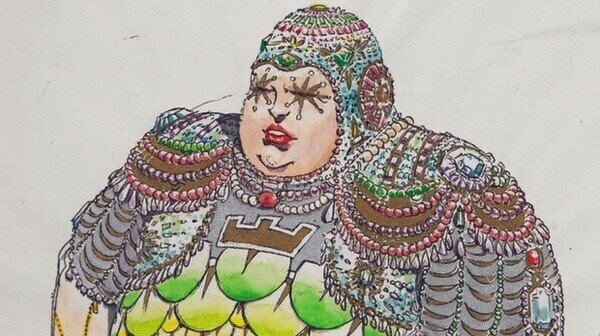

リンチ版は原作を好きに誇張しまくって完全に『イレイザーヘッド』の流れの80年代風フェテッシュなリンチの映画になってるし・・・ホドロフスキー版もまた原作を好きに誇張しまくって極彩色の70年代ドラッグカルチャーど真ん中のホドロフスキーの映画にしようとしていたし・・・ヴィルヌーヴ版は2020年代の作品って感じですよ。リンチ版・ホドロフスキー版が熱い、多少バカ映画っぽかったのに対し、ヴィルヌーヴ版はクールで賢い映画!って感じ。も〜みんな「原作の真髄を映画化しました!」とか言いながら結局自分の撮りたい作品を撮ってるんですよw。しかもそれぞれの時代性を色濃くまとっている。
これって比べられないでしょ。ラーメンとスパゲッティと蕎麦、どれが一番美味しい麺類か!?って比べるようなもんでw・・・どれも食べたい。
しかしヴィルヌーヴ版は蕎麦っぽかったですねーw。盛り蕎麦。
色調もモノトーンに近くて水墨画のよう、各種デザインも、そして俳優の演技も大胆な省略を極めたミニマリズムで超あっさり味でした。



今回のティモシー・シャラメ演じるポールと、1984年リンチ版のカイル・マクラクラン演じるポール、どちらもザ・王子様で最高なんですが、じつは演技の表現方法としてはほぼ真逆なんですよね。これが面白かった。
「比べられないでしょ!」とか言いながら、この2つを比べてみましょうw。
カイルのポールが「体格も立派でいつも寛大な笑顔(ニコニコしてる)、男性的・青年的な魅力」なのに対して、ティモシーのポールは「華奢でナイーブなこじらせ顔、中性的・少年的な魅力」で演じられています。アプローチが真逆!それでいて両方ともポール・アトレイデスに見えるんですよね。具体的な演技の話をしてみましょう。
カイルは80年代的なキャラクター演技法で「外面的」にポールのロイヤルで無垢な感じを演じています。部下に対しては等しく全員に寛大な笑顔を見せているし、両親に対しても礼儀正しい・・・まさにイメージとしての皇室というかロイヤルファミリーの見た目です。
それに対してティモシーは2020年代風のコミュニケーションの演技法で「関係性」を演じることでポールのロイヤルで無垢な感じを演じています。彼は特に思い入れの無い部下に対して丁寧で優しい態度をとりますが、厳しい教師ガーニイに対しては思春期的な対応をとり、大好きな兵士ダンカンには全力で駆け寄って抱きついたりw、相手によって態度が全く変わります。両親に対しても父親に対しては大人ぶるのに母親に対しては甘えてみたり(笑)
・・・そう、ティモシーは相手との「関係性」によって変わる態度を演じることによって、少年から青年に変化する思春期の、揺れ動き葛藤するポールを表現しているんですね。
とくに熱さを感じる箱に手を入れる「ゴム・ジャッバールの試練」のシーンが面白かった。リンチ版のカイルは箱に手を入れて苦しんでいる間、ずっと未熟ながらも勇敢なポールを演じていたんですが、今回のティモシーのポールは途中で目の前のベネ・ゲセリットの教母に対して「なんでこんな酷いことするのですか?」みたいな懇願するような目つきを見せたりしていますからねw。ポールの苦痛に対する反応の表現に相手との関係性を持ち込んでるんです。
ティモシーのポールは男性に対しては「一人前の男として評価されたい!」と思いながらも、女性に対してはふと甘えてしまうところがあるんですよ。(朝食のシーンで、お母さんに水を取ってもらったりしてますね。)
そんな「思春期の葛藤」を抱えたポールが、様々な出来事の中で母親や人々との「関係性」の更新してゆくことによって自立してゆく緻密な演技の組み立ては、まさに堂々たる主役っぷりでした。




映画『ドライブ・マイ・カー』の回でも書きましたが、現代的な芝居は、脚本上の構造も、演技の手法も「直線的に目的に向かって進む」のではなく「彷徨いながら居場所を発見してゆく」ものです。
カイルのポールは最初から救世主になるためにまっすぐに進んでいきますが、ティモシーのポールは最初は特に目的があるわけでなく、彷徨いながら、最初には全く想像もしなかった革命家へと成長してゆきます。
彷徨い・・・夢の中に出てくる女性チャニとの関係なんか特にそうでしたね。カイルのポールはチャニと出会ってすぐキスしますが(笑)、ティモシーのポールはチャニと敵対的な関係性で出会って、その中でチャニの大叔母のナイフを借りたり、何度も距離を測りなおすことで関係性が更新されてゆき、パート1の終わりではまだ恋人同士にまではなってないですからね。きっとパート2でも関係性は彷徨いながら、何度も更新されていって最終的にはなんらか強固な関係が築かれるのだと思います。
これってカイルがやっているような「外面的」なキャラ演技ではここまでの関係の変化のディテールを緻密に演じるのって不可能なんですよね。
この相手との関係性の多重構造を演じることで複雑な内面を持つ人物を描き出す演技法は、まさに2020年代的です。さすがティモシー・シャラメ。
彼は『レディ・バード(2017)』や『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語(2019)』での芝居も超魅力的で素晴らしかったですが、さらに磨きがかかったと思います。
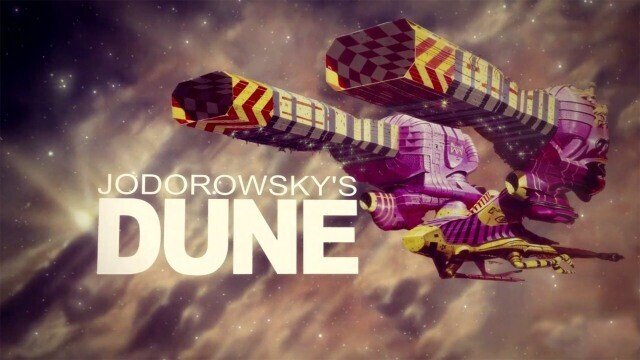


さて最後にアレハンドロ・ホドロフスキー監督が撮るはずだった『DUNE』についてもちょっと書きたいのですが・・・今回ヴィルヌーヴ版を映画館で見て、家に帰ってリンチ版をBlu-rayで見返して・・・そうしたらホドロフスキーの撮りたかった『DUNE』の姿が明確に見えてきた気がしたんですよw。
それはヴィルヌーヴもリンチも「原作を最大限に尊重して」とか言いながら、結局は自分好みの『DUNE』を撮っていたからです(笑)。
ドキュメンタリー映画『ホドロフスキーのDUNE』のクライマックスで、『DUNE』が撮れなくなったホドロフスキーが、絶望的な気分でリンチ版の『DUNE』を映画館に観に行くくだりがあります。
「映画が始まった時には私は今にも泣き出しそうだった。だが見ているうちに私は不思議と元気になっていった。映画のあまりの酷さに嬉しくなった・・・おいおい、大失敗作だ!!!」
と満面の笑顔で語る最低なオヤジなんですが(笑)気持ちはわかります。
原作『DUNE』の本質をリンチが撮り損ねている!とホドロフスキーは言うのです。リンチ版の欠点はストーリーがわかりにくいとか色々あるのですが、『エル・トポ』の『ホーリー・マウンテン』の監督ですよ?おそらく天才芸術家ホドロフスキーにとってはそんなことは些細なことでしょう。ではホドロフスキーの言うところの原作『DUNE』の本質とは何だったのか・・・それは「ドラッグによる人間の意識の拡張と、超人化。そしてその超人による宇宙の平和革命!」だったのではないかと思います。
彼は言っています「私が作りたかったのは、LSDをやらなくてもあの高揚感を味わえる、人間の心の在り方を変える映画だ」と。
1965年に発表されたフランク・ハーバートのSF小説『DUNE』に出てくるメランジ(香料・スパイス)とは「人類に時間と空間を超越する力を与える香料=ドラッグ」で、人間の意識を拡張して宇宙空間を折り畳んで宇宙を移動することすらもできる・・・要するに60年代に世界的に流行ったドラッグや幻覚剤による意識革命・平和革命の話なんですよね。
原作『DUNE』の世界はコンピューターやAIとの戦争で人類が滅ぼされそうになった経験から、コンピューターやAIなどの思考機械が禁止されていて、その代わりにドラッグによって意識を拡張された超人が超能力の力で宇宙を折り畳んで高速移動するという設定なのだそうです。(すげえ!)
その「ドラッグによる革命」の要素、リンチ版にはミュータントパイロットが超能力で宇宙を移動する描写があったくらいで、薄いんですよね。ヴィルヌーヴ版になるとそのシーンすらも削除されていて、メランジ(香料・スパイス)のドラッグ性・それによって人間の能力が超人的に拡張される!という描写はほぼ全カットな状態です。まあ時代ですよね。いまドラッグ礼賛の映画を撮る監督はいませんから。
なのでおそらくホドロフスキーがヴィルヌーヴ版『DUNE』を見たら、リンチ版の時以上に元気になるのではないのではないでしょうかw。「彼も『DUNE』の本質を分かってない!俺だけだ!」と(笑)。
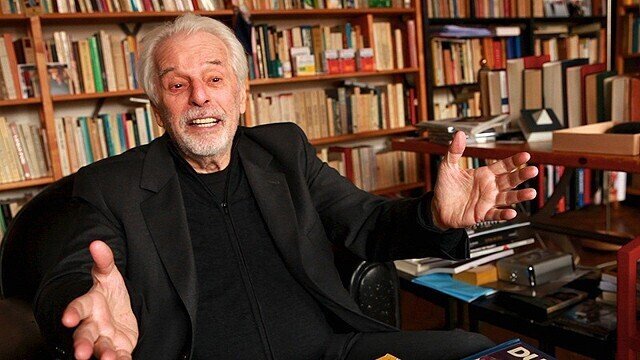



ホドロフスキー版の『DUNE』のデザイン画はどれも極彩色で豪華絢爛で、ヴィルヌーヴ版の墨絵のような方向性の真逆のものです。だって宇宙船がピンクと紫と黄色ですからね(笑)これはドラッグカルチャーそのものでしょう。
そしておそらくホドロフスキー版『DUNE』は、リンチ版以上に男性的なパワーに溢れた作品だったのではないかと思います。キャストが凄い・・・オーソン・ウェルズ、ウド・キアー、サルバドール・ダリ、ミック・ジャガー、デヴィッド・キャラダイン・・・70年代のザ・男性社会!みたいな面子が並んでいて・・・とてつもなく魅力的ですw。
そんなわけで、ボクがヴィルヌーヴ版『DUNE』を観て一番切実に思ったのは「ホドフスキー版の『DUNE』を観てみたい!!!」ということでした(笑)。
リンチ版と3つ並べて見比べたら最高じゃないですか。3人の天才監督がそれぞれに全力で撮った「オレ流『DUNE』」なんですから。そんな贅沢ほかに無いですよね。
ああ、3本の映画について語ったら、とんでもなく長文になってしまいました。ここまで読んでくださった方、ありがとうございます。
そんなわけでドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の『DUNE/デューン 砂の惑星』映画館で絶賛公開中です。そしてもし面白かった場合は1984年のリンチ版と、そしてドキュメンタリー映画『ホドロフスキーのDUNE』もアマプラで見ることをオススメしますw。
小林でび <でびノート☆彡>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
