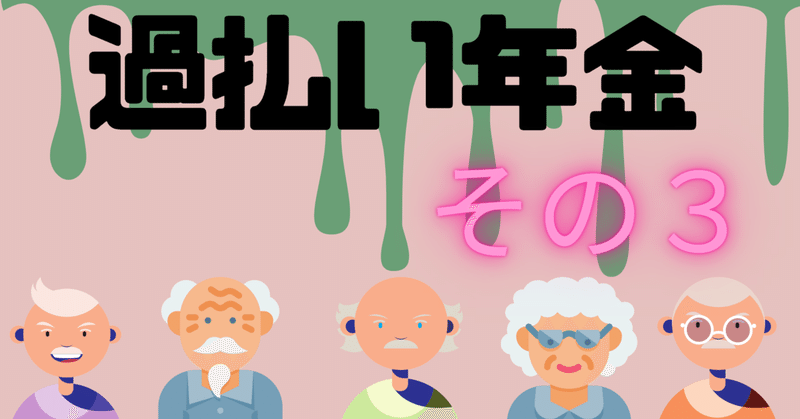
過払い年金の返納中に死亡、残りは相続? ー過払い年金解説その3ー
本人の年金から返済していた場合は、遺族が返納する必要はありません。しかし、年金機構から請求される場合があります(ケース②)。なぜこのような事が起こるのか、この道20年、年金のプロが徹底解説します。
目次
1 過払い年金の原因、再裁定
2 過払い年金の返納額
3 返納の方法は2種類
4 再裁定による過払いも内払調整できる?
5 内払調整の他に年金から徴収する方法は?
6 発想の違いでこの間違いが起きた
7 おわりに
1:過払い年金の原因、再裁定
今回は、誤った被保険者記録に基づいて裁定されるケースについて解説しようと思います。
被保険者記録とは、国民年金の加入期間や保険料の納付記録、会社からの給料額(標準報酬月額)などを記録したものです。
加入記録が漏れていたり、重複があったりと、被保険者記録が誤っていると、当然年金額も誤って決定されます。
なぜ、被保険者記録が間違えてしまうのか?
本人や会社からの届出の漏れや誤り、行政側の管理ミス等原因は様々です。年金記録問題を覚えている人はお分かりになると思いますが、紙の記録からコンピューターに移行する際の転記ミスなどもあります。
年金受給者の被保険者記録に誤りが判明すると、年金額や振込履歴などを記録している受給記録を変更しないといけません。
裁定を取り消して、再び裁定を行う事になります。これを「再裁定(さいさいてい)」と言います。
2:過払い年金の返納額
再裁定に伴って、年金の未払いや過払いが発生します。
年金を何十年ともらい続けていると、過払い分は相当な金額になる事もあります。なかには一千万円を超えるような事もありますが、時効は5年と定められていますので、直近の5年分のみ、返納する義務が発生します。
なぜ、返納は5年分となるのか?
年金の受け取る権利は5年とされています(厚生年金法92条・国民年金法102条)。年金の請求が遅れてしまって、5年経過した場合、年金が全く受け取れなくなる、という事ではありません。
例えば、65歳から受け取れる人が、71歳になって請求した場合、65歳から66歳までの1年間に受け取れたであろう年金は時効により消滅してしまいます。
71歳の直近5年間分(66歳以降)は受け取る事ができます。
再裁定の考えも同じで、再裁定の時点から直近5年分の受け取る権利が発生します。しかし、前の誤った裁定により既に受け取っている部分があります。
未払いであれば、その差額を受け取る事ができ、過払いであったら、その差額を返納しなくてはいけません。
要するに、誤った年金の直近5年分の総額と、正しく決定した直近5年分の年金総額の差額です。再裁定という行政処分によりこの差額が確定されます。
前の誤った裁定が取り消された事になるので、これが法律の根拠なく受け取っていた不当利得になります。
差額なので、一円単位まで確定し、これが一つの返納金債務となります。
直近5年を見る基準は再裁定の時点で、債務額は5年分総額の差額です。「再裁定基準の総額ベース」で返納金債務が発生します。
国にとっては、これは返納金債権が発生した事になりますので、取立しなければなりません。債権が発生した時点から時効が進行するので、何もしないで月日が経過すると回収できなくなります(会計法30条)。

3:返納の方法は2種類
過払いが判明し、返還請求を受けた場合、現金による納付の他にもう一つ方法があります。
過払い年金を今後受け取る年金で調整する“内払”という支払調整方法です。
内払とは厚年法39条に規定された、誤って支給した年金も、今後支払う年金の内払いとみなす事ができる規定です。
さらに詳しく解説します。
内払のできる条件
厚生年金法第39条2項
年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
つまり、内払調整の事務処理を行うという事は、「間違って支払った年金も有効な給付であったとみなし、先払いをした事にします。」「先払いをしたのだから、今後支払う年金は当然その分減額になります。」という事です。
間違った支払でも有効とみなす訳ですから、当然、内払調整の事務処理を行った時点で国の債権は消滅します。
条文をみると、過払いの原因を「支給停止」と「減額改定」の処理が遅れた場合、と見ることができます。
内払調整ができる条件は
支給を停止するべきだったが、何らかの原因で停止できなかった場合や減額改定の処理が遅れて多く支払ってしまった場合です。
4:再裁定による過払いも内払調整できる?
さて、では当初の年金記録が誤っていて、裁定をやり直した「再裁定」により過払いが発生した場合は、この内払調整の処理が出来るのでしょうか?
判例により明確な答えが出ています。
三 内払調整の許否について
法39条は、本来支給すべきではなかった年金が支給された場合において、その後に支給すべき年金があるときに、すでに支払った年金を返納させ、改めて別の給付を行うことが被保険者、受給者双方にとって煩雑であるため、それまでに支払われた従前の年金は、新しく支給すべき年金の内払とみなし、その差額のみを追給するという簡便な方法によって処理することを目的とするものである。
このような同条の趣旨からすると、同条第2項後段にいう「年金を減額して改定するべき事由」に、算定の基礎とされていなかった被保険者期間が存在することが判明し、再裁定処分によって年金額が減額されるべきであったという事由も含まれるものというべきである
再裁定により年金が減額となり、過払いが発生しても、「内払調整」の対象である事が確認できました。
年金機構は、「再裁定」によるもの、「停止・減額改定もれ」によるもの、全ての過払い年金について、年金法の内払調整を行うことが出来るのです。内払調整の事務処理を行うことで、返納金債権を消滅させる事ができるのです。
現金分割納付中に死亡した場合は相続するが、年金の内払い調整期間中なら相続なし、不公平ではないか?という疑問が生じます。
年金の内払調整を行う事は、国は「債権回収の費用や手間から解放される」という利益を得ているのです。これが現金返納との違いです。
利益を得たのに、死亡した途端「債権は復活する、遺族から取立だ」という虫のいい話にはなりません。
5:内払調整の他に年金から徴収する方法は?
年金を受け取る権利は特殊なものです。一般の債権とは事なり、「生活費の根幹をなすもの」であり、差押えも禁止されています(厚年法41条)。
民法510条により差押え禁止財産は相殺できません。
年金は差押えも相殺もできません。
先ほど、内払調整をすれば債権が消滅すると述べました。仮に債権が存続する、と考えた場合、「内払」と名を変えた「差押え、または相殺」を行うことになります。よって、債権は消滅している、と考える以外にないのです。
国は過払い年金の回収をどのようにすればよいか?ですが、現金で返納させるか、年金法の内払調整を使うか、2通りしかないのです。
3章で 返納の方法は2種類 と述べた根拠もここにあります。
では、遺族の方が受けている年金から死亡者の過払い分を差し引いてよいか?という疑問にお答えします。
前述のとおり、差押えも相殺もできません。
年金法の内払調整はあくまで本人の年金のみです。
厚年法三十九条の二は、死亡届の遅れで振り込まれてしまった場合の規定なので、過払い年金債務の相続とは関係ありません。
遺族本人の年金から死亡者の過払い分を差し引くことはできません。
遺族の方から回収する方法は、現金納付の一択です。
年金法において、遺族の方から取立する方法の規定はありません。
規定が無い、という事は裏を返せば「遺族から取り立てる事を想定していない」という事です。
年金に過払いが判明した場合には、どのような原因にせよ、内払調整の規定により、国は過払い額を将来給付する年金から回収し、債権を消滅させる事ができるのです。債権が無い以上、相続の事を想定する必要はありません。
死亡者が希望して、生前に現金分割納付していた場合のみ、遺族が引き続き現金で納付する必要があるだけです。
年金機構が遺族に取立を行う場合、「返納方法申出書」という書類の提出を求めてきます。
現金による返納か、遺族の方自身の年金から調整するかを選択し、分割の回数等を回答する書類です。
さて、先ほど遺族からの取立は現金納付一択と説明し、その根拠も示しました。
にも関わらず、現状は遺族自身の年金から返済する事もできるのです。
おかしいと思いませんか?
年金機構が遺族本人の年金から返納させる法的根拠、これは何なのでしょうか?
公式な見解は示されていませんが、考えられるのは2パターンしかありません。
1 年金法を類推している
2 一般法を使っている
このどちらかです。
国民の権利義務に関する事ですから、年金法であれば法改正等の法整備が必要です。明らかな違法行為と断言できますが、こちらの考えだと問題は起きません。
先に差押えも相殺も禁止されている、と説明しました。どちらにしても明白な違法行為です。
しかし、問題が起こるのは、2の方です。民法の差押・相殺を根拠にする場合です。
過払い年金については、全て内払調整で回収できる、と述べました。
しかし、これを使わず受給者本人に対し、年金機構は差押・相殺による年金の支払調整を行っているとすると、どのような影響があると思いますか?
6:発想の違いでこの間違いが起きた
年金機構は、過払い年金の取立で、支給する年金を差押、または相殺を行っているという発想なのです。当然債権は存在する、と考えないといけません。
差押・相殺を根拠にすれば、遺族本人の年金でも、誰のどんな年金からでも回収する事ができます。
差押・相殺調整で年金の一部を返済に充てていた方が返済途中で死亡したとします。返納金債権は存在していると考えているので、遺族に相続します。
内払調整、差押・相殺調整、今後支払う年金から回収する、という点では全く同じです。過払いの額を満たすまで、年金の支払いを減額する、という事務処理です。
両者とも、今後支払う年金額を調整するという効果は全く同じなのです。
生存中だと効果は同じなので実害はありません。しかし、調整期間中に死亡した場合、大きな差がでてしまいます。
我々が、年金の過払いは「内払調整により債務は消滅した」と思っても、年金機構はそう考えていないのです。「差押・相殺調整をしていた」から債務は残り、相続します、こう言ってくるのです。
これがケース②の発生する理由です。
内払調整で債務は無くなったはずなのに、遺族が取立される理由です。
内払調整は、年金機構にとっても受給者にとっても、双方にメリットのある調整方法です。
そもそも違法ですが、仮に、民法上の差押・相殺が可能だったとします。年金法で内払調整の規定が用意されているのに、これを使わずに、わざわざ民法の規定を使う事が許されると思いますか?
裁判所は、「年金機構の自由だ、どっちを使ってもいい」と言うと思いますか?
年金機構が勝手に「これは差押・相殺調整でした、債権は存在しています、相続するから返納して下さい」と言っても、遺族には関係ありません。
死亡した受給者が年金の一部から返済していたのは、年金法の内払調整です。いや、返済ではなく「先払いを受けていた」だけなのです。
7:おわりに
過払い年金解説1~3をご覧いただき、ありがとうございました。死亡者の過払い年金を遺族が返納する必要がない事を徹底解説しました。
不幸にも大切な人を亡くされ、心を痛めているご遺族に、さらい追い打ちをかける取立、しかもそれが法的根拠の全く無いものなのです。
取立をする年金事務所の担当者も悲惨です。業務命令には逆らえない、精神が削られる遺族への取立、察するに余りあります。
惨劇の元凶は何なのでしょうか?いつか解明される日が来る事を願います。
ご不明点は社労士デスクSにお問い合わせください。
初回相談は無料です。
実際に返納したご遺族の方はお急ぎください。取り戻すのにも時効があります。パートナーシップ弁護士は行政訴訟のエキスパートです。安心してご相談ください。
過払い年金解説シリーズ1~3をお読みになって、どのような感想をお持ちでしょうか?
問題なのは死亡者の過払い年金だけでしょう、生存している受給者本人への返納金取立は適正に行われている、と思われたかもしれません。
果たしてそうなのでしょうか?
死亡者の過払い年金を取り立てる理由を考えたらおのずと答えは出ます。
過払い年金解説シリーズはまだまだ続きます。生存している受給者本人に対する取立について考察します。
【過払い年金解説その4 まだまだある 過払い年金の違法な取立】
これは、年金請求して初回の振込にまとめて受給した人のケースです。察しのいい人はこれだけでピンと来るのではないでしょうか?
【過払い年金解説その5 全ての過払い年金取立は間違っている】
衝撃的なタイトルです。このように題した理由は?過払い年金解説シリーズの集大成です
過払い年金の相談について、基本的に無料で行っています。正直言って、採算の合わない事業です。過払い年金取立の現実に納得いかない方、社労士Sがやろうとしている事について賛同頂ける方、ぜひサポートお願い致します。
