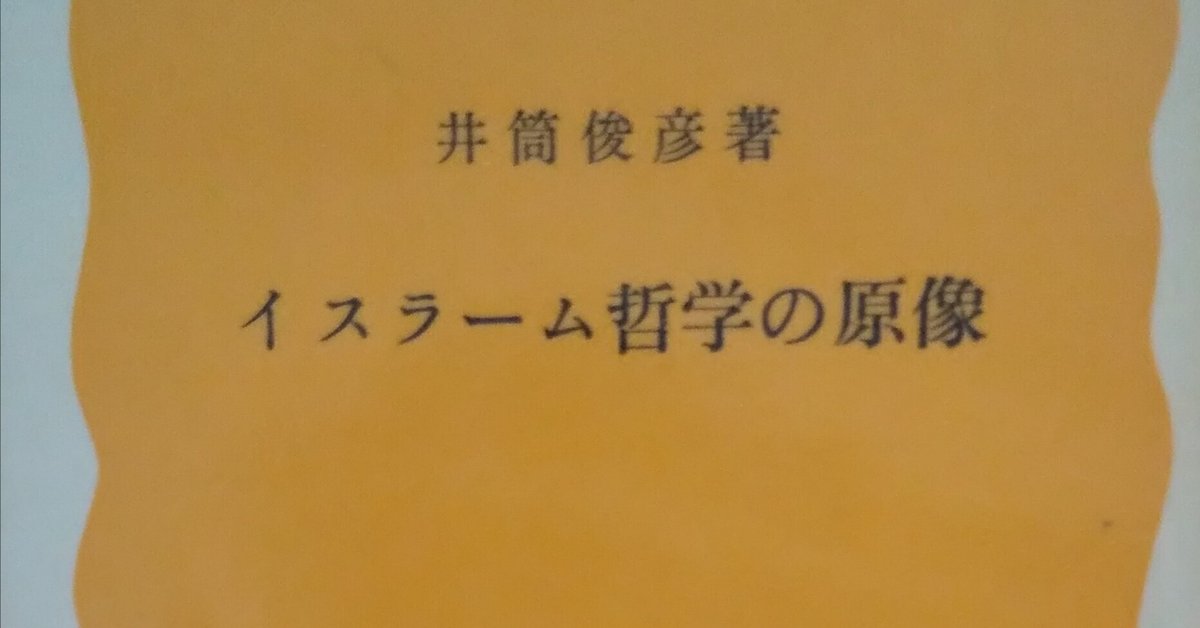
存在と自己顕現
イスラーム哲学について、私は何を知りたいのだろうか。たとえばアリストテレス哲学との関係だとか、アヴェロイズムとの関係だとか……どうも二次的な関心しかないように思える。だから、今回の話が何らかの変節になることを期待している。
井筒俊彦著『イスラーム哲学の原像』(岩波新書)を読んだ。西洋哲学史におけるイスラームだとか、そういうまどろっこしい話ではない。直球ど真ん中でイスラームの、神秘主義哲学における存在論の話である。
「神秘主義哲学」と一息で言ってしまったが、神秘主義と哲学とはイスラーム思想史上で区別すべき概念である。本書の主題は両者の接触と融合の過程を示し、「存在一性論」(ワフダ・アルウジュード waḥda al‐wujūd)の分析を通して神秘主義哲学の特色を明らかにしていくというものである。また、より広い視座としてはイスラーム哲学の研究を通して東洋哲学全体の構造を明らかにするという狙いもあるようだ。
まずはイスラームにおける神秘主義と哲学との関係に関して予備的な確認をしたい。安易な単純化は避けるべきだろうが、この関係は新プラトン主義的神秘主義とアリストテレス的哲学という風に問題を読み換えてもよいかもしれない。
ちょっと面白い話なのだが、この思想史上の二潮流に関して歴史上先にイスラームに受容されたのは新プラトン主義の方であるらしい。西洋哲学史を学んだことのある人であれば、イスラーム哲学と聞いてイブン・スィーナーやイブン・ルシドといったアリストテレス研究者の名を思い浮かべ、「イスラーム哲学=アリストテレス哲学」というイメージを持つ人がいるかもしれない(偏見である)。だが、そうしたアリストテレス研究に先立ち、新プラトン主義の受容があったのであり、アリストテレス研究も新プラトン主義の影響下にあったということは十分留意すべき点であるように思える。
では存在一性論の話に入ろう。存在論においてしばしば存在と存在者との区別が問題になるが、これは存在一性論においても同様である。感覚の対象となる事物、具体的なモノとしての存在者と、存在者を存在者たらしめている存在。イブン・アラビーがウジュード (wujūd) と呼ぶこの存在概念を井筒は「存在活力」とか、「宇宙に遍在し十方に貫流する形而上的生命的エネルギー」と説明する(114頁)。要は物ではなく力のイメージである。
ある意味、存在は産出者的なのであるが(「者」というと存在者的になってしまい説明が難しい)、また別の言い方では存在はガイブ(ghaib)とも呼ばれる。「隠れて見えない状態」という意味なのだが、こうなると存在は有というよりも無のイメージだ。余談だが、ギリシア語で真理を意味するalētheiaは忘却・隠蔽を表すlēthēに否定の接頭辞aが付いた言葉なので、なんだか親戚のような風情がある。
さて、隠蔽性あるいは無としての存在は人間の意識の対象とならない混沌であるといえる。存在一性論ではこの始原的混沌が自らを分節し・限定づけていくことで現象的世界、すなわち存在者の世界が形成されると考える。存在におけるこの分節・限定の働きを存在の自己顕現(タジャッリー tajallī)と呼び、これこそが存在一性論において最も重要な概念である。
存在が自らを存在者として顕現させるという考え方は、初期ギリシア哲学やアリストテレス哲学における一と多との問題、あるいは新プラトン主義における一者と流出の問題と考えてもよい。そして神学的に考えれば神と被造物との関係に読み換えることもできるだろう。だがこの発想は汎神論的解釈が可能であり、これが一神教にとっての危険思想であったことは時代背景として頭に入れておくべきであろう。
本来峻別させられる存在と存在者、あるいは神と人間との関係は、自己顕現の理論においてその対立が消融させられてしまう。両者は一つに合わせて認識される。だが「一つに合わせて認識される」とはいっても、それだけでは二元論を無理やり一元論にしたにすぎない。無論そんな単純な話ではないのだ。
この議論の面白さは、自己顕現の構造が理論化されている点にある。簡潔にいえば絶対無的次元における存在と、有的次元における存在者の間の、無でも有でもない中間を考えているのである。
「有無中道の実在」(アーヤーン・サービタ a‘yān thābita)と呼ばれるこのある種の媒介概念は、現象的存在者にとっての原型、プラトン風にいえばイデアとして考えられている。井筒は「限りなく柔軟で流動性を持った存在の鋳型」(130頁)と説明するが、存在一性論ではこの鋳型を通して経験的・現象的多の世界が成立していると考える。
こうした議論は「なぜ何もないのではなく、何かがあるのか」という形而上学における伝統的な問いと根底において通じているように思える。存在を無と考えるのであれば、私はなぜ世界を認識し、個別の存在者として存在してしまっているのか。こうした問いに存在一性論は無から有に至るプロセスを提示するのである。
……どうも説明が上手くいっていない気がする。今回の感想は最初から書ききれないだろうなと思っていたので、形而上学的理論に先立つ宗教的実践、スーフィズムにおける修行の話を省略した。だがそのせいで存在論とパラレルな関係にある神秘主義的な意識論・心理学の議論を本稿では説明できていない。これが失敗の根源であるように思える。とはいっても修正する気力が残っていないでの今回は諦めよう。
考究の収穫としては、使い古された二元論であるのだが、西洋的有の形而上学と東洋的無の形而上学という対立を発見したことである。本稿の最初の方で少し述べたが、井筒はイスラーム哲学を通して広く東洋哲学について考えている。そういう意識があるので存在一性論の議論を説明する際にも、頻繁に仏教哲学や中国哲学の概念をアナロジカルに利用していく。このとき結節点となるのが無の概念である。私自身、少し前に考えていた『易経』や道家思想に関係する問いとリンクするところがあり、問題設定としては興味がある。
逆に、西洋的有の形而上学なんて簡単にいってしまったが、その淵源はどこにあるのだろう。やはりパルメニデスだろうか?存在一性論においてギョッとさせられるのは同一律がしばしば崩壊していく瞬間であり、これは「あるものはある」という一番確実に思える約束が成り立たなくなってしまうからだろう。だがそんなに簡単に同一律は無くなったりするものだろうか。最近の私はついつい学び始めの知恵に夢中になり、初心を忘れているような気がする。改めてガチガチの有的形而上学からの反省が必要かもしれない。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
