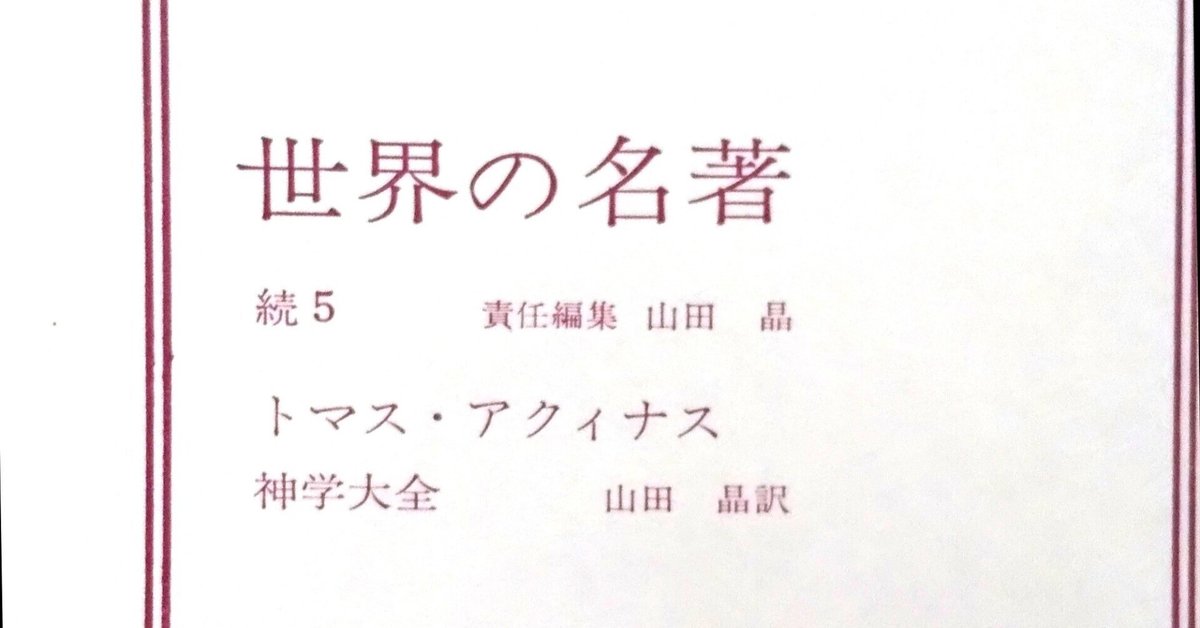
存在のアナロギアについて
はじめに
アリストテレス哲学におけるアナロギアの用法に「プロス・ヘン(pros hen)」というものがある。Stanford Encyclopedia of Philosophy では“in relation to one”と訳されており、日本語でも出隆が「一つのものとの関係において」と訳している(岩波文庫『形而上学(上)』四巻二章(1)の訳注に詳しい〔349頁〕)。
プロス・ヘン的アナロギアに関する議論は中世のスコラ学において「帰属のアナロギア(analogia attributionis)」として整理されているのだが、勉強不足で詳細を知らない。ということで、この時代の一番でかい哲学者に尋ねてみようと思う。
……どうでもいい話だが本当に大柄な人であったらしい。
今回読んだのは山田晶 責任編集『世界の名著 続5 トマス・アクィナス』(中央公論社)。本書は解説と『神学大全』(第一部の第二六問まで)の訳出とから成り立っている。本稿では第一部第四問第三項「何らかの被造物は神に似た者でありうるか」を読みながら、トマスの語る「存在のアナロギア」の理解を目指そうと思う。
1.議論の整理
「何らかの被造物は神に似た者でありうるか」という問いに対して、トマスはまず以下の四つの異論を提示する。
①『詩編』〔第八五篇八節〕で「主よ、神々のなかで、あなたに似た者はいない」といわれている。ここで神々と呼ばれているのは天使のことであり、天使ですら神に似ていないのなら、被造物であればなおのことである。
②類似(比較)は類が同じものの間に成り立つが、神と被造物とは同じ類に属さない。
③「似ている」といわれるものは形相において一致するものである。しかし、形相において神と一致するものは何もない。
④被造物が神に似ているとしたら、神が被造物に似ているという事態が起きるが、これは不合理である。
これらの異論に対して、トマスは形相における共通の仕方に応じて類似性を以下の五つに分類する。
(1)最も完全な類似:同じ性格(rationem)と同じ仕方(modus)によって、同じ形相において共通するがゆえに「似ている」といわれるもの。たとえば、二つの等しい程度に白いものが白さにおいて「似ている」といわれる場合。
(2)不完全な類似:同じ性格による形相において共通するが、同じ仕方によってではなく、より多くとより少なくという程度を有するもの。たとえば、より少ない程度に白いものがより多い程度に白いものに「似ている」といわれる場合。
(3)種に基づく類似:作用者の形相を結果が受け取るもの。作用者と結果とは同じ種に含まれ、両者は同義的に同じ名で呼ばれる。たとえば、人間が人間を生むという場合。
(4)類に基づく類似:作用者の形相を結果が受け取るまでには及ばないが、類的な類似性によって作用者の形相を結果が受け取るもの。たとえば、太陽が地上の生き物を生むという場合。
(5)類を越えた類似:「存在する」という共通点において、作用者の形相の類似性を結果が分有するもの。たとえば、被造物が神に似るという場合。
※「性格」は「定義」と解した方がわかりやすいかも?
以上の議論を元に、トマスは先に述べた四つの異論に解答を与える。
①´何かが神に似ていないという意味は「完全な仕方で似ることはできないにしても、なしうるかぎりにおいて似ている」と解するべきである。
②´神と被造物との関係は類を異にするものではない(同じでもない)。神は類の外に在りながらすべての類の根源となっているという仕方で被造物と関わっている。
③´被造物の神への類似は形相においていわれるのではなく、「本質による有」である神と「分有による有」である被造物との関係が「有」という同じ名においてアナロギア的にいわれるに過ぎない。
④´相互的な類似性(AはBに似ており、かつBはAに似ているといえる関係)は同じ階級に属するものの間でしか成立しない。
2.アナロギアへの考察
以上が第四問第三項の議論のまとめである。説明の都合、上記では類似性を五つに分類したが、実際にトマスが数えている類似性は三つである。この点から考察を始めよう。
トマスが数えている類似は(1)「最も完全な類似」、(2)「不完全な類似」、そして(3)「種に基づく類似」の三つまでである。(4)の「類に基づく類似」は第四の類似とは呼ばれず、「種に基づく類似」と対比的に述べられるにとどまる。また、(5)「類を越えた類似」は(3)と(4)とを踏まえた帰結として(igitur)として語られている。
疑問に思うのは、(1)と(2)とには完全・不完全の区別が設けられているが、(3)以降にはこの区別がないことである。そうなると、(3)以降の類似は不完全未満ということだろうか。一先ず、(1)、(2)の類似と(3)、(4)、(5)の類似との間には何か原理的な差異があることが推察される。
これを踏まえて、ここでトマスが考えている類似を(1)、(2)のグループと、(3)、(4)、(5)のグループとに分けて考えてみようと思う。便宜上ここでは前者を比例的類似、後者を関係的類似と呼ぶことにする。
2-1.比例的類似
(1)最も完全な類似
比例的類似に関しては、白さが例として挙げられている。たとえば明度10の二つの白いものがあれば、それらは白さにおいて完全に類似しているといってよいだろう。むしろ、白さにおいて等しいものである。
(2)不完全な類似
これに対して、白と灰色という二色を考えてみよう。白色は明度10であり、灰色は明度5であるとする。このとき、両色は白さ(あるいは無彩色?)という形相を共有しているが、明度という数値において程度の差がある。これが不完全な類似と呼ばれるものである。
しかし、白が白に対して100パーセント一致していることと、灰色が白に対して50パーセント一致していることとに完全・不完全の区別を設けたところで、両者の区別は本質的なものではなく、量的な差異に過ぎない。グラデーションといってもよいだろう。ゆえに、(1)「最も完全な類似」と(2)「不完全な類似」とに認められるのは程度の違いであり、両者に原理的な差異はないと考えられる。
なお、ここで考えられている比例的類似は、哲学史的にはアリストテレスのいう幾何学的アナロギア(analogia geōmetrikē)に分類できるだろう。すなわち、A:B=C:Dの四項関係に定式化できる(白:明度10=灰色:明度5というように)。
2-2.関係的類似
(3)種に基づく類似
関係的類似に関しては、最初に人間が例として挙げられている。「人間が人間を生む」というのはアリストテレスが頻繁に使う言い回しで、トマスもそれを念頭に置いていると考えられる。アリストテレス風の説明をするとしたら、親(作用因)は自らと同じ人間(形相因)である他者すなわち子という終局(目的因)を結果するということになるだろう(厳密にいえば父親の精液が作用因、母親の月経血が質料因と考えられている)。
これをトマス風に言い直せば、子が親の形相(人間)を受け取るという仕方で、「人間は人間を生む」といわれることになる。形相に対して結果が「受けるもの」(recipiens)、作用者が「受け取られるもの」(receptum)と考えられており、これ以降関係的類似の議論は形相を軸とした結果(受けるもの)と作用者(受け取られるもの)との関係に基づいて展開される。
(4)類に基づく類似
次に太陽と地上の生き物とが例として挙げられているが、太陽と生き物との関係は親と子との関係と同じ仕方で類似しているのではない。たとえば、太陽が生き物を生むと言表すること自体は可能である。だがこのとき、子が親の形相を受け取るように、生き物が太陽の形相(恒星?)を受け取ってはいない。そうなると、太陽と生き物は互いに全く無関係であるのだろうか。
この関係をトマスは「類的な類似性によって太陽の形相を受けるにとどまる」(188頁下段)と説明する。つまり、限定的にではあるが生き物も太陽の形相を受け取っているのである。なお、ここでいわれる類的な類似性による形相に関して、具体的には「物体」であると訳注では考えられている(注7〔190頁下段〕)。従って改めていい直すと、生き物が太陽の類的形相(物体)を受け取っているという仕方で、「太陽は生き物を生む」といわれる。
(5)類を越えた類似
最後に神と被造物とが例として挙げられている。これまで作用者と結果という観点から、種における共通性と、類における共通性とについて考えてきたが、神と被造物とは種においても類においても共通するところがない。
これは第三問第五項「神は何らかの類のうちにあるか」の問いに対する「神はいかなる類の内にもない」という解答を前提としている議論である。簡潔に説明すれば、ここでトマスが考えている「類」(genus)とは、アリストテレスの考える最高普遍概念としての述語形態(カテゴリー)のことである。また、「類のうちにある」(esse in genere)というのは、主語が類によって述語づけられることだ。言い換えれば、神が類に含まれないということは、神が述語づけられないということである。
これを踏まえて神が類に含まれないという主張は(a)神の現実態に可能態は附加されえない、(b)「有」(ens)は種差を持ちえないので類でもありえない、(c)神において存在と本質とは異ならないという、以上の三点から論証されている。
話を戻そう。神と被造物とがいかなる類においても共通するところがない、というのはそもそも神がいかなる類にも含まれないからである。換言すれば、神は類に対して外在的である。そうなると、神と被造物とは互いに全く無関係であるのだろうか。
この関係をトマスは「存在するということが万物に共通であるように、何らかのアナロギアによって作用者の形相の類似性を分有するであろう」(188頁下段)と説明する。
これまで用いた表現に合わせれば、被造物は神の〈形相の類似性〉を受け取っているという仕方で、「被造物は神に似ている」といわれることになる。どうやら被造物は神の形相それ自体を受け取っているわけではないようだ。詳しく考えていこう。
まず、ここでいわれている存在とは「神の存在」と「被造物の存在」とである。先に述べたように神の存在は類に対して外在的であり、その一方で被造物の存在は類に対して内在的である。ゆえに、外在的・内在的という区別において両者の存在の仕方は同義的(univoce)ではない。だが、存在しているという共通性を完全に否定することもできないので異義的(aequivoce)と言い切ってしまうこともできない。
同義的でも異義的でもない関係。こうした神と被造物との関係を取り持つのが「分有」(羅: participatio, 古希: methexis)の理論である。分有とはプラトン哲学の発想であり、イデアと感覚的個物との関係を論じるために用いられるのだが、トマスはここで存在の共通性を論じるためにこの理論を活用している。すなわち、イデアの分有理論を方法として用いながら、存在の分有について論じている。
これまでの議論で、作用者から形相を受け取るものとして考えられてきた結果は、ここでは神の存在の分け前にあずかるという仕方で〈形相の類似性〉を受け取っている。受け取る・受け取られるものとして考えられてきた形相が、ここでは分有された存在として考えられていることに注意したい。それゆえ、単に「作用者の形相を受け取る」ではなく、「作用者の形相の類似性を分有する」という持って回った言い方がされたのである。
被造物は神の存在を分有という一種の限定された仕方において受け取っている。すなわち、有限的存在者である被造物は無限的存在である神の存在をそっくりそのまま受け取ることはできない。この限界・有限性が被造物における本質(類としての実体)である。
被造物は自らの本質において神の存在を分け与えられた「分有による有」(ens per participationem)であり、これに対して存在と本質とが一致する神は「本質による有」(ens per essentiam)である。両者は有(ens)という同じ名で呼ばれるが、同義的とも異義的とも説明できないこの関係は、もはやアナロギア的(analogice)と呼ぶことしかできない。これがいわゆる、トマス・アクィナスの「存在のアナロギア」である。
なお、トマスのアナロギア理論はしばしばアナロギア・エンティス(analogia entis)として紹介されるが、これに関して本書の解説で注意が促されている。執筆者の山田はアナロギア・エンティスとは「存在者のアナロギア」であり、「有限なる存在者と有限なる存在者との間に成り立つアナロギアなのである」とする。そして、この解釈はフォイエルバッハに見られる誤ったトマス解釈として退けられている。これに対してトマスの用いるアナロギアは、無限なる神と有限なる存在者との間に成り立つ「存在のアナロギア」(analogia secundum esse)であると述べられている(49頁下段-50頁上段)。本論とは少しずれたが、重要な指摘であると思われるので付言しておく。
おわりに
本稿ではトマスの考える類似性を比例的類似、関係的類似の二つに分けて考察した。比例的類似においては共通する形相の下での量的差異が問題とされた。また、関係的類似においては共通する形相の下での作用者と結果との関係が問題とされた。
関係的類似については更に、有限・無限の区別がある。すなわち、種・類に基づく類似は有限的存在者の間に成り立つ類似であり、類を越えた類似は無限的存在と有限的存在者との間に成り立つ類似である。
……本当はプロス・ヘン的アナロギアとの関係まで考えたかったが、そろそろ筆を置こう。とても疲れた。それでも「同義的とも異義的ともいえない」なんて書いているくだりは、パルメニデス的な形而上学の根本問題にぶち当たってしまった風情があり実に味わい深かった。こういう話は好きだ。
とはいっても、今回この文章を書くにあたって私が読めたのは解説(コンパクトで分かりやすくて最高!)と第一問から第四問までである。『神学大全』は全体で五一二問(二六六九項)あるらしいので、本当にごく一部しか読めていない。続きを読むのは、少し休んでからにしたい気分だ。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
