福祉に関する情報集(随時更新)
※随時確認はしていますが、更新が反映されていなかったり、執筆者が間違えていたりすることもあります。利用に当たっては、ご自身で担当機関へ再確認をお願いします。
発達障害ナビポータル
発達障害ナビポータルは、厚生労働省と文部科学省の協力の下、国立障害者リハビリテーションセンター(発達障害情報・支援センター)と国立特別支援教育総合研究所(発達障害教育推進センター)の両センターが共同で運用する発達障害に関する情報に特化したポータルサイトです。(サイトより)
発達障害情報・支援センター
住居に関するサポート
「グループホームに入りたい」だけでなく「借りられる家がない」「保証人が立てられない」などについてもサポートが受けられます
厚生労働省の発達専門プログラム
厚生労働省が昭和大学と開発した、発達障害の特性に合わせたパッケージ型認知行動療法があります。健康保険で受講可能です。
支援プログラムを受けられる病院リスト
発達障害向け専門プログラムの概要
※東京都のものです
支援医療機関リストの中に、通えそうな場所があったら、直接問い合わせて受講可能か確認した上で、主治医の紹介状を持ってたずねてください。
「コミュニケーション力アップコース」(ASD向け、22回)
「計画・実行力アップコース」(ADHD向け、13回)
「ステップアップコース」(修了者向けアフターケア)
使われるテキスト
https://www.amazon.co.jp/dp/479110952x
自立生活援助について
https://plushearty-salon.com/situation/service-contents-d/
一人暮らしの障害者が使えるサービスです。
ヘルパーさんに生活の支援をしてもらうことができます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html
利用者の負担額について
障害年金支援ネットワーク
https://www.syougainenkin-shien.com/
NPO法人「障害年金支援ネットワーク」のホームページです。障害年金受給に関して、無料で相談ができます。
各種手帳・年金についてのまとめ
「身体障害者手帳」について。
主な申請先
・福祉支援事務所
・自治体(役所の)福祉課
主な等級判定人
・自治体より嘱託された指定医
等級は1~7級。
複数の障害を持つ方には
(各障害単独等級を)総合的に踏まえた判定が行われます。




手帳申請に必要な提出物
・申請書
・診断書
・本人写真(縦4cm×横3cm)
自治体の担当窓口で
(提出者/申請支援対象本人の)
マイナンバーカードもしくは身元確認可能なものを提示する。



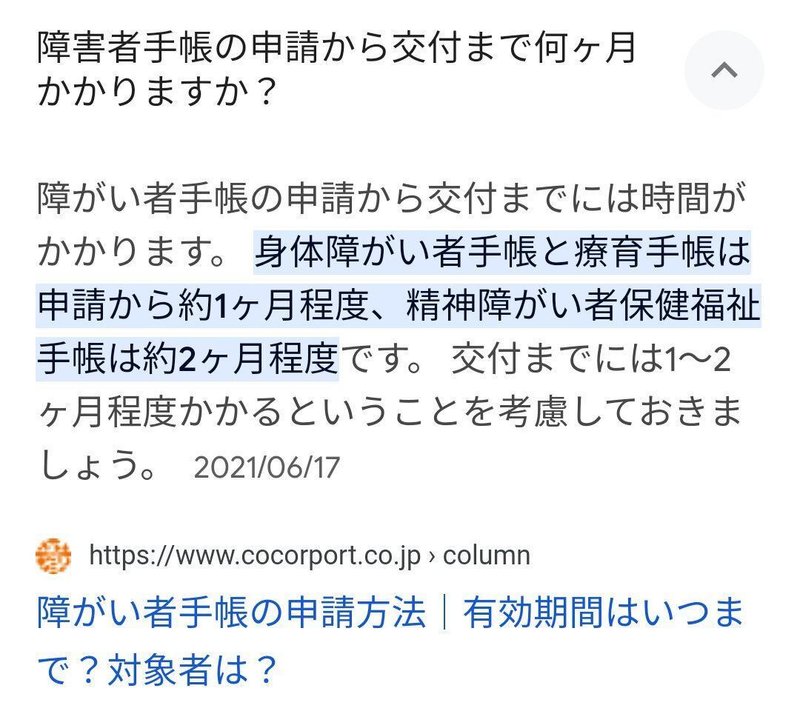
精神障害者保健福祉手帳について。
主な申請先
・区や市町村役所の福祉課
主な等級判定
・(自治体)精神保健福祉センター
等級は1~3級。
通院先担当医が出来ることは
患者さん依頼の「診断書(医学的視点の意見書)」作成。
等級判定は不可




手帳申請に必要な提出物
・申請書
・診断書
・本人写真(縦4cm×横3cm)
自治体の担当窓口で
(提出者/申請支援対象本人の)
マイナンバーカードもしくは身元確認可能なものを提示。




(現時点の)療育手帳について。
主な等級判定機関
・18才未満…児童相談所
・18才以上…知的障害者更生相談所
直接の管轄は
区や市町村役所の福祉課。
軽度~重度『知的障害』と
判定を受けた者に各都道府県知事(政令指定都市の長)の下、発行。
判定基準は全国一律ではなく、自治体によっては適用範囲が
広めに設定されてる場合(※具体例…茅ヶ崎市)もあります。


療育手帳の判定基準に
受給条件として「知能指数」を重視する傾向ありますが
行う検査の種類は
判定機関所属の心理士が決めます。
知能検査ではなく
発達検査が実施されたケースもあるそうです。




「障害年金の等級」について。
SNS/臨床現場でも
「障害者手帳」等級判定と混同されてる方を散見します。
障害『年金』等級判定機関
→日本年金機構
障害の程度が重くなった場合
等級変更になる事も。
☝手帳(身体/精神/療育)も然り。




『後遺障害(保険用語)』とは?
思わぬ事故に遭遇し
医療機関で治療/加療しても
「日常生活が困難」な障害症状が
残ってしまう状態です。
(具体例の1つとして)
交通事故の後遺症で適用されるケースが多い模様です。
主な後遺障害等級判定
→自賠責障害調査事務所




実は…あまり知られてない話。
自治体の保健所にも
民間の生命保険会社にも
医師がいます。
保健所在籍の医師
→公衆衛生医師(保健所所長兼務)
生命保険の診査医
→社医もしくは嘱託医
医師同士でしか理解が困難な
実務スキルの経験則/医学的知識/情報もあります。




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
