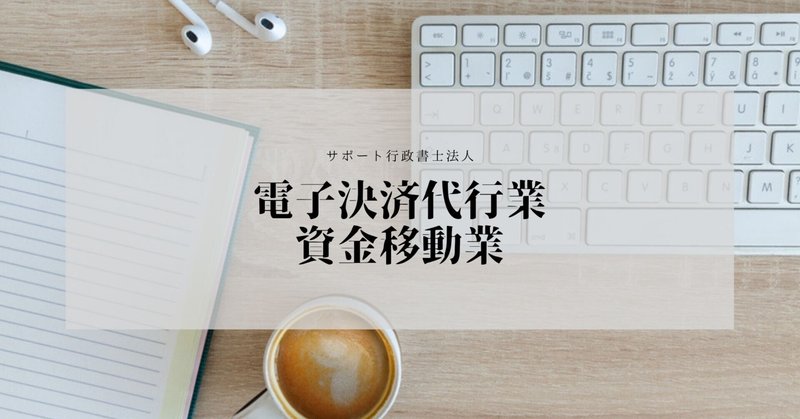
電子決済等代行業を登録したい人必見!申請について(概要編)
はじめまして。サポート行政書士法人の田村です。
今回は、「電子決済等代行業の申請」について解説します!
おそらくこのnoteにたどり着いた方の多くは、電子決済代行業の申請を検討されていると思います。
しかし、電子決済等代行業の申請をするために、「電子決済代行業 申請 やり方」とか「電子決済代行業 申請 方法」とかをWebで調べてみても、金融庁や金融機関の難しい言葉が並んでいて、一体自分が何をしたら良いのかが理解しづらいですよね。
そのため、このnoteでは電子決済等代行業の申請について分かりやすく解説していきます!
多くの人がつまずくポイントも紹介しますので、是非お役に立ててください。

【はじめに】
本noteでの解説はあくまで非公式的なものです。
あくまで個人的な解説なので、公式の情報は以下サイトをご参照ください。
https://www.fsa.go.jp/common/shinsei/dendai/index.html
【どんな事業が電子決済代行業にあたるのか?】
まず初めに、どういった事業が電子決済代行業にあたるのかを解説していきます。
電子決済代行業は以下の2種類の事業形態があります。
まず、①について解説します。
これは、一般的に「更新系」と呼ばれ、送金サービス等に利用されています。
この「更新系」は、銀行法第2条第17項第1号で定められていることから第1号と呼ばれることもあります。

<APIとは?>
ここで、電子決済代行業で登場する「API」という言葉を紹介します。
既にご存知の方は飛ばしてもらって構いません。
「API」とは、「Application Programming Interface(アプリケーション・プログラミング・インターフェイス)」の頭文字をとった言葉です。
インターフェイスとは、コンピュータ用語でいうと、「何か」と「何か」をつなぐものという意味を持ちます。
したがって、APIとは、「アプリケーション」と「プラグラム」をつなぐもの、という意味になります。
つまり、ここで言うAPIとは電子決済代行業者のアプリケーションと金融機関のシステムをつなぐことを指しています。
次に②についてです。
こちらは、「参照系」と呼ばれ、家計簿アプリ等に利用されています。
この「参照系」は、銀行法第2条第17項第2号で定められていることから第2号と呼ばれることもあります。

こちらも「更新系」と同様に金融機関とAPI契約を結ばなければなりません。
さて、ここまで電子決済代行業にあたる事業を確認しました。
ここからは、登録までの流れを紹介します。
【電子決済等代行業の登録までの流れ】

①事前相談
管轄の財務局又は財務支局おいて、登録申請予定者が登録申請の概要書を提出します。
その後、提出した概要書に沿って、当局から当該サービスについての質問回答や補正が求められます。また、状況によって面談することもあります。
「該当性あり」と判断されれば、金融庁によるドラフト審査に移ります。
②申請書 一式のドラフト審査
このフェーズでは、登録申請書のドラフトを提出します。電子決済等代行業の申請において、山場になるフェーズです。
ここでは、申請書一式の記載内容に過不足がないか、社内体制が電子決済代行業の要件を満たしているか等をチェックされます。
このチェックをクリアできなければ本申請には進めません。
所要期間は約2~3ヶ月と言われています。
③本申請
ドラフト審査に合格した後、ようやく本申請が可能となります。
標準処理期間は 1ヶ月とされています。
「標準処理期間」とは、申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間のことです。
そのため、申請の内容や混雑具合などによって、実際の処理期間がこれを超えることもありますので、あくまでも目安となります。
本審査で承認されれば、電子決済等代行業者として登録できます。
④登録後
登録が完了しても終わりではありません。
登録後は、「電子決済等代行業に関する報告書」を1年に1度、決算期から3か月以内に提出する必要があります。

【申請前に必要なこと】
次に、申請前にやっておかなければいけないことを紹介します。
まず、必要なことは電子決済等代行業を行うための管理体制を整えることです。
電子決済代行業者に対して、システムリスクや内部態勢の整備が求められています。
そのため、ドラフト審査では以下の項目に対して細かい管理体制が追及されます。
システム部分だけでも以下の10項目について、明確に体制を整備しなければなりません。
(1)当該電子決済等代行業者におけるシステムリスクに対する認識等
(2)システムリスク管理態勢
(3)システムリスク評価
(4)情報セキュリティ管理
(5)サイバーセキュリティ管理
(6)システム企画・開発・運用管理
(7)システム監査
(8)外部委託管理
(9)コンティンジェンシープラン
(10)障害発生時等の対応
これに加え、以下のシステム以外の内部態勢の整備も求められています。
(1)法令遵守態勢等
(2)反社会的勢力による被害の防止
(3)利用者保護措置
(4)利用者に関する情報管理態勢
(5)苦情等への対応
(6)事務リスク管理
【電子決済代行業に登録するための必要書類】
電子決済代行業の登録には、膨大な添付書類が必要となります。
また、提出するだけではなく、「電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等」などを参照しながら、審査に通るように記載する必要があります。
これらの書類に不備があれば再提出などが求められ、登録までの期間が延びてしまいます。
実際に「自分たちだけで、法規制に沿った社内体制を整備し、必要書類をすべて揃えるのは苦労する。知見や実績のある行政書士等に相談しなければ登録は難しい」というお声をご相談者の方からはよく聞きます。
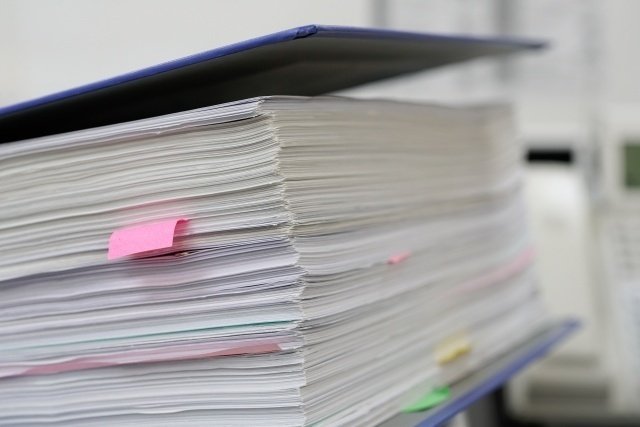
【最後に】
今回は、電子決済等代行業の申請について大まかな流れを解説しました。
次回は、事前相談のフェーズについての解説・注意点を投稿する予定です。
電子決済等代行業について、「どうやって体制を整備したらいいか分からない」とか「必要書類をどのように作成したらいいか分からない」といったご質問がございましたら初回無料で相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
電話番号:03-3526-3915
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
