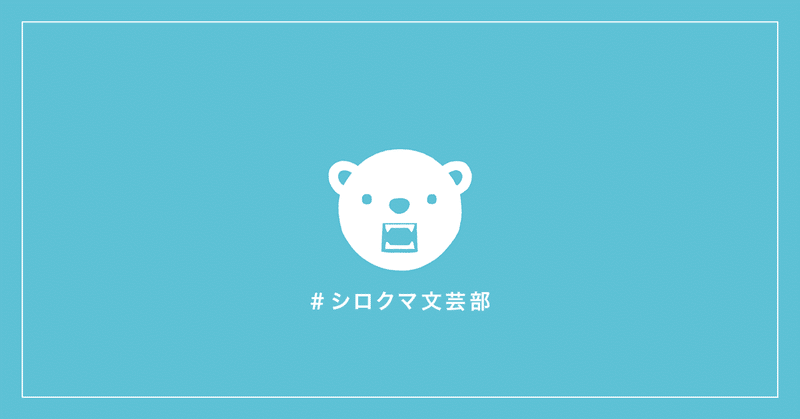
十二月屋(#シロクマ文芸部)
「十二月屋はまだじゃろか」
ちりん。
片付け忘れた軒先の風鈴が鳴った。
文机にひじをつき、ぼおっと出格子越しに路地を眺めていた橙子は、耳の後ろでかすかに鈴のような声がふるえた気がして、
「十二月屋って、なあに?」と振り返った。
黒髪を肩で切り揃え、梔子色の縦縞のきものに、黒地に椿柄の被布をはおった六歳ぐらいの少女が、橙子の肩越しに窓の外をうかがっている。
「あなた、どこの子? かってに人の家にあがったら、あかんよ」
少女は、しまった、という顔をする。
「あなたのおうちは、どこ?」
「ここじゃ」
ぶっきらぼうに足もとの畳を指さす。
「うーん。このあたりは、似たような町家が多いからまちがえたんやろか」
ちょっと困ったな、と橙子は腕を組む。
座っている橙子と女の子の背丈は同じくらい。少し目線をあげると、切れ長の瞳とぶつかる。泣きだすかと恐れたが、怯えるふうでもなく凪いだ湖面のごとく平静である。よくみると、鼻筋が通り均整のとれた面立ちで、その落ち着き払った態度のせいか神々しいほどだ。
憧れだった京町家に八月の末に引っ越して三月あまり。京の人づきあいについて聞いてはいたが、目に見えぬ塀の感触は日ごとに確かになり、ご近所のことなど橙子にはまだよくわからない。このくらいの歳の女の子のいる家があっただろうか。
「お名前は?」
「名か?」
ふむ、と少女は小首をかしげる。
「ザシキ……ワラシじゃろうか。人の子は妾のことをザシキ様とか、ワラシ様とか呼びよるの」
ワラシ? 変わった名前だなあ。「和楽詩」と書くのだろうか。橙子はてきとうに脳内変換してみる。カシワっていう著名なデザイナーもいるし、このくらいは普通なのかもしれない。それにしても、今どき、きもの姿の女の子など珍しい。時季的に少し遅めの七五三参りの帰りだろうか。
「おうちの人が探してはるやろから、とりあえず表に出てみよか」
ザシキさんなんて家あったかなあ、と橙子は土間に置いてるモカシンに足をつっこむ。あれ? 少女の草履が見あたらない。
「ワラシちゃん、草履はどこで脱いだん?」
上がり框につっ立っている少女に問う。
「そこ」と土間をさす。
あれ? と橙子は目をこする。上がり框の端の三和土に子どもの草履がある。さっき見たときには、そんなもの無かったような。あれれ?
顔をあげると、女の子はいたずらっぽい目で微笑んでいる。
明かりとりの窓から射す冬の光は昼でもほの暗いし、影になって見落としていただけかもしれない。
「ほな、行こか」
少女の手をつないで、表の引き戸を開ける。
橙子は表に出て手を引く。ところが、少女は出てこようとしない。
「なにしてんの」と少女の手を引くが、幼いのに力が強くびくともしない。駄々をこねて足を踏ん張っているようなそぶりもない。橙子はぎゅっと力を込めて引いてみたが、女の子は涼しい顔で戸の内にいる。
「妾はこの家の守り神であるゆえ、この屋敷から出ることはかなわぬ」
「神……様?」
「いかにも」
うわあ、失礼しました、と橙子はあわてて手を放す。
「あたし、霊感ないよ。なんで見えてるん?」
「手違いというか、うっかりしとったいうか」と、自称神様の少女がごにょごにょと口ごもりながら、「あのな」と一段と声をひそめる。
「妾の姿も声も、他の者には見えてもおらぬし、聞こえてもおらぬぞよ」
「えっ」
橙子は背後を振り返る。往来で何人かが、遠巻きに不審げな視線を向けている。橙子はあわてて家に入り、ぴしゃりと戸を閉めた。
「人の子は妾のことを座敷童と呼んでおる。古い家の気から生まれ、屋敷に住まいて、家を守る神である」
橙子がネット検索に目を走らせている傍らで、行儀よく正座して、神様と名乗る少女は自らの由来を滔々と述べている。ネットの記事には「いたずら好きの神様」とあった。思いあたる節がいくつもある。
後で食べようと置いていたドーナツがなくなっていたり(食べたのを忘れた?と思った)、夜中にトイレに行くと電気が点いたり、消えたり(電燈の不具合かしら)。枕元でコオロギが何匹も跳ねて驚いた夜もある(すき間だらけも風流ね)。廊下が濡れていて転んだこともあった(雨漏りかなあ)。いつも、どこかで、クスクスと笑うような気配があったが、橙子は風の音と思っていた。
そういえば不動産屋さんが言ってたっけ。「なぜか、すぐに借り手が出ていかはるんですわ」と。「せやさかい格安物件なんやけど、よろしいか」と念押しされたのを思い出した。
「ころころ、ころころ住まう者が変わってな」退屈していたんだそうだ。
「そちは他の者とちごうて、何をしても動じぬから、妾もうっかり気を抜いてしもうたんじゃ」
「はっきり見えるいうんは、妾と波長が合うんじゃろな」
なぜ姿が見えるのか、という橙子の問いに、童姿の神様はくどくどと言い訳をする。二十五歳の橙子の前では、叱られている子のようにみえる。
「もう姿を現さんように気つけるさかい、許してたもれ」
寂しげな笑みを浮かべながら、すうっと透けていく。
「待って、消えんとって、ワラシ様」
橙子はあわててワラシに抱きつく。
気の遠くなるほど長い長い歳月、ワラシは誰に相手をされることもなく、独りぼっちでこの家を守ってきたのか。退屈しのぎのいたずらだけを慰みにして。なかなか近所に知り合いのできない橙子も、寂しさを募らせていたのだと思う。Webデザインの仕事をする傍らで、神様が炬燵に入って茶をすすり、あれこれ話しかける。おかしな状況だとわかってはいる。だが、ワラシ様がそこにいる、というだけで底冷えのする町家の空気がまあるくなる気がするのだ。
「ところでワラシ様、十二月屋って何?」
「西洋では十二月に三太郎と申す者が贈り物をしてくれるのであろう?」
サンタクロースのことか。
「人は、ほれ、そのネットとやらいう不可思議を使うて物を購うじゃろ」
知っておるぞ、と鼻をふくらませる。
「そのような通信網は神の世界では古来よりあっての。神気網と申す」
ワラシは最近お気に入りのココアをふくむ。口のまわりがココア色だ。
「あたしが住むまでは、それで食料品とかを買ってたの?」
「否。本来、神とは何も食べずともよい。衣も替えずとも、常に心地よく清潔に保たれておる。まあ、妾は人の子の食べ物が好きじゃがな。無くても困るものではない」
ワラシは目を細めながらココアを飲む。
「十二月屋とは、年に一度、神の御用聞きをする。妾は、毎年、十二月屋で求めたものを、この家に住まう者に贈っておったのじゃがな」
童姿の神様は微かに眉を曇らせる。
「なぜか、気に入ってもらえぬ。妾からの贈り物に気づくと悲鳴をあげるか、汚いと捨てるのじゃ」
ココア色のため息を吐く。
「西洋の物なら気に入るかと思うて、マンドレイクとか申す植物を贈ったらな、あわてて荷造りをして翌日に出ていってしもうた」
橙子も大きなため息をもらす。
「他にどんなものを贈ったんですか?」
「イモリの黒焼きじゃろ、河童の皿じゃろ、動く狛犬もあったな」
この心優しい神様の想いはいつも空振りなのだ。
その冬、いちだんと冷え込んだ朝のことだった。
土間に小さなつづらが置かれていた。上蓋には、「十二月屋」の札が貼られていた。
「ワラシ様」と呼ぶと、「届いたか」とにこにこしながら土間に駆け下り、「まだ見てはならぬ」と両袖で隠す姿が愛らしかった。
日本の神様に西洋の神の行事はどうだろう、と思ったけれど。ワラシ様は、その外見同様、子どもの喜ぶことに目がない。クリスマスについて由来も含めて説明し、「ツリーにぶら下げた靴下に贈り物を入れてプレゼント交換をしませんか」と提案すると、「すばらしき習わしじゃ」と喜んだ。
ただし、と一つだけ条件をつけた。
「この靴下に入るものに限ります」と、橙子がこっそり編んだ編み目のふぞろいな大きな靴下をツリーに吊るすと、目を輝かせ「相わかった」と神妙にうなずいていた。
十二月屋に何を注文しはったのだろう。
大事そうにつづらを抱えるワラシ様の後ろ姿をみながら橙子は微笑む。
イモリの黒焼きでも、河童の皿でもかまわない。
だって、もう、とびっきりのプレゼントを戴いているもの。
ワラシ様、あなたの居るこの家で末永く暮らせますように。
<了>
…………………………………………………………………………………………………………………
今回も、またまた、ギリギリに。
小牧部長様、いつもありがとうございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
サポートをいただけたら、勇気と元気がわいて、 これほどウレシイことはありません♡
