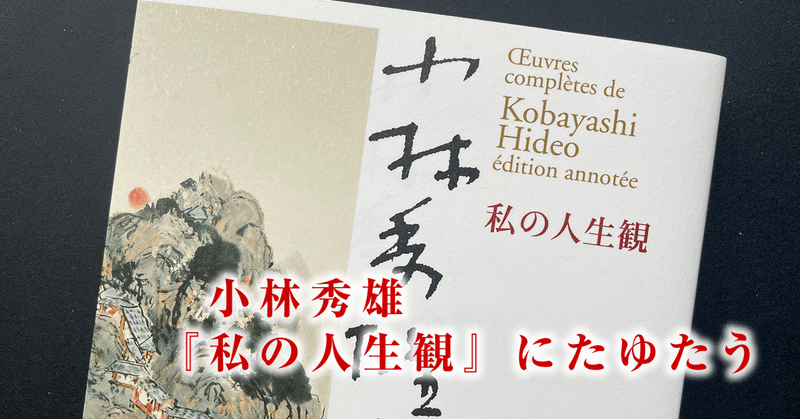
心の眼で観よ
江戸時代の剣豪・宮本武蔵が死を迎える1週間前に述べたといわれている『独行道』のなかの一つ、「我事に於て後悔せず」という言葉に触れたことをきっかけに、小林秀雄は宮本武蔵の「見の目」「観の目」について思いをめぐらせる。ここは、『私の人生観』に強い感銘を受けた人々が、必ずといっていいほど言及するところである。
本文では「細川忠利の為に書いた覚書」とあり、『小林秀雄全作品』第17集p164の注釈によれば、「寛永十八年(一六四一)に書き上げた『兵法三十五箇条』のこと」とある。これは宮本武蔵直筆の原典が残されておらず、『兵法三十五箇条』というのも通称である。ただし、これが後の『五輪書』に結びついたことは明らかであり、この「見の目」「観の目」についても同様のことが書いてある。
目付之事
目を付と云所,昔は色々在るなれ共,今伝る処の目付は,大體顔に付るなり。目のおさめ様は,常の目よりもすこし細様にして,うらやかに見る也。目の玉を不動,敵合近く共,いか程も,遠く見る目也。其目にて見れば,
敵のわざは不及申,両脇迄も見ゆる也。観見二ツの見様,観の目つよく,見の目よはく見るべし。若又敵に知らすると云目在り。意は目に付,心は不付物也。能々吟味有べし。
このような宮本武蔵の言葉について小林秀雄は、立会いで相手の方に目を付けるとき「観の目強く、見の目弱く見るべし」と要点を押さえてから、言葉の説明に入る。
見の目とは、彼に言わせれば常の目、普通の目の働き方である。敵の動きがああだこうだとか分析的に知的に合点する目であるが、もう一つ相手の存在を全体的に直覚する目がある。「目の玉を動かさず、うらやかに見る」目がある、そういう目は、「敵合近づくとも、いか程も遠くを見る目」だというのです。「意は目に付き、心は付かざるもの也」、常の目は見ようとするが、見ようとしない心にも目はあるのである。言わば心眼です。見ようとする意が目を曇らせる。だから見の目を弱く観の目を強くせよと言う。
なんと解りやすい説明なのだろう。小林秀雄の文章は難解だという評価が定着しているが、ただ知る、認知することを「分かる」、考えたうえで理解することを「解る」というように使い分けるならば、小林秀雄を批判する人たちは、きっと「分か」らないのだろうし、「解」ろうともしないのだろう。
ひとつ気になるのは「心眼」という言葉。これは『小林秀雄全作品』第17集の本文にもルビがふっていないので、講演でどのように発音したかは分からない。しかし、物事の真実の姿をはっきり見抜くことができる心のはたらきを意味する「心眼」ではないのではないか。
この『私の人生観』でも小林秀雄がすでに触れた源信(恵心僧都)は『往生要集』において「行者は心眼を以て己が身を見るに、またかの光明の所照の中にあり」と述べている。これまで、仏教思想から「観」とは何かをひたすら論じてきた小林秀雄は、考えることによって得られる智慧の力によって、肉眼では見られない物や一切の本質を見抜くはたらきを意味する「心眼」と発音したのではないだろうか。
小林秀雄にとって、この「心眼」という言葉は大切なもので、文章でも講演でも繰り返し用いている。本稿でもよく言及している『信ずることと知ること』はもともと『信ずることと考えること』という講義をもとにした「講演文学」である。
歴史は、諸君の肉眼なんかで見えるものじゃない。心眼で見るんだよ。生物学がいう眼の構造など、非常に抽象的なものです。ベルグソンは、人間は眼があるから見えるのではない、眼があるにもかかわらず見えているのだと言っているよ。僕の肉眼は、僕の心眼の邪魔をしているんだ。そして心眼が優れている人は、物の裏側まで見えるんだ。
『信ずることと考えること』は講義と、学生との対話が、いずれも音声として残っている。いま引用した箇所において、「心眼」という言葉は3回繰り返されているが、音声を確認すると、すべて「しんがん」と発音している。仏教の話をしていないので、「心眼」ではなく「心眼」でもいいのか、それとも、音としてはもともと区別してなかったのかどうかは分からないが、興味深いところでもある。
(つづく)
まずはご遠慮なくコメントをお寄せください。「手紙」も、手書きでなくても大丈夫。あなたの声を聞かせてください。
