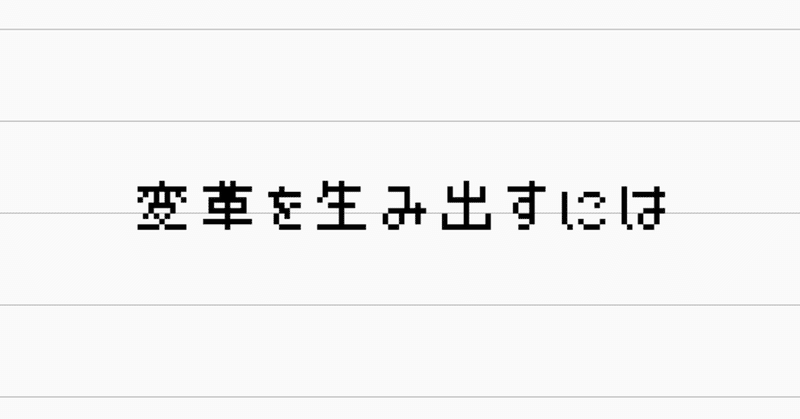
<期間限定公開>第15章:変革を生み出すには
組織変革の必要性
企業が立ち上げた事業や、事業を運営するために必要な組織は、一度出来上がったらそれで終わり、というものではありません。企業が直面している環境は日々変化しており、事業も組織もそれに合わせて変えていかなければなりません。重要なのは、常に変化する環境に対して、企業の事業や組織が適切に変わっていけるように、いかに組織が学習を続けられてるかという点にあります。
大幅な組織変革には、当然ながらトップマネジメントの関与が大きく求められます。しかし、現場から推し進められる変革もあります。組織変革において、①トップが主導して変えていくことと、②現場の変化から新しい知識を生み出していくという、二つの手法があります。組織変革は、上層部に任せていればいいものではなく、組織全体に取り組んでいく必要のある問題なのです。組織が学習していくプロセスは、組織学習(organizational learning)と呼ばれています。本章では、組織がいかにして新しい事柄を学んで変革に繋げていくのかについて、考察していきます。
組織が学ぶことの難しさ
組織学習と個人の学習の違い
組織の学習についてまず理解すべきは、組織が新しい事柄を学ぶということが本質的に難しいという点です。組織は人々の集合体であり、新しい知識を習得するのはミクロで見れば個々人です。しかし、個々の人間が学んだことを合わせれば組織学習になるわけではありません。また、仮に個人が何か新しいことを学んだとしても、それがすぐさま組織として学んだことになるわけでもありません。
一般に、組織学習には、4つのプロセスがあると言われています。
・知識獲得:組織が新しい知識を獲得すること
・情報分配:情報が共有されていること
・情報解釈:メンバー間で、ある情報に関する共通の解釈があること
・組織記憶:知識が将来利用のために蓄積され、実際に組織行動に変化が起こること
また、組織記憶には、様々な定着の形があります。そうして、組織に定着したもののことを、経営学では組織ルーチン(organization routiine)と呼びます。マニュアル、標準業務手続き、公式化、文書化された規則のように、組織内で明示されているものから、暗黙的に組織メンバーの間で共有されている、組織の文化、慣習、信念、知識、技術といったものまで含みます。すなわち、その組織にいる人が理解し、日々の作業の進め方を規定しているものが、組織ルーチンです。組織学習とは、個々のメンバーが獲得した情報が、組織内で共有された上、何らかの形でその組織の通常の「やり方」(組織ルーチン)を変化させることを意味します。組織ルーチンが変化して初めて、学習内容は個人を超えて組織に定着するのです。一度、組織ルーチンとして組織に根付かせることができれば、長期にわたって継続することが可能です。
個人の学習とは違い、組織学習においては、情報が共有され、共通の解釈が生まれ、実際に将来に活かされる形で組織に記憶されることで、初めて組織として十分に学習したといえます。
組織ルーチンのジレンマ
組織学習が本質的に難しいもう一つの理由は、組織ルーチンが安定的な性格を持っているが故に、なかなか変えづらいという特徴を有しているからです。規則やマニュアルを変更するには手間がかかります。また、組織メンバーの中には、現行の規則やマニュアルを必要と思っている人もいるので、変更しようとすることに対して抵抗されることもあり得ます。組織文化や監修に至っては、多くの人がそれを当然視しているが故に、変えようという発想自体が出てこない可能性も考えられます。
さらに、組織ルーチンの存在そのものが新規の学習を弱める効果を持ちます。組織が長期的に存続するためには、変化する環境に適応していかなければならないので、従来の知識や技術を活用して効率的に事業運営をするこ(活用)と、新しく変化した環境や技術について調査し自社の新しい可能性を探索すること(探索)の、両方が重要です。
ところが、人々が組織ルーチンに従って行動し続けると、活用は促進される反面、探索が阻害されます。継続的な活用は、現行の活動の改善を促すかもしれませんが、新しい可能性を探索こと、すなわち新規の学習を妨げるという弊害を招くのです。多くの場合、こうした組織は、こうした失敗から学ばず、また長期的なあるいは広い視野を持たず近視眼に陥ってしまうことなります。組織学習は、学習した内容を組織ルーチンとして定着させる必要がある反面、その組織ルーチンが新たな学習を阻むというジレンマを有するという点に注意が必要です。それを克服するには、どのように組織において人々が新しい可能性の探索や新規の学習を行えるかを意識的に考え、そのための手段を確保していく必要があります。
組織学習におけるトップマネジメントの役割
組織学習の本質が組織ルーチンの構築や変更であることを考えると、組織が本当の意味で学び、変わるためには、トップマネジメンの関与が必要不可欠であると言えます。ルーチンの変革とは組織の手続きや文化を変えることがであり、そのためには経営者による承認や行動が求められるからです。
トップによる関与が重要なもう一つの領域は、組織メンバーが適切に革新的な学習ができるように、組織の場を整えることです。組織が新しい環境に適応できなくなっている場合には、新しい環境に対応するように組織の価値観を刷新する必要があります。まず、組織の旧来の価値観のうち、時代おくれになったり不適合となっていたりするものを捨て去らなければなりません。このことはアンラーニング(学習棄却)と呼ばれ、新規の学習を行う上で重要なものの一つと考えられています。そして、アンラーニングのカギとなるのが組織文化の変革です。組織文化は明示的あるいは暗黙的に組織の価値観の基盤となり、組織メンバーのものの考え方や行動の基準となているからです。
しかし、組織全体に浸透している組織文化の変革は容易ではありません。多くの組織メンバーにとって組織文化は、組織に入った後に学習し、仕事を遂行する上で参照すべきものとして、当然のように組織に存在しています。解離に一人の組織メンバーが異を唱えたとしても、その人が組織全体を巻き込むような変革を成し遂げるのは非常に困難です。歴史ある組織や規模の大きな組織ほどこうした傾向は顕著になるでしょう。それゆえ、組織ぶんかの変革には、組織の上層部の主体的な関与が期待されます。トップマネジメントがアンラーニングを行い、時代に不適合な価値観を捨て去るべく組織文化を変革しない限り、組織全体を貫く価値観はなかなか変わらないものです。変革が必要とされる時期においては、組織文化の体現者であるべきトップマネジメントこそが、従来のやり方や既存の組織文化に染まらない姿勢が求められます。
学習する場としての組織
組織学習を促進するためには、以下の二点を行い、組織を整える必要があります。
既存の常識を疑う
第一に、アンラーニングのため、組織メンバーには既存の組織の目的や前提そのものを疑うことが求められます。クリス・アージリスとドナルド・ショーンは、組織における通常の学習と、組織変革を生み出すような新しい学習hの違いを、シングルループ(single-loop)とダブルループ(double-loop)と説明しています。
シングルループとは、問題解決を図り、その結果に基づいて学習することを指します。私たちは、何らかの行動をとった結果として失敗すると、そこから反省して次の行動を修正します。これがシングルループです。これに対して、ダブルループとは、結果だけでなく、既存の目的や前提そのものを疑うことで、新しい考え方や行動様式を取り組んでいくことを意味します。世の中の大きな変化に対応していくためには、従来のやり方に基づいた学習や継続的改善では不十分なことが多々あります。そこで、ダブルループ学習が求められるのですが、これを実現するのは容易でありません。
基本的に、個人の行動は、過去の経験や成功の記憶に基づいていることが多々あります。経験豊富な人ほど自分の価値観や判断に自信を持っているでしょうし、場合によっては過去の成功体験が自尊心やアイデンティティにつながっていることもあるでしょう。こうした時に、その価値観を否定されるのは、非常に嫌なものですし、つい防衛本能が働きがちです。すると、自分に批判的な厳しい意見を言う人を避けたり、自分自身でも判断の根拠をあまり疑わなくなってしまいます。こうした状況はいずれも、ダブルループが起こりにくくなります。
組織の場合、状況はより複雑です。ダブルループを阻害する要因として、アージリスとショーンは、組織には「信奉理論」と「使用理論」の二つがあると述べています。信奉理論とは、組織が表向きに「こうあるべき」と掲げ、望ましいと考えている行動規範であり、使用理論とは、組織メンバーの行動を実際に支配している行動規範です。
組織が掲げる理想と、実際には組織メンバーが行動する上で参照している行動規範とが、同じであることが望ましい状況です。しかし、建前と本音という言葉が日常的に使われることからもわかるように、現実には多くの場合信奉理論と使用理論は乖離していることが多々あります。この乖離が、イノベーションや組織変革を阻害する要因なのです。
こうした状況を防ぐのひ必要となるのは、組織メンバーが主体的に判断をして既存の使用理論の有効性を疑うことです。そこで組織には、以下の二点を考慮して組織を整える必要があります。
・広くてオープンな情報;広く有効な情報が入手可能であること。それによって、従来のやり方と新しいやり方の比較ができること
・コミットメント:メンバー自身による自由な選択が可能であり、やり方を変えてもそれに専念できること
これらの状況が整うと、既存の価値観を疑うことや自身の考えを表明することが期待でき、それによって組織内の建前と本音の矛盾を解消したり、不都合な事実の隠蔽が抑制され、効果的な問題解決にもつながることになります。実際に新規事業開発に携わる組織では、多くの企業において外部から積極的な情報収集が奨励され、またメンバーがその仕事に専念でき、かつかなりの自由度が与えられています。新しいビジネスを創造しようとするこれらの組織では、メンバーが組織の既存の常識に縛られないような体制が求められるからです。
組織学習を生み出すには、組織メンバーの価値観や認識を新しいものへと変えていかなければならず、従ってそれを可能にする状況を作り出す必要があります。そうした場において、組織内の個々人が既存の価値観に縛られずに考えられるようになることが、変革を生み出す革新的な組織学習につながっていくのです。
実践コミュニティを構築する
組織メンバーの学習について意識する必要があるもう一つの点は、学習が個人で完結するものではなく、社会的プロセスによって行われるということです。組織は多くの人々からなり、互いにやりとりすることが可能です。こうした社会的な相互作用が、個人の学習を促進あるいは阻害することがあります。一人で学習するよりも、集団で学ぶからこそ、より効果的な学習ができるのです。
では、どのような場合に、組織おいて学習を促進することが社会的な相互作用が生み出されるのでしょうか。ウェンガーは、組織学習を高める上で、実践コミュニティ(community of practice)の重要性を指摘しています。実践コミュニティをウェンガーは、「あるテーマに関する関心や問題意識、熱意などを共有し、その分野の知識や技能を、持続的な相互交流を通じて深めていく人々」と定義しています。つまり、熱意を持った人間をバラバラに存在させておくのではなく、彼らが持続的に交流できるような状態を整えることが、学習する集団を作り上げることにつながります。
このような実践コミュニティは、うまく働くと徐々に広がっていくものでもあります。新しくコミュニティに参加したメンバーは、当初は何をして良いか分からなくてお、そのコミュニティに参加し続けることで、何をすべきかを学習していきます。ウェンガーは、「正統的周辺参加」(legitimate peripheral participation)という考え方で、組織メンバーがコミュニティへの参画するプロセスと彼らが学習するプロセスが深く結びついていることを強調しています。正統的周辺参加とは、新たにコミュニティに加入したメンバーが、正規のメンバーとして(正統的)認められながらも、周辺的な役割をを担っている(周辺参加)状態のことを意味しています。周辺的な役割の遂行や古参メンバーの活動を観察することで、新規加入者は次第にコミュニティの一員としてのアイデンティティと活動に必要な知識や技能を獲得していき、参加しています。そうして一人前のメンバーとしての参加への至ります。
このように考えると、コミュニティを活発に機能させ、メンバーにとって効果的な学習の場になるためには、新規加入者が一人前のメンバーに至るまでの参加の過程に気を配る必要があることがわかります。簡単な仕事でもきちんと役割を与え、組織の正規メンバーとして遇することが、新規加入者の学習にとっては重要なのです。また、継続的に新しいメンバーが入ってくることも重要です。コミュニティにとっての新参者は、その常識に縛られない新しいアイディアの源泉であるからです。そう考えると、実践コミュニティでは、古参メンバーと新規メンバー双方の間における活発なコミュニケーションが重要であることがわかります。
新たな知識の創造
最後に、新しく学んだことを組織の中で形にしていくプロセスについて考えていきましょう。こうした活動を、知識創造と呼びます。この知識創造のプロセスについて、野中郁次郎らはSECIモデルを用いて説明しています。このモデルは、知識自体が人々の協働を通じてどのように変化していくかを説明しているのが特徴的です。
このモデルを学ぶ上で、まずは知識には暗黙知と形式知の2種類があるということを理解する必要があります。形式知とは、言葉・図・記号等で言語化された知識を指します。これに対して暗黙知は、経験や勘に基づくもので、個人としていは理解していても、言葉やその他の手段で言語化するのが難しい知識を指します。
新しい知識を生み出すためには、暗黙知が重要です。形式知化されている知識は、容易に伝達や共有が可能で、すでに世の中に出回っていることが多いのに対して、暗黙知は、他人に共有されていないがゆえに、世の中で十分に活かされいない可能があるからです。このように暗黙知は個人の中に「内面化」(internalization)されていて、他人にはわかりづらく、場合によっては当人でも自覚していないことがあります。
こうした暗黙知をどうにかして把握することが、知識創造の最初の一歩です。これを「共同化」(socialization)であり、暗黙知を有する人と直接一緒に過ごし、対話や観察を繰り返しながら暗黙知を共有していきます。この過程で、相手に共感することが重要だと言われています。相手に共感して、相手の思いや考えを理解しようと努めることによって、明示的な言葉としては十分に伝えられていないものの、その本質に迫っていくのです。
しかし、暗黙知をそのまま知識として十分に活用できないよで、試行錯誤をしながら具体的に言語化していきます。これが「表出化」(externalization)と呼ばれる過程です。問題の源泉を暗黙的に共有した後に、それを言語化するという活動です。繰り返し行ったヒアリングや観察を踏まえて、自分自身で言葉や図などの形にしていきます。
こうして言語化された形式知を、他の形式知と組み合わせながら、より体型的な知識にしていく過程が「連結化」(combination)です。言語からされたコンセプトを、社外内の知識や技術を組み合わせて実現していくという過程がこれに当たります。
そして最後に、この新たに体系化された形式知を活用する中で、組織メンバーは様々なノウハウを「内面化」し、それが次の新たな組織学習の基盤となっていきます。一度組織の問題解決を経験したメンバーは、組織運営についてのノウハウを自分なりに身につけることになります。これが新たな内面化です。
このように、知識創造プロセスは、共同化、表出化、連結化、内面化という4つの活動があります。SECIモデルは、この4つの活動の頭文字を取ったものです。一連のサイクルを繰り返すことで、組織は新しい学習を深め、変わっていくことができるとされています。このSECIモデルから、知識創造は集団的なプロセスであることがわかります。暗黙知はそれを共有している本人も表現し難いものなので、同じ時間を過ごす、密接なコミュニケーションを取る、よく観察する、とった活動を通じて、集団で共有していく必要があります。

一方で、このモデルは、集団がただ一緒に時間を過ごすだけでは新たな知識の創造には不十分であることも示しています、暗黙知はそのままでは実践可能は知識にはならないので、それを意識的に形式知として体系化していく必要があるからです。共同化・表出化、連結化、内面化の遂行には、それぞれ異なる方法を要するため、今何が必要かを適切に見極めなければなりません。
本章の内容から、環境の変化に応じて組織が変わっていくためには、既存の事業を効率的に運営する組織を整えるだけでは不十分であることがわかると思います。効率的な組織の追求が、組織メンバーの新規の学習を阻害し、硬直さを生み出してしまうことがあります。こうした状況を防ぐためには、組織のトップが主体的に関与して、組織メンバーが適切に新しい学習に取り組める場を構築する必要があります。それ同時に、組織メンバの一人一人が主体的に学習していくことも必要です。組織に変革をもたらすような学習が、トップによるものであるとは限りません。組織で働くメンバー全ての学習に変革の可能性があり、誰もが変革の主体になりうるのです。こう考えると、どれほど大規模な組織のおいても、重要なのは一人一人の組織メンバーであり、各自が組織市民として成熟しているかであることもわかるでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
