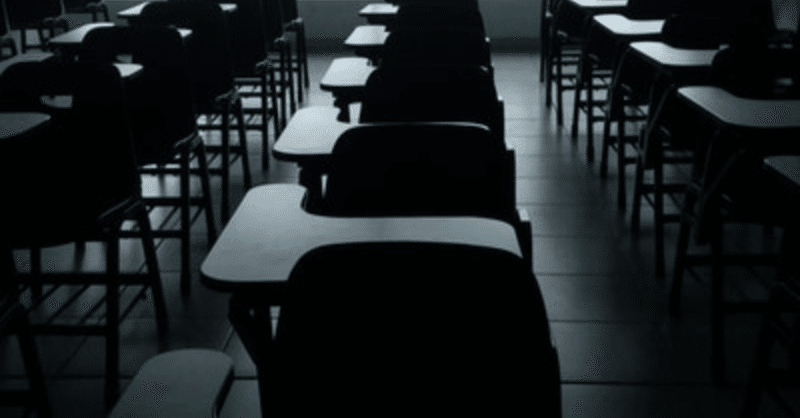
絶対善と教育とメディア
学校は何を教えるところだろうか。私は生きていく上で必要な技術を学ぶところという整理をしている。基礎学力、コミュニケーション、その中に一定の共通善の共有も含まれる。ただ、この共通善の共有は極めて扱いが難しく、特に日本は過去に全体主義体制で教育が利用されたので特に神経質になっている。
言論統制という本の中で、言論統制に強く関わった鈴木大佐の生涯が語られている。興味深いのは元々は教育者である鈴木大佐が、徐々にメディアの重要性に気づき関わっていくところだ。メディアも教育も本質的には変わらず何を善とするかを伝え、人を変えていく機関だという認識に立つ。
しかしながら、善を伝えるための仕組みとしてメディアも教育もあるのであれば、いったい善とは何かという問いに答えなければならない。この善を決める役割を中央に集め全体で統一していくのが全体主義と呼ばれるものだろうと思う。しかし、この仕組みは一度狂うと歯止めが効かない。
過去の学びから、本当に大事なルールは共有しつつ、何が良いかはその都度みんなで話し合いながら決めていきましょうという仕組みを我々は採用している。いやそもそもそういうルールだったけれど、暴走しないように箍をはめた。これはまどろっこしいが暴走は防げる。そしてこの仕組みには、そもそも絶対善などなく私たちがそれを話し合うしかないという前提に立っている。
普遍の絶対善はあるという説明をするならば、人類を超えた存在、例えば神が必要になる。しかし、神様が何が善かを決めましたという説明では、違う宗教や無神論者は納得できない。だから、いろんなことを信じている人たちが集まり、みんなでルールを決めましょうねとするしかない。
では、この仕組みを機能させる為に参加者はどのような資質が必要になるのか。それは何が正しいことかを自分で考えつつ他者とうまくコミュニケーションを取れる能力だと思う。大事なのは考える力であり、言われたとおり実行する力ではない。後者の人間が増えれば大切なことは何かという議論が成立しない。
こうしてメディアは共通善を伝達するという役割は放棄し、できる限り情報をそのまま伝えるという姿勢を取り、教育は正しいことを伝えるのではなく何が正しいかを考えさせるという姿勢をとったと私は認識している。その仕組みによって多様な価値観が生まれ、善について語りながらルールを調整していく。
歴史的にみると、ただ一つの正しいことで全体を統一しみんなを幸せにするんだという純粋な思いからくる行動は、いつも暴力的な最後を迎えてきた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
