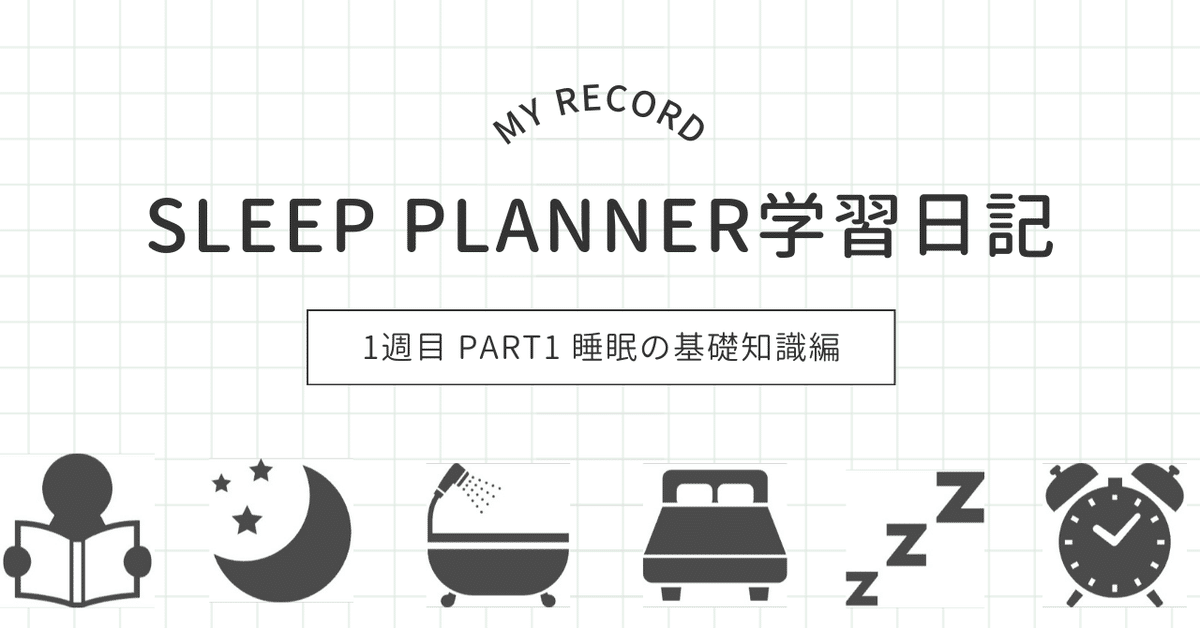
SLEEP PLANNER 学習日記1週目
こんにちは。
山下大輔です。
社会人2年目24歳の時以来、18年ぶりの資格勉強を開始します。
資格を取ることが目的ではなく、学んだことを身につけるために記録をつけることにしました。
Part 1:睡眠の基礎知識
1:睡眠と疾病について
睡眠不足により、「肥満」「感染」「がん」「精神疾患」などの悪影響がある。
肥満
睡眠不足により、食欲を更新させるグレリンが増加して、食欲を抑制するレプチンが減少するため、肥満につながる。
感染症
風邪の発症率は、睡眠時間が5時間未満の人たちは7時間以上の人に比べておおよそ3倍になる。
また、睡眠時間が少ない場合には、予防接種の効果が十分に発揮できないという報告がある。
がん
睡眠不足により、免疫細胞が減り、免疫反応は低下する。
がんを促進する慢性炎症や、細胞ストレス、血管新生に関連する多くの遺伝子を活性化させる。
乳がん→平均睡眠時間が6時間以下では、7時間と比較して1.6倍高くなる。
前立腺がん→睡眠時間が7~8時間と比較して、6時間以下では発症率が高くなり、9時間以上では発症率が半分以下になる。
精神疾患
睡眠不足が原因で、情動を司る扁桃体がネガティブな情動刺激に対して過剰反応を示すようになる。
要因は、感情が暴走しないようにブレーキをかける脳内の前帯状皮質と扁桃体の機能的接続性が弱まること。
2:睡眠のメカニズムについて
睡眠の種類
1953年、睡眠は、大脳が2つの状態から構成されることが発見される
レム(Rapid Eye Movement=急速眼球運動)睡眠。とノンレム睡眠。

入眠してから、レム睡眠とノンレム睡眠を繰り返し、朝にかけてレム睡眠が増えてくる。
ノンレム睡眠の中でも入眠時の最初のノンレム睡眠が一番深い眠りで、だんだん浅くなっていく。
入眠時の最初のノンレム睡眠の質を高めていくことが睡眠の質を上げる。
『睡眠周期=90分、起きる時間から90分単位で逆算すると良い』という説があったら、実際には睡眠周期は一定ではないため、効果的ではない。
睡眠の役割
1:大脳の休息
2:記憶の整理し、定着or消去する。
3:睡眠不足になると休息されず、脳内の老廃物が排出しないとアルツハイマーの原因になる。
加齢と睡眠との関係
1:睡眠時間の短縮
2:眠りが浅くなる。
3:加齢が進むについて、記憶や注意力が低下、意欲や感情のコントロール機能が低下する。
女性、赤ちゃん、子供、ペット
それぞれの特徴があり、正しく理解する必要がある。
女性:生理周期に影響がある。
赤ちゃん:月齢年齢ごとに必要な睡眠時間が異なり、だんだん短くなっていく。
子供:睡眠不足は、病気がかかりやすくなり、脳の発達に影響がある。
学力や運動能力も下げ、情緒が不安定になったり、食欲のコントロール力が下がり、肥満の原因になる。
ペット:人と睡眠周期が異なり、分割睡眠をとるため、互いに影響を与えないようにする必要がある。
睡眠に関するなんとなくの知識から正しい知識へ
『睡眠周期=90分、起きる時間から90分単位で逆算すると良い』という説を信じていた部分があったが、それでは意味がないことを学びました。
一部正しくて、一部間違っているというなんとなくの知識ではなく、
正しく理解することが、良い睡眠をとることにつながることがわかったので、引き続き、勉強を続けていきます。
合同会社ChStyle
山下大輔
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
