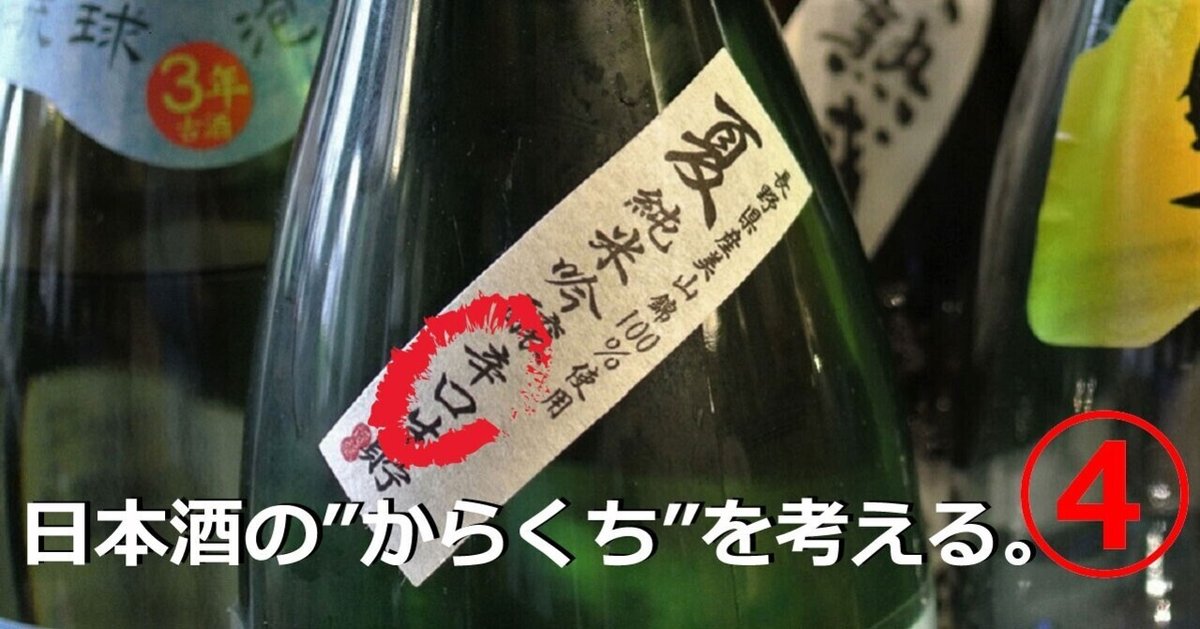
日本酒の”からくち”を考える。④
●ラベルに”辛口”と書いてあっても思ったほど辛口に感じない!?
日本酒のラベルに”辛口”と表記されているものを見かけることがあるかと思います。辛口のお酒なんだ!と思って買ってはみたものの、実際に飲んでみると一緒に買った辛口と書いてないお酒の方がむしろ辛く感じる、といったこともしばしばです。
これは日本酒のラベル表記における辛口表記は絶対評価に基づく表記ではなく、相対評価に基づく表記であることが原因となっています。いわば当社比でこのお酒は辛口ですよ、というものです。そのお酒の醸造元のラインナップの中で、スタンダードなお酒、プレミアムなお酒、デイリーユースのお酒、と様々ある中で当蔵のラインナップにおける辛口の位置づけのお酒はこれですよ、というニュアンスです。なので、違う醸造元のお酒同士を比べるとそれぞれの基準が異なっているので、A蔵の辛口酒よりB蔵のスタンダード酒の方がより辛口だ、というケースが出てきます。
もともと日本酒は地産地消の側面が非常に強く、地元に流通するお酒はその地元の醸造元のものがほとんどでした。当然銘柄が入り乱れることもなく、当社比の表記で問題ありませんでした。しかし現在は流通網が発達し、ECもこの1~2年でより浸透し定着して、誰もが各地方のものを容易に手に入れられるようになってきました。辛口度合いの絶対評価をすることは非常に難しいと感じますが、少なくとも当社比による記載に関しては、今後どうしてくかを考えるタイミングに来ているように感じます。
●”日本酒度”
辛口度合いをはかる数字の一つとして旧来より使われているものに「日本酒度」というものがあります。日本酒度は、糖分が多いと比重が重くなる性質を利用して水分中の残存糖度を数値化しているもので、水を0として辛口は+、甘口は-で表します。残存糖度を表している指標ではありますが、実際に飲んだ時の味わいは糖と共に含まれる他の成分とのバランスによって変わってくる部分が大きく、一概に日本酒度が高いから辛口であるとは言い切れません。ラベルに日本酒度の表記があった場合も、判断材料の一つとして酸度や他の要素と合わせて考えあわせていくべきです。

●脱”からくち”の時代
1980年代に辛口日本酒ブームというものがあり、淡麗辛口の日本酒が一世を風靡しました。時代はバブル最盛期を迎え、軽快さや明快さが良しとされる時代でした。アサヒスーパードライが1987年に辛口をセールスポイントに売り出されるに至ったのも必然性がありました。豊かな時代を背景にこれまでの安価で甘口の三増酒を忌避して、その反動から本格派の辛口のお酒に価値が置かれた側面もあるかと思われます。
しかし90年代初頭にバブルがはじけ、それ以降は清酒の出荷量も右肩下がりの状況が続いていきます。バブルがはじけた影響を残しながらも、狭くなっていくマーケットに対して2006年には三増酒の製造を法律的に製造できなくする変革もあり、環境面での変化と共に現実を受け入れながら頑張る若い世代による新しい動きが出てきます。
そんな中で2010年代を迎え、2000年代からの取り組みが徐々に結実して本格派の日本酒、特定名称酒の復権が起こり日本酒ブームを迎えます。現在では嗜好性の多様化、商品の多様化が受け入れられていて、かつてとは違い辛口に限らず様々なタイプで質の高いお酒が選べるようになってきています。
正に脱近代、脱からくちの時代を迎えている(すでに数年前に迎えていた)と言えます。この点を飲み手も売り手も意識して多様な日本酒を楽しむようアップデートしていった方が、より豊かに日本酒を楽しめるようになっていくのではないかと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
