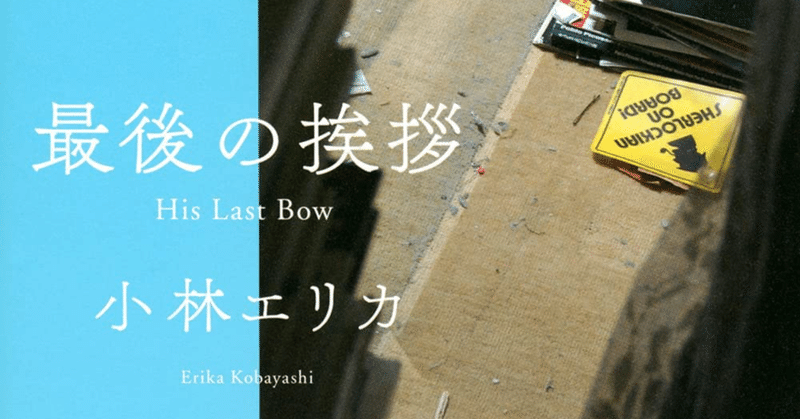
小説に穿たれた鏡合わせの滝 小林エリカ『最後の挨拶 His Last Bow』(講談社)
小林エリカが『最後の挨拶 His Last Bow』と題した小説を発表した時「これは読まなければならない」と身構えたひとがどれほどいたでしょうか。幸運なことに、私はそのひとりでした。
日本シャーロック・ホームズ・クラブを結成するほどのシャーロキアン(シャーロック・ホームズ愛好家)であり河出書房新社版『シャーロック・ホームズ全集』を共訳した小林司・東山あかね夫妻。かれらの子女であり、複数の領域にまたがった創作活動を展開して、小説「マダム・キュリーと朝食を」では第27回三島由紀夫賞ならびに第151回芥川龍之介賞の候補に選ばれた著者が「最後の挨拶」と題した小説を書いたこと。正題だけでなく副題として置かれた「His Last Bow」も、言うまでもなく宿敵モリアーティ教授とシャーロック・ホームズがライヘンバッハの滝で格闘した有名な短編小説の原題にあたります。否が応でも期待は高まるというものです。
「最後の挨拶 His Last Bow」を読み始めると、戦前の少年期から始まる父の個人史、語り手であり末娘にあたるリブロの誕生を軸とした家族史、そして家族が看取る父の最期が順繰りに語られていき――それらがトリニティを形成していることに気付きます。並行する三つの物語はそれぞれ異なる時を往還して、父の個人史は家族史に、家族史は父の最期に繋がっていく。そのようにして徐々に浮かびあがってくるのは、ひとつの大きな家族小説(ファミリー・ロマンス)です。
語り手にリブロという名前が与えられていることからも窺えるように、三つの物語を含む本作を読んでいると、本への愛にやさしく包みこまれている心地がします。書物へのひとかたならぬ親しみがあるからこそ、父の最期に至るまでの家族の物語だというのに、エスペラント語の参考書が繋ぐ冗談のようにドラマチックな両親の出会いや、シャーロキアンたちがライヘンバッハの滝を見に行く仮装旅行など、随所に微笑ましいエピソードにあふれているのでしょう。
均整のとれた構成でかたちづくられた家族小説の枠には、しかし作者みずからの手で、ふたつの穴が穿たれています。ひとつは、冒頭の引用に始まり章題にも敷かれているシャーロック・ホームズの冒険譚。もうひとつは、東北大震災です。物語が綺麗に纏まることを拒むかのように、虚構と現実の双方から穿たれた穴は鏡合わせのようでもあり、ホームズをのみこんだライヘンバッハの滝壺さえ想い起こさせないでしょうか。
一方の“穴”にあたるシャーロック・ホームズの冒険譚は、この物語をあくまでフィクションに引き寄せる役割を担っています。家族史を家族小説にするために、本来であれば小林エリカ本人であるはずの語り手のポジションが架空の人物に与えられていることも含めて、作者は読む側が受ける印象よりも慎重に、家族史という現実を家族小説へと虚構化させる手順を踏んでいるようにも思えます。
そのうえで、三本の糸が、しなやかな一本の糸となって編まれて終わってもよかった物語に、エピローグのようにして東北大震災という現実が穿たれているのも、この物語を完全な虚構に陥らせない強い意志を感じさせます。
シャーロック・ホームズは作者みずからの手によってライヘンバッハの滝にのみこまれて死んだ筈が、あろうことか甦ってワトソン博士の前に、そして読者の前にふたたび姿を現します。しかし実のところアーサー・コナン・ドイルが直接復活の活躍譚を書くまでもなく、読者が存在する限り、ホームズに本当の死が訪れることはなかった筈です。登場人物は永遠に生き続けられるのだから。また本を開けば、いつでもそこに。
デス博士は微笑する。「だけど、また本を最初から読みはじめれば、みんな帰ってくるんだよ。ゴロも、獣人も」
「ほんと?」
「ほんとうだとも」彼は立ちあがり、きみの髪をもみくしゃにする。「きみだってそうなんだ、タッキー。まだ小さいから理解できないかもしれないが、きみだって同じなんだよ」
しかし「最後の挨拶 His Last Bow」を読み返す私たちの前にリブロの父親が再び現れたとしても、作者の父親が帰ってくることはありません。「私」を書く虚構と現実のせめぎあい。それは愛らしくも悲しい家族小説(ファミリー・ロマンス)の底を流れる、小説家の葛藤でもあります。滝壺に落ちるようにして私たちもまた、絶えず虚構と現実のはざまを漂いながら「最後の挨拶 His Last Bow」という小説を読んでいる時間だけは、鏡の向こう側にいる作者と同じ感情をわかちあい、不思議な明るさに包まれるのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
