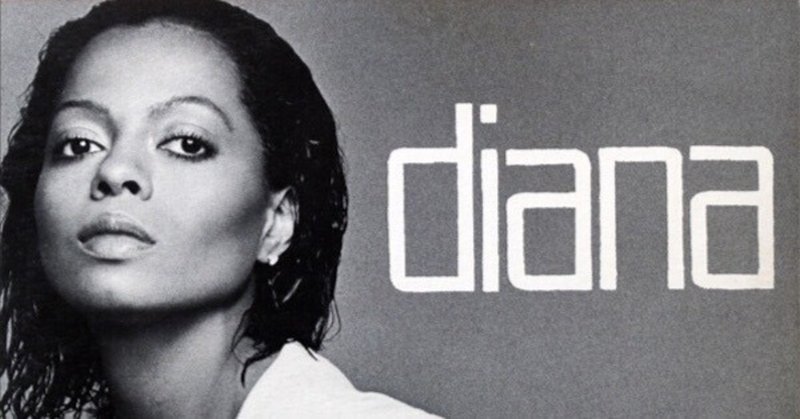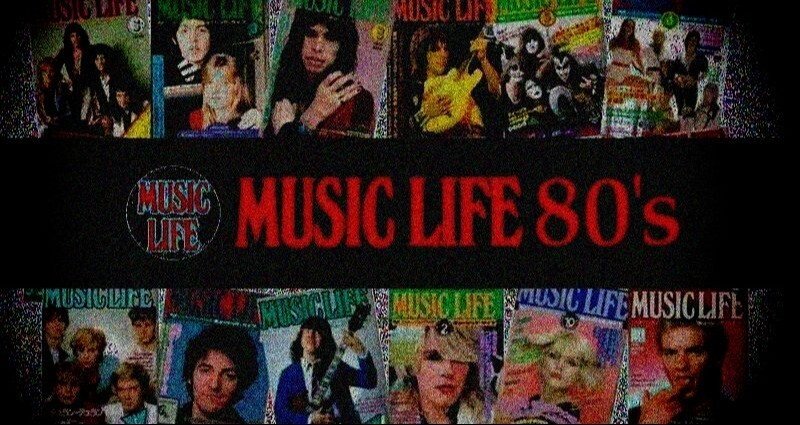
about 80's Music... ファントマ、ミュートマ、SONY MUSIC TV、ベストヒットUSAで形成された“昭和40年男”のお気に入りから厳選した記事などをひとま…
- 運営しているクリエイター
#洋楽

【名盤伝説】”Luther Vandross / Never Too Much” 真打登場 究極のメロウヴォイスを堪能しましょう。
MASTER PIECE US出身のR&Bシンガールーサー・ヴァンドロスのソロデビューアルバム『ネヴァー・トゥ・マッチ』(1981)です。 幼い頃から地元でシンガーとして活動し、プロダクションに所属して様々なミュージシャンの作品に参加していました。1974年にはUKグラマラス・ロックの大スターデヴィッド・ボウイのアルバムにバックアップ・ボーカルとして参加、75年にはブロードウェイ・ミュージカル「ウィズ」には自身の楽曲が採用されています。 その後、ダイアナ・ロス、ロバータ・

【名盤伝説】”Stevie Wonder / Hotter Than July” 灼熱の日々をポップなダンスチューンで乗り切るのだ!
お気に入りのミュージシャンとその作品を紹介しています。泣く子も黙るソウル系SSWのスティーヴィー・ワンダー。1980年リリースの19作目のオリジナルアルバム『ホッター・ザン・ジュライ』です。 スティーヴィーといえば名盤多数、ヒット曲は数知れず、R&B界屈指のヒットメイカーです。特に『Talking Book』(1972)や『Songs In The Key of Life』(1976)は超名盤。この『キー・オブ…』に続く4年振りのオリジナルアルバムが、この『ホッター…』にな

【名盤伝説】“Narada Michael Walden / The Dance of Life” ジャズ・ファンク界の名ドラマー&プロデューサーによる都会派ダンス・ミュージック。
MASTER PIECE ナラダ・マイケル・ヴォルデンは1952年USミシガン州出身のドラマー&プロデューサーです。10代の頃からセッションマンとして活動し、超絶テクを誇るジャズ・フュージョン・ユニットのマハヴィシュヌ・オーケストラにビリー・コブハムの後釜ドラマーとして参加するなど、その技量は折り紙つきでした。後にリッチー・ブラックモア脱退後のディープ・パーブルに参加する悲劇のギタリスト、トミー・ボーリンのバンドでもプレーしています。 1975年からソロ名義でも活動を始め、