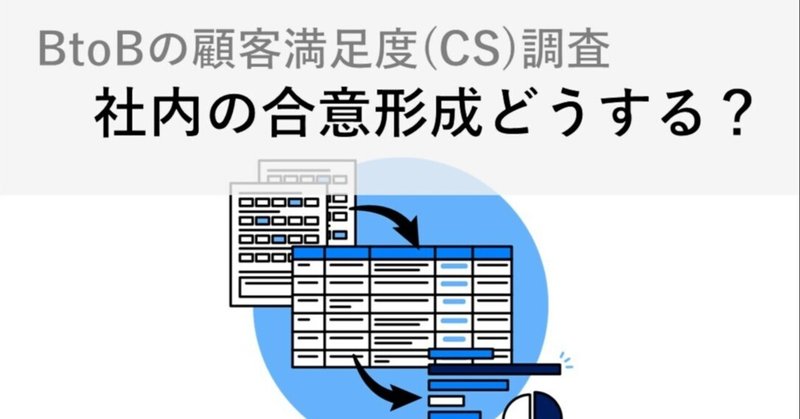
BtoB企業でも顧客満足度調査をやってみたい。でも社内で反対意見がある場合の対処方法②
前回に引き続き、顧客満足度(CS)調査を始める際の一番最初で一番大きな壁である、社内の合意形成について書きます。
前回は「それ何のメリットがあるの?」に対する考えを書きました。
端的に言うと「分かりやすいメリットの有無よりも自社にとって意義があるか?で判断しませんか」という話でした。
100%の合意形成が必要なのか?
社内で初となる試みを実行する際に、社内が100%合意形成できるケースは稀です。すぐに思いつけて全員が合意するような取り組みは、すでに実行されているからです。
新しい施策に対する組織やチームの反応を、私はキャズム理論の応用で考えています。
新しいものを使いたがるイノベーターから、アーリーアダプター、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティまで(企業で考える時はラガードは入れません)。
レイトマジョリティはCSのような施策には懐疑的で当然です。
社内の誰かの提案内容を全員がすぐに合意する(鵜呑みにする)組織のほうが問題があります。
慎重なレイトマジョリティも、納得して効果が分かれば動いてくれるので、最初に巻き込む層ではない、というだけです。
複数の専門性を持った人が集まる企業という場において、全員の納得をすぐに得ることは困難です。特に、やってみないと効果がはっきり説明できない施策の場合は尚更です。お客様に自社やサービスの評価を聞く、という施策もこの分類に入ります。
新しい施策のはじめかた
私たちが勧めるのは、
・「納得はできないが理解はした」という信頼関係に基づく合意
・トライアルの実行(1サービスや1部門での先行実施)
・先行者が得たノウハウの共有と、教育・啓蒙活動
この3つです。
LTSの主業である企業変革を目的としたコンサルティングでも、ほぼ同様のアプローチをしています。
もし、CS調査に限らず新しいチャレンジをはじめたいのであれば
「〇〇をやってもいいですか?」ではなく
「〇〇をやりたいです。私たちの部署で試験的に実施して報告します」
という宣言をしましょう。
大事なのは、変化そのものはゆっくりでもいいので、まず小さく始めること。そして、経営層などステークホルダーには定期的に報告をすること(進んでいなくてもいい)。許可をもらう・100%の合意を待つ、という責任の放棄や共有をやめること、です。
実際にCS調査を始める場合
社内の反対意見やメリット提示を求める声への対処は前回~今回書いた通りです。意義や目的を決めて(仮置きして)、あとは実際に始めてみた結果からフィードバックして再定義するのがよいと思います。
とはいえ、どんな課題を解決できるのか?目的は?という部分の疑問は残ると思いますので、簡単に書いて終わりにしたいと思います。
前半の記事にも書きましたが、お客様の声の活かし方は企業の状況によって異なります。ザックリ定義すると、
・創業直後→サービス開発(顧客のフィードバックが有効なサービスなら)
・事業成長化フェーズ→現状把握やサービスの課題発見のため
・組織拡大フェーズ→優良顧客識別、自社サービスの価値再発見のため
・ブランド構築フェーズ→マーケティング活用
このような活用イメージになります。
(このテーマはもう少し深掘りして、別の記事として書こうと思います)
自社の場合はどう活用できそうか?などの相談があれば、私たちも一緒に考えますので、気軽に連絡頂けると嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
