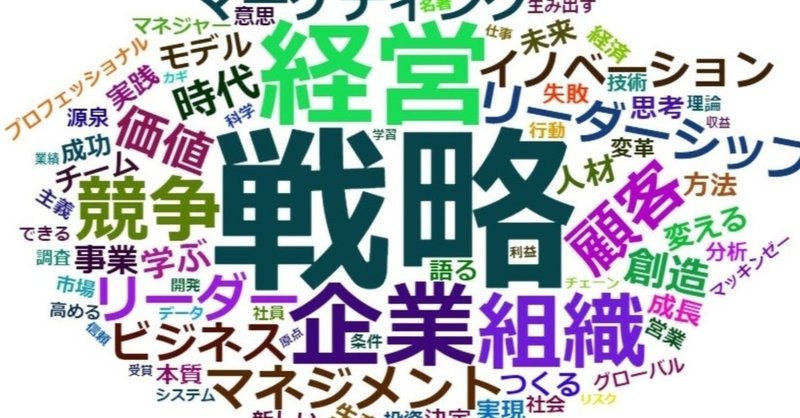
【マルコフチェーンって知ってる?】本を読んでわからんかった言葉をググった。
どうも、クレドシップの緒方です。
ここ最近、ビジネス本を何冊か読んでて、わからんかった単語を一気に調べてみました。
得にマーケティング用語っていろいろありますね、頭文字省略はむずい。
完全に覚える必要もないのでしょうけど、ググるの大切ですね。
ググるのは21世紀の教養科目と思ってます。
わからんことをわかるのが、一番むずいですね。
以下何個知ってましたか? 何個も知ってた人、後学のため普段どんな本読んでるかぜひコメントください!
マルコフチェーン
Markov chainとは、確率過程の一種であるマルコフ過程のうち、とりうる状態が離散的(有限または可算)なもの(離散状態マルコフ過程)をいう。また特に、時間が離散的なもの(時刻は添え字で表される)を指すことが多い(他に連続時間マルコフ過程というものもあり、これは時刻が連続である)。マルコフ連鎖は、未来の挙動が現在の値だけで決定され、過去の挙動と無関係である(マルコフ性)。各時刻において起こる状態変化(遷移または推移)に関して、マルコフ連鎖は遷移確率が過去の状態によらず、現在の状態のみによる系列である。特に重要な確率過程として、様々な分野に応用される。
RFM分析
RFM分析とは、Recency (直近いつ)、Frequency (頻度)、Monetary (購入金額)の3つの指標で顧客を並べ替え段階的に分け、顧客をグループ化した上で、それぞれのグループの性質を知り、マーケティング施策を講じる手法です。「直近いつ」という概念が入っているので、デシル分析のように過去に一度だけ高額商品を購入した顧客と、最近少額だがたくさん購入してくれている顧客が同一グループに入るようなことはなく、明確に分けて分析することができます。
https://www.albert2005.co.jp/knowledge/marketing/customer_product_analysis/decyl_rfm
Deploy
配備する、配置する、展開する、配置につく
システム開発におけるデプロイとは、開発したアプリケーション(機能やサービス)をサーバー上に展開・配置して利用できるようにすることです。
Webアプリケーションであれば実行ファイルをWebサーバーやアプリケーションサーバーにアップロードして、その実行ファイルを実行することでサーバー上でアプリケーションを動くようになり、ユーザーが利用できる状態になります。この一連の作業がデプロイです。
つまりは、
実行ファイルを動かしたい環境に置く
実行ファイルを実行する
これらを行うことがデプロイです。
https://engineer-club.jp/deploy
リカレント教育
recurrent education リカレント教育とは、生涯にわたって教育と就労のサイクルを繰り返す教育制度のことです。 リカレント(recurrent)とは「反復、循環、回帰」を意味するため、リカレント教育は日本語では「回帰教育」「循環教育」などと表現します。
主に学校教育を終えた後の社会人が大学等の教育機関を利用した教育のことを指す。生涯教育を受けて発展した概念であり、職業能力向上となるより高度な知識や技術、生活上の教養や豊かさのために必要な教育を生涯に渡って繰り返し学習することを意味する。これには、仕事に就きながら必要な知識や技能を習得する教育訓練を行うOJT、仕事を一時的に離れて行う教育訓練(OFFJT)も包含されている。
XGboost
勾配ブーストを用いた決定木(GBDT)によるクラス分類や回帰はデータ分析コンペでも非常によく使われています。その中でも2016年に出されたXGBoostはLightGBMと並びよく使われている手法です。
LightGBM
LightGBMは、Light Gradient Boosting Machineの略で、元々Microsoftによって開発された機械学習用の無料のオープンソース分散型勾配ブースティングフレームワークです。これは決定木アルゴリズムに基づいており、ランク付け、分類、その他の機械学習タスクに使用されます。
GUIツール
Graphical User Interface あるいは、ウィジェット・ツールキット (widget toolkit) とは、グラフィカルユーザインタフェース (GUI) を構成する部品の集まりである。通常、ライブラリやアプリケーションフレームワークの形式で実装される。分野によって、ウィジェットはコントロール、コンポーネントとも呼ばれる。デスクトップアプリケーションの作成に用いられる。
SECIモデル
SECIモデルとは、野中郁次郎教授(一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授)が提唱した、知識創造活動に注目した、ナレッジ・マネジメントの枠組み。個人が持つ暗黙的な知識(暗黙知)は、「共同化」(Socialization)、「表出化」(Externalization)、「連結化」(Combination)、「内面化」(Internalization)という4つの変換プロセスを経ることで、集団や組織の共有の知識(形式知)となると考える。
「共同化」とは、経験の共有によって、人から人へと暗黙知を移転することである。「表出化」は、暗黙知を言葉に表現して参加メンバーで共有化することである。「連結化」は、言葉に置き換えられた知を組み合わせたり再配置したりして、新しい知を創造することである。そして「内面化」は、表出化された知や連結化した知を、自らのノウハウあるいはスキルとして体得することである。
ナレッジ・マネジメントでは、SECIのプロセスを管理すると同時に、このプロセスが行われる「場」を創造することが重要である。
SEDA人材
意味的価値と機能的価値の両方を合わせた統合的価値を考える枠組みとして「SEDAモデル」を紹介します。SEDAはサイエンス(Science)、エンジニアリング(Engineering)、デザイン(Design)、アート(Art)の頭文字です。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO13918680Q7A310C1KE8000
SEDAモデルでは、意味的価値における問題提起として、右上にアートを位置付けます。デザインとアートの違いは、顧客の要望に合わせるのがデザインで、自らの哲学や信念を表現するのがアートです。
機能的価値について問題解決と問題提起が必要なのと同様、意味的価値についても両方が必要です。顧客が主観的に意味づける価値を商品・サービスに反映させるのがデザインであり、顧客に新しい意味を提案するのがアートなのです。

最近読んだ本たち
クレドシップでは、人材開発についてのご相談や異業種間ディスカッション絶賛ウェルカムです!
→ jun.ogata@credo-ship.com
人材業界の見立てについてレポートまとめもしていますので、ぜひ少しでもお悩み、ご相談、等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。ぜひとも一緒にお悩みを分かちあい、お力に慣れたら幸いです。
~~~~~~~~~~~~~~
クレドシップでは、求人代理店、人材派遣会社などでのHR業界に特化した新規開拓営業を支援するSFAアプリ「シエスタ」を提供していたり、社内研修などを行っております。
ご連絡はお問い合わせフォーム、
もしくはinfo@credo-ship.co.jp、
もしくは板井やクレドシップメンバーをご存知の方は直接ご連絡していただいても構いません。
まずはラフぅにお話をさせて頂ければと思っております。
どうぞよろしくお願いします!!
~志を企てる~| 株式会社Credo Ship.
キャリア教育事業、ビジネス研修事業、ビジネスコンサル事業を提供しています。
https://www.credo-ship.co.jp/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
