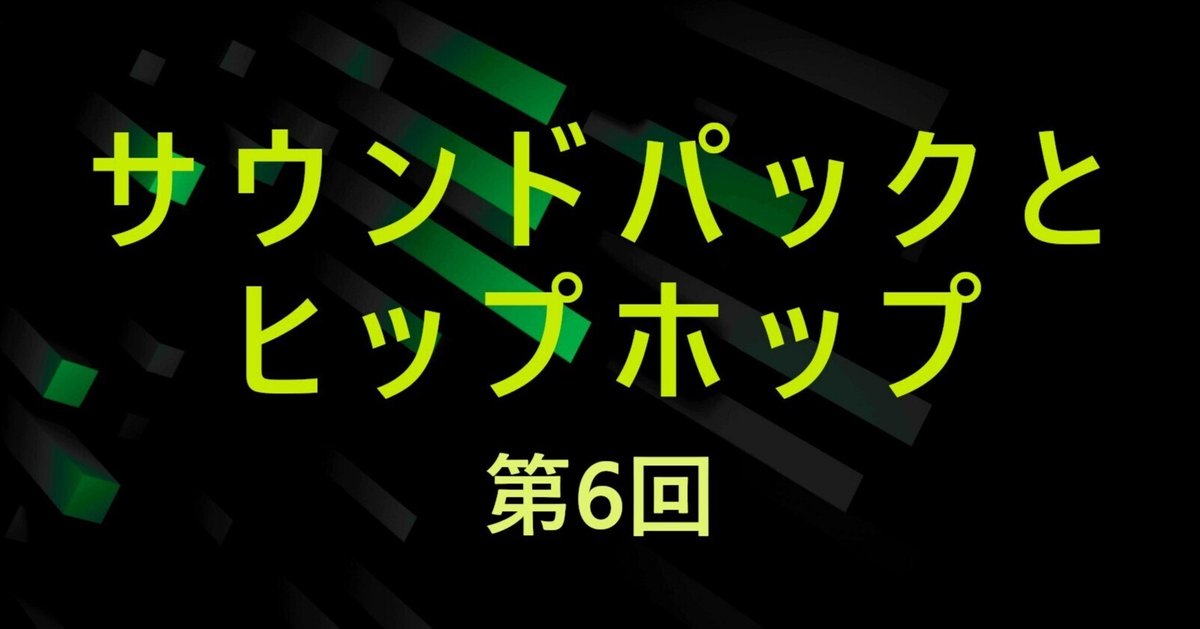
「ヨレ」だけではないJ Dillaサウンド、その音色の多彩さが与えた影響【サウンドパックとヒップホップ 第6回】
私が「サウンドパックとヒップホップ」と「極上ビートのレシピ」の連載を行っていたメディア「Soundmain Blog」のサービス終了に伴い、過去記事を転載します。こちらは2022年3月18日掲載の「サウンドパックとヒップホップ」の第6回です。
なお、この記事に登場する曲を中心にしたプレイリストも制作したので、あわせて是非。
音楽史に残る偉人、J Dillaが再び話題
日本を代表するスーパースター、星野源がNHKで始めた音楽番組「星野源のおんがくこうろん」が大きな話題を呼んでいる。特にヒップホップリスナーの間で。歴史を変えた音楽家にスポットを当てた同番組の第1回で、デトロイトのプロデューサーである故J Dillaを取り上げたのだ。
J Dillaはリズムを整える「クオンタイズ」を使わずにビートを作り、揺らぐ心地良さを提示したことで知られている人物だ。星野源も同番組で取り上げたソロ作「Donuts」やD’angeloの「Voodoo」など関わった名作の数々は多くのアーティストに影響を与えた。
そんな音楽史に残る偉人であるJ Dillaのドラムは、その特徴的なリズムの組み方だけではなく鳴りの面でも多くのビートメイカーから愛されている。Spliceで提供されている公式(!)の「The Fantastic Sounds of Jay Dee AKA J Dilla」のほか、J Dillaからインスパイアされたドラムキットも非常に多く世の中に出回っている。今回はそんなJ Dillaの魅力を掘り下げ、その試みからサウンドパック活用のヒントを探っていく。
多彩なサンプリングソースから生み出される豊かな音色
J Dillaについてビートの揺らぎ以外によく指摘されるのが、そのサンプリングソースの幅広さだ。数多い代表作の一つ、2001年にリリースした『Welcome 2 Detroit』の収録曲「BBE (Big Booty Express)」では、Kraftwerkをサンプリングして地元デトロイトの名前を冠したタイトルにふさわしいテクノの要素を注入。そのほかSlum Villageが2000年にリリースしたアルバム『Fantastic Voyage Vol. 2』では冨田勲をサンプリングするなど、どんなジャンルでも貪欲にそのビートに取り込んでいった。
現在はこういった幅広いサンプリングソース選びは当たり前だが、ジャズやファンクといった生演奏のオーガニックなジャンルからのサンプリングが基本だったブーンバップの文脈で、1990年代からこういった試みを行っていたことはかなり先進的だったと言えるだろう。また、J Dillaのキャリアやビートの魅力を解説した書籍『J・ディラと《ドーナツ》のビート革命』では、「CDからはサンプリングしない」、「ヒップホップからはサンプリングしない」といった当時のサンプリング・ヒップホップにおける常識をJ Dillaが打ち破っていたことが指摘されている。もしJ Dillaがこういった常識にこだわっていたら、サウンドパックの浸透も遅くなっていたに違いないだろう。
この多彩なサンプリングソースの選び方は、必然的に豊かな音色をJ Dillaのビートにもたらした。J DillaをフックアップしたA Tribe Called Questが1998年にリリースしたアルバム『The Love Movement』では、TOWA TEI「Teachnova」をサンプリングした「Find A Way」などで浮遊感のあるサウンドを提示。先述したSlum Villageの冨田勲ネタ曲「Climax」も近いタイプの心地良さを備えたビートだ。こういった宙に舞うような美しさは、DrakeやFrank Oceanなどが2010年代に進めた流れの先駆けとしても楽しめる。
こういったメロウなビートも得意とし、近年はローファイ・ヒップホップのルーツとして語られる機会も増加傾向にあるJ Dillaだが、攻撃的なビートも多く作っていた。遺作となった2006年リリースの『The Shining』では、冒頭を飾る「Geek Down」からワブルベースやエレキギターのようなエッジーな音使いを披露している。また、かつて1st Downというデュオで共に活動した元相方ラッパーのPhat Katが2007年にリリースしたアルバム『Carte Blanche』では、テクノ的なエレクトロニックな音使いで緊張感たっぷりに仕上げた「Nasty Ain’t It?」やミニマルで荒々しい「Cold Steel」などを制作。Phat Katの鬼気迫るラップとのコンビネーションは多くのリスナーを魅了した。
J Dillaのこれらの試みは、WajeedやBlack Milkなどの周辺プロデューサーと共にNYや西海岸とは異なるデトロイトのスタイルを作り上げていった。近年はBabyface Rayや42 DuggのようなEastside Chedda Boyzなどの系譜にあるデトロイト出身者が多く活躍しているが、J Dilla的なスタイルをデトロイトの音として浮かべる方も多いだろう。J Dillaと仲間たちの取り組みには、それだけの大きなインパクトがあったのだ。
カラーをキープしつつ異なるスタイルに挑戦する姿勢がビート制作のヒントに
J Dillaの作風はブーンバップやネオソウルの文脈に留まらない。同郷のラップデュオのFrank N’ Dankが2003年に制作したアルバム『48 Hours』では一切のサンプリングを使わずに808も取り入れたバウンシーなビートを披露。「All Seasons」ではGファンクにも挑んでいる。
また、J Dillaの2003年といえばMadlibとのユニット、Jaylibでのアルバム『Champion Sound』のリリースもあった。同作でも「Raw Shit」でGファンク的なシンセベースが効いたビートを披露しており、J DillaのGファンク愛が確認できる。
そのほかにも2000年代前半に制作されたアルバム『The Diary』でも「Trucks」でGファンクに挑んでおり、40 Gloccが2011年にリリースしたミックステープ『C.O.P.S: Crippin’ on Public Streets』収録の「Feels Good To Be A Gangsta」で同様のビートを聴くことができる(なお、「Trucks」のビートは2016年にSnoop Doggが「My Carz」で使用している)。こういった曲でもJ Dilla独自のドラムや質感はしっかりと発揮されている。自身のカラーをキープしながら、普段のイメージとは異なるスタイルに挑戦するその姿勢は、今日のビート制作においても大きなヒントになるのではないだろうか。
その後のシーンの見取り図に与えた影響についても補足しておこう。Dr. DreやSnoop Dogg、Madlibは西海岸のアーティストだ。この西海岸とデトロイトの交流は、Aftermathに所属していたラッパーのBishop Lamontと、J Dilla周辺プロデューサーのBlack Milkによるコラボプロジェクト「Caltroit」に繋がった。Icewear VezzoやSada Babyといった現行デトロイトの人気ラッパーの多くは、ALLBLACKやDrakeo the Rulerなど西海岸勢とサウンドとシーンを共有しているが、J Dilla周辺のこの動きはその先駆けと言えるだろう。
J Dillaとハイパーポップ、そして未来
多彩なサンプリングソース選びや自由な発想、そして他アーティストとの交流などで多くの名作を生み出したJ Dilla。先述した『J・ディラと《ドーナツ》のビート革命』で翻訳を担当した批評家/ビートメイカーの吉田雅史は、「ディラにとってはサンプルはあくまでサウンドの欠片であって、その歴史性などは関係なく、どれもがフラットに並べられている」と指摘しているが(参照:Real Soundの記事「『J・ディラと《ドーナツ》のビート革命』訳者・吉田雅史に聞く、ヒップホップ批評の新たな手法」)、この歴史性を感じさせずにフラットにミックスする感覚は現代の先端的なエレクトロニック・ミュージックにも繋がる部分である。
たとえば近年「ハイパーポップ」と呼ばれている潮流がそうだ。ハイパーポップとは100 gecsやunderscoresなどに代表される、ポップパンクやトラップなど多彩な要素のカオスなミックスと過剰なヴォーカルエフェクトなどが特徴の音楽。『ユリイカ』2022年4月号で特集が組まれるなど、日本でも近年大きな注目を集めている。
そのルーツの一つとして知られる人物で、宇多田ヒカルの最新作『BADモード』にも参加しているUKのアーティスト、A.G. Cookは、2020年にSpotifyのハイパーポッププレイリストのゲストキュレーターに選ばれた際にJ Dillaの「Welcome To The Show」を選曲している。
A.G. Cookはこの選曲は(どちらかというと悪い意味で)話題を集めたが、その際A.G. Cook本人は「ハイパーポップに興味がある人、ハイパーポップを定義しようとしている人は、Qebrus、Max Tundra、Kate Bush、J Dillaなどのセレクションから何かを見出すことができると思う」とツイートしている。多彩な側面を持ったJ Dillaの魅力は、今後も様々な角度から再発見されていくに違いない。
My goal was really to just make something compelling & I think that anyone interested in or trying to define Hyperpop would find something in Qebrus, Max Tundra, Kate Bush, J Dilla and all those selections...
— A. G. Cook (@agcook404) September 25, 2020
J Dillaは2006年に惜しくもこの世を去り、サウンドパックが浸透した時代にビートを作ることはできなかった。レコードからのサンプリングにこだわるビートメイカーが多かった時代にCDからのサンプリングに挑んでいたJ Dillaは、もし存命だったら恐らくサウンドパックを使ったビートメイクも行っていただろう。しかし、現在活動しているビートメイカーがその「もし」を継いで素晴らしいビートを生み出すことはできる。そしてそれを担うのは、今この記事を読んでいるあなたかもしれない。
ここから先は
¥ 100
購入、サポート、シェア、フォロー、G好きなのでI Want It Allです
