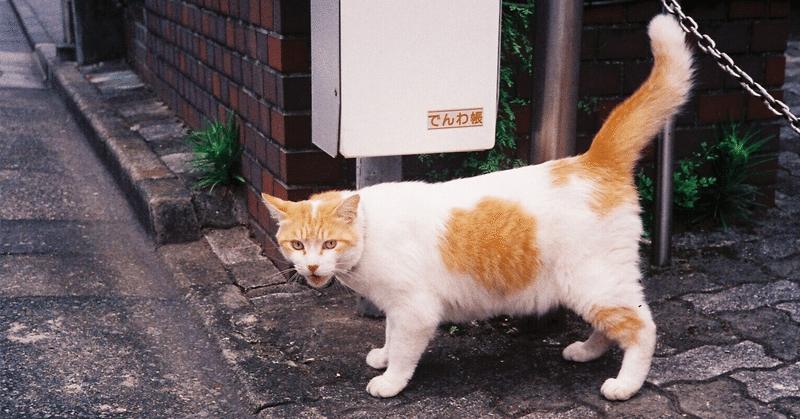
飛べない自分を祝福せよ【エミリ•ディキンスン#507】
現代の猫は室内で飼われるようになってから、ますます飛べなくなった。それは可哀想だ。
孤独の詩人エミリ•ディキンスンも猫を飼っていたようだが、19世紀のニューイングランドでは、土の上を存分に這い回って、小鳥を見つけたのだろう。お定まりのことが起きる。小鳥を見つけるとじっと見つめて、音を立てずそろりと近づいて、四つ足をばね仕掛けにして襲いかかるー
だが小鳥が一瞬先に飛び立つ。鳥には空があるが猫にはないのだ。それは残念なのか。パラパラ漫画のような展開がある次の詩を訳してみよう。
She sights a Bird — she chuckles —
She flattens — then she crawls —
She runs without the look of feet —
Her eyes increase to Balls —
Her Jaws stir — twitching — hungry —
Her Teeth can hardly stand —
She leaps, but Robin leaped the first —
Ah, Pussy, of the Sand,
The Hopes so juicy ripening —
You almost bathed your Tongue —
When Bliss disclosed a hundred Toes —
And fled with every one —
(J507)
そやつは鳥をみて ほくそ笑む
身を低めて そろりそろりと
抜き足差し足近づいて
目をまんまるにさせて
あごはだらんと 腹へらし
歯ぎしりをさせて
飛びかかる瞬間ー小鳥が飛んだ
なんてこった!砂を喰む子猫
希望は熟れてしたたって
舌をどっぷり潤わせても
小鳥のつま先から飛び去る
飛べない自分を祝福して
(りり〜郷訳)
シンプルな詩は三連で擬人化となる。詩人が謳うのは希望。希望とはなんだろう。小鳥を捕獲すること?噛みついて歯の下に広がるジューシーな肉汁?そうとも言えない。
希望とは「得ようとすること」なのだろう。獲得できたら希望はそこで終わり。獲得できないから、落ちこんでもしばらくしてまた挑む。小鳥までの距離は詰めた。飛びかかる速さも増した。噛み付く技術も研ぎ澄ましてきた。でもやっぱり小鳥はあと一歩のところで飛んでいく。やってみて、やってみて、やりきれないことを見出し続ける。その繰り返しが希望の正体なのではないか。
希望には羽がある。自分に羽が生えなくても、一瞬であっても、その羽で自分を飛ばしてくれる瞬間への妄想もまた希望である。だからこそ逆説的だが、飛べない自分を祝福しなけれならない。それが人生ってやつなのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
