
ジャズ・アルバムのライナーノーツ(5) 『ハービー・ハンコック/ライト・ミー・アップ』
先日の『バタフライ』から4年後、ハンコックの「ポップ・アルバム」の代表作(かな)、『ライト・ミー・アップ』です。21年前に書いたもので、今読むとなんというか自分でも興味深いことが書いてありますね。
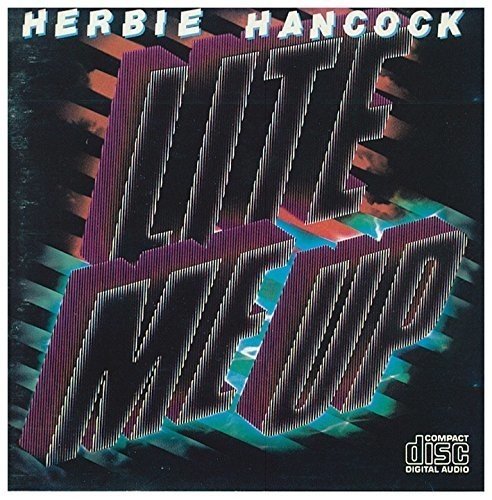
ハービー・ハンコック/ライト・ミー・アップ
ハービー・ハンコックぐらい、さまざまなタイプの音楽に手を出す「ジャズ・ミュージシャン」も珍しい。そのレンジの広さというか好みの多様性というか節操のなさは、おそらく偉大な二人の先達、マイルス・デイヴィスとクインシー・ジョーンズから学んだものなのだろう。とは言え、マイルスやクインシーの場合、それぞれの指向の違いはあるにせよ、決して後ろを振り向かずに、彼らにとっての「その時点での最先端」の音楽を常にクリエイトしようとしていた、という、いわば「進歩主義的わかりやすさ」があったわけだが、アコースティックなピアノ・トリオ作品とこの『ライト・ミー・アップ』のような「どポップ・ミュージック」をほぼ同時期に制作してしまうハンコックは、スタイルを変貌させるのではなく、同時多発的に複数のタイプの音楽を演奏してしまう「ラディカルな無節操さ」という点で、マイルスやクインシーを大きく上回っている。
まあ、本人としては、単に「かっこいい音楽」と「はやりもの」が好きなだけかもしれないが(笑)、「道」を極める一貫性に価値を見いだす傾向が強いジャズの世界(マイルスだって「過去を振り向かない一貫性」で評価されてきた部分が大きい)において、ここまで徹底して「かっこよければ何でもあり」を貫いてきた姿勢(あ、これも実は「一貫性」ですねえ)が、後続世代のミュージシャンに与えた影響は大きいはずだ。
というわけで『ライト・ミー・アップ』(82年)だが、73年の『ヘッド・ハンターズ』以来、ハンコックのやる音楽をずっと支持し続け、もちろんマイルス時代の演奏や60年代のリーダー作もすべて大好きなわたくしも、このアルバムを買ってきて最初に針を落としたとき(当時はLP時代だったのですね)、「うう……」とか言って頭抱えました、実は。だってこれ、「ただの流行りのAOR」としか思えなかったんだもん。もちろん、ヴォコーダーを導入して「歌をうたう」という荒技(!)を実現させた『サンライト』(78年)あたりから、ハンコックのポップ・ミュージックへの傾斜はあったわけで、同年の『フィーツ』はヴォコーダー・ヴォーカルの嵐だし、80年リリースの『モンスター』ではビル・チャンプリンやグレッグ・ウォーカーといった専業ヴォーカリストを迎えて、ポップ・シングルとしていつでもヒット可能、みたいな音作りになっていたわけだから、今にして思えば、何も『ライト・ミー・アップ』でことさらに驚くこともなかったのだろう。あ、そうそう、前作の『マジック・ウィンドウズ』(81年)は、基本的にはヴォーカルものが多いブラコン系(古いか)のアルバムだったのだが、最後の曲がエイドリアン・ブリューと共演した「ニュー・ウェイヴ」っぽい(ますます古いぞ)サウンドのものだったので、そのイメージとの落差が大きかったのだなあ、きっと。
などと17年たって一人で納得してもしようがないが、『ライト・ミー・アップ』が同時代のハンコック・フリークたちを落胆させた最も端的な理由は、「ハンコックのかっこいいソロがほとんどない!」ということに尽きる。それまで、ポップでファンキーなサウンドを楽しみ、その上で展開されるハンコックの緊張感あふれるソロを楽しみ、そのとき音楽の場に生じる「絶妙のミスマッチ」的なスリルを楽しみ……という贅沢な楽しみを享受してきたハンコック・ファンたちにとって、「ハンコック、ソロがなければただのクインシー<詠み人知らず>」に思えたのも無理はないのだった。逆に言うと、このアルバムはハンコックにとってほとんど「暴挙」とも言うべき大冒険だったわけだ。彼にとっての最大のセールス・ポイントであるスリリングなロング・ソロを回避して、あくまでも「曲の間奏」としてのシンプルなソロしか弾かず、純粋に「ポップ・ミュージックのサウンド・クリエーターとしてのハンコック」が成立しうるか、という課題に挑戦したのだから。おまけに、2曲ではヴォコーダーなしの「素」でヴォーカルを取り、「ヴォーカリストとしてのハンコック」にも挑戦しているわけだから、「過激なチャレンジ」という点では、『ライト・ミー・アップ』はハンコックの諸作の中でも際だっている、と言えるのだ。
さてさて、この文章をここまで読んできたあなたが、いったいどんな世代でどういう音楽がお好きなのか、当然のことながら僕には分からない。しかし、もし「何だか妙なCD買っちまったなあ」と、このライナー読んでお思いだとしたら心配はご無用です。ジャズ・ピアニストとしてのハンコックのみに興味があるのなら別だが、このCDに入っている音楽は、82年の時点での「最新のダンス〜ポップ・ミュージック」としてきわめて良質なものであるだけでなく、「98年の耳」で聴いても十分に楽しめるサウンドなのだから。それは60〜70年代のソウルほどには「レア」な感触ではなく、現在のブラック・コンテンポラリー・ミュージックと地続きでありながら、「人力=アナログ」の太く、温かい味わいを感じさせるものだ。ハンコックがここで最も強く意識していたサウンドは、クインシーの『愛のコリーダ』や、クインシーがプロデュースしたマイケル・ジャクソンの音なのだろうが、それらよりもどことなく親密な「手作りの味」が感じられるのは、やはりハンコックが本質的に、自らの手で音楽をつくる「プレイヤー」だから、なのだろうか。
*
ここでのハンコックはプロデューサーでありコンポーザーであり、キーボード・プレイヤーでありヴォーカリストであるわけだが、個々のそうした役割をさらに上の次元で統括する「リーダー」ークインシー名義のアルバムでのクインシーのようなーこそが、この作品でハンコックが目指した「役割」であるに違いない。それにしても、当時のクインシー一家の中核をそっくり借りてきた、とも言える人選には驚いてしまう。まずはクインシーの80年代前半における代貸、とも言うべきロッド・テンパートン。<パラダイス><キャント・ハイド・ユア・ラヴ>を除く6曲がテンパートンの曲(<ザ・ボム><ゲッティン・トゥ・ザ・グッド・パート><ギヴ・イット・オール・ユア・ハート>はハンコックとの共作)であり、その6曲のリズム・セクションは、ルイス・ジョンソン(b)〜ジョン・ロビンソン(ds)〜ポリーニョ・ダ・コスタ(per)という、当時のクインシー・サウンドの定番トリオだ。ホーン・アレンジとホーン・セクションの仕切りはジェリー・ヘイだし、シンセサイザーのマイケル・ボディッカーもクインシーのアルバムでおなじみだし、パティ・オースティンやポウレット・マクウィリアムスもヴォーカルで加わっているし、もうこの6トラックに関しては「テンパートン=クインシー路線」の人選とサウンドそのまま、と言ってよい。
イントロの一発でそれと分かるスティーヴ・ルカサーのギター・サウンドから、すっきりしたトーンのリズム・ギターと、軽快なくせに実はずしりと来るベース〜ドラムスに導かれて、明るくポップなメロディが始まると、後はもうあれよあれよと気持ちいいサウンドが流れていき、気がつくと曲はもう終わっていた、てな感じの<ライト・ミー・アップ>は、「さてハンコックさんは何をしてたのでしょう?」という問題を出したくなるほどにリーダーの影が薄いトラック。しかしこれをタイトルにしたところを見ると、ハンコックはこの「ひたすら明るいどポップ路線」を、このプロジェクトのメイン・アイテムにしたかったのだろう。リズム・パターンとギター・リフが同時期のマイケル・ジャクソンっぽい<ザ・ボム>も、ハンコックのシンセ・ソロが聴けるとは言え、やはり「テンパートン〜クインシー調」そのままの音作りだ。その点、イントロのもやもやした雰囲気といい、エレクトリック・キーボードの音色といい、ハービーのヴォコーダーによって歌われる美しいマイナーの旋律といい、<ゲッティン・トゥ・ザ・グッド・パート>は、明らかにハンコックが主導して作られた曲だろう。シンセのソロも「いつものハービー」してて、保守的(?)ハンコック・フリークも一安心、てな感じだ。
次の<パラダイス>は、ジェイ・グレイドンがプロデュースしてデヴィッド・フォスターとビル・チャンプリンが曲作りに協力した、いかにも「エアプレイ系」のサウンドを持ったトラック。ゆったりとした3連のリズムと、ブリッジ部分のしゃれたコード進行が実に印象的で、ついにヴォコーダーを外してナマで歌ってしまったハンコックのヴォーカルも、まあ「うまい」わけじゃあないけど、なかなかに涼しげだ。続く<キャント・ハイド・ユア・ラヴ>は、これまたブラコン系の売れっ子プロデューサーで、元々は超絶技巧ドラマー(何たってマハヴィシュヌ・オーケストラ、ジェフ・ベック・グループ、ウェザー・リポートのドラマーだったんだから!)であるナラダ・マイケル・ウォルデンのプロデュース。こちらもハンコックがヴォーカルをとっているが、さっきよりかなり生々しい声で(苦しそうな声、というべきか……)、思わず手に汗握ったりして。あはは。
<ザ・ファン・トラックス>と<モーターマウス>の2曲は、再び典型的なテンパートン=クインシー風の音作りだ。どちらもウェイン・アンソニーのリード・ヴォーカルに、ハンコックのヴォコーダー・ヴォーカルが絡むあたりが新趣向なのだが、全体の雰囲気としては「スペシャル・ゲストのハンコックさん」みたいに聞こえるのは辛いよねえ。
そして最後の<ギヴ・イット・オール・ユア・ハート>は、ゆったりとしたリズムに乗るマイナーのメロディがいい、従来のハンコック色がかなり強い曲。ここではハンコックとパトリース・ラッシェンが「ヴォコーダーでデュエットする」という、何ともおもしろい趣向を披露してくれているが、いちばんの聴きどころは、このアルバムで最長の、ハンコックのエレクトリック・ピアノ・ソロだ。メロディックかつリズミックで、途中からホーンズのリフとユニゾンになるあたりも実にかっこいい、「ハンコック隠れ名演」に数えても決しておかしくないソロであるのだ、これは。まあ、最後だけはピアニストとしてのワザを見せておきましょうせっかくだから、ということなのだろうか。
(August,1998 村井康司)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
