
ジャズ・アルバムのライナーノーツ(3)『クラウス・オガーマン/夢の窓辺に』
今回のライナーノーツ発掘は、クラウス・オガーマンの『夢の窓辺に(Gate of Dreams)』です。オガーマンとマイケル・ブレッカーの『シティスケイプ』と一緒に2007年に書きました。
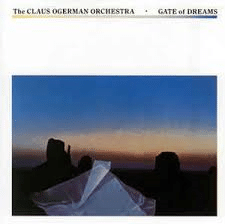
クラウス・オガーマン/夢の窓辺に
ジャズ=フュージョンの世界には、数多くの名アレンジャーたちが活躍しているが、ことストリングス・セクションの美しさと品格の高さ、という点では、クラウス・オガーマンの右に出る者はいないだろう。この『夢の窓辺に(GATE OF DREAMS)』が録音された1976年といえば、オガーマンはジョージ・ベンソンの『ブリージン』やマイケル・フランクスの『スリーピング・ジプシー』といったヒット・アルバムに、洗練された響きのストリングス・アレンジを提供していた時期にあたる。この2枚のプロデューサーであるトミー・リピューマにとって、オガーマンの編曲はまさに必要不可欠のものであったに違いない。豪華なソロイストたちを贅沢に起用したこの組曲は、オガーマンだけではなく、リピューマにとっても「夢の実現」だったのではないか、という気がする。
さて、この『夢の窓辺に』は、もともとはバレエのための音楽だった。72年にアメリカン・バレエ・シアターの依頼によって「大編成オーケストラとジャズ・グループのための」という条件で作曲された「サム・タイムス」という曲に手を入れたものが、『夢の窓辺に』である、というわけだ。ちなみに「サム・タイムス」は72年7月14日に、デニス・ナハトの振り付けによって、リンカーン・センターにあるニューヨーク・ステイト・シアターでプレミア公演が行われた。公演評には、「大胆なオリジナル・バレエ」(ニューヨーク・デイリーニュース)、「クールで、モダンで、統一感があって、ナウな、魅力的な作品」(アソシエーティド・プレス)、「チャーミングなジャズ的作品」(ニューヨーク・マガジン)などがあり、おおむね好評だったようだ。その後「サム・タイムス」は、カナダ国立バレエ団やクリーブランド・バレエ団などにも採り上げられている。
また、初演と同じスコアがオガーマンの指揮で73年5月に録音され、「シンフォニック・ダンス」とのカップリングでレコード化されている。演奏はニューヨーク・スタジオ交響楽団で、フランク・オウエンス(ピアノ、オルガン)、ヴィニー・ベル(ソロ・ギター)、ドン・トーマス(リズム・ギター)、ゴードン・エドワーズ(ベース)、アル・ロジャース(ドラムス)がフィーチュアされている。あいにく音源が入手できなかったため、このライナーで『夢の窓辺に』との比較ができなかったのは残念だ。
*
このアルバムの主役であるクラウス・オガーマンのキャリアを、駆け足で紹介しておこう。1930年4月29日に、当時ドイツ領だったラティボー(現在はポーランド領)に生まれたオガーマンは、ピアニストとしての音楽教育を受け、50年代にドイツでアレンジャーとしての活動を始めた。59年にアメリカに渡り、以来彼はニューヨークに住んで、ポップス~ジャズ~フュージョンの領域で、売れっ子アレンジャーとして活躍するようになる。
63年、クリード・テイラーがプロデューサーとなったヴァーヴ・レコードで、オガーマンは数々のヒット作に編曲を提供した。アントニオ・カルロス・ジョビン、ビル・エヴァンス、ウェス・モンゴメリー…。67年にテイラーがA&Mレコードに移籍し、「CTI(Creed Taylor Issues)」シリーズの制作を開始したのちも、オガーマンはテイラーのために数多くのアレンジを提供している。また、ポップスのフィールドでは、コニー・フランシス、ドリフターズ、クインシー・ジョーンズのプロデュースによるレスリー・ゴーアなどの仕事が有名だ。そして70年代後半になると、オガーマンは前述したようにトミー・リピューマがプロデュースするワーナー・ブラザーズのジャズ・フュージョンやAOR(Album Oriented Rock,またはAdult Oriented Rock)の作品で、しゃれたストリングス・アレンジを提供するようになった。
自己名義のシンフォニックな作品も、70年代以降のオガーマンは数多く発表している。ビル・エヴァンスに書かれた、ジャズ・ピアノとオーケストラのための作品「シンバイオシス」(74年)、この「サム・タイムス」=「夢の窓辺に」、マイケル・ブレッカーのテナーとオーケストラのための「シティスケイプ」(82年)などが著名だが、クラシックのソプラノ歌手やヴァイオリニスト(ギドン・クレーメル)を迎えたコンチェルトもある。
21世紀に入ってからの仕事としては、やはりリピューマがプロデュースした女性歌手、ダイアナ・クラールの『ルック・オブ・ラヴ』(2001年)が代表的なものだ。
*
「夢の窓辺に」は、もともとバレエのために書かれた曲だということもあり、リズムの多彩な表情の変化が特に印象的な作品だ。3つのパートに分かれている「過ぎゆく秋」にそれは顕著で、リズムの動きを追って聴いてみると多くの発見がある。
まずピアノで、印象的な5音のモティーフ「C-F-Bb-Eb-Db」が演奏され、それにオーケストラのロングトーンが答える、というかたちで曲が始まる。このモティーフは「過ぎゆく秋」の中で、ときには転調して何度も登場し、重要な役割を果たしている。そしてオケのゆったりとしたアンサンブルにギターがヴァイオリン奏法で絡み、「パート1」は静かに推移していく。リズムがはっきりとしたエイト・ビートになり、いかにも「フュージョン」風のコード進行がはっきりしてきたところで登場するのは、ジョージ・ベンソンのテクニカルなソロだ。ここのあたりはベンソンの『ブリージン』や『イン・フライト』に組み込んでも違和感がなさそうな展開で、ドラムのハイハットはエイト・ビートから16ビートに自然に移行する。聴き手が驚くのは次の瞬間、ドラムのハイハットが刻むビートが、両手による32分音符になってパート2が終わるところだ。そしてパート3は、ピアノの5音のモティーフと32分音符のハイハットの上のアンサンブルを経て、それとは対照的な、アーシーなエイト・ビートに変化する。コード進行もマイナー・ペンタトニックの一発だけで、ジョー・サンプルのエレピ・ソロもデイヴィッド・サンボーンのアルト・ソロも、ブルージーでアーシーな雰囲気を湛えている。そして場面はまたオーケストラの静かなアンサンブルへと変わり、ピアノのソロで消え入るように曲が終わるのだ。
「カプリース」以降のトラックについての分析は紙幅の関係で割愛するが、多彩なリズムと色彩感豊かなアンサンブル、そしてソロイストたちの個性的なソロのバランスが、どのトラックも実に周到に考え抜かれている点に注目していただきたい。「カプリース」の速いリズムとグローフェやコープランドを思わせる明るいオーケストレーション、そして後半に登場するマイケル・ブレッカーのソロ、という構成は、このアルバムの中でも特に成功している部分だと思う。
こうして聴いていると、クラシックのコンチェルトがそうであるように、この「夢の窓辺に」は、さまざまなオーケストラやソロイストによって、何度も再演されるべき価値のある作品だと、つくづく思ってしまうのだ。オガーマン自身の指揮による再演ももちろん聴きたいところだが、現代の一流ミュージシャンをソロイストに据えて、意欲的なシンフォニー・オーケストラが「21世紀ヴァージョン」を試みてもおもしろいはず。それはもちろん「シンバイオシス」や「シティスケイプ」にも言えることだ。日本のオーケストラ関係者のみなさん、いかがですか?
(June 2007 村井康司)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
