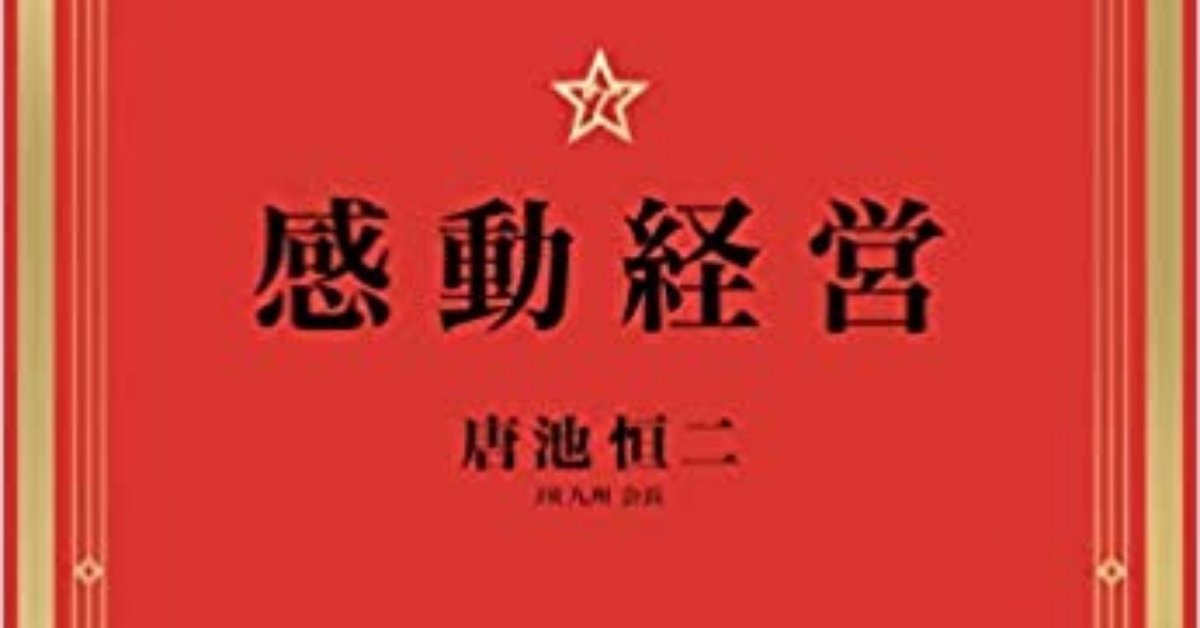
【感動経営】
概要
JR九州の経営の苦悩と喜びの軌跡の物語
現代は「感動飢餓」の時代であり、「感動のない仕事は仕事ではない」と著者であるJR九州会長の唐池氏は言う。
経営において、サービスにおいて、組織もしかり。
感動が少なくなってきた日本のあり方に対して、自身の体験を通して「感動経営」の重要さを改めて見直すべき時がきてるのかもしれない。
私的な要約
感動させる仕組み
・ななつ星という存在
博多から3泊4日の九州一周旅
競争率316倍!当選者は泣く人も
当選からツアーコンダクターはお客様と数ヶ月で20回程度!のやりとりをし、手紙も直筆
→当選してから既にお客様の感動を演出は始まっている
・感動する人が「ひと」を感動させる
「どうやったらお客様に感動してもらえるか」と考えよ
「仕事が出来る人は感動できる人」である
→ 自分があたかもお客様になったかのような感覚になれると素晴らしい
元気にさせる仕組み
・職場で働く皆を元気にするために
大きな声とスピードで「氣」を引き込む。氣とは「活力」「オーラ」「雰囲気」を指す
挨拶、夢、スピードが組織を元気にする
・会社の成長に「異端」を尊重しよう
->新しい意見や試みを排除するな!
->挑戦したものを褒めちぎろ!
->すると「みずから作る」人が増える
企業として経営者として
・変わらなければ、会社は滅びる
->企業30年説を打ち破れ!
->そのためには「変化に対応できるか」が全てである
->勇気をもって「変化」し、「進化」せよ
・経営者に必要なのは誠意誠意誠意!
->ドラッカーも経営者において、絶対に必要な先天的要素だと断言
->トヨタのアメリカでのリコールも公聴会に豊田社長が自ら素早く行動し、誠意を持って対応したことにより、事態は収束した
・リーダーはいつも「ゆったりと笑顔で」
->悪い報告を聞くときも笑顔で
->ライバルにも敬意を払い、礼儀正しく
->いつも注目させているという意識を持て!
・リーダーは「よく歩き、話し、勉強せよ」
・メモは「ワンワード」で。絵もあれば尚良し
・リーダーは難しい局面の時に「決断する人」
・リーダーのすべきことは
->崇高な「使命感」をもち
->「猛烈な勉強」を行い
->ものすごいスピードで「行動」せよ
・「感動のセンサー」が高い人になれ
->それがアイデアになり、ヒントになり得る
・「任せる」なら最後まで「任せきろ!」
->スタッフを成長させるために必要な事
->我慢と覚悟が必要
->最後のリスクの部分は予め考慮すべき
・数字を時間単位まで細分化して、スタッフに身近な目標として共有せよ
->年間目標を日・時間単位まで落とし込む
->そうすることでスタッフの実感が湧く
・経費削減は楽しくやろう!
->コンテスト形式もあり
->節約や我慢ではなく、仕事のスキームや方法を0ベースで考え「工夫」で解決する
・顧客満足をサービスを良くしていくために
->新規顧客の獲得は既存顧客の維持より5-10倍のコストがかかる
->既存顧客の満足は他ならぬ「サービス」というソフト面の向上を指す
・「自己満足」はやめよう。全ては顧客が知っている
->「至れり尽くせり」は必ずしも顧客に届くとは限らない
->顧客満足度を100%を目指すとコスト高
->黒字確保のため、バランスの見極めが必要
・安全は「眠る」。事故はいつでも起こりうると心得よ
->意識していてもどうしても「眠る」もの
->ルーティンや仕組みで普段から意識づけ
->無事故100%は意識次第で簡単に崩れ去る
「伝えるという」難しさ
・簡単に自分の想いは伝わらないと心得よ
->トップが自分の言葉で話せ
->書面で簡単に伝わると思うな!
->シンプルに話せ!
->情報が多いと本当に伝えたいことが紛れてしまう
->繰り返し何度でも話せ!
->組織が大きくなれば「伝える」より「祈るような気持ち」で。(松下幸之助より)
職場の環境について
・整理、整頓、清掃の効果
->逆境の時ほど、職場を清潔に!
->段取り、人間関係、心の荒みなどの改善
->主に心においての効用あり。企業の業績と因果関係は何かしらあるだろう
->松下幸之助氏、永守氏など名だたる経営者も実践
・人に見られると「意識」が変わる
->仕事への意識、身だしなみ、やる気全て
トラブルが起こったときに
・手ぶらでもいいから「すぐに会いに行け!」
->対面だと人はずっと怒り続けるのは難しい
->かえって好転する場合も。著者の経験から
悩んでいる時の解決方法
・悩みを声に出して、「なんとかなるさ!」
・頭にあることはメモをしろ!
->頭のタスクをなるべくスッキリさせる
・嫌なやつほど早く会いに行け!
->2メートル以内で話せば、意外と大丈夫
ドラッカーの言葉を最後に
「経営管理者が学ぶことのできない資質、習得することができず、もともともっていなければならない資質がある。才能ではなく真摯さである」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
