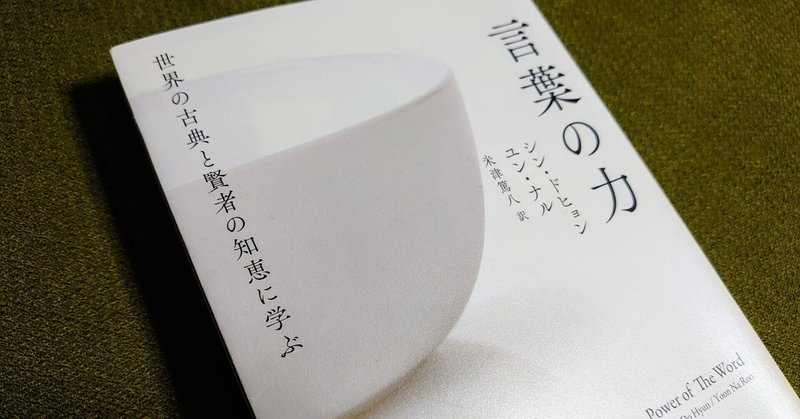
『言葉の力』 シン・ドヒョン 、ユン・ナル
若いころは自己啓発本というものがほんとうに苦手で、自分探しに興味をもったこともなかった。自分は自分、確固として存在するもので良いも悪いもなく、私は好きなものを(時には好きでないものも強制的に)見たり聞いたり経験したりして勝手に学ぶから、したり顔の自己啓発本に教えてもらうことなんて何もないと思ってた。
若い頃の話です。
あまり若くなくなって変わった。今は自己啓発本とも少し仲良くなった。
自分を疑わない姿は、若いからこそ可愛くも勇ましくもあるもので、中年になればただの傲慢だ。そして、若くなければ注意してもらえることも少なくなる。
なまじ経験に裏打ちされてしまった価値観や思考のクセに自分ひとりで気づき、修正するのは難しい。
また、世の中のすてきな人は、いくつになっても往々にして学び続けているなと思う。各自の専門性を突き詰めるだけでなく、人間としての器を磨き続けているというか。
「実るほど頭が下がる稲穂かな」とは、「そう心がけるべき」という格言ではなく、「実ってもなお己の未熟を知るからこそ頭が下がる」という自然の成り行きなのかもしれない。
みずからを戒め、あわよくば高めるために、何か手立てが必要だ。そう気づいたとき、自己啓発本の手っ取り早さがわかったw そして、いくつか読んだり、その道に詳しい人の話を聞いたりするうちに腑に落ちることがあった。
それは、人間の知恵や気づきは古今東西、あまり変わらないのではないか、ということ。釈迦とキリスト、サルトルもユングも、アドラーも、実は言っていることは異口同音なのかもしれない。
本書は、古今東西の古典や名著から引いた言葉を現代の視点からわかりやすく読み解いている。マインドフルネスとかエッセンシャル思考とか、最新のデザインが施されたものもいいけれど、長大な時代の風雪に堪えてきた深遠な言葉は、そう若くなくなった心身に沁みる。
少しずつすべてを読み終わったあともこの本を手元に置き、目次を見てそのときどきでピンときた項や、パッとひらいたページをさらったりして、繰り返し読んでいます。
たとえばこんなふう。
◆
【「切に問う」ことが変化への第一歩だ】
〇広く学びて、篤く志し、切に問いて、近く思う―――子夏
観点は自分の立場や社会のイデオロギーによって決まる(たとえば男性中心社会では、その価値観を内面化する)。そのため、新しい観点を生み出すには意識的に努力する必要がある、という言葉。子夏は孔子の一番弟子。
・広く学ぶ‥‥知識の範囲を広げる。そのために人文学を学び、ものの見方を根本から揺さぶる。
・篤く志す‥‥勇気を育む。社会の不条理に気づき新しい観点を打ち立てるには、世間の冷たい視線にも耐えなければならない。
・切に問う‥‥問題意識を持つ。文の最後のピリオドを消して、そこにクエスチョンマークを書き込むには、すでに満たされている水を疑うことだ。
・近く思う‥‥日常を見つめなおす努力。世界についてあれこれ考える前に、まず自分と自分の周囲からじっくり観察する。自分が変わることこそ、真の変化への第一歩である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
