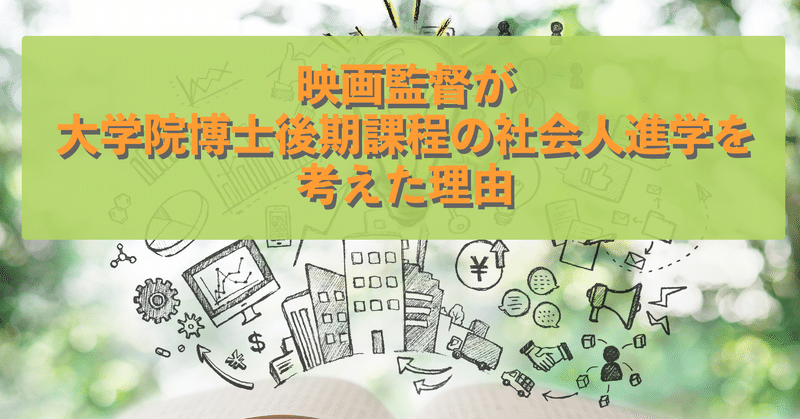
映画監督が大学院博士後期課程の社会人進学を考えた理由
小生は映画監督をしております。
現在、新作の映画に向き合いながら、各地で講演会やワークショップのお仕事を担当させていただいております。
現在の仕事の方だけでも大変満足をしている小生が、
なぜ、この時点で博士後期課程に進もうと考えたのか。
そもそも大学院博士課程とはなんぞやということを思う方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にそのことをお伝えしたいと思います。
博士後期過程、大学を卒業すると、大学院がありまして、
修士課程(博士前期課程)2年と博士課程(博士後期課程)3年に分かれております。
理系の方は、修士に進まれてから就職した方が多いのではないでしょうか。
修士課程は、学部で学んだことを元にして、実践的な研究を行い、
その専門性を元にして、メーカーや建設、製薬などの業種に就くことルートが多いかと感じております。
小生の場合は、学部を卒業して、駿台予備校の講師をしながら、
映画の下積みをするという独特なキャリアに進みましたが、
その後、映画とコンテンツビジネスを専門とした研究室を出て、
修士号を2つ取得しております。
小生は現在、映画監督として「ノー・ヴォイス」と「あまのがわ」という劇場公開作品を2本手掛けました。
学生時代は応用物理を専攻しながら、人間科学部という学部で心理学をひたすら勉強するという変わった学生でした。
幼少期から学生時代まで学校でのいじめに悩み、また親子関係も悪かったことから、人間関係の感情のもつれやずれはどうして起きるのかを知りたくて、大学生後半は、臨床心理士(カウンセラー)を目指していた経緯があります。
人生の運命的な導きから、映画の下積みをするようになったのが23歳。
そこから映画のご縁が繋がり、長らく映画制作をするようになったのでした。
では、そんな自分がなぜ博士後期課程に進学したいと考えるようになったのか。
自分ならではの特徴的な理由があるのですが、一つひとつかいつまんでお伝えしておきます。
Q:そもそも一般的にはなぜ博士後期課程に進むのか?
この問いから考えてみたいと思います。
そもそも大学院とは、大学とは異なり、与えられた勉強する場所ではなく、社会に寄与する課題を抽出し、検証し、解決する研究機関ということです。
ですので、授業を受けて試験を終えれば称号がもらえるという場所ではなく、自身の関心と社会の抱える課題とを照合させて、如何に新規性を生み出していけるかという場所です。そのために、既存の研究を綿密にリサーチして、論文や専門書も十全に理解をしながら、自身の研究テーマやリサーチクエスチョンという問いを掲げて、研究を進めていきます。
博士後期課程は三年となっていますが、三年で修了できず五年・十年掛かる方も少なくありません。よくプロフィールに、博士後期過程満期単位取得退学と表記があるのは、期間内で博士号(Ph.Dと表記されます)が取得できなかったことを意味するのです。
では、その博士号の取得を目指す理由は何か。
一般的には、学術機関で就職をし、研究分野に従事されたいという方が多いかと思います。しかし、博士号を取得しても正規の就職ができずに任期付で研究機関に所属するポスドク(ポストドクター)の数は多々おり、博士号を取得した後の、キャリアの選択に関しては、前途多難の状況がうかがえます。

日本においては、学術界と産業界の連携が限定的な仕組みとなっていることがこの要因の一つに挙がるかと思います。
アメリカは、博士号を取得した人材を高く評価して、企業における専門的な研究を行う貴重な資産と捉えているのです。

(引用:荒磯恒久(2014), 産学官連携, https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsip/10/1/10_1_1/_pdf)
欧米は研究機関での専門性と企業におけるスタートアップでの研究開発部門に連結が強いのに対して、日本の場合は、大学などの研究機関と企業との関係性が脆弱なために、研究機関で育成される人的リソースの価値を抽出仕切れていない状況です。
加えて、国家戦略としても研究にかける予算も違いが大きく見受けられます。昨今のアメリカ、中国、はたまたインドにおける急速な科学技術進展において、日本は未来を見据えた産学官連携を軸とした投資の概念が薄いことが感じられます。

(引用:PRESIDEND ONLINE https://president.jp/articles/-/31772?page=2)
そんな状況の中で、日本における博士号取得者は、国民の数が半数である韓国と同等であり、海外がアカデミックの専門性に重点をおいているのに比べて、日本は専門性ある人材を国や企業が活用してしく仕組み作りが醸成されていないことが理解できるかと思います。

(引用:帰国便利帳 https://www.kikoku-benricho.com/doctor/)
Q:博士号の価値とは?
博士号は研究者のパスポートと言われているくらい、学術分野では、博士号があって初めて一人前の研究ができるという認識があります。
昨今では、ビジネス系やアート系で博士号なく教授職に就いたり、特任といって特定の業種で高い成果を挙げた方が特任教授・特任准教授として採用されるケースも多々あります。
上記にあげました通り、学術分野でのキャリアを選択される上で、
博士号の取得は半ば必須といっても過言ではないかと思います。
では、それ以外の目的とはなんなのでしょうか。
実は小生のように社会人になって、5年〜20、30年とキャリアを重ねてから社会人大学院に入る方の数は少なくないと感じています。
小生も母校のデジタルハリウッド大学大学院の修士課程在籍時には、
IT関連、テレビ業界、デザイン業界、マーケティング、ファッション等、
様々な業種の方々と共に学びを享受しておりました。
修士と博士とでは毛色がだいぶ異なりますが、社会人において博士号取得は、
ご自身のキャリアを幅広くさせるための一つのキャリアアップに繋がることのだと思います。
多様性が広がり、終身雇用制度も過去の産物となっている昨今において、
一つのキャリアに縛られた生き方が一般的ではなく、
逆に複数の仕事につきながら、自身の活動の幅や可能性を広げていく生き方が広がっているのだと思います。
ですから、専門的な研究ができる証として博士号は、研究機関だけではなく、企業や産学連携・産官連携においても、ご自身の実績を表明する一つのエビデンス(証拠)であり、ステータスにもなりうるものだと考えています。
またグローバル化の現代は、博士号が海外の企業における就職やビジネス交渉の一つのツールになることも考えられます。
日本と海外では博士号の価値が異なるため、外資企業とのビジネスを展開する方にとっては、博士号は新規ビジネス・キャリアを開拓する上でも重要な存在になってくることも考えられます。
ここまで博士号取得の二つの理由を述べましたが、三つ目は自己実現欲求だと考えます。
88歳で博士号を取得された尾関清子さんや、77歳で博士号を取得された吉岡憲章さん、この方々はご自身の仕事やキャリアというよりも、自身が生きている証を日本の歴史に貢献することや後世への価値継承を目的として、博士号に挑まれた方たちだと考えています。人生で長らく向き合ってきた経験を元に、そこから培われた知識を論文に残していくことで、次世代に向けた社会的かつ学術的貢献に寄与されたいということは、外的な要因ではなく内的な自己目的的な活動を貫く人間としての一つの生き様のように感じてなりません。
学びとは、生涯死ぬまでが学びだと考えています。大学受験や資格取得は本来通過点であるはずですが、それが目的化してしまうと、自分がなんのために仕事に就くか。なんのために生きていくかの生きがいやりがいを見失ったまま、生活をすることになります。
ですが、社会人になってからの学びというのは、昭和時代の押しつけ・支配の教育とはかけ離れ、自らの関心ごとを主体的に追究していく動機が存在しています。そのため、今後学術機関もリカレント教育(生涯学習)の観点より、大人のための学びほぐし、学び直し(リスキリング)の概念が強まっていくことが必要だと思います。
日本は大学に入るのは難しいが卒業するのは容易であると言われているように、形骸化された大学のあり方が問われて久しいですが、大学に入ることが目的とならず、洗練された学びを追究した機関であることをしっかりと内省、検討していく段階にすでに入っていると考えています。
Q:では古新はなぜ博士後期課程に進学を希望するのか?
今までの記述をまとめますと、博士後期課程進学の目的には、大きく3つとして、
1:大学・研究機関での就職をしたいためのキャリアパスポートして
2:企業における昇進やマルチキャリア、グローバル展開のツールとして
3:人生における集大成としての自己実現的価値として
では、古新は1〜3のどれなのかというと、実はどれも若干当てはまるようで、ストレートに入る項目がないのが現状です。強いていうと、3が近いのですが、自身の場合は、今後のキャリアステージにおいて、アカデミック分野での研究のメソドロジー(手法)を理解した上で、今までの活動をそれに則り総まとめして、次のステージを迎えたいいう意図があります。
どういうことかというと、小生は元は物理と心理を専門にしてきた人間で、そのまま大学院は映画の現場というアカデミックとは真逆な環境において、人間性やクリエイティブ技術を向上させ、デジタルハリウッド大学大学院において、起業をいたしました。
物理・心理の学術分野、映画を通じた地域振興や教育活動、アントレプレナーとしての起業/経営と三つのジャンルを経験してきて、それぞれの分野で学んだ知識や知恵は、横連携でつなげていくことでさらなる価値を生み出し、次世代に向けた教育的かつ文化的な資産やリソースを残していけると考えたのです。
昭和の時代はバブルが起こり、そこに人は陶酔し、資本主義に依存し、その結果、幸せのあり方や人間関係が希薄のまま平成の三十年が過ぎ去った現代社会、8050・7040問題、ひきこもり問題、経済格差はじめ、様々な社会課題において、過去・現在・未来の文脈で課題と向き合えている人材が日本にはまだまだ限定されているのではないかと思ったのです。
上記にあるとおり、教育と企業の関係が強固でない現状において、アートやクリエイティブ・エンターテインメントには、人と人とを繋いでいく潜在的な価値があるのですが、如何せん、このエンターテインメント分野特に映画は単体での興行や国内の利益を追求した限定的な産業になっており、教育や企業、海外展開の可能性はまだまだ訴求できておらず、より一層、クリエイティブな分野が学術分野や地方創生などのコミュニティ形成と連帯をしていく可能性を拡張させていきたいと考えたのです。
大企業や資本が経済の潮流として表層的に注目されてきたなかで、コロナにより資本だけでは持続的な社会にはならないことを多くの方々が感じられたのではないでしょうか。生活者が笑顔で暮らしていく上で、人的繋がりや協働性、国内の精神的な価値の共有が、人間としての営みを豊かにさせ、そして、次世代に向けて私たちが受け継いでいくべき幸せの価値や文化的価値を広く分かち合いたい。
これから小生の活動は、現在の映画・教育の分野から地域に根ざしたフィールドワークに拡張されていきます。その時に、先ほど上述した通り、分断されているアカデミックの役割は、地域・生活者・企業・アート/クリエイティブを連結していく貴重なアクターになりうると考えているのです。その時に、学びを続けるという概念は、現代社会を自分らしく生き抜いていく必須のマインドになっていくと考えています。
小生は、学術機関で長年培われてきた価値ある研究や理論は、実践を伴わせることで、随伴的に共創されていくのだと考えるのです。
だからこそ、小生が行ってきた実践という暗黙知であり抽象的活動を、学術という分野において形式知として具体的活動に一旦掘り下げて、それを元に、新たに抽象的活動へと円環させていくことで、小生が独自で培ってきましたクリエイティブリソースやナレッジを実践活動の現場で仲間たちと共同化させていき、この時代を共創的に切り拓いていく活動を行いたいと考え、社会人博士後期過程にチャレンジしようと決意したのでした。
物理・心理・映画と理文芸3分野を活動してきて、今回博士後期課程にて専門にするのは社会科学になります。
社会科学の中でも文化人類学を現在、専門的に研究を始めております。
先日、大学院の入試面接を受験してまいり、担当教官の先生や面接をご担当いただきました教授陣皆様には貴重なご指導をたくさん賜りました。
無事、大学院合格になるかは、次回以降にお伝えすることとなりますが、
入試を終えて、合否がでる前の現在、自身の気持ちをまとめておきたいと思い、このような投稿をいたしました。
社会人の方で博士後期課程進学を検討されている方にとって、少しでも有益な内容をお伝えできていましたら、幸いに思います。
ぜひ、この続きのレポートも書きますので、フォローにてご注目いただけましたら幸甚です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
