
【連載 Bake-up Britain:舌の上の階級社会 #2】 クリスマス・プディング(2/3)
「階下のものたち」と「階上のものたち」
というわけで、クリスマス・プディングもまたイギリスという国が背負ってきた資本主義の歴史と切っても切り離せない食べ物なのだ。あのずっしりとした重み、子どもには少しきついかもしれないスパイスとラム酒やブランデーの香り、なんといってもスエットの光沢に満ちたあの悪魔的な黒さ。聖なる日の「ディナー」に出される食べ物のはずなのに、なんとなく罪深い食べ物のような気もしてくるから不思議である(なお、英語の「ディナー(dinner)」は「その日の主たる食事」を意味し、必ずしも「夕食」を指すとはかぎらない。そして、何時に「主たる食事」を取るのかもまた階級によって異なる)。
その悪魔的な食べ物を、材料や出来の良し悪しは別にして、クリスマスに皆で食べる、という習慣ができたのだから、まあイギリス国民を代表するものだという認識が広がったのだろうが、では一体誰がクリスマス・プディングを「作る」のかを考えると、やはりそこには大きな分断が見えてくる。

労働者階級の家ではそれを自分たちで作って食べるが、上流階級の家では「階下」のキッチンで料理担当の使用人たちが作り、「階上」の主人やゲストたちが食べる。もちろん、いまや手作りというのは一般的ではないだろうが、かつて、そう、クリスマス・プディングが登場する小説として『クリスマス・キャロル』に次いで有名な、アガサ・クリスティーの『クリスマス・プディングの冒険』が書かれた1920年代には、「階下のものたち(downstairs)」が「階上のものたち(upstairs)」が食べるクリスマス・プディングを作っていた(いまもある種の階級の暮らしではそうである)。
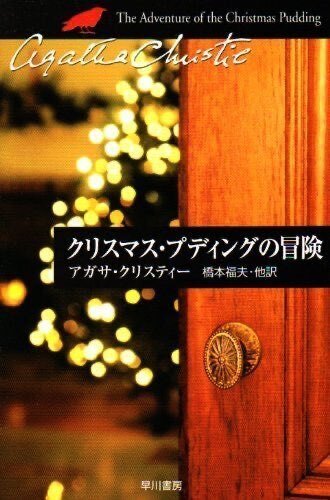
この物語の中で名探偵エルキュール・ポアロは、「イギリス連邦のために動いている」という人物から、ある国の王家のスキャンダルになりかねない事件を解決してほしいと依頼を受ける。王家に代々伝わる高価なルビーが、英国旅行中の王子の密かなランデ・ヴーの現場から行方知れずになってしまい、それを探し出して欲しいというのだ。犯人が潜伏していると目されるマナー・ハウス「キングス・レイシイ」に入り込んだポワロは、そこで「イギリスの田舎の古風なクリスマス」を過ごしながら、いつものように「灰色の脳細胞」を駆使して事件を見事にルビーを取り戻すのだが(以下ネタバレを含む)、事件解決の糸口は、誰がクリスマス・プディングを作り、誰がそれを食べるのかの「分業」にあった。

犯人が盗んだルビーを隠した場所、それがクリスマス・プディングだった。名探偵の来訪を耳にして動揺した犯人は、調理中のプディングのなかにルビーをこっそり忍ばせ、クリスマスが終わったら外に持ち出そうと考えた。その家のキッチンでは、クリスマスの正餐(ディナー)に出すプディングのほかに、元日に食べるためのプディングが用意されており、その元日用のプディングに犯人はルビーを隠したのだ。
銀紙で包んだ6ペンスコイン(今では2ペンス)をプディングに仕込み、それが入った部分が皿に盛られた人に幸運が訪れる。そんなクリスマス・プディングの習慣に範を取ったようなトリックなのだが、階下のキッチンでちょっとした「手違い」が起きてしまい、犯人の思い通りに事が運ばなくなる。使用人の一人が食料品室で寝かしてあったクリスマス用のプディングを棚から下ろす際にあやまって落としてまったために、元日に食べるために取ってあった方のプディングが、皆が囲んでいるテーブルに出されてしまったのだ。その「手違い」に気づいたポアロは一計を案じ・・・と、あとは早川書房の文庫本で楽しんでいただきたい。

犯人がルビーをプディングに隠すことができたのは、「キングス・レイシイ」のクリスマス料理を取り仕切ったミセス・ロスがプディング作りにあたって、「ステア・アップ・サンデー(Stir up Sunday)」という「昔のままの習慣」を守ったからである。「ステア・アップ・サンデー」とは、家族全員で順番にプディングの具材を混ぜ合わせ、それぞれ願いごとを唱えるという儀式めいた習慣のことである。クリスマス・プディングは長く寝かしておくほど美味しくなるため、本来はクリスマスの数週間前に仕込むのが「昔のまま」のやり方なのだが、その年のプディングが作られたのはクリスマスの数日前だった。その時、ミセス・ロスは来客も含め屋敷にいた者たち全員に声をかけ、プディングを混ぜさせたのだった。犯人はその最中にルビーをプディングに入れたのである。

だが、犯人が労働者階級の家庭のようにプディングを作っていたならば、つまり、プディング生地を数回混ぜ合わせるだけでなく、蒸す、寝かせる、型から取り出す、テーブルまで運ぶ、ブランデーでフランベする、切り分ける、というすべての調理に関わっていたならば、そして作る場所と食べる場所が同じフロア(階)にあったならば、「手違い」を事前に察知できたはずだ。プディングの味は作ってみなければわからない(the proof of the pudding is in the making)。
マナー・ハウスの「階上」では、ディナー・テーブルを囲む誰もがそれぞれの思惑を隠しつつ、それぞれの欲望を満たそうとしているが、自分たちで食事を作ることはない。一方「階下」では使用人たちが共同で「階上」の主人やゲストたちに食べさせるものを作る。クリスティーが「階下のもの」によるささやかな抵抗を意図して書いた、とはまったく思われないけれど、結果的に「階下」のものの裁量が、「階上」のものの悪事を暴くことになったのだ。
そもそも、これが労働者階級の家であったならば、このミステリー自体が成立しなかっただろう。両親共働きが普通だった労働者階級の家庭では、そうしないと間に合わないという事情もあったが、ともかく家族総出でプディングを作ったのだから。階級による分業が当たり前なマナー・ハウスのクリスマスと、作る人と食べる人が一致する労働者階級のクリスマス。
この違いは、富を生み出すのも利得を享受するのも最終的には個人であると、それも主意的で合理的な個人であると想定している資本主義と、集合的な力が集合的に発揮されることで資源が必要に応じて集合的に再分配される社会主義の違いだとも考えられる。クリスマス・プディングが際立たせる階級闘争。
(続く)
ミンスパイのレシピ
(直径6cmのタルト型、12個分)

材料
ペストリー
薄力粉 200g
きび砂糖 30g
塩 ひとつまみ
無塩バター 100g
卵 1個
ミンスミート(フィリング)
レーズン 50g
サルタナレーズン 50g
カレンツ 50g
クランベリー 50g
レモンピール 30g
* レモンの皮すりおろし1個分でもよい。
アーモンド 30g
クッキングアップル 50g
* 紅玉、ブラムリーなど酸味のあるもの。
無塩バター 50g
黒糖 50g
ブランデー 50g
ミックススパイス 2g
* コリアンダー50%、シナモン20%、ナツメグ10%、ジンジャー10%、クローブ10%を基本にお好みでブレンドを。
仕上げ用
卵白 1個分
粉砂糖 少々
ミンスミート(フィリング)を作る
アップルを細かく刻み、残りのミンスミートの材料とともにボールに入れ、全体がよく馴染むまで混ぜ合わせる。
これを密閉した容器に入れ、冷蔵庫で1週間ほど寝かす。

ペストリーを作る
小麦粉をボールにふるい入れ、砂糖、塩、バターを加えて、指先で手早くこすり合わせ、粉チーズのような状態になったら、卵を加えてざっくり混ぜ、ひとまとまりにする。この生地をラップで包み平らに整えてから、冷蔵庫で1時間ほど休ませる。
冷蔵庫から取り出した生地を麺棒で3mmほどの厚さに延ばし、抜型で焼き型よりも少し大きな円形に12個抜き出し、またパイの上にのせる生地を星形などの抜型で12個抜き出しておく。
円形の生地を型に敷きこんで、フォークで数か所、空気穴をあけてから、かぶせの生地と共に冷蔵庫で20分ほど休ませませる。

ミンスミートをつめて焼く
型に敷きこんだ生地にミンスミートを入れて、上から押してぎゅっと詰め込み八分目ぐらいまで入るようにする。
星形などのかぶせの生地をのせ表面に溶いた卵白をぬってから、170℃のオーブンで20分ほど薄く焼き色がつくまで焼く。
パイが冷めたら、トレイにならべて茶こしなどで粉砂糖を振りかけてサーブする。

* 次回の配信は12月23日です。
The Comonner's Kitchen(コモナーズキッチン)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
