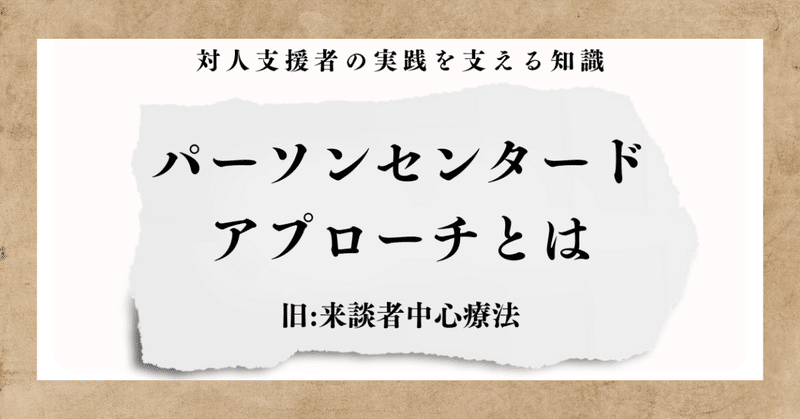
パーソンセンタード・アプローチとは
この記事では、アプローチの理論説明をしていくにあたり、関係するロジャーズの他の理論を、部分的に参考にしています。
たとえば、人をどのような存在として認識しているのかという「パーソナリティ理論」や、「セラピィの理論」を一部参考にしています。これらの関係する理論については、別途記事にしてご紹介して参ります。
それではさっそく、アプローチに関わる「パーソナリティ理論」の一部をご紹介していきます。
1-1.パーソナリティ

アプローチ理解のために、先に「パーソナリティ理論」(1)の説明を簡単に行います。
人は、幼い頃から環境と自分の関わりによって、さまざまな概念を作ります。
たとえば、お母さんにだっこされていると落ち着くなど、あまり言語化されていないものも含めて、自身の感覚からそれがどのようなものであるかの理解を形成します。
他にも「お菓子は好き」や「思うままに走り回るのが楽しい」などの概念も作られ、このような自身の感覚に直結した概念が集まって、人格や性格とも言い換えられる「パーソナリティ/自己構造Self-structure」が作られます。
1-2.無条件の肯定的配慮

幼児期の保護者との関わりから「無条件の肯定的配慮(Unconditional positive regard)」を体験します。具体的には、オムツが汚れて不快であったのをサッパリさせてくれたり、空腹を解消してくれたりという、幼児にとってはなんだかよくわからないけど、関わりによって落ち着かせてくれたという体験のことを指します。このことから「無条件の肯定的配慮」とは、なにもしてなくてもそのままを認められ、大切にされていることを意味します。
そして「無条件の肯定的配慮」の体験から「肯定的な自己配慮(Positive self-regard)」という感情体験を起こす特徴をもった概念群が、パーソナリティに作られていきます。これは、実際に保護者との関わりがなくても、同じように認められ、大切にされている体験を、自分が自分に提供することを指します。
つまり、安心感の源泉を内面に持てるようになるので、不安があっても独りでも落ち着くことができるようになる、ということです。
1-3.条件の価値

成長するに従い、条件についての概念も作られます。これは、自身の感覚に直結しない概念が、パーソナリティに含まれるようになることを指します。
たとえば、電車のなかではしゃぎたくなって保護者に「はしゃいではいけません」と怒られた場合、「怒られるのはイヤ」という自身の感覚に直結した概念が働きつつも、同時に「電車のなかではしゃぐと怒られるから、電車のなかではしゃぐのはイヤ」という間接的な概念が作られます。これによって、電車のなかではしゃがないことで「おとなしくしていて偉いね」などの存在肯定を体験していくようになります。つまり、間接的ながらも、自分にとって価値ある概念が形成されるのです。
このように、社会的な側面に接することが増える分、他者からの評価によって作られる概念が、パーソナリティの割合を多く占めるようになります。
それは、大人になるにつれ、保護者との関わりから概念を作っていたのと同様に、個人がその時属する社会的場面での関わりからも、他者評価による概念が作られていくことを指します。
1-4.自身の感覚と概念のズレ

個人にとってさまざまな関わり、特に「社会的に重要な他者」と呼べる人物との関わりは、生涯に渡って影響力があります。
社会人でいえば、会社の上司やお客様に、いい評価をされて、自身の存在価値を感じられる時、社会的に作られた概念でそのことを受けとり、さらに「人に喜んでもらえるのは素直に嬉しい」という自身の感覚に直結した概念による受けとり方が、感情体験として起きるかもしれません。
しかし、自身の感覚に直結せず、社会的に作られた概念のみで、上記のような出来事に接した場合「これが合格点であり、次も同じかそれ以上のことをしなくてはならない」といったような、厳しい評価による安堵感や次の機会に対するプレッシャーへと発展することがあります。
これがあまりにも長期化すると、自身の感覚では「かなり疲れていて嫌だ」という社会的に作られた概念とのズレが顕著になり、疲労状態と概念による社会的評価とのギャップから、緊張・焦りなどが高まり参ってしまうこともあります。
それでも、この自身の感覚に寄らない間接的に作られた概念を、あとから作り替えることができます。これを「心理変容」や「自己構造の再体制化」と呼びます。
社会的な関わりから作られた概念は、社会的な関わりのなかで、再体制化できます。そもそも他者評価によって、概念が作られるならば、本人の感覚を認める他者との関わりを通して、新たに概念を作ることもでき、そうしてできた概念は、自身の感覚と社会性を伴ったハイブリッドな概念ができることになります。
このことから、パーソンセンタード・アプローチでは、支援者がクライアントの感覚を理解し、無条件に認めることを徹底するのです。
2.内側からのクライアント理解

上記の「自己構造の再体制化」のために、パーソンセンタード・アプローチは、どのように関わっていくのでしょうか。
「1-1.パーソナリティ」の概念の説明で、ひとの主観的な体験は、それまでに作られた感覚に直結した概念と、間接的に他者からの評価を取り入れて作られた概念の二通りがあることをみてきました。
ここから伺えることとして、クライアントが体験している主観は、それまで出会ってきた関わりから作られた概念を通して、さまざまな出来事を受け取り、クライアントの主観が生まれているため、その人の体験を理解するには、同じようにその人の感覚を生理的に備え、まったく同じ生育過程や出会いの履歴を辿らない限り、他者が理解することは不可能といえます。
このことを前提に、ロジャーズは他者が少しでも理解していく方法として、内側からの理解を提案しました。
これは、心理テストやカテゴリーに分類することで、クライアント理解を外側から進めるのではなく、目の前のクライアントの感情体験を、なぜそう感じ思うのかの受けとり方も含めた内側からの理解を、想像と確認というプロセスで行っていくことを指しています。
3.クライアント理解の方法
3-1.共感的理解

パーソンセンタード・アプローチでは、クライアントの語りに表れる主観的体験に対して、支援者がなぜそう思い感じるのかも含めて理解していきます。
その理解は、瞬時に行われるのではなく、支援者がクライアントに「こういうことをお感じになったのでしょうかね」というスタンスで、確認をしていく受け答えが中心になります。
つまり、対話のなかで、試行錯誤でとらえ直していくことによって、理解を形づくっていくことになります。
提唱者であるロジャーズは、これを「共感/感情移入(Empathy)」と呼び、また晩年の1980年には「今ではそれを『共感という状態』と定義しません。それは過程であって状態ではないと思うからです。」(2)と、共感はプロセスによって作られていくことを明言しました。
3-2.確認する方向

確認をしていく内容については、クライアントの内面で絶えず変化し続けている意識内容が、主となります(3)。
そして、ここには、意識内容にのぼってきそうになっている事柄も含まれます。「喉元まで出ているんだけど」のような感覚が指す、言葉になりそうでならないニュアンスも、このクライアント理解に含まれているのです。
3-3.確認する内容

支援者の受け答えの方法は、クライアントの語りから「こういう主観的体験をされていたのかな」と推論的に想像し、そこに感情移入して浮かび上がってくる感情体験について、クライアントに確認していく方法をとります。
その確認内容が、確かなものであっても違っていても、それを受けとったクライアントの意識に反応が起こり、そこから再度支援者が想像し、それを確認することで、クライアントはより具体的な内省へと発展していくことができます。
この感情移入による想像から、クライアントを理解する方法について、ロジャーズはよく「推理」「仮説」「立証」という表現を、下記のようによくしていました。
「このようにしてその感情移入に含まれている推理と仮説とを立証したり反証したりするのである。このような認識の方法がセラピィにおいて非常に有益であることがわかってきた。感情移入的推理を最大限に働かせたとき、そのようにしてクライエントの主観的世界について得られた知識が、クライエントの基盤とパーソナリティ変化の過程を理解させるのである。」(4)
つまり、パーソンセンタード・アプローチにおける「共感」とは、温かくそのままを認めている「無条件の肯定的配慮」とは別に、とても知的な活動を表しているといえます。
3-4.「一致」という条件
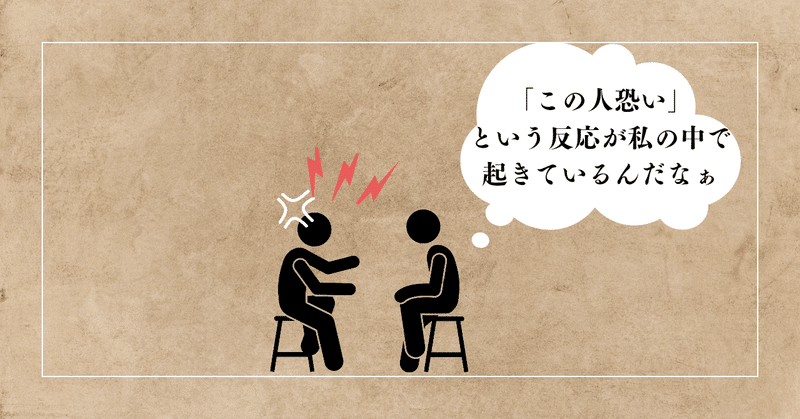
クライアント理解のため、この確認を求めていくあり方には、条件がつけられています。
それは、支援者側が「一致していること」というものです。
ここでいう「一致(Congruence)」とは、クライアントの語りを聞いて起きる支援者側の内面の反応と、支援者の意識が一致していることを指します。
もう少し分かりやすく説明するために、なぜ「一致」をするのか、という理由をみていきます。
ひとつは、ひとえにクライアント理解のためです。
クライアントの感情体験にある怒り・不安・恐れなどが、語りを通じて起きる支援者独自の怒り・不安・恐れなどの感情体験を、クライアント理解に混ぜ込まないよう、クリアな状態にしておく必要があります。
支援者独自の感情体験を伴ったままクライアント理解を進めると、感情によって受けとり方も変わってしまうため、クライアントの受けとり方がわからなくなってしまいます。そうなると、クライアントの主観的体験を理解することは、一層困難になります。
こういう時に「一致」が役立ちます。
人は、自身の反応を意識が受け入れていると、落ち着くことができます。つまり、自身の気持ちを脇においたり、感じないようにするのではなく、自分の感情として認識しておくことで、感じていることと意識していることが、一致した状態を作ります。そうして、感情の処理を促しているのです。
このことについてロジャーズは、以下のように表現しています。
(※引用の文中にある「彼」は、セラピストのことを指しています。)
「彼は、"私はこのクライエントを恐れている"とか、"私の注意力は私自身の問題に集中しているので、彼に耳を傾けることができない。"というような体験をするかもしれない。セラピストが、このような感情を自分の意識に否定しないで、自由にそうあることができるならば(もっと別の感情であってもよい)、われわれの述べている条件は満たされているのである。」(5)
受け入れることが難しい場合、支援者自身がセッションを受けることによって、あらかじめ受け入れやすくしておくことができます。
著者の考えになりますが、経験をつむほど、社会的に良いとされていることも、クライアントを含むすべての人にとって良いものとは言えないな、と感じることに多く遭遇するようになります。
そして、その社会通念は、当然のように自身の概念にも含まれています。そのことに気づく度に、この概念を、自身の感覚を受け入れた内容に再体制化しておくと、クライアント理解の際に、無条件の肯定的配慮を一貫して行えるようにもなります。この意味で、支援者は、常に支援を通して成長し続けるのだといえます。
このことは、そのまま「一致」をする二つ目の理由にもつながってきます。
それが、支援者が一貫して受容的な姿勢から「無条件の肯定的配慮」を、クライアントに伝えるため、というものです。
ここでの「無条件の肯定的配慮」は、『1-1.パーソナリティ』に出てきた『そのままを認められ、大切にされていること』という特徴を持った関係性と同様のものを指しています。
『1-1.パーソナリティ』の末部でも触れましたが、パーソナリティは、他者からの評価によっても作られます。
セッションでは、支援者が社会的な他者として、クライアントの感覚をそのまま認めることで、クライアントは自身の感覚を受け入れやすくなります。
結果的に、感覚を拒絶していた概念を、感覚を受け入れた概念にしていくこと=自己受容が、内省のなかで起こりやすくなります。
このプロセスはとても繊細な作業になるため、受け入れがたい感情が表れて苦しみをクライアントが感じたときも、一貫して温かく受け入れている支援者が「無条件の肯定的配慮」を伴った理解の確認をしていくことで、クライアントは、認めてくれたものとして、その感覚を受けとることになり、苦痛が緩和され、感情を否定していた概念について、内省していくことが可能になるのです。
これは、クライアントの防衛的反応を減らすことにもなっており、同時に、支援者が達成したクライアント理解の分、信頼関係(ラポール)の構築にもなっています。
引用文献
(1)Rogers,C.伊東博(編訳)1967,パーソナリティの理論,ロージァズ全集8,パースナリティ理論,岩崎学術出版社,pp.225-243.
(2)Rogers,C.R.1980,A Way of Being.Houghton Mifflin.畠瀬直子(監訳),1984,人間尊重の心理学:わが人生と思想を語る,創元社,p.133
(3)Rogers,C.伊東博(編訳)1967,クライエント中心療法の立場から発展したセラピィ、パーソナリティおよび対人関係の理論,ロージァズ全集8,パースナリティ理論,岩崎学術出版社,p,207.
(4)Rogers,C.伊東博(編訳)1967,クライエント中心療法の立場から発展したセラピィ、パーソナリティおよび対人関係の理論,ロージァズ全集8,パースナリティ理論,岩崎学術出版社,p,209.
(5)Rogers, C. R. 1944 The Development of Insight in a Counseling Relationship. Journal of Consulting Psychology.8,pp.331-341.伊東博(編訳),ロージャズ全集4:サイコセラピィの過程,岩崎学術出版社,p.124.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
