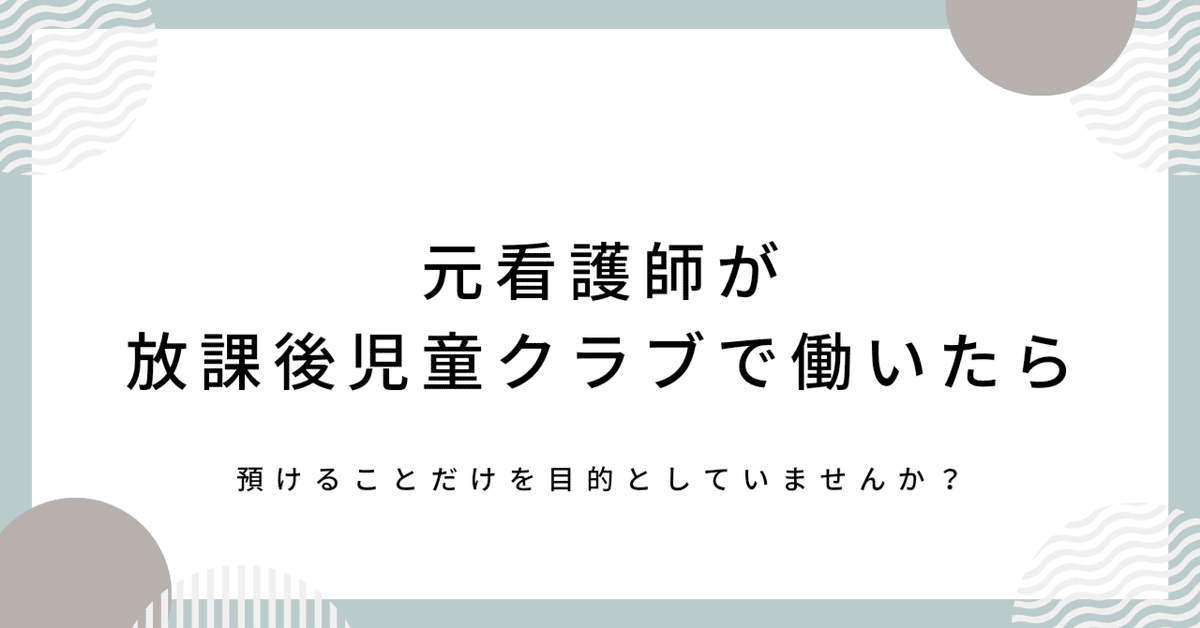
〈83〉加配をつけてもらえない①
神経発達症(発達障がい)などがあり、マンツーマンの支援が必要な子どもには加配をつける。
保育園や幼稚園ではスタンダードですか。やはり人員不足でつかないことも当たり前ですか。
筆者の放課後児童クラブでは加配がつかないのがスタンダードなんですけど、何なのですか。
小学校で支援級にいたり、個別支援がついていても、学童保育では誰にも支援してもらえないんですけど、それでいいんですか。
せっかく幼児期に療育に通って積み上げて、小学生になってからこそ大事な、新たな積み上げ期間に入るのに、パッと支援が切れた状態にするんですけど、大丈夫ですか。
暴言や暴行、脱走など対応困難児童が複数人いることで、他の児童や放課後児童支援員の安全やメンタルヘルスを守れないんですけど、どうしたらいいんですか。
自治体は子ども達のことも、放課後児童支援員のことも"数"としか見ないのですが、どうしたらいいのですか。
議会の答弁が広報に載ることがありますが、長もちゃんと無知で、"数"としての答弁を繰り返すんですよ。
質問する議員も「そうじゃない」と食い下がってくれるほどの知識がないので、議論になっていないのだろうと安易に想像できます。
筆者の放課後児童クラブでは全国的にも稀か、神経発達症(発達障がい)(グレーゾーン含む)の在籍割合が50%を超えています。
在籍児童の全体数が20人に満たないとしたって、多いですよね。
それを有資格者2名、無資格者2名がシフト制で回しています。時給働き、扶養の範囲内などいますから、常時4人ではありません。手薄さはわかっていただけると思います。
それでも一生懸命学び続け、子ども達と向き合う職員だから、他の学童保育所より手厚いと保健福祉を知っている方々からは評価はされていますけど…
疲弊しているので全然嬉しくありません。
そもそも筆者の放課後児童クラブは、自治体の地理的状況や制度設計の甘さなどで、都市部では放課後デイサービスや新たに発達支援センターに繋げるような程度でも、どんな子どもでも全て受け入れています。
ただ全てを受け入れることはインクルーシブとは言いませんからね。
来年度はさらに神経発達症児や知的障がい児の割合が高くなることが数年前から想定されています。
そのため何度も自治体の職員には、
「周辺に放課後デイサービスなどの支援施設が無いからと言って放課後児童クラブに"ただそこにいる状態"にするのではなく、きちんと支援施設へ繋げることが必要」
「やむを得ず放課後児童クラブに入れるのなら、発達支援センターなどとの連携はマストとして支援員へのサポート体制を整えることが必要」
「神経発達症や知的障がいの程度が重いなら加配を」
と訴えてきました。
加配は…来年度予算をつけることもしないようです。
想定されることは、トラブル、感情の爆発、怪我、脱走、排泄介助、着替えの介助、学習支援が同時進行で起きる日々。
ならば保護者にもそういう保育環境になることを覚悟していただかなければ。
「ケンカばかりする」「怪我させられた」「解決してくれない」と支援員だけが責められることの無いように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
