
主任試験合格レベル論文実例集の感想
お疲れ様です。
今日は家から走って丸の内オアゾに行き、本を数冊買い漁りました。
良い運動になりました。
大学生の時が51キロ、29歳の健康診断で体重が57キロでしたが、それからX年が経過し、現在69キロです。身長は変わっていません。これは由々しき事態ですね。現在、自分に減量命令を出しています。
さて、本日は、公務員関係で気になった本があったので購入しました。
1 本日購入した本
「合格者が書いた主任試験合格レベル論文実例集」(公人の友社出版)です。
発売日は2020年の1月15日ということで大体1年前のようですね。新しい本といっても良いのではないでしょうか。
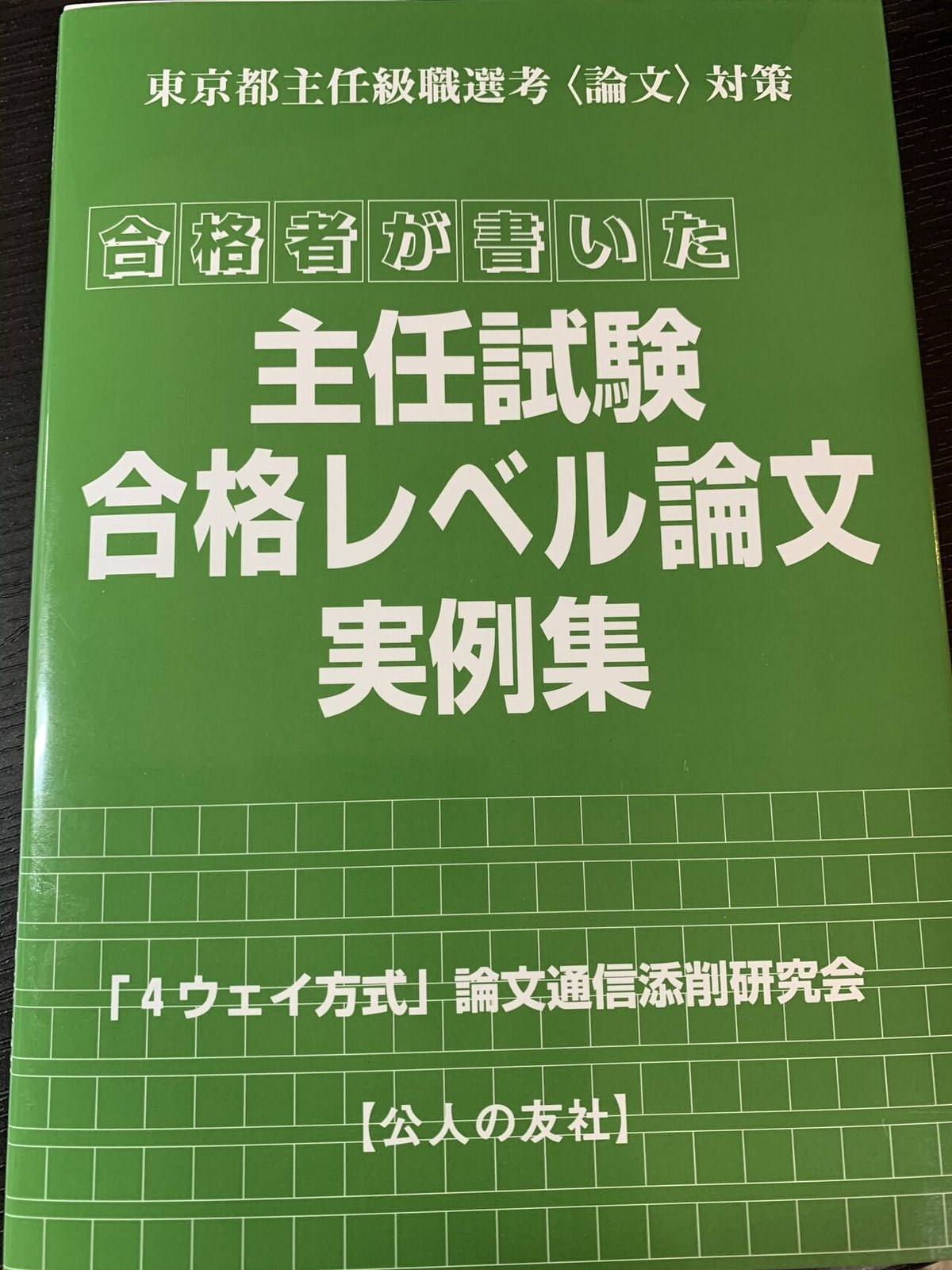
2 主任試験とは
主任試験については、東京都人事委員会は公表している資料を参照ください。
なお、この資料は、東京都人事委員会ホームページ人事委員会定例会のページで公表されているものですから特に秘密ではないようです。(令和2年6月26日第13号議案)
この主任試験ですが、私も論文作成には苦労しました。なぜならイマイチ何を勉強したら良いか掴みづらかったからです。
司法試験は法律勉強すれば良いし、公認会計士なら財務会計等を勉強すれば良い・・・という感じなので、試験自体は難しいですけど、勉強すべき点は明確ですよね。
主任試験は本に書かれてるように、都政もの(東京都が今後なすべき政策が問われている)、職場もの(職場問題の解決策が問われている)が出題されるというわけなんですが、事前にどんな勉強をすれば良いのかさっぱりでした。
よく分かっていない中で、管理職に過去問や類題を解いて添削してもらっていましたが、方向性がよく分からずゴミのような答案を作成していましたね。合格答案も読んで何となく書けるような気になっただけでした。
ゴミを作成してしまい、管理職と紙業者と清掃業者の皆様には申し訳ないことをしたと思います。
実際の試験ですが、司法試験には合格していて程よく文書作成経験があっても、初回の主任選考は論文が絶望的に書けずに不合格でした。
確か論文の評価はCだったと思います(A〜E)。このランクは不合格者の中での順位だったと思いますので、散々な内容だったのでしょう。このCにも絶望しました。
翌年は課長から、さすがに合格しろや、と相当尻を叩かれて2ヶ月間土日を使って勉強したので合格しました。ちなみに当時本庁で仕事をしていたのですが、合格可能性はある、悪くない、という感じでお墨付きは頂いておりません(汗)
なお、合格者には評価ランクは出ません。
3 本の内容(答案作成の感覚を掴むには良い)
さて、この本の話にしましょう。
この本は、参考事例とともに参考答案が複数掲載されています。
「都政もの」の方は、「こんな感じで書くんだな」という意識で採用試験対策にある程度使えるのではないかと思います。8ページから31ページまでです。
主任試験対策としては、一定程度参考にはなるもの、都政もので書くことを念頭に置くのであれば管理職選考A向けの勉強をした方がいいかもしれません。
管理職選考Aは都政ものオンリーです。管理職は都政全体を意識して組織のマネジメントを担う職層ですからね。
主任試験を直ぐに受けるような層であれば、管理職選考Aも視野に入れている人も多いのではないでしょうか。より上位レベルの論文を見据えて勉強しておいた方が効率的です。
他方、「職場もの」は完全に主任選考用です。A I論文は34ページから112ページまでですね。A II論文は113ページから134ページ、B論文も136ページから150ページまでに掲載されています。こう見ると、職場ものの方がページが割かれていますね。参考答案が多数掲載されていますので、「こういう感じで構成していくのか」という掴みには良いのではないでしょうか。
他に試験情報が手に入る環境かどうかにもよりますが、まとまった情報が入る環境にないのであれば、取り敢えず、この本を読んで答案の感覚を掴むのは良いと思います。
この本の参考答案を暗記するのはダメですからね。
参考答案を読んでからが試験対策の始まり・・・だと思います。
4 合格経験者の私見
私が受験した時は、事例が長文化していたものの「職場もの」に資料はありませんでした。
近年の「職場もの」は資料があるため、複雑化しているように思われます。
とはいえ、求められている「思考」は変わらないと思います。
どうやって勉強するのかという点ですが、職場ものは問題文に、当該職場においてこれは問題では!?という記載がありますね。
「問題になるところ」が見当たらない!、というあなたは取り敢えず過去問等でこれは問題なんだというケースを見つけるところからスタートしましょう。
なお、私も最初はそのような感じでしたが、そのような感じでもしっかり勉強すれば合格するので大丈夫です。
もっとも、前記の「問題になるところ」は年度によって変わりますし、資料も変わるでしょう。だから暗記しても意味はないと思います。
そこで、組織で仕事をしている自分を念頭に、ここを放っておくとや主任の俺やばそう・・・、とか、これ放っておくような主任は使えんな・・・、と思うところをピックアップすると良いかもしれません。
「問題になるところ」は多分放置したら相当まずいところのはずなので、これそのままにしておくと、どうなるのか?ということを想像することも大事でしょうね。
(例)上司・同僚とのコミュニケーション
(例)情報共有・周知
(例)報告
(例)後輩の指導・成果物チェック
(例)段取り・進捗管理
(例)役割分担
多少重なり合うところもあると思いますが、大体こんなところが問題になるんじゃないでしょうかね。この本を読むと上記のあたりも見えてくると思いますので、自分なりに整理してみると良いと思います。
その後、自分なら問題点を①どう処理するか?それをやることで②どう効果があるのか?という点を考えていくと良いと思います。以上は私の感覚なので他の人には当てはまらないかもしれません。
(具体的な文書の流れや、解決策も本の参考答案に書いてありますが、答案作成に向けたスケルトンみたいなページはないので、頑張って自分で見つけましょう。)
一応主任なので、課長代理の存在は蔑ろにしないでください(笑)
課長代理に「相談の上」など、職層を意識することも大事だと思います。
「言うは易く行うは難し」、ですが、私も何とか生みの苦しみでがんばりました。
仕事を言語化するって難しいですね。
最初からすらすらできる頭の良い人が羨ましいです。
珠世さんに論理的思考力が向上する薬を作って欲しいです。
受験生の方は頑張ってみてください。
取り敢えず仕事でコケるのは論外なので、仕事は頑張ってください。
ノーミスで仕事しろ、というよりはちゃんと周りとコミュニケーションを取って上手く仕事を回していくということです。
・担任事務をきちんと回せているか、
・報告はしているか
・相談はしているか
・自分の仕事だけでなく周りをサポートできているか。
などなど。こう考えてみると、結構大変ですね。私も出来ていなかったところもあると思います(今でも出来ているのだろうか・・・(汗))。
取り敢えず一人で戦わず、組織の一員ということで無理せず頑張りましょう。
あせらず たゆまず おこたらず、です。(湯島天神の鉛筆に彫られています)
あと主任になりたいオーラは必ず出しておいてください。
上司も人ですからね。
頑張っている人は合格させたいと思ってくれていると思います。
あとは、頭の良い同僚・先輩がいると良いかもしれません。頭が良いというのは学歴というよりも思考力ですかね。まぁ、大抵は思考力がある人は学歴もありますが・・・。私はそのような先輩もいたので、自分の思考力を高めるのに大いに助かったと思います。同期に対して昇任試験の相談は何となくしにくいかもしれませんので、先輩がおすすめです(笑)
ちなみに上司にチェックしてもらう時は、ある程度自分の方を固めた方が良いと思います。色々なアドバイスを貰って崩壊しないようにしてください。
健闘を祈ります☆☆☆
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
