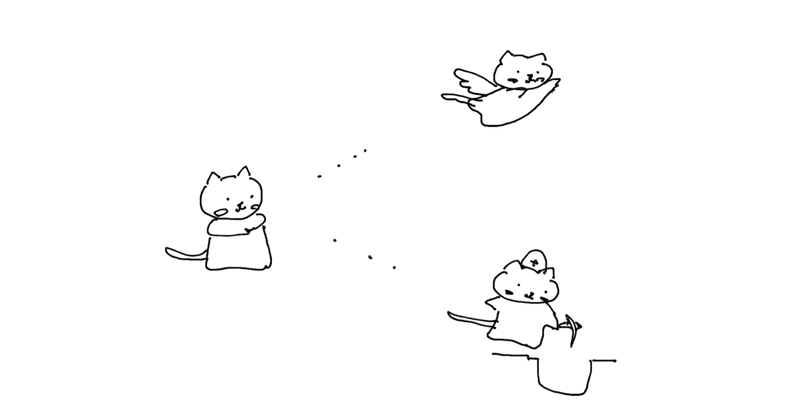
【Sマナ07】100年続く発信を、どうすれば創り上げられるのか
100年はちょっと大きく出てしまったのですが、長く愛される発信の秘訣は、経営に通じるところがあると感じています。
SNSも経営も、よくわからない状況に直面しながら、なんとか手探りで進んで行く点では全く同じなのです。
前回では、変化が激しいSNS環境に対応する能力を考えてみました。今回は、変化に対応する能力はどうすれば身につくのかを考えてみます。
経験を通じて知を学ぶことが大切
![]()
SNSの環境は常に変化しています。受け手のニーズも、競争相手も変わり続けているからです。しかも、その変化が速いのがSNSの特徴です。
そのような環境では、より速く経験し、より速く学ぶことが、受け手に求められる発信に繋がります。学びの力は、そのまま発信の力でもあるのです。
経営理論でも、会社が学ぶ過程を研究する「組織学習」という分野があり、それは「経験」を通じて生じる「組織の知の変化」の研究と言われます。
そんな組織学習において、非常に重要な考え方と言われているのが、マーチさんが提唱した「知の探索」と「知の深化」の概念です。
知の探索とは、これから広く知られる可能性のある新しい知を追い求めることで、知の深化とは、既に知っている知の活用を意味します。
新しいことに挑戦することは大切なのですが、今取り組んでいることをしっかりとやり切ることもまた大切。問題はこのバランスなのです。
扱い慣れた・評判の良い話題に囚われる
![]()
一方で、意識しないと発信は深化に偏ります。これは会社も同じでして「コンピテンシー・トラップ」と呼ばれる能力開発の罠にはまるのです。
発信において、自分が得意な話題は自然と取り上げる回数が増えますし、取り上げる回数が上がれば、それだけ上手くなります。
また、そんな上手くなった発信は評価されますので、その評価を得るためにも、また同じ話題を取り上げるようになるのです。
このように、ある話題に対して能力が最適化されてしまい、他の話題を取り上げられなくなる状態がコンピテンシー・トラップです。
本人としては、求められていたことを当たり前にやっていたのに、変化した環境についていけなくなる日が来ることから罠と言われます。恐ろしい。
これに抗うためには「新しいことへ挑戦する仕組み」を持つことが必要になります。それが出来ている発信者は変化への対応力が高く強いのです。
話題の多様性を確保する仕組み
![]()
分かりやすいのが、グループで発信をすることです。大人向けの例では『東海オンエア』が有名ですが、ティーンズに大人気なのが『すとぷり』です。
すとぷりは「基本顔出し無しのアイドルグループ」です。「会いに行ける」どころか、YouTubeで「いつでも会える」アイドル。
6人グループで、全員が参加する公式YouTubeチャンネルと、メンバー個別のYouTubeチャンネルがあります。総登録者数は圧巻の合計800万人超え。
ヒカキンで1,000万ですからね。とんでもない登録者数です。
全員で集まってライブや企画動画。それぞれのメンバーが、歌動画や、ネタ動画、ゲーム実況動画と独自色の強い発信をしていることが強みです。
常に誰かが新しいことをしており、また、バラエティに富んだ発信が用意されているので、ファン層も幅広く掴むことが出来ます。
さらに、すとぷり内だけではなく、他の配信者とのコラボも積極的に行っており、それが鮮度を上げ、新たなファンを獲得する要因になっています。
変化に対して圧倒的な強さを持つ、まさに「今の時代」のアイドルグループです。彼らの発信スタイルはとても勉強になります。
基本個人プレーのnoteでも、今後はもっとチームプレーをする発信者が増えていくような気もしたりしなかったりです。
ダイバーシティは一人でもできる
![]()
このように、個性のあるメンバーが集まると変化に強いのです。変化が激しい環境でこそ、ダイバーシティはより輝きます。多様性の強みです。
では、個人ではダイバーシティが無いかと言うとそんなこともなく、「イントラパーソナル・ダイバーシティ」という考え方があります。
これは、「様々なことを経験している個人は、様々な側面でパフォーマンスが高い」との結果が、多くの研究で出ていることから来ています。
変化への対応は、未知への対応でもあります。
未知には、既存の経験の組み合わせで対応するしかなく、その幅が広いほど有効な対抗策が浮かびやすいのだと言われます。
この経験の組み合わせがすごいと感じる発信者が、美容系YouTuberのあかりんこと吉田朱里さんと和田さん。です。
あかりんさんは、元NMB48のメンバーで、2020年12月に卒業。NMB48のメンバーの頃から、モテメイクのYouTube発信で有名でした。
そのきっかけも、他のメンバーと比べて何か特徴を持たないといけないと危機感を抱いた、とのことですから非常に戦略的です。
美容にアイドルの経験を掛け合わせて、独自の発信スタイルを確立。最近はB IDOLというコスメブランドを立ち上げ、活躍の幅を拡げています。
他方、和田さん。は、元美容部員の方で、その経験を活かしてYouTubeで発信。YouTuberを始めるきっかけは、担当ブランドの日本撤退だったそう。
昔にYouTuber経験があったこともあり、当初から高クオリティの発信を連発。一般人からの出発ながら、あかりんと同等の登録者数を誇っています。
和田さん。が取り上げたコスメは、即売り切れることでも有名です。今では、雑誌や美容系動画の監修など、やはり活躍の幅を拡げています。
このお二人の特徴は、前回の話のように、発信に「美容系」という明確な軸があることです。
加え、過去の経験を活用したり、新しいことに取り組んだりと、イントラパーソナル・ダイバーシティをフルに活用しているお二人だと感じています。
変化に対応するための知識や経験は、誰しもが持っているのです。
面白い発信とは、如何にそれを上手に組み合わせて表現できるかである。そんなことを教えてくれるお二人です。
変化を当たり前にすること
![]()
このように、変化の激しいSNSで長い間発信を愛されようと思うならば、自分もまた変化することが必要です。
そのためには、「知の深化」だけではなく、「知の探索」を意識して行うことが大切。そして、知の探索には、多様性が活きます。
それを複数人で担当できれば強いですが、一人でも自分の中の経験を組み合わせることによって確保することもできるのです。
そんな、組み合わせによって新しいことに挑戦する仕組みを持つことが大切なのです。なので、私もこのような慣れないnoteを頑張って書いています。
ちなみに何かで読んだ話ですが、人は普段と異なることをして失敗したときに一番後悔を感じるそうです。いつも通りにすればよかった、と。
逆に考えれば、変化や挑戦が当たり前になっていれば、たとえ失敗してもそこまで後悔しないとも言えるのではないでしょうか。
やはり、変化できる人は、生き残る力が強いのです。
同じままでいるよりも、
人生は変化があった方が面白い。
大阪なおみさんの言葉です。変化は楽しいものでもありますよね。新しい自分を見つけられた時には、やっぱりワクワクします。
変化には、変化で立ち向かってみませんか。
皆さまの発信のご参考になりましたら幸いです。
ではでは。
<過去のnoteはこちらから>
最後まで読んで頂きまして、ありがとうございます!頂いたサポートは、noteを書きながら飲む缶コーヒーになっています。甘くて素敵な時間を頂きまして、とっても幸せです。




