
自分の違和感を大切に
何故かそう思ったら、そうなのです。
普段過ごしている中で、突然何かが閃くことってないでしょうか。何故かは分からないけれども、こうした方が良い、逆にこれは違うという閃きです。
この閃きで動くと「右脳的だね」と言われます。感性で動いていると言われがち。ビビビ婚的なものですね。また、ちょっと古いか。
ただ最近、資料の中で違和感を覚えた数字があったのですが、やっぱりそこのロジックがおかしかった、ということがありまして。
この閃き系は、軽んじてはいけいないなと改めて思うのです。
違和感とはズレである
![]()
違和感は、しっくりこない感じや、落ち着かないさまと言われます。何か状況が感覚的に気持ち悪い。そんな感覚ですね。
仕事でこの違和感を感じるという時は、何かがズレている時です。このズレは、自分の中のあるべき水準と、実際の水準のズレです。
自分の中のあるべき水準は、自分の経験の中で培われるものです。自分としては、これが普通と思う水準。日々の中で培われた満足できる水準。それが、あるべき水準です。
この水準は、長く仕事をやればやるほど、固く高くなっていくものです。自分のこれまでの経験から、こうであるべきと思う水準が、いつの間にか自分の中で出来上がっているのです。
それと現実がズレている時に、違和感は感じられるものです。そのため違和感を感じた時というのは、何かが、自分の水準からおかしいと感じるときなのです。
違和感アラートの例
![]()
例えば、ということで、以下のスライドがあったとします。私はこのようなスライドを見るともう結構しんどかったりします。
1箇所は目に見えてズレているのですが、実は3箇所、よく資料の中で起こるズレが含まれています。
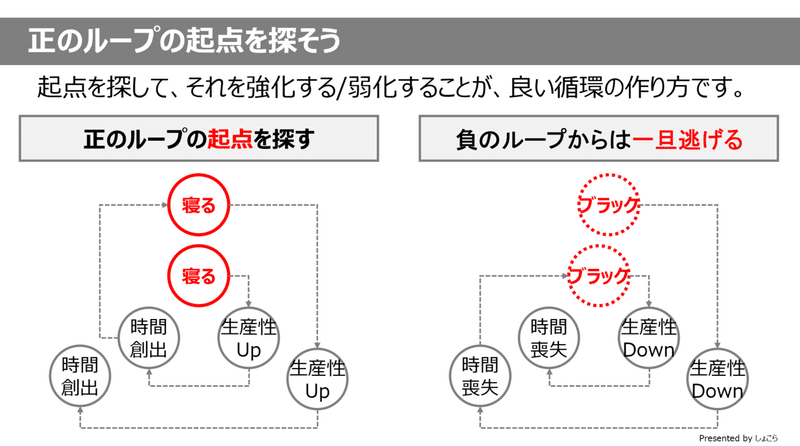
内容に目が行く前に、その配置や構成といった、スライド全体からものすごく「気持ち悪い感じ」を受けてしまうのです。
こうなるともう、内容が頭に入ってきません。「何か気持ち悪い。何故だろう」という方に意識が向いてしまうのです。
ちなみに、3箇所は以下の通り。位置のズレが2箇所と、フォントが異なる部分が1箇所です。特に、メッセージの場所のズレは頻度と重要性の割には、無視されやすいところです。
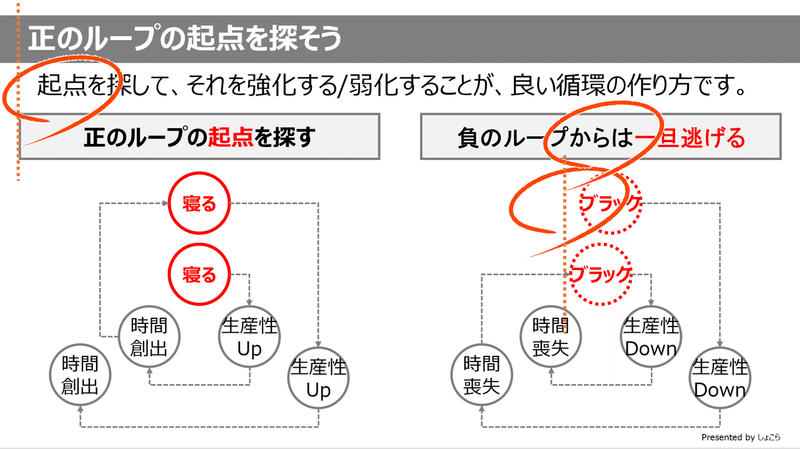
正直、微妙な違いですよね。おそらく、ズレていても、話自体は問題無く進むのだと思います。
ただ、人によっては「なんだかこのスライド気持ち悪いな」と思わせ、内容に集中できなくさせてしまうのです。
そんなことが起こり得ることには、少し注意が必要かなと思います。
自分の違和感センサーは信じるべき
![]()
このように、違和感は自分の思う水準とのズレであり、それを感じたということは、何か現状に満足できない要素が混ざっているということです。
この違和感センサーのアラートを放置することは危険なのです。後から考えると「やっぱりそうか」となってしまう。
そのため、違和感センサーが鳴った時には、なぜ違和感を感じているのかを考えることは大切だと思います。
一方で、違和感は小さなものです。普段の生活の中で無視しようとすればできる範囲のものだったりします。「ん?」という感じに過ぎません。
妥協点として、アウトプットの重要性でどこまで付き合うか決めましょう。重要なアウトプットの中で感じる違和感は、やっぱり無視してはいけないのだということが、今回の件からの学びです。
映画の『スパイ・ゲーム』では、スパイの訓練を受けるブラッド・ピットが、ロバート・レッドフォードに、「周囲に異常がないか、常に見ろ」と言われます。
これも、異常=違和感を感じるということは、危険があるということであり、それは彼らにとって死活問題なのです。そんな生活は、とても私には出来そうにありませんが。
自分の感覚を信じましょう。違和感を感じるということは、しっかりと考えると、言語化された違いに辿り着けるものなのです。
まあ、After Carnivalなのですけれどもね!涙
ではでは。
<似たような話題かも>
<関連する本かも>
内容は今回の話とは異なるものの、違和感を感じている状態は何故なのかを突き詰めていく過程を示してくれる本です。違和感は、何故違和感を感じるのか、どうしてその状況が生まれたのか、そしてどうすれば良いのかという、思考の連鎖を生んでくれる大切な感覚なのです。
<このnoteを書いたしょこらはこんな人です>
<Twitterもぜひフォロー下さいませ>
最後まで読んで頂きまして、ありがとうございます!頂いたサポートは、noteを書きながら飲む缶コーヒーになっています。甘くて素敵な時間を頂きまして、とっても幸せです。


