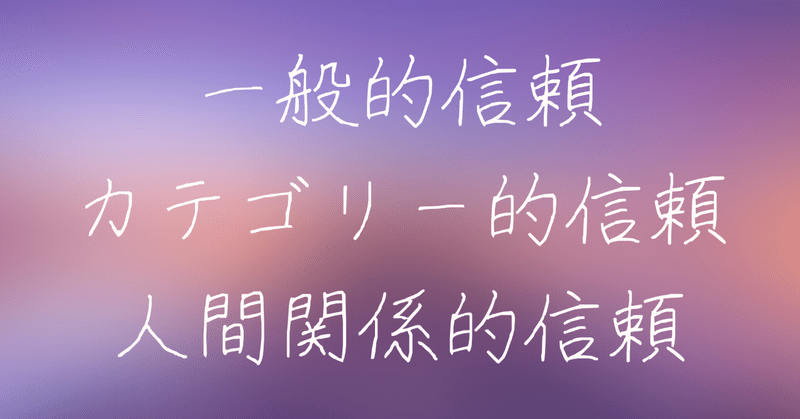
「信頼」の3つのタイプ ~信頼したりされたりするための指針 ~
以前、信用と信頼についてのnoteを書いたところ、各所からフィードバックをいただきました。そのなかに「信頼という言葉をもっと深掘りしてみてほしい!」という反応があったので、書きながら考えてみます。
ここで先人の知恵を借りたいと思います。
20年以上前に出版された「信頼の構造」という本では以下のように信頼(trust)を定義しています。
信頼=「相手の人格や相手が自分に対してもつ感情についての評価」
ここから自分で信頼を分類したりしようかと思ったのですが、すでにこの本のなかで分類されているのを発見してしまいましたw
なので、今回はそれを紹介してみようと思います。最後にわたしなりに、信頼したりされたりするための指針を書いてあるので、ご参考になれば嬉しいです。
①一般的信頼
初対面の他人を信頼するかどうかについて、私たちのデフォルト値がこの一般的信頼です。「人を見たら泥棒と思え」というのは一般的信頼が低い態度。逆に「渡る世間に鬼はなし」というのは一般的信頼が高い態度です。
この一般的信頼が高いと信じやすくだまされやすいナイーブな人だと思ってしまいそうですが、実はその逆で、一般的信頼の高さは社会的知性(とくに人間性検知能力)と相関関係にあります。
人間性検知能力が高いからこそ、初対面の他人を信頼することができると言えます。
②カテゴリー的信頼
相手が「日本人」だから信頼する、相手が「家族」だから信頼する、というのはカテゴリー的信頼です。相手についてカテゴリーについての情報があるときに発動する信頼です。
たとえば、アロハシャツにアフロでグラサン、といった服装をしている人がいたとして、その人が実は「大学教授」であるというカテゴリー情報を知ったとたんに信頼するようになったとしたら、それはカテゴリー的信頼でしょう。
一般的信頼が低い人でも自分の家族は無条件に信頼する、というのもカテゴリー的信頼です。このようにカテゴリー的信頼は一般的信頼を上書きすると思います。
また、人によっては大学教授だからといって信頼するわけではないと思うので、このカテゴリー的信頼には個人差が大きくあります。
③人間関係的信頼
特定の個人との関係性で発動する信頼です。仮にカテゴリー的信頼で大学教授を信頼する人だとしても、その中で信頼できない個人がいるかもしれません。そのように、カテゴリー的信頼を上書きするような個別の関係性に基づく信頼を人間関係的信頼と呼びます。
ちょっとした出来事で関係性がかわり、信頼するようになったり信頼しなくなったりすることもあるので、非常に流動的な信頼の形態だと言えます。
信頼が必要な時代に生きる私たちの指針
いろんなタイプの他人と出会い、共通の実践をする機会の多いこの時代では、信頼すること、されることは非常に重要です。
だから、他人を信頼できるように人間性検知能力を高めて「一般的信頼」を高めておきたい。「渡る世間に鬼はなし」をデフォルト値にしておこう。もし搾取されたら逃げればいいし、それは人間性検知能力を高める学びになるはずです。
また、他人から信頼されるように、カテゴリー的信頼や人間関係的信頼を高めるような情報を伝えていこう。この2つの信頼は「情報依存的信頼」とも言われているので、自己顕示にはならない程度の自己開示は、慣れておくといいかもしれません。
最後まで読んでいただきありがとうございます!サポートも嬉しいですが、ぜひ「スキ!」をつけたりシェアしたりしてほしいです!それが次の記事を書くチカラになります。
