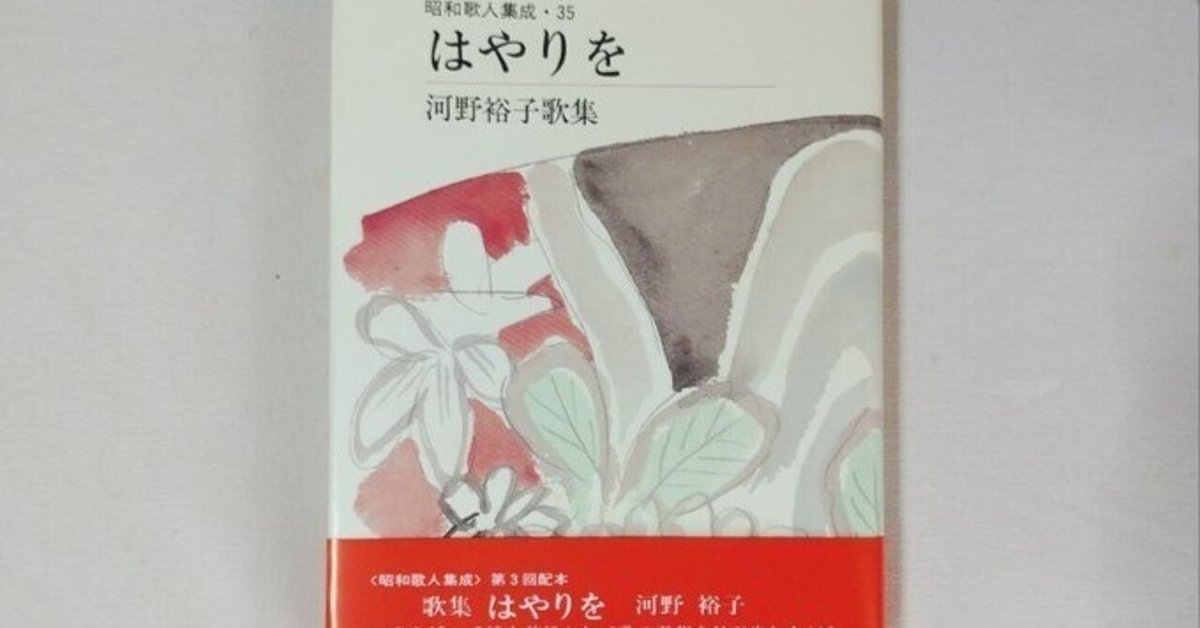
河野裕子『はやりを』 18
ああここに人の憂ひにさも沁みてくれなゐ掲ぐさざんくわの花 さざんかの花を見た時の主体の心に、憂いが満ちていたのだろう。さざんかが掲げる紅い色がその憂いに沁みてくる。「ああ」「さも」と感嘆の気持ちを表す言葉が複数使われ、切迫した心が表現されている。
夕日さして一本の柿の古木あり睡りのやうな憂ひを感ず 同じ家に所属するものとして木を見ている。木を人間のように感じるのは河野短歌の一つの特徴だろう。自分より年長の木。夕日に照らされたその木を見ていると、眠りに似た憂いを感じる。比喩に実感がある。
ひのくれはこんなに誰も居なくなり柿の古木もぼんやりとして 多くの人が居るはずの家なのに、夕方には人が居なくなってしまう。気力が弱まっている自分同様、柿の古木もその寂しさにぼんやりとしてしまっている。木に自分の心が転移してしまっているのだ。
たつたこれだけの家族であるよ子を二人あひだにおきて山道のぼる 家族で登山に来た。夫婦の間に子供二人を挟んで山道を登っている。こうして見ると、昔の大家族と違って本当に小さな家族だと実感される。初句八音だが、内容のためか、あまり頭が重い印象は無い。
灰いろの柿の古木を守るがに家はその屋根をはつかに傾(かし)ぐ 最終連の「日本の花」十二首の内、三首がこの柿の古木を詠っている。河野の特定の木に対する愛着が表れた例だと言えるだろう。さらにその柿を守る形の家。河野の心の拠り所が分かるように思う。
2023.6.20. Twitterより編集再掲
