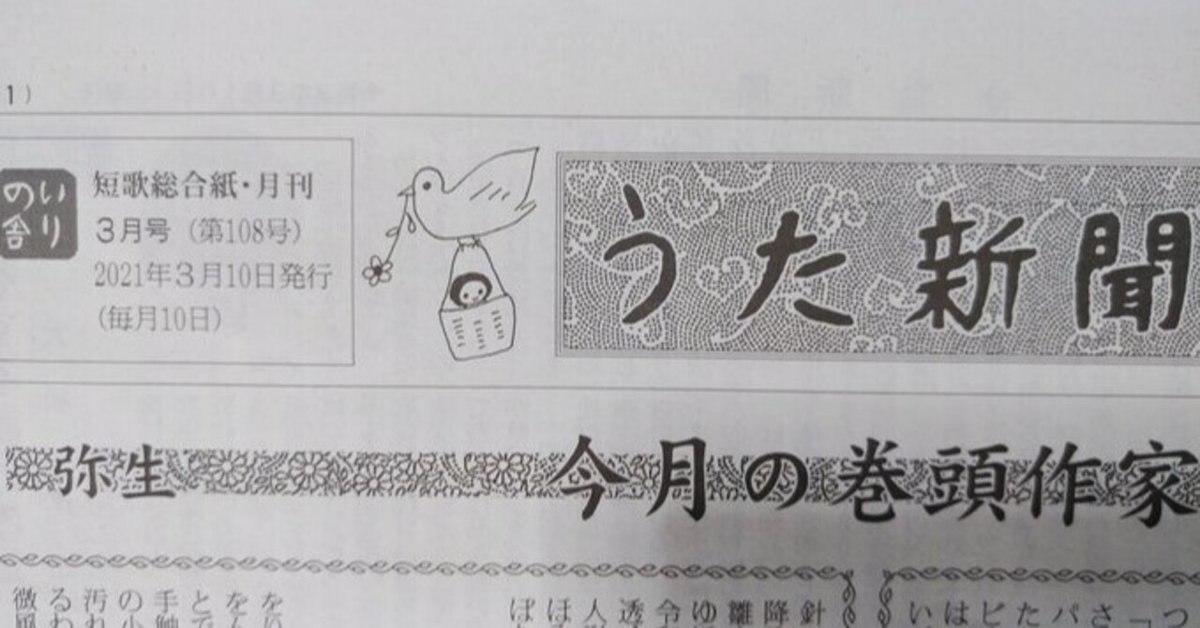
『うた新聞』2021年3月号(1)
①汚れたら死ぬ人形の並びをり死なぬ気がするわたしの前に 川野里子 雛人形をテーマに生と死を描く。人形は形代として人間の霊を宿す。死は想定外。しかし商品の雛人形は汚れたらキズ物として捨てられる。死なぬ気がしているだけで、自分は必ず死ぬと知っている主体。生死の逆転。
②吉川宏志「東日本大震災から10年」〈危険は何も変わっていない。けれども、人間は弱い存在なので、そればかり考えていると、精神がおかしくなってしまう。それで見えないものは見ないようにする。〉震災の時も、コロナの時もそうだった。一人にも、社会という集団にも当てはまる。
〈現在、短歌において重要なことは何だろう。(…)危機を忘れないこと、偽のイメージにごまかされるのではなく、本質に迫る言葉を生み出すこと、に尽きるのではないか。〉そして、そんな言葉を自分も生み出し、また他者の言葉を評価していくことだろう。
③大松達知「するする読める」千葉聡『グラウンドを駆けるモーツァルト』について〈短歌のおもしろさは「するする読める」ことにはなく、切り取られた言葉に引っかかりながら(顔をあげて窓の外を見たりして)、じわじわと心に沈む何かを感じることにあるのではないか。〉永田和宏が「一首の滞空時間」と言っていたことと通じる。一ページの字数が少なくても読むのには時間がかかるのが短歌だ。歌を味わうことは、歌に込められた時間を味わうことでもある。大松の疑問は販売促進の惹句に対してのものだろう。
④大松達知「するする読める」黒瀬珂瀾『ひかりの針がうたふ』〈かつての劇画調の大仰さやナルシスト感が、現実生活の底辺にうまく着地し、溶け込んでいる印象。〉結果的に褒めているのだが前半なかなか辛辣だ。「かつての」は主に第一歌集のことだろう。〈この欄の初回と二回目にはなぜこの時代に文語脈の歌を作るのかを考えた。その答えがこの歌集にもある。この詩形で人生の重みを引き受けるのにはまだ文語の重みが必要のようだ。〉なるほど。短歌に文語が不要だとは全く思わない。ただ、なぜ文語が「重み」と捉えられるのかをもっと聞きたい。
2021.4.1.~2.Twitterより編集再掲
