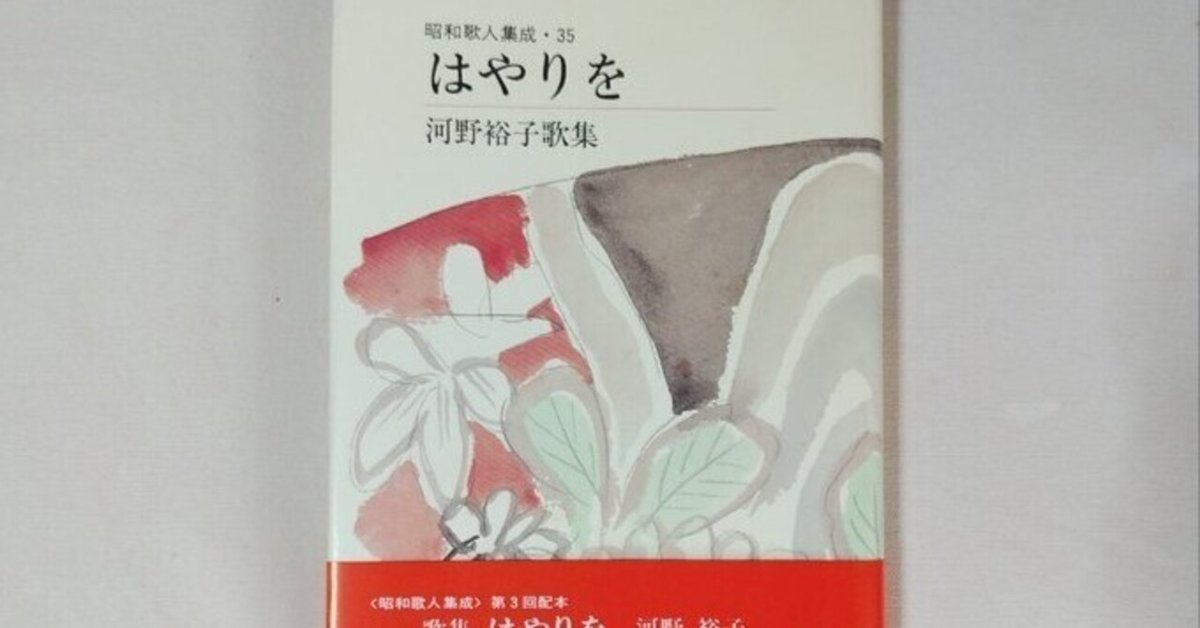
河野裕子『はやりを』 8
ずいぶん間が空いてしまったが、またしばらく『はやりを』を読んでいきたい。
はろばろと湖心に向けて漕ぎてゆくこころとこころの夜半の曳航 実際の曳航ではなく、心の状態を表す比喩だろう。広い琵琶湖を夜半眺めながら、その湖心に向けて心の舟を走らせる。二人の気持ちは櫂を漕ぐように揃っている。「ろ」の音の繰り返しがリズミカルだ。
過ぎてゆくほのかなことば ひるがほのそよぎの中に無人駅ありき 話し言葉は録音などしない限り、全て消えてしまう。その儚さを「ほのかな」と表現する。旺盛な蔓植物である昼顔がそよぐ中に無人駅があった。記憶の中をたどるような風景が上句と調和する。
追ひつけぬわれと知るゆゑその深きこゑは更なる優しさを帯ぶ 初句は歩く速度とも、何かの達成の喩とも取れる。きみに追いつけないわれ。それが分かっているからきみの声は更に優しさを帯びる。二人の関係性の優しさ、きみの思いやりの深さ。
眼を閉ぢてこゑを味はふああこゑは体臭よりも肉に即くなり 声は唯一無二、その人のみのもの。目を閉じて相手の声を味わう。体臭が肉体につくよりも、声の方が肉体にぴったりと貼り付いている。この肉体にはこの声しかない。肉体が死ねば声も死ぬのだ。
真裸であるより他なき生身なり鱗飛ばせて魚を逆剥ぐ 生身で生きていくほかはない人生。真裸の剝き出しのまま生きる。何かで取り繕ったりはできないのだ。同じく裸の魚の鱗を剥ぎ、更なる裸にしていく。その身を食べるための、言葉を使わない、体当たりの動作だ。
2023.6.10. Twitterより編集再掲
