
学習者から気づきをもらう - Batch01振り返り
先日、自分たちではじめた日本語スクールJ-Speak Lab
その初めてのクラスとなる1期生が卒業した。
ちょうど創業して1年が経つタイミングでもあるので、
振り返りとこれからについて書き記しておく。
J-Speak Labとは。- - - - - -
4ヶ月間ひたすらビジネス日本語をアウトプットするコミュニティ型のスクールだ。MOOCsなどのコンテンツ学習ではなく、コホート型学習(CBC)モデルをベースにビジネス日本語教育の文脈に落とし込んだカリキュラムを提供している。(この辺はまた今度書きます。)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Batch01では初回ということもあり、かなり小規模開催であったが、そんな生まれたてのサービスに参加してくれた学習者たちには感謝でいっぱいだ。
参加にあたって、不安や心配事もあったと思うが、選択し挑戦してくれたこと。そして本業や家庭と両立しながらも、かなりの量の課題にもついてきて、一緒に学習してくれたこと。誇りに思う。
反省 -うまくいったことを振り返る。
「"実践ベース"の授業です ! 」説明会にくる人に最初に説明する際によく使う表現だ。
今回この「実践ベース」というのを、かなり高い解像度で実践、提供できたんじゃないかと思う。
すでに就職している方がほとんどなので、自分の業務に関する内容を持っており、そんな学習者たちをターゲットにしているので、自分の業務ベースで、テーマに沿ったタスクを自分で設定を作り、自分で課題を作成する。
自分が扱っている商品の紹介や業務トラブル設定し、その対応までについて、メールや資料作成、プレゼンまで作ってくる。
課題発表時には、学習者同士で自分の課題の状況説明までセットで行い発表する。(自由にサービス考えてくる場合もある。)
実際に学習者から、
同僚の日本人社員に「なんか日本語うまくなったね」と言われるようになりました!。や「もうチェックなしで顧客へメール送っていいよ!」と言われましたと報告が上がってくる。
これはまさに狙っていたことが、うまく行ったと実感した瞬間だった
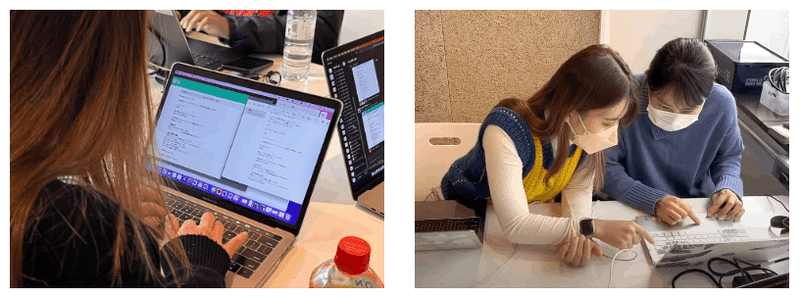
反省 -コミュニティ形成の難しさ。
授業以外のコミュニティ形成はかなり難しかった。
クラス外のメンタリングはそれなりに稼働もしており、うまく活用できたが、Slackでの学習共有や質問投げなどは、もうちょっと色々な仕掛けが必要だった。
私たちはあえてN3〜N1というある程度レベルの幅を持たせてクラス形成している。
その分、クラス外のコミュニケーションや学習者同士のP2Pが非常に大事になる中で、途中離脱(次のBatchで参加)の生徒を出してしまったのはもっとこちらからの意図的な仕掛けが必要だったなと感じる部分だった。
生徒は勝手には育たない。いいクラスちゃんと仕掛けがある。
これはもっといろんなクラスを見て学びを盗んでいこう。

反省 -次のBatchで実践すること
細かい修正点を挙げたらキリがないので、
大きなトピックとして以下2つ。
- デプスインタビューで深掘る。
これまではフェーズごとやカリキュラム終了時にアンケートを取ったり、カルテのようなものを用意したりしていたが、表面上の数字集めやコメントではなかなか本音を掬いきれない。
サービス初期だからこそ、デプスインタビューをする。
併せて学習者の情意フィルターに関する内容と目標設定と評価の具体化についても、より解像度を高くしてあげることできるはずだ。

- コンテンツは丁寧に。共有は身軽に。
領域ごとに必要な日本語表現が異なるから難しい。という言い訳をせず、ビジネス語彙表現の共通するものは学習のレールを敷き、専門領域に関するものはパーツごとに準備する。
各自でできるインプット学習は今より丁寧に、幅を広めて用意しよう。
そして学習、質問、雑談などあらゆる共有は雑でもいい。まずは投稿をすること。この辺の細かい仕掛けを増やしていく。
振り返り-Final Output Speech
これまで、規模は小さいながらも、30〜50人ほど企業や個人、学習者たちが毎回オーディエンスとして参加してくれる(相方の発信力の賜物…感謝です。)中で、いつもメッセージへの共感に関するコメントをいただける。
私たち自身も、この当日の発表を聞いてる瞬間が一番心を動かされる。

拍手を受けるという経験。
人前に立ち、「さぁ話そう」と思ったときに起こる、手汗、足の震え、口の乾き……このような一連の症状は、これは原始人が野獣に遭遇したときの「逃げるか戦うか」という体の反応と同じなのだ
人前に立つのは「何かを失うかもしれない。」「どう評価されるだろう。」と何か怖いものに感じることや、失敗してトラウマになる人もいるかもしれない。
それでもJ-Speak Labでプレゼンを実施しているかは、
人前で話し終えて拍手を受ける経験というのは大きな成功体験になるからだ。
ひとつの成功体験にはトラウマを凌駕する力がある。
これは私自身が外国語学習や越境学習を通して感じた原体験だ。
総合競技「プレゼン」を鍛えれば、話す力のすべてが育つ。
先日読んだ本にはこう書き記してあった。
「話す力」というのは教育のラストワンマイル。
総合競技「プレゼン」を鍛えれば、話す力のすべてが育つ。
「考える力」「伝える力」「見せる力」この3つの要素をそろってようやくプレゼンが完成する。そして母国語でも難しいことを日本語というハイコンテキストな文化背景を持った言語で行うのだ。
先日登壇した学習者が前日のメンタリングでこんなことを言っていた。
「日本語の表現は本当に難しい。含みのある表現を使ったり、でもそれだとプレゼンの時は伝わりづらくなったりする。」
その後も、深夜2時までやっていたメンタリングで、こういう表現はどうだろう?と投げかけると、ある表現に衝撃を受け「これだ。この表現だ・・・。」と衝撃を受けたような様子だった。
ストーリーを考えて、
伝える内容に構成して、
表現を磨いてオーディエンスに見せる。
「プレゼン」を鍛えれば、話す力のすべてが育つ。私も改めてそう思った。
これからのこと - 私たちのサブテーマ
J-Speak Labのことについてや、これまでの振り返りをベースに書いた。最後にこのスクールが掲げている、サブテーマについて触れておく。
このスクールで実現したいことは学習者のスキルアップの他にもう一つ、「日本語教育業界のアップデート」をサブテーマにしている。

既存サービスツールを使いながら、学習や学習環境のDX化を目指して、いろんなツールの導入をしているが、それでも実際にクラスを行うと学習者から課題の気づきをもらえることがある。
今回のBatchではメールタイピングに悩む学生から、ビジネス日本語のメールタイピングアプリのアイデアを得て、動くものを作った。
(Batch02の学習教材の一つとして試します!)

今回のように、ただのスクールではなく、学習者から気づきをもらって、テクノロジーで解決する。そしてそれらを試す研究所としてのラボ(LAB)の意味を、私たちは「J-Speak Lab」という名前に込めている。

学習者だけじゃないよ。
それ以上に教師もインプットとアウトプットしようね。と
みんなでお尻叩いていきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
