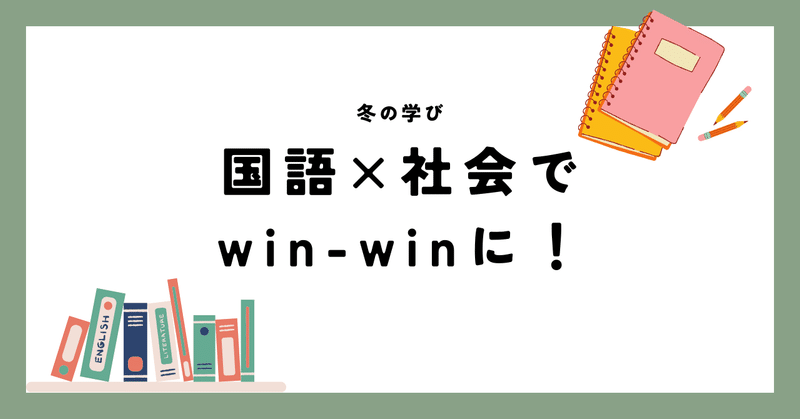
国語×社会でwin-winに! 冬の学び#5
前回の記事の続きになりますが、光村図書のウェブサイトに、「単元系統一覧表」というデータが掲載されています。
例えば、「話すこと・聞くこと」と一口に言っても、この系統表では、「言葉の準備運動」「聞く」「対話の練習」「話し合う」「話す」と5つの領域に分けて書かれています。
1年間の中で、それを順序よく、6年間でスパイラルに学習するような構成になっています。
これを、他教科とコラボして考えたどうなるのかを示してみたいと思います。
令和6年度から教科書は新しくなりますが、既に各教科書会社から、令和6年度の教科書に合わせた年間指導計画が出されています。東京書籍の3年生のものを見てみます。
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/shou/shakai/data/shakai_3_keikakusaian_202307.pdf
各単元で、次のような「生かす」活動が設定されています。紙面を見ていないので、文面からの推測になります。
市の様子→市を宣伝するポスターをつくる
生産・工場→キャッチコピーを作る
販売→新聞にまとめる・生産者、販売者と消費者のつながりを考える(関係図?)
消防・警察→図や表にまとめたあと、標語をつくる
市の移り変わり→ポスターにまとめて、市役所の人に見せて意見を聞く
当然ながら、教科書会社が違うと、この辺りの整合性とか連携の部分はちょっと弱くなっている気がします。ですが、社会科でまとめをするためにポスターの作り方やキャッチコピーの作り方を指導していては、時間がいくらあっても足りません。そこで、国語科との連携なのです。社会科の教科書に出ている例は例示なので、変更もありだと思います。
国語の教科書の例に合わせて、このように変えてみてはどうでしょうか。
市の様子→市の様子を離れてくらしている◯◯さんに、様子を伝える手紙を書こう
生産・工場、販売→仕事を見学してみつけたくふうをつたえる報告文を書こう
消防・警察→消防・警察のひみつを教えます!(説明文)
市の移り変わり→〇〇市物語をつくろう!
活動を変えるだけでなく、確かな相手意識があることで、学習が進むことは、諸先輩方の実践で証明済みです。そして、これらの文章の書き方を学ぶためにも、国語の教科書に掲載されている教材文を読んで、書き方を学ぶ必要性が生まれます。国語科にとっても、社会科にとっても、win-winなわけです。こんな実践はいかがでしょうか。
ご感想、ご意見を頂けたらうれしいです!お読みいただき、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
