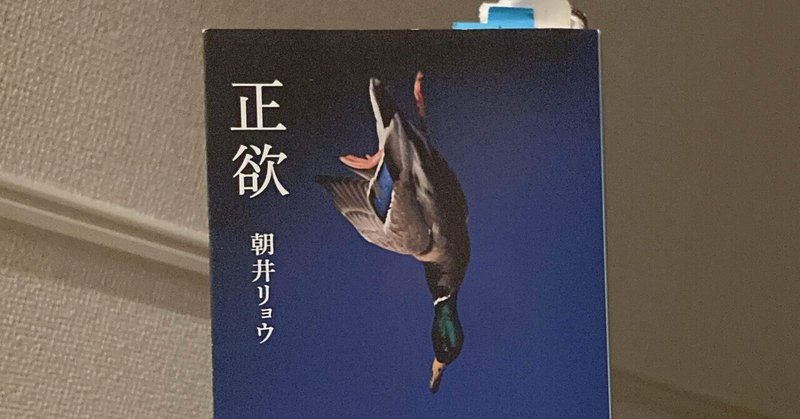
[本]「正欲」を読んで
ネタバレになるかもしれないので、大丈夫な方のみ読んでいただければと思います。
-----------------------------------------------------------
語彙力と思考力がないばかりに扱いきれない、自分の頭の中で動き回っている苦しさに似たもの、感情、それら全てに言葉が付与されていくような感覚。
それと同時に、読めば読むほど、流れてきた思考が抱えきれず頭から溢れていく。
東畑開人さんによる解説に、「この物語は手に余る」とあった。「正欲にがんじがらめにされる」とも。
まさにそうだと思う。手にあまる。がんじがらめ。
誰かにとっての正しさが、誰かにとってはそうでなかったりする。結局のところ正しさって何なのか。....こう書き出してみて、続けようとするが、まとまっていないあらゆる思考がそれを邪魔する。書いては消してを繰り返す。がんじがらめ。
ただ、やはりこの言葉に収斂するのではないかと思う。
「多様性とは、都合よく使える美しい言葉ではない。自分の想像力の限界を突き付けられる言葉のはずだ。時に吐き気を催し、時に目を瞑りたくなるほど、自分にとって都合の悪いものがすぐそばで呼吸していることを思い知らされる言葉のはずだ。」(p.248)
自分の想像力を遥かに凌駕するほどのものが、隣で息をしているかもしれないという事実を知っておく。自分の正しさを押し付けることをせず、ただそうした事実があることを知っておく。この場合、自分は知られる側かもしれないし知る側かもしれない。どちらもあり得る。このことを私は知っておくべきなのではないか。
最後の方に、「網を編む」という表現がある。
死を望みつつも、どこかで生を求めていて。自分をを「この星に引き留めて」おくために、繋がりを作って、落ちても受け止められる網を、互いに、一緒に、編んでいく。卑屈になるのにはもう飽きたから。この世界で生きていくしかないから。自分の為に。その網をなしているものが何であれ、そこに孤独や死がないのなら、それでいい。
あともうひとつ。
私は親が苦手だ。家族が苦手だ。
帰る家はあるけど、帰りたい家はない。でもどうしてなのか分からない。経済、教育、環境全てに恵まれていた。今だって学費、家賃、仕送り、光熱費を払ってもらっていて、あらゆる経済的恩恵を享受している。そして親がそうしてくれるのは、家族だからだという。
だけど私は、それが分からない。「家族だから」と言ってしまえば全てに説明がつくかのように行っている人のことが、理解できないでいる。
愛を受け取っていたはずなのに、私はそれを返せない。持ってないものは渡せない。だから返すフリしか、できない。
そのどうにも埋まらないズレが、苦しかった。
「そんな風に思いたいわけじゃないのにね」(p.281)
夏月のこの言葉で、少し救われた気がした。
そんな風に思いたいわけじゃない。
本当は、自分の哲学を晒して、対話ができる関係性でありたかった。愛してるよ大切だよって心の底から思えて、伝えられる人でありたかった。
本当は、そう思いたい。
私のズレは消えないし、何も解決しないけど。
本当はそう思いたいわけじゃないのにね、と言われたことで、ズレを抱えていること、そしてそういう自分に対する嫌悪感全てを、まるごと肯定してもらえたように感じた。だから、少し楽になれた気がしている。
「私たちみたいな、という言葉が、テーブルの真ん中に落ちる。
同じ界隈、という言葉も、テーブルの真ん中に重なっていく。
『その人、ひとりでいないといいね』
うん、と佳道は頷く。
『誰も、ひとりでいないといいよ』」
(p.308-9、一部中略)
読後の心地よい疲労感と、全てを捉えきれいないことに対する悔しさと。
--------------------------------------
最初は読んでいて、先に書いたように、自分の今抱えているこのぼやっとした「生きづらさ」に名前がついていく、言葉が付与されていく感覚があった。
芥川龍之介が「唯ぼんやりとした不安」で死を選んだことに、何となく共感していた。
ぼんやりとした不安。捉えようのない、不意に現れてからずっと居座っている、原因がわからないから無くし方もわからない、だからただ抱えるしかない、この不安。
私にとっては、その不安に、言葉がついていくようだったのだ。
そして気づく。
じゃあ私に不安を与えているのは一体何なのか?
読んでいる途中で、また気づく。
孤独だからなんじゃないか、と。
小説の中で、年末年始のイオンが出てくる。
「大切な人に」「家族や仲間たちと」
そう言った言葉が並ぶ、明日生きていたい人のための場所。一緒に過ごせる人がいる人のための場所。誰かに必要とされている人のための場所。
「しんどいよね、年末年始って」
「自分が誰の一番でもないってこと、思い知らされるっていうか」
「大晦日とか正月って、人生の通知表みたいな感じがする」(p.275)
自分もそうだ。ただ読んでいて、そう思った。
親友がずっと、「誰かの一番になりたい」と言っていたのを思い出す。私にはよく分からなかった。ああ、こういうことか、と今更納得する。恋人と一緒にいる彼女は今、孤独ではないのだろうか。聞いたことはないけれど、少なくとも、私は彼女と以前のように孤独を共有することはできないと感じている。でもそれはきっと、彼女が孤独でない何よりの証拠だろう。ならそれでいい。
私の孤独はどこからくるのだろう。
次はそう考えてみる。読み進めていく。
「『そんな風に思いたいわけじゃないのにね』
そんな風に思いたいわけじゃない。
本当は両親とも、それ以外の人とも、人生や未来、色んなことについて話したい。
哲学を晒して対話をしてみたい。
(中略)
これまで出会った人たち全員、修のことも沙保里のことも、本当に嫌いになりたかったわけじゃない。
こうして身体を上下させながら生きている自分のことだって、本当は愛したい。」
(p.281)
そうだ、と思った。
家族が苦手で、そんな自分が嫌だった。
でも家族に会うと、息ができなくて、苦しかった。
できれば会いたくない。帰省だってしたくない。家賃学費仕送り光熱費、これまで20年間私を生かすために使われたお金を含めたあらゆる経済的恩恵と、親の教育リテラシーのおかげで今がある。それに対して何かしなければならないという、娘としての義務みたいなものだけが、私を家族の元へと向かわせる。
でも、本当は、そんな風に思いたいわけじゃない。
映像の奥にある、家族愛という言葉でしか形容できない感情を共有している親子みたいになりたかった。そういう家族を、持ちたかったのだ。
最近ある友人が、両親の離婚が決まったらしく、「帰る家がなくなった」と言っていた。
それを聞いて、私は思う。
私には帰る家はあるけど、帰りたい家はないんだ、と。
そして思う。帰りたい家がない、それはつまり、帰りたいと思える人が私にはいないのだ、と。
私はひとりなのだ、と。
また読み進める。
読み進める。
「『もう、卑屈になるのも飽きたから』
飽きた。
もう、卑屈にすっかり飽きたのだ。
生きていたいのだ。
この世界で生きていくしかないのだから。」(p.379)
こうして主人公たちは、自分をこの世に繋ぎ止めてくれるものを、自分たちで紡いでいく。
また読み進める。
そして八重子が言う。もう誰かに分かってもらおうとか、どうでもいい、ばいばいでいい、と塞ぎ込もうとする人間に、言う。
「そうやって不幸でいる方が、楽なんだよ」(p.449)
誰かに分かってもらいたい、分かち合いたい、孤独になりたくない。そう思うからその先で傷つくことになる。だから、不幸なままでいた方が楽なのだ。そう思っていた。
でも、八重子が叫ぶ。分からないから、話そうとしてるんだ、理解できるか分からないけど、理解したいのだ、と。
不幸なことを言い訳にして逃げたくない、自分を削るものばかりのこんな世の中でも、こんな自分でも、生きていくために。
だんだん、細かった光の線が柔らかく広がっていくように、希望が見えてくる。
最近、生まれて初めて「しんどい」と言えた。
自分が話してるんじゃないかとたまに思う人に、哲学を晒せる人にも、最近出会えた。
でもそれは、自分が傷つく覚悟を持って、ご飯行こうと誘い、関係を深められたからだ。
少し前まで、人を誘うのが苦手だった。
自分のことを話すのが、苦手だった。
傷つくから。自分を守るために、閉ざすしかなかったから。
でも、いろいろなことが重なって、傷つく覚悟を持ってでも、私は今を変えたいと思うようになった。もっと色んな人と話したいと思えるようになった。
その結果、「しんどい」と言えるようになった。哲学を晒すのが怖くない人に、出会えた。
それとほとんど同じタイミングで、読み終わる。
何故か、大丈夫な気がしてきたのだ。
孤独は消えていない。誰の一番でもない。
でも、今は、大丈夫な気がしている。
この本は、私にとって、光になった。
このタイミングで出会えたのは、本当に運命なんじゃないかと、馬鹿みたいなことを思うくらいに、大切な本になった。
先に映画を見に行って、それで読もうとなったのだが、映画の主題歌であるVaundyさんの「呼吸のように」という曲が、また私の孤独に寄り添ってくれる。最近公開されたMVの磯村勇斗さんやひとり立っている女性が自分に見えた気がしたり。
ちょっと感傷に耽りすぎか。
まあ、とりあえず。
「明日死にたくない」と思える人たちに、この世界はどう見えているのか、私は知りたい。
今はそれを生きる理由にしようと思う。
もう一度読もう。
長くなりました。もう4000字超えました。
また。
大屋千風
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
