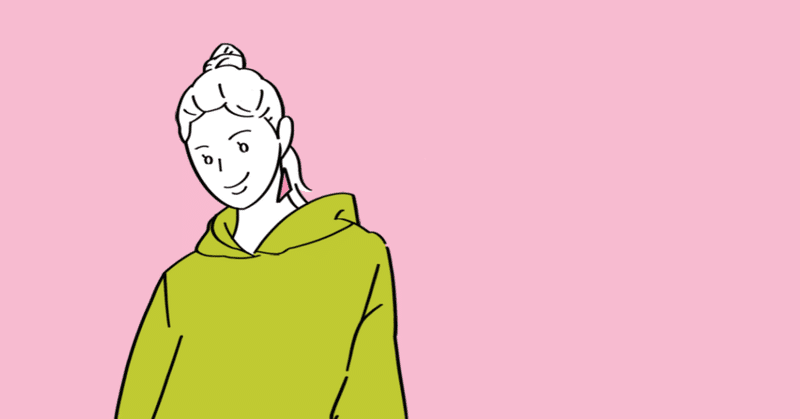
裏起毛と、わたしの間にあるもの。
服を買った。あたたかいスウェットを。黒のシンプルなデザインで、早速お気に入りになっている。
しかも、裏起毛なので暖かい。
いや、暖かいはずだった。
木枯しが、ひょおっと、脇を通り抜けて行った。その刹那、スウェットの中にまで、秋の風は忍び込んできた。
暖かいと思って買ったはずのスウェットは、私を暖めてはくれなかった。
裏起毛だというのに。
*
ぽつり、ぽつりと街灯が立ち並ぶ暗い坂道を、とぼとぼ歩きながら考えた。
どうして、暖かいはずのスウェットを着ているのに、こんなにも冷えるのだろう。こんなにも、秋の風を感じるのだろう。裏起毛だというのに。
答えは簡単だった。
サイズが合っていなかったのだ。
いや、合っているのかもしれない。小柄な私はいつも、Sサイズを購入する。
だから、このスウェットもSサイズ向けだ。少し大きいかもしれないが、ダボっとしたシルエットが可愛いので、そこは誤差の範囲内だ。
じゃあ、もっと小さいサイズを買えば良かったのだろうか?
問題は、そこにはない気がしている。気がするだけで、確信はできなかった。
考えを深めようと頭を働かせる度、冷たい風が服の中にまで通り抜け、あちらこちらに巡らせた思いまでも一緒に、連れて行ってしまう。秋の深い、夜の中に。
両の腕をギュッと組み、自分の体を抱きしめる。
ああ、寒いなあ。
裏起毛だというのに。
*
コンビニに立ち寄る。
生暖かい空気が遠慮もなしに、冷えた身体を包み込む。気まずい暖かさに触れ、心がぐにゃりと緩む。
中にもう一枚、着込めば良いのかな。薄手の何か、カットソーかシャツか、そういう類のものを。
だけど、それじゃあ、触れられないのだ。裏起毛の、あの柔らかさに。
裏起毛はいつだって暖かいけれど、特に暖かさを感じるのは、触れた瞬間だ。何人たりとも拒まない、平等な優しさ。神様の愛も、こんな感じなのかもしれない。
ああ、触れていたい。あの優しさに。温もりに。
いつまでもずっと、すやすやと眠る猫の額を撫でるように、優しく、そっと、触れていたいのだ。
それを隔てるのものは、必要ではない。むしろ、あってはならない。裏起毛と、私の間にあっていいものなんて、ない。
だから私は、薄手の何か、カットソーかシャツか、そういう類のものを着込むなんて、できることならしたくなかった。
じゃあ、どうすれば良いのだろう。
私を暖めてくれるはずの存在を、直に感じて、その愛に触れるには、どうすれば。
コンビニの外の空気は、さっきよりも冷たくなっていた。
*
どうすれば良いのか、なんて考えたところで答えは出ない。ただ、一つだけハッキリしたことがあった。
それは、私は「間違った」ということ。
あの時、あのスウェットを「裏起毛だからきっと暖かい」と、そう思ってしまったこと。それが間違いだった。
もちろん、試着はした。試着せずに洋服を買うことは、ない。
あの日も、スウェットを試着した。
ああ、裏起毛なんだ。暖かくて、心地良くて、可愛くて、買うしかないな。そう思って購入に至った。
だけど私は、ちっとも気づかなかったのだ。
その試着室に、秋の、冷たい、木枯しが吹き付けることは決してない。ということを。
試着室の中はいつだって、完全で、完璧で、穏やかで、健やかで、平和で、守られている空間だ。そのことに、気づかなかったのだ。
困難など一つもない空間で、私は価値を見出そうとしていたのだ。
だから知る由もなかった。このスウェットに、秋の冷たい風が通り抜ける隙間があることを。暖かいに決まっていると、油断していた。
だって、裏起毛だから。
あんなにも触れたい、触れたいと思っていた裏起毛に、今、触れて気づく。
そこには愛なんてなかったし、温もりなんて全くなかった。
付き合えば、結婚すれば、恋人になれば、家族になれば。
そこには愛があると思っていた。温もりがあると思っていた。
だって、裏起毛なのだから。恋人なのだから。家族なのだから。
雨や風や雪や、あられや嘘や嫉妬、依存、偽り。そういったものは、試着室には一切ない。
だから、気づけなかったのだ。
裏起毛が暖かいのは、触れた時だけだということに。
やはり私は、薄手の何か、カットソーかシャツか、そういう類のものを一枚、中に着込むべきなのだろうか。
あるいは、スウェットのことは諦めて、もっと暖かい素材のセーターにすべきなのだろうか。
あるいはーーーーーー。
裏起毛と、わたしの間にあるもの。
木枯しが通り抜ける隙間なんてない、温もりだけの冬が、いつかきっと訪れますように。
いつもありがとうございます。いただいたサポートで、瑞々しいりんごを買います。
