
2024年1月のふりかえりと読書記録
今年は早くも1月5日から授業が始まり、授業最終回が大学や開講曜日によってそれぞれズレていて、最後は29日(年々、授業期間が長くなっているような…)。
少しずつ授業準備が減っていったので、ものすごくきゅうきゅうというほどではなかったものの、なんとなくアレコレあって、初詣も行けないまま1月が終わりました。(^_^;)
授業以外では、昨夏のチェコ行きを反映させた小さな原稿を書くのに、関連書籍を集めて読んで。
その他、下の息子が美術部の先生から勧められたというので日展の京都巡回展を観に行ったり、
仲良くしていただいている先生と恒例のプチ打ち上げ女子会をしたり、
映画(「オキナワサントス」「Filip」→いずれも後日別途記録予定)や「シュルレアリスムと日本」展を観に行ったり、
何科目か私の授業を取ってくれて、意欲的に取り組んでくれた卒業生さんたちの大学最後の授業が、ちょうど私の授業だったので、ミニ打ち上げ&卒業おめでとう会をしたりと、お楽しみも入れることができました。

この学年は、入学前にコロナが流行り出して、1年生春学期はまるっきり大学に入れませんでした。大学生活の半分くらいは、行動に大きな制約がかかっていたのではないかと思います。その学年が、もう卒業とは…
そんな思い出話や、これからのことなどを楽しくお話して、お腹いっぱいになって、これからますます羽ばたいていかれる若者の活躍を祈念して、晴れやかにお別れしました。
2月は、まずは採点。今学期は200人ほどの科目があるので、ヒーヒーになりそうです(汗)
それを終えたら、片付けしたり、勉強したり、文章を書いたり、じっくりとインプットに励む予定です。
読んだ本の数:13
読んだページ数:3385
ナイス数:391

美術泥棒 (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズⅣ)の感想
図書館でひょいと見つけて。数年に渡ってヨーロッパ数か国の美術館から、アーミーナイフ1本で白昼堂々250点もの美術品を次々に盗んでいったカップルの話。売り払うわけではなく、ただただビビッときた美術品を自分の手元に置いておきたくて盗みを重ねる。ええ~ほんまかいなと何度もつぶやきながら夢中で読み進める。主犯の窃盗癖が酷くなっていって、とうとう発覚するのだが、そのあとからは元恋人や母親の供述が主犯と食い違い、果たしてここまで読んでたこともどこまでが本当なのかわからなくなる。著者が泥棒に入れ込んでしまったのか。
読了日:01月03日 著者:マイケル・フィンケル

生還者(サバイバー)たちの声を聴いて: テレジン、アウシュヴィッツを伝えた30年の感想
著者はナチ・ドイツ占領下のチェコのテレジン収容所で子どもたちが描いた絵を日本に紹介しつづけているノンフィクション作家。すでに関連本は何冊も出されているが、本書は30年に渡る元被収容者らとの交流を振り返るもの。もうじゅうぶんやってきた、いやまだまだ伝え続けねばならないという切迫した思いが伝わる。
読了日:01月05日 著者:野村 路子
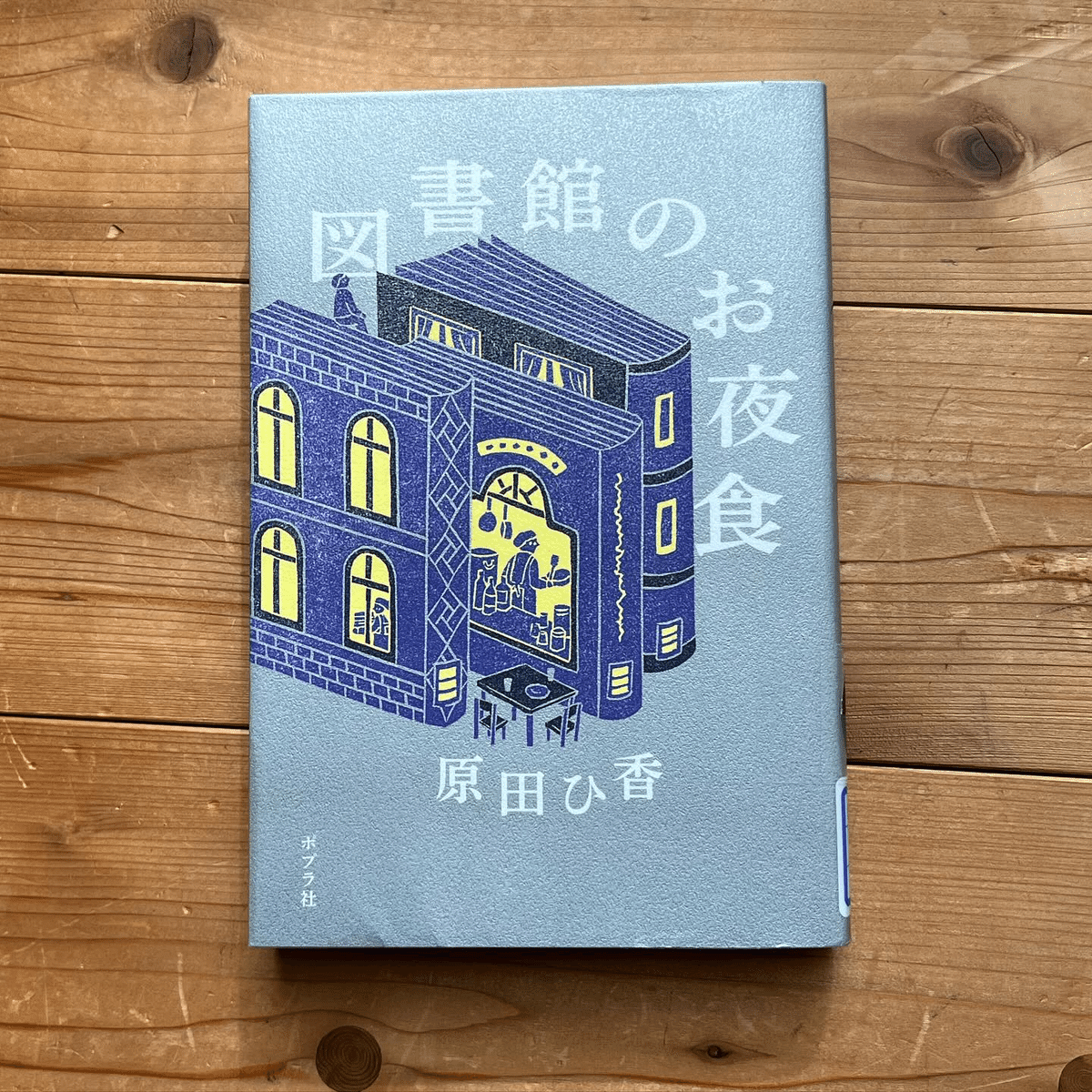
図書館のお夜食 (一般書)の感想
図書館でお夜食?と本屋さんで見かけて気になっていた本。作家の遺した書籍をまとめて受け入れて閲覧に供する、夜にだけ開いている図書館に集まってくる人々の話。みんな少しずつカゲというか事情のある人たちなのがわかっていくという趣向なのだが、終盤で話が急に素人くさくなって中途半端に終わる。設定を詰めきれずに書き始めてしまったのだろうか。タイトルのお夜食とは、この図書館のカフェのまかないで、本の中に出てくる食事を再現したメニュー。この設定も良かったのになあ。残念。
読了日:01月06日 著者:原田 ひ香

改訂新装版 テレジンの子どもたちから: ナチスに隠れて出された雑誌『VEDEM』よりの感想
チェコのテレジン収容所で生み出された子どもたちによる雑誌を日本に紹介した本の改訂版。親と引き離され、すし詰めの部屋での共同生活、まったく足りない食事や衣服、きつい労働を強いられるなかでも、子どもたちは豊かな芸術性を発揮した。そうした創作活動を導き、支えた大人たちの存在も紹介。関西ウーマンの書評連載で取り上げました。https://www.kansai-woman.net/Review.php?id=202368
昨夏、訪れたテレジンの様子をまとめたブログへのリンクも貼っています。併せてどうぞ!
読了日:01月10日 著者:林幸子

日本列島「現代アート」を旅する (小学館新書)の感想
直島や金沢21世紀美術館、東京藝大の美術館などで現代アートをプロデュースしてきた第一線の専門家による、日本国内で楽しめる現代アートの紹介。柔らかい語り口で、わかりやすく親しみやすく作家や作品が紹介されていて制覇したくなる。マーク・ロスコの作品を観に行こうと思って借りた本だが、アートファクトリー城南島にも行こうとさっそく計画に組み込んだ。金沢の「ブルー・プラネット・スカイ」はある時間帯に、その場にいないと体験できない特別な作品らしい。これもまた計画しなくちゃ。
読了日:01月11日 著者:秋元 雄史

僕の陽気な朝 (文学の冒険シリーズ)の感想
次々本を読む演習で取り上げる学生さんが現れたので再読。ずいぶん昔に読んで面白かった印象はあったものの内容はすっかり忘れていた。社会主義体制下、職を追われ、資格などがいらない仕事にしか従事できなくなった作家の実体験を反映した短編小説。深刻過ぎず、ユーモアとエロティシズムとペーソスの効いた、ああチェコ…な雰囲気。地下出版しかできなかったクリーマの本が民主化後、発行されたときには、サイン会に長蛇の列が出来たそう。それほどの人気作家なのだが、邦訳がほとんどないのが残念。
読了日:01月14日 著者:イヴァン クリーマ

ナチス占領下の悲劇 プラハの子ども像の感想
絶版になった草の根出版会「母と子でみる」シリーズの『プラハは忘れない』と『エルベの誓い』を合冊した本。前者は1995年当時の様子がわかって興味深い。ここで「ひとりぼっちの地下記念館」として紹介されているハイドリヒ暗殺犯立てこもり現場は、今では国の「英雄」記念碑として多くの観光客を集めている。後者は、WW2時に、米ソ軍が合流したエルベ川での邂逅をめぐる話。こちらは初めて知ったことばかりでこれまた興味深かった。
読了日:01月18日 著者:早乙女 勝元

野の花は生きる―リディツェと広島の花たちの感想
ナチ高官暗殺の報復で消し去られたチェコの村リディツェの話から、広島の似島で原爆で亡くなった家族の遺骨を探す遺族の話へと繋がっていく。執筆当時にまだ続いていたベトナム戦争を憂う作家の思いが背景にある。児童文学者のいぬいさんの文章の美しさと挿絵がマッチしている。現在入手しにくくなっているようだが、読み直されるべき本。
読了日:01月21日 著者:いぬい とみこ

トミーが三歳になった日―ユダヤ人収容所の壁にかくされたベジュリフ・フリッタの感想
戦時中にドイツが設けたテレジーン・ゲットーに収容された画家が我が子のために秘密で描いて隠していたスケッチに、のちに解説とことばをつけて本にしたもの。絵はほのぼのしているが、解説や生き残った関係者の話は非常に重い。両親を失ったトミー本人も生き延びて彼を引き取った画家の同僚夫婦もトラウマを抱えて非常に辛い日々を送ったよう。昔、図書館で納本のアルバイトをしていたときによく見かけていたが、内容はまったく知らなかった。テレジーンの博物館に原画(複製?)が展示されていたが、駆け足でじっくり見れなかったので再訪したい。
読了日:01月21日 著者:ミース バウハウス

侵略日記の感想
本を次々読む演習で学生が取り上げてくれた。本書はロシアによる全面侵攻直前から半年の記録。クルコフはロシア出身だが、ウクライナ人として生きる覚悟を前面に出していて緊張感がある。発表した学生も言っていたが、日本の報道だけではわからない現地の雰囲気や具体的な動き、人々の思いが伝わってくる。本書は英語で書かれたものからの翻訳なせいか細かな訳注はないが、あればあまり詳しくない読者に親切かも。クルコフは2013-4年のマイダン革命のときの日記も出していて(『ウクライナ日記』)、そちらもたいへん面白い。
読了日:01月22日 著者:アンドレイ・クルコフ

わたしはスター―テレジンからの生還者の感想
著者はドイツ南部の村からチェコのテレジーン・ゲットーに強制移送されたユダヤ人。本書では、ユダヤ人差別の歴史的経緯と、著者個人の体験とが語られる。テレジーン・ゲットーでは通常は大人と子どもは別に収容されたのだが、著者は父が第一次大戦での負傷退役軍人ということで家族でまとまって暮らすことができ、解放まで生き延びることができた。とはいえ、ゲットーでの暮らしは酷いものであったには違いないが、家族揃っての帰還後も温かく迎えられ、家業も再興できたこともあってか、比較的明るさのある本になっている。
読了日:01月24日 著者:インゲ アウワーバッハー

マトリョーシカのルーツを探して 「日本起源説」の謎を追うの感想
「マトリョーシカは日本の入れ子細工が起源だった」説を検証した本。検証の方法やわかったことが調査のプロセスに沿って易しい言葉で説明されているので楽しく読み進めた。結論を言えば「まだわからない」ということになるが、それでもここまでにわかったことや周辺情報だけでも充分興味深い。本題とは少しずれるが、日本に赴任していたニコライ大主教の日記に、大津事件のときロシア皇太子が手当てを受けた家をロシア人が買い取ろうと相談を持ちかけたという記録があるとのこと。面白い~。大主教日記、見てみよう!
読了日:01月27日 著者:熊野谷 葉子
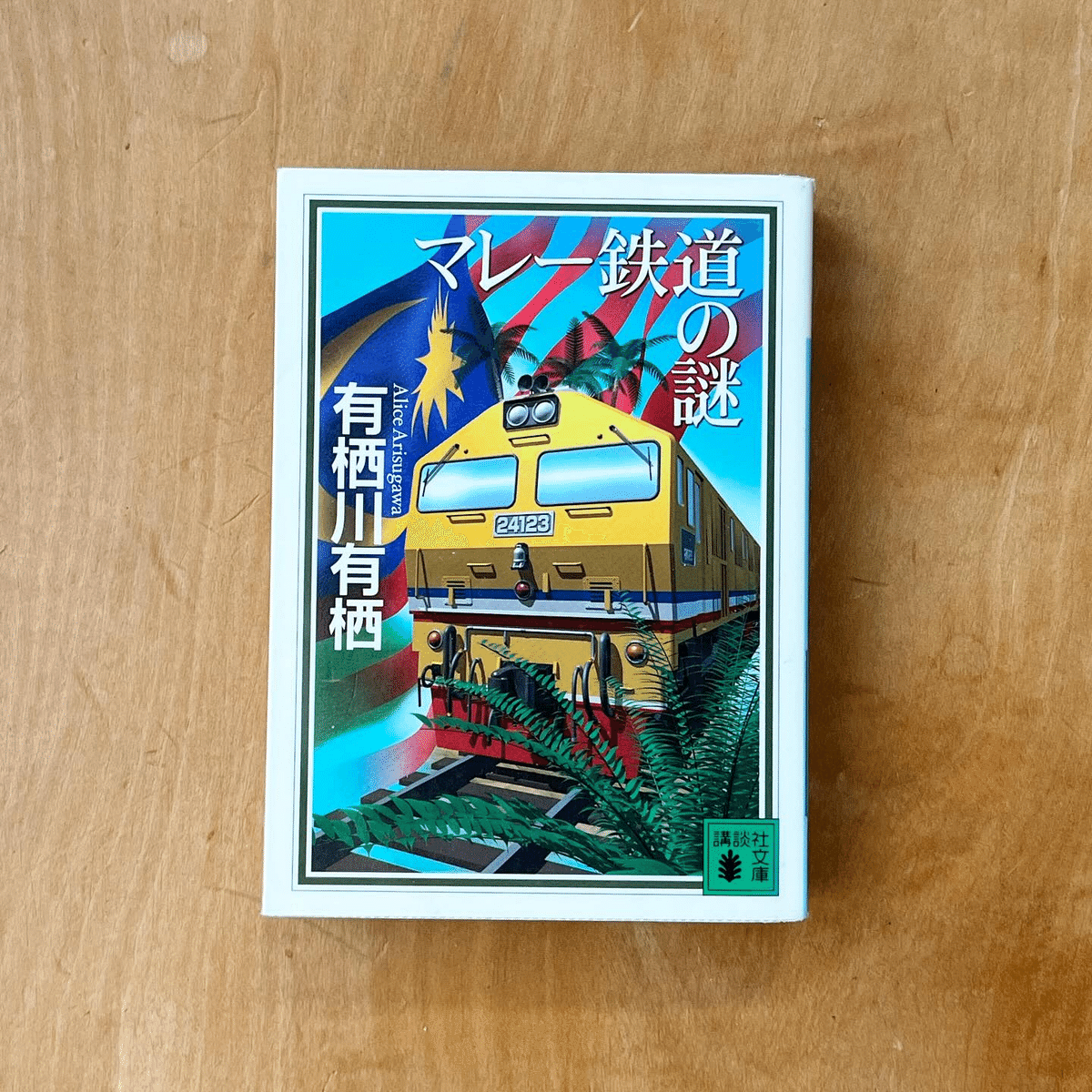
マレー鉄道の謎 (講談社文庫)の感想
夫氏が借りてきたのを私も。学生時代の友人が経営するリゾートホテルを訪ねて行った主人公らが連続殺人に出くわす話。密室トリックはちょっと無理があると思うし、名探偵役の大学助教授のキャラクターもいかにも過ぎて、そんなに良いとは思わないけど、作家と同名の登場人物の存在が嘘っぽさを和らげていて、コミカルさを出していて楽しく読める。この同名キャラの心の声が他の登場人物から発せられる偏見なんかを中和していることで、この作家の小説は読んでいてモヤモヤしないんだなと今作で確認した。
読了日:01月30日 著者:有栖川 有栖
読書メーター
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
