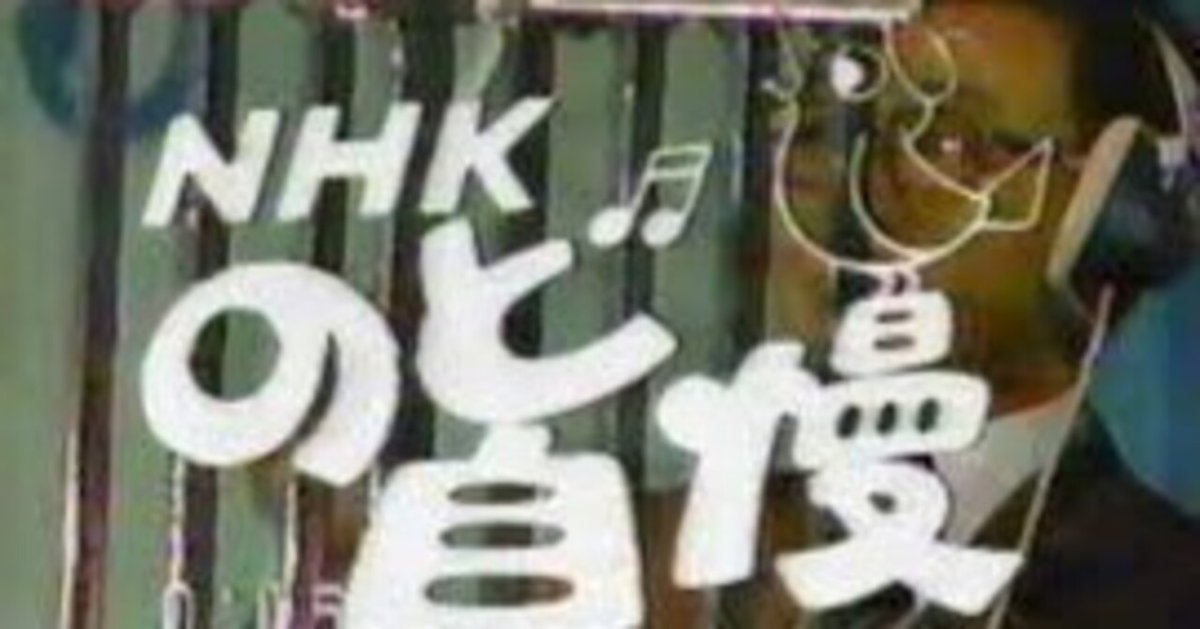
戦後歌謡曲の歴史
個人的な印象
今より単純な和音展開とリズム。
戦後にレコード&映画で明るい曲が大ヒット。実は…
1946年発売「リンゴの唄」(そよかぜのテーマ曲。作曲:万城目正(まんじょうめ・ただし)並木路子の歌唱)は、戦後に希望をと、明るく歌われた大ヒット曲の代表だが、実は、戦中に作曲された。
1947年発表「東京ブギウギ」(鈴木勝の作詞、服部良一の作曲、笠置シヅ子の歌唱)は、アメリカへのあこがれの現れと解釈されている。実は、服部と笠置が所属する松竹楽劇団は、戦前から活動しており、この2人がジャズのリズムである「ブギ」を用いたのも戦前からである。戦前からアメリカ音楽の洗礼を受けていた作曲家などが、戦後に再び戻ってきたと言える。
戦前の音楽家が、戦後も活躍を再開したことから、戦前・戦後の音楽と区別をはっきりするのは難しそうだ。
「リンゴの唄」「東京ブギウギ」のように、当時娯楽の王であった映画で主題歌として使われ、レコードでも人気になるという流れは主流になっていたらしい。レコード会社は、大衆的な(明るく分かりやすい?)音楽を作り出そうとしてきた。しかし、戦後に明るい曲が出回るのは、抵抗を感じる者もいたらしい。知識人層は、レコード会社の企画する大衆音楽に対して、単純とか低俗というような評価をしていたという。

ラジオで別れの歌がヒット
戦後は、国民に希望を与えるような明るい曲がヒットした印象がある。しかし、お茶の間で映画と並ぶ娯楽の王となったラジオからは、抑留や海外からの引き上げを経験した人の心の刺さる、別れを歌う曲がヒット曲のほとんどだったという。例えば、「悲しき竹笛(作曲:古賀政男。歌:奈良光枝)」「啼くな小鳩よ(歌:岡晴夫)」「夜のプラットホーム(作曲:服部良一。歌:二葉あきこ)」「港が見える丘(作曲:東辰三。歌:平野愛子)」「フランチェスカの鐘(作曲:古関裕而。歌:二葉あき子)」「湯の町エレジー(作曲:古賀政男。歌:近江俊郎)」「長崎の鐘(作曲:古関裕而。歌:藤山一郎)」「水色のワルツ(歌:二葉あき子)」などが挙げられる。
GHQ占領下のラジオ放送
NHKの「のど自慢」は、ラジオ番組として1946年1月に始まった。この番組は、GHQの放送民主化指令で企画されたものであった。戦前のレコード歌手は音楽学校出身者か有力な作曲家や歌手の弟子がほとんどだったため、素人がラジオに出演できることに、民主化を感じられる。
なぜかは定かでないが、のど自慢大会で合格するのは、より西洋芸術音楽に近い歌唱法で芸術歌曲に近い楽曲を歌う出場者だったらしい。GHQの好みだったのだろうか。
アメリカの影響を受けたヒット曲
レコードからではなく、ラジオから有名になった作曲家に三木鶏郎(みきとりろう)がいる。1947年に連合国軍占領下で開始された三木初のレギュラー番組『日曜娯楽版』では、日々のニュースや話題等を風刺した「冗談音楽」をつくり、一世を風靡した。もちろんGHQの批評はご法度だったらしい。
占領終結後、民放に移った三木は、CMソングを次々とヒットさせる。テレビ普及後はさらに民衆に広まった。三木は、戦前に西洋芸術音楽の教育を受けていた。また、占領軍のキャンプでの演奏を行っていた。そのこともあり、(西洋の)分厚く複雑なビッグバンドの響きや洗練されたコーラスが、彼の考える高尚な大衆音楽のモデルだった。
占領終結前後から、占領軍のキャンプでアメリカ軍のために音楽活動していた歌手が、大衆相手に活動を始めた。その筆頭、江利チエミと雪村いづみは、同年齢の美空ひばりとともに「三人娘」を形成した。
江利チエミは、1952年にアメリカの歌を和訳して歌った「テネシーワルツ」でデビューしている。ちなみに、実写版の初代サザエさんを演じている。江利の父の名は益雄(ますお)と偶然の一致だ。


戦後歌手への世代交代
戦後、戦時歌謡の作詞家・作曲家の中には戦争賛美に加担したことを「戦犯」といわれ、活動をやめる者もいた。それからは戦後派の歌手が勢いをつけ、中には、のちに「演歌」と呼ばれるようになるジャンルを発達させていった者もいた。1963年には、日本のレコード会社の1つ「コロムビア」の1部門であった「クラウン」が独立し、演歌を専門とした。
三人娘の1人の美空ひばりは、流行歌(ラジオ側から言えば歌謡曲)出身で演歌歌手的なスタンスの認識であるようだ。
世代交代が進む中、歌手・作曲家の藤山一郎は、戦前(1931年)から戦後にかけて長らく歌手として活躍した。藤山は、オペラ歌手・歌謡曲歌手の2つの顔を持ち、はっきりした日本語の発音が定評だ。1992年には、「長きに渡り、歌謡曲を通じて国民に希望と励ましを与え、美しい日本語の普及に貢献した」として、国民栄誉賞を受賞。1949年の大ヒット曲、映画と同名の主題歌「青い山脈」は、発売から40年経った1989年にNHKが放映した『昭和の歌・心に残る200』においても第1位となっている。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%B1%B1%E4%B8%80%E9%83%8E
1959年活動開始のザ・ピーナッツは、和製ポップスという新たなジャンルを日本に持ち込んだ。また、1962年デビューのビートルズ等の洋楽も日本に輸入された。
1960年代を境に、日本の歌謡曲は多様化していったようだ。
1990年代はJ-popやラップ等の新分野も流行。
感想
昔の曲はみんな、リズムが単調で、和音展開も同じものばかりかと思っていた。しかし、服部良一の東京ブギウギや、三木鶏郎のCMソングなどを聞くと、ジャズの早く軽快なリズムや複雑な和音展開が取り入れられた曲もあって意外に感じた。
演歌が1ジャンルになったのは、1960年代と予想外に最近だった。
レコード会社やラジオ放送局、芸能プロダクションなど、その時代の勢力の影響もあったり、ある1人の歌手の斬新な曲から新しい感じのジャンルができたりしながら、これからも歌謡曲は変化していくのだなとしみじみとした思いである。
追記
使われている楽器
最近の曲は、ドラムやベースの入っている曲がほとんどな気がする。昔の曲は、バックがオーケストラであることが多い気がする。
声質
最近は、ハスキーボイスとかも使っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
