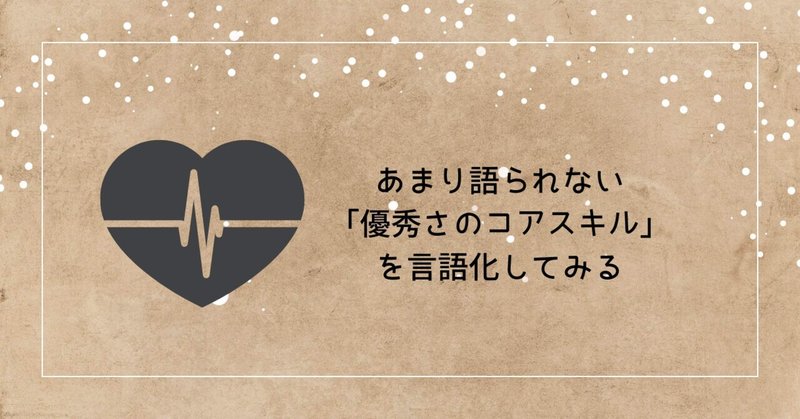
【全文無料】あまり語られない「優秀さのコアスキル」を言語化してみる
この記事は有料設定にしていますが、全文無料で読めます。もし内容が気に入ったら投げ銭してください。喜びで踊り狂います。
仕事では、専門性よりも大事なコアスキルが求められる。
チルちゃんは働くなかで↑を痛感しているのですが、それに気づいている人/気づいていない人で二分化されている印象があります。
特にフリーランスはこのコアスキルが無いと下請け作業者から抜け出せません。
また、スキルが高くても「うわぁ、この人と仕事しづらいなぁ」と思われてしまうため、悪い面を指摘される前に契約を切られてしまいます。その辺は正社員よりもシビアです。
コアスキルが無いと成長も遅いし、信用も築けません。ではそのスキルとは何なのか。私が思うのは「自主性と自己改善のスキル」です。
今回はそのことについて語ってみたいと思います。
【前提】仕事とは「課題解決」であり、解決した分だけお金になる
以前、経営学者の楠木健氏がこんなことを語っていました。
趣味と仕事は明確に違います。趣味は自分のため、仕事は誰かのためにやるものです。
僕はバンド演奏をライブハウスでやるんですけど、誰も来てくれないんです。
なぜか。これは趣味であり、価値が無いからですね。
鋼の錬金術師の「等価交換だ!!!」じゃないですが「相手に課題の解決を提供した、その対価としてお金を貰える」というのが仕事の本来の姿です。
この課題解決、切り分けると2つの大変さがあります。
課題を解決すること
課題を設定し、原因を突き止めること
課題を解決すること
課題解決の大変さなんて、そんなの課題の難易度によりますよね(あたりまえ体操)。
私みたいなライターは多くの場合「(○○のための)記事が欲しい」といった依頼をされます。つまり課題設定(記事が欲しい理由)はクライアントが既にしているため、私たちはそれに準じた成果物をお渡しすればOKです。
あえて言葉を選ばなければ「記事を書けば完結する仕事」……とも言えるかもしれません。
もし日本にライターが1人しかいなかったら注文が殺到&入札競争が起きるでしょうが、ライターは副業本業含め沢山いますし、AIの進化もすさまじい。つまり「簡単な記事が欲しい」というニーズは比較的解決しやすいので、もらえるお金は少なくなります。
課題を設定し、原因を突き止めること
課題解決より難しいこと、それは課題設定と原因探しです。
個人のキャリアを考えるときもそうですが、「なんかうまく行かない」ときはそれなりの原因があります。それは内部(自分)由来かもしれないし、外部(自分以外)由来かもしれません。両方のときもあるはずです。
原因を特定できないまま行動ばかりすると遠回りですし、さまざまなリソース(時間とか労力とか)をムダに消費してしまいます。
お腹空いている原因はご飯を食べていないからなのに、それに気づかず電気屋さんで電池を買い「満腹にならない」と嘆いている。ありえない話のようですが、ビジネスのように答えのない問いを扱うときは似たようなことは各所で起きています。
原因さえ突き止めれば精度の高い実行ができるので、大切なのは課題を設定し、原因を突き詰めることです。
(ad)▼一言でいえば「イシューからはじめよ」
しかし、原因を考えるのって難易度が高い。
似たような課題があったとしてもその原因は異なることが多いため、物ごとを多角的に見ながら仮説を立て、原因であろうスポットをオリジナルブレンドで仕立てなくてはなりません。
例えば「仕事が受注できない」という課題があったとき、悪いのは営業なのか成果物なのかコミュニケーションなのか、営業だとしたら口下手だからかアポ数が足りていないのか………
このように課題は複合要因によって成り立つため、クライアントに高い価値を提供するためには「成功はどんな要素からなるか」を解像度高く想像できる知識・スキルが必要となります。
(ad)▼解像度といえばこれ。「価値のある解決」について書いてある本で、良書でした。
(ad)▼誰かの踏襲になるだけだと足りない。ノウハウコレクターからの脱却。
「課題を設定して原因を突き止められること」は課題解決の根本であり、影響が大きいうえ誰にでもできるものじゃないので、貰える金額も高くなります。
自主性と自己改善のスキルが無いと、ほかのスキルも身につかない
さて、ここで問題なのですが、解像度なんてそう高く持てるものじゃないんですよね。なので解像度は後天的に高くしていく必要があります。
にも関わらず、いつまで経っても解像度を上げることができない、上がっていかない人たちも少なくありません。
なぜならその人たちには解像度を上げていくスキルがないからです。解像度を上げるためのスキル、それこそが【自主性と自己改善】のスキルだと思います。
では自主性/自己改善とはいったいどんな要素で構成されているでしょうか。
自主性
自分で「うまくいかない原因」を考える時間を持っている
課題解決を人任せにしない、当事者意識と責任感がある
自己改善
至らなさ、ダメな部分があっても自尊心に帰結せず、非を認めて受け入れられる
指摘された部分を治すための時間を確保し、アクションを取っている
つまり、優秀さとは「認めたくないこと」を認められる精神的・心理的な強さ
と
「行動の結果を受け入れるのは自分」という当事者意識によって作られるのかもしれません。
自己保身に走ると「原因」が曇って見える
「自分の意見は間違っているかもしれない」と思えることを知的謙虚(Intellectual Humility)と言います。
この概念はソクラテスの「無知の知 (知らない、ということを知る)」から始まり、2000年頃からリチャードポールの「クリティカルシンキング理論」などでその重要性が強調されてきました。
常に「自分は間違っているかも」という認識を持てる人は新知識や時代の変化に寛容ですし、失敗を人のせいにしないので視野も広い。
よく「自分は変えられるが人は変えられない」と言いますが、知的謙虚を持つ人は変えられる自分に原因を求めるので、問題解決においても建設的なアプローチを取ることができます。
でも……知的謙虚を持つのって難しいんですよね。特に自尊心が欠如している場合、なけなしの自尊心を無意識に守ろうとするので「自分は正しい、間違っていない」という意識が先んじてしまい、現実を受け入れることができません。
「じゃあ知的謙遜があれば安泰だ…!!」と思ったらそうでもなく、知的謙遜を持ちすぎていた場合、それはそれで意思決定ができません。前述の「自主性」が無くなってしまう。
私がライターになったのは、ちょうど某高額スクールが倒産した頃でした。高額費用は戻ってくることなくTwitter(当時)は阿鼻叫喚。
これは詐欺的な教材で損をしたケースですが、ライターに限らず至るところで「情報の売買」は行われています。コンサルも広義では「情報を売る仕事」と言えるかもしれません。
情報を買う人は、ある程度の知的謙虚があります。しかし同時に主体性が欠如していると以下のようなことになりがちです↓
自分で知見を獲得しようとせず、誰かに教えてもらって何とかしようとするため、身にならないままお金と時間だけが減っていく
情報取得先を比較検討しないので、語気が強い「内容が薄い高額商材」を買ってしまう。また、生活が苦しくなるレベルの投資をしてしまう
先人が時間をとって教えても暖簾に腕押しなので、見限られてしまう
要は、主体性のない人は自分の思想を持たないため判断軸がなく、どんな人の意見も鵜呑みにしてしまうため「情報の選別」ができません。また「誰かに育ててもらえば成功できる」と思っているため自分でスキルを身につける意識が薄く、実行力も低めです。
こうなってしまう原因は、知的謙虚を持てない理由とかぶるところがあります。要は「自分で決めても大丈夫」という自信がない。そこまで自分を信じきれないのです。
「自分はどうしたい?」にしっかり耳を傾けてみる
自主性は他人の目を気にしていると身につきません。「私はこう思う、こうしたい」という想い・行動は多くの場面で他人と衝突しますし、ときには喧嘩したり、嫌われたりすることもあるでしょう。
また自分が本気でやりたいと思っていることも、実は他人の模倣だったりします。
(ad)▼まだ買っていないけれど気になる本。高評価が周りにもチラホラ
最近では女性が金銭的自立をするようになり、かつての「男性を立てるのがイイ女」という価値観から「自立した女性がカッコイイ」という価値観に変化しました。
やりたいこと、なりたい姿は時代情勢や周りの声によって霞んでしまうのが当たり前です。ですが、それでもまだ「やりたいこと」の多様性は残っている。
また、世の中には「仕事ができるけど信用を無くしていく」人もいます。こういう人は表面的なスキルはあるけれど、コアスキル(自主性と自己改善)が足りていません。
仕事をするモチベーション(欲望)が「自分の価値を証明するため」なので高い社会的地位を求めて努力するし、それが本当に自分の欲望だと思っています。
でも、そういう人が本当に欲しいのは社会的地位ではなく「他人に認められること」だったり「愛されている実感」だったりします。それを「偉くなりたい」という偽物の欲望で隠してしまうのはイシュー(原因の特定)が間違っている。
本当にそれはやりたいことなのか?誰かの目を気にしていないか?を定期的に振り返ることは大事だし、人の目を気にするにしても「私は○○のタイプの人に好かれたいから、少し背伸びしたい」まで決めておけば、それは自分の意志になります。
「ありたい人リスト」のススメ
私は年始に「やりたいことリスト」を100個書いています。
このやりたいことリスト、簡単に実行できること(○○のお店に行く、とか)には役立つのですが、他人が絡む願い(〇〇で評価を得る、など)を叶えるには不向きだし、当時はやりたいと思っていた項目なのにモチベが下がっているものもありました。
そこで書き始めたのが「ありたい人リスト」です。
例えば───自由になりたい……と言ってフリーランスを目指す人は多いですが、フリーランスになったからと言って自由になれるか……?といえば微妙ですよね。(自由の定義とは?という話でもあり)
でもここで「自由な人でありたい」と自身を定義づければ、それは精神的なものとなります。もしかしたら会社勤めでも達成できるかもしれない。少なくとも、フリーランスのみを目指すよりは選択肢が広がるでしょう。
表面的なスキルも大切ですが自身のスタンスは仕事にも現れるので、定期的に振り返ってメンテナンスするといいんじゃないかなと思います。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
