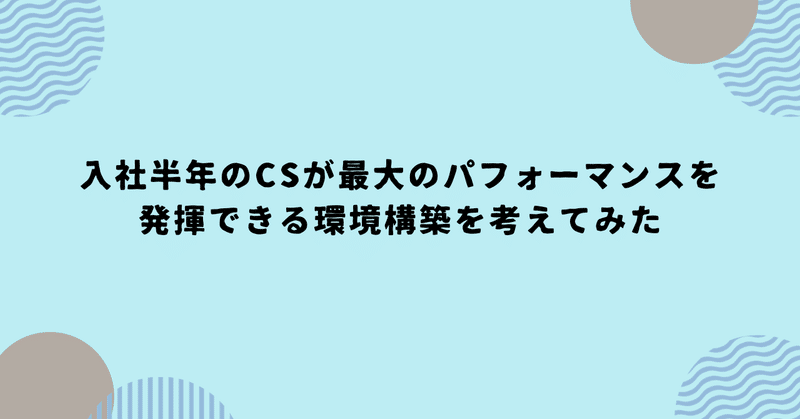
入社半年のCSが最大のパフォーマンスを発揮できる環境構築を考えてみた
はじめまして。LayerXのバクラク事業部カスタマーサクセスの島田です。
LayerX内ではkanacchiと呼ばれています!
現在はオンボーディングチームとリテンションチームを兼任し、オンボフローの再精査やアダプション期の環境構築をしています。
現在、CSメンバーが色々なテーマでnoteを書いていますが(最下部に以下にリンクありますので是非読んでください!!)私は現在入社して今月でちょうど半年が経過するところなのでCSのメンバーレイヤーでの入社は私が一番社歴が若いです。
ほかのメンバーとは異なる視点からnoteを書きたいな〜と思い、今回は入社してからの社内のCS環境の現状と今後の環境構築にフォーカスしてみることにします。お付き合いくださいませ!
入社時のCSの環境
前述の通り、私は2023年4月に入社して今月で半年が経過します。
入社からはたった半年ではありますが、やはり成長スピード、プロダクトリリース、機能アップデートなどさまざまな側面で入社前から超爆速だと聞いていたLayerX、、、思ってた通りの爆速!で半年でもかなり色々な変化があったと思います。
CSの変化で言うと、今までのLayerXバクラク事業部のCSは<“カスタマーサクセス”というものは職種に限らずプロダクトと顧客とのあらゆる接点において想起されるべき概念>という、元CSMgrのkajiさんがnoteに書いている内容を忠実に再現している組織で、特に顧客オンボーディングにおいては1to1で顧客に向き合う超ハイタッチ、マインドはホスピタリティ溢れるメンバーが日々顧客対応に奔走している印象を入社後も強く受けました。(ここはある意味想像通りでした)
ただ、今までのフェーズはそれが必要であり正しいと感じる一方で、この先の事業の成長を見据えたCS組織の構築という視点で見ると、私の入社したあたりの時期からが、ちょうど次のフェーズに進むタイミングなのだろうなと感じていたな、と今振り返ると思います。そのため丁度入社のタイミングの4月、7月、そして現在10月とクオーターごとにチーム改変を進めフェーズに合わせた組織変更がありました。これは今までのやり方を変える、のではなく今までのマインドを踏襲しつつ事業成長にあったCS構築のタイミングが今なのだと感じています。
これからのCSに求められていること
今までのCSの、特にオンボ期のホスピタリティ高いアプローチはある意味完成系に近く、これからはハイタッチのみに頼らない形での、ロイヤリティの高い顧客を創出ができるかが、最重要ポイントになってくることを社内の共通認識として感じており、同時にCSに今一番求められていることだと思っています。(そのためのチームの分化でありミッションであると感じています)
各チームの定義や施策ベースの内容はretentionチームのchisuminさんやExpansionDevelopmentチームのmacchiさんがnoteへ記していますが、どのチームもロイヤルカスタマーの創出をすることがretention rateのキープに繋がり、retentionrateのキープはexpansionを生み出す、そしてそれぞれの数値が高い顧客がロイヤルカスタマーである(ほかにもロイヤルカスタマーであることを示せる指標はありますが)、という好循環を生むことを目指し取り組んでいきます。
そんな好循環を生み出すべく、それぞれのチームや個人が限りなく高いパフォーマンスを標準的に発揮させるには、まずは環境構築が重要であり必要になると感じています。ここでやっとタイトルの環境構築についてのお話へ!(長い)
高いパフォーマンスを発揮するためには
最適な選択肢を最短ルートで選べることが重要
それぞれのチームや個人が限りなく高いパフォーマンスを標準的に発揮させる環境ってどんな環境?と思うでしょうが、まずは各々が【最適な選択肢を最短ルートで選べる】ということが最重要だと思います。当たり前と言えば当たり前ですよね。
今まではそれぞれの超ハイタッチなやり方で顧客対応をしていたため、運用提案、事例把握、仕様理解が個人のスキルや記憶、社内ナレッジの個々の検索力に託され属人的になりやすい環境になっていました。
またスピードが速い会社であるが故に状況に適応させることが最優先となり結果的に人力での作業でなんとかする、と言う場面も多くなっていました。
【最適な選択肢を最短ルートで選べる】環境を作ることで誰でも一定のスキルがある状態を作ることができ、それぞれのチームの本来のミッションへ向き合うことができる
=個々、チームそれぞれが高いパフォーマンスの発揮に繋がる
=好循環を生み出しロイヤルカスタマー創出に繋がる
と考えています。では、それならその環境ってどんなことをする必要があるか?という具体を次に書いていきます。
もちろんやれることはたくさんあるのですが、まずは目先のやるべきこと、という視点で3つ挙げてみます。
社内ナレッジの徹底整備
現在、ありがたいことに社内にはたくさんの知見、調査情報、活用事例が情報としてはたくさんある状態です。これは非常に良いことだと思います。
この次のステップはこの情報への検索性や最新性を担保し、高い水準でのスキルセット標準化をすることが今後の課題であると思っています。
また、technologyの力を借りて人力での管理体制を極力無くせる環境作りを目指していこうと思います。
プロダクトチームとの連携体制構築
CSの仕様理解と質の良い現場要望FBがCSがフロントにいる意味であると言っても過言ではないと考えています。現在も勿論連携はしておりますが、より強固なCS<>プロダクトチーム連携を構築する必要があると思います。
連携というのは単に情報連携するのではなく、スムーズな連携を目指し、プロダクトの成長がお客様への還元となるよう取り組みたいです。
属人的な作業の自動化
徹底的に無駄を省くことで最短ルートで選択できることの手助けをし、空いたリソースでプロアクティブなアクションへと繋げることで前述の分化したチームのパフォーマンス最適化に繋がると考えています。
高いパフォーマンスを発揮できることが
事業・お客様共に最大の還元となる
上記のことは突拍子もないことではなく至極当然と言えば当然なのですがこのタイミングで土台を作り直す、というのは意外と根が深く、、、
またこの作業をやっても直接何かの数字がぐんと上がる成果があるのか?と言われるとそればnoだと思います。正直定量的に評価されることはかなり難しい領域ででも手をつけると深淵すぎてめちゃくちゃ大変…なのにそのわりにはアウトカムが少ない…となりがちだと思います。
ただ私はこの一見守りに見える取り組みは攻めの土台作りだと思っているので諦めたくない!と常に思っています。
何事もこつこつと粘り強く固い土壌を整備することで個人も組織もひとつ上のステップに辿り着くことができると信じています。
これは今までの経験上、遠回りに見える環境整備に力を入れてきたことが結果として成果に繋がる土台になってきたことを実感しているからです。
これは決して今までのやり方を否定するものでは全くなく、今のフェーズだからできることだと強く感じています。
サンプル数が少ない中で整備することは難しく、今この状況だから取り掛かることができる領域だからです。
1年前に同じことができるか?と言われると少し難しい気がしています。
今ここで取り組むことで今一緒に働いているメンバーも、これから一緒に働く未来のメンバーもより高いパフォーマンスを発揮できることが事業にとっても、お客様にとっても良い効果をもたらすと思っています。
最後に
今こういった環境整備に着手し始めたところではありますが、まだまだやりたいこと、やるべきことはたくさんあります、私は環境構築にフォーカスを当てて書きましたが、ほかメンバーはチームごとの取り組みを書いていますので、ぜひ読んでみてください!
もし興味があれば一度カジュアル面接でお話しましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
