
日本癌学会 CancerX リポート 1「多様性によるがん医療・研究の躍進」
こんにちは。CancerX 広報担当のかまさんです。
2022年9月30日(金)神奈川県横浜市のパシフィコ横浜で、
第81回日本癌学会学術総会 CancerX特別企画セッションが行われました。
テーマは「多様性によるがん医療・研究の躍進」
今回はこのセッションを取材しました。
1)特別セッションとは

日本癌学会、CancerX特別企画セッションは、CancerXが日本癌学会の協力の下に行う特別企画で、今年で2回目になります。
今年は社会的な必要性が高まっている
「Diversity, Equity, and Inclusion (DE&I)」に焦点を当て、
医療の分野の方だけでなくビジネス分野の方も参加いただき活発な議論を交わしました。
2)セッションの概要は・・・
第81回日本癌学会学術総会「CancerX 日本癌学会」
〜多様性によるがん医療・研究の躍進〜
英題:JCA×CancerX: Accelerating Cancer Research by DE&I (Diversity, Equity and Inclusion)
【パネリスト】
上野 直人 氏/CancerX共同発起人・ 共同代表理事/テキサス大学MDアンダーソンがんセンター教授
大谷 直子 氏/大阪公立大学 大学院医学研究科 分子生体医学講座 病態生理学 教授
中村 健一 氏/国立がん研究センター中央病院 国際開発部門 部門長
半澤 絵里奈 氏/CancerX共同発起人・ 共同代表理事/ 株式会社電通グループ DJNサステナビリティ推進オフィス シニアマネージャー/ cococolor編集長/JAAA DE&I委員会委員
日色 保 氏/日本マクドナルドホールディングス株式会社 代表取締役社長 兼 CEO
【座長】
後藤 典子 氏/金沢大学がん進展制御研究所 先進がんモデル共同研究センター 分子病態研究分野 教授
三嶋 雄太 氏/CancerX共同発起人・ 共同代表理事/ 筑波大学 医学医療系 助教 / 附属病院 再生医療推進室 副室長
3)気になるセッションの内容は
登壇者からは、自己紹介と合わせて、それぞれの立場や体験をもとにした話がありました。

CancerXの上野共同代表理事は、CancerXはいろんな人たちの多様性を重視していることから「Collaborate」「Change」「Cross out」の3つの柱を説明。「がんと言われても動揺しない社会」の構築のために、
18のCancerAgendaを作り活動していることを紹介しました。

同じくCancerXの半澤共同代表理事は、
「経営者」「保育士」というキーワードで画像検索すると、
それぞれ「ビジネスマンの男性」「エプロンを付けた女性」の画像が
提示される「検索のアンコンシャスバイアス」という事例を紹介。
アンコンシャスバイアスが社会に潜んでいることを示しました。

大谷さんは、80年の歴史を持つ日本癌学会で、初めての女性理事となりました。大谷さんは、現在行っている肥満と癌の関連性の研究を紹介したあと、癌学会女性科学者委員会で長く活動された経験から、女性研究者をもっと増やすために、更新の育成にも力を入れたいと話しました。

中村さんは、日本国内でも地域によって受けられる治験の数の差を紹介し、地域間の治験へのアクセス格差を指摘しました。そして、オンライン診療を活用してこの差を埋める準備をしていることを紹介。また、コロナ治療薬の世界での開発を例に取り、治験ネットワークをアジア全体に広げ多様性を確保することによって、危機に強くなると同時に、新しいイノベーションを作り上げることにつながると話しました。

日色さんは、前職であるジョンソン・エンド・ジョンソン時代、ダイバーシティに取り組み表彰もされたが、表彰されるためにしたわけではなく、ビジネスのパフォーマンスを上げるために取り組んだことを強調。マクドナルドに入社直後の店舗研修の経験から、多種多様な人間が働いていることをさらに強く感じ、「多様性に富む会社が強い会社である」が世界の常識であることを話しました。

4)多様性を担保する重要性とは
後半は相互討論が行われ「多様性を担保する重要性」についてそれぞれ意見を交わしました。

上野さんは、アメリカでの現状について、勤務する病院の約2万2000人の職員のうち約7割が女性で、ダイバーシティ教育は徹底されているものの、
人種差によるシニアポジションの問題があり、その問題を病院が重要視していること。また、一例として臨床実験のデータが、白人の臨床試験が主となっており、十分な多様性がないことにFDAが懸念を抱いているしていることをあげ、研究開発のスピードをさらに進めるには、多様性が重要視されていると話しました。
日色さんは、同質性の高い組織は、一見強そうに見えるが環境の変化に弱く、実は弱い組織であることを指摘。ビジネス界でも医療界でも、イノベーションが生命線であり、ダイバーシティが高い組織は、組織として新しいものを評価する土壌があるため、イノベーションが起こりやすいと話しました。
中村さんは、多様な組織ではコンセンサスを取ったり、まとめたりする際に時間がかかるため、多様性は面倒と思っている人が多い。その中でマネージメントするコツとして、何でも認めるのではなく、多様性の中でもどうしても譲れない価値観をしっかり保持することが重要で、同時にその周辺部分については広く受け入れることによって、多様性を新たなイノベーションを生み出す力とすることができると話しました。
半澤さんは、必要なことはトップのコミットメントだと指摘。医療界、産業界は異なるように見えて本質的な部分は一緒。共有できることも多いので、様々な立場で継続的に話し合っていくことが重要だと話しました。
日色さんは、「御社はダイバーシティが進んでいるので話を聞きたい」と他の企業から視察にお越しになる。いらっしゃるのは、人事部やダイバーシティ推進室という肩書の方が多いが、そもそもそういう組織ができることが、企業にとっては他人事。自分ごとにしていないということではないかと指摘。社長に限らずやっぱり、リーダーシップポジションにある人が、自分1人がオーナーシップを持ってやるっていうのが重要だと指摘しました。

5)最後に・・・
1時間のセッションは多岐にわたる内容でした。
いかに自分ごととして「多様性」をどう捉えるのか、考えるきっかけとなりました。
CancerXでは、2023年2月に行う「World Cancer Week 2023」で、この討論の続きをセッションとして開催することとしました。
また、登壇者のみなさんがあげた事例の数々が、いろいろと気づくきっかけになったため、このNOTEで引き続き書いていきたいと思います。
6)World Cancer Week 2023開催のお知らせ
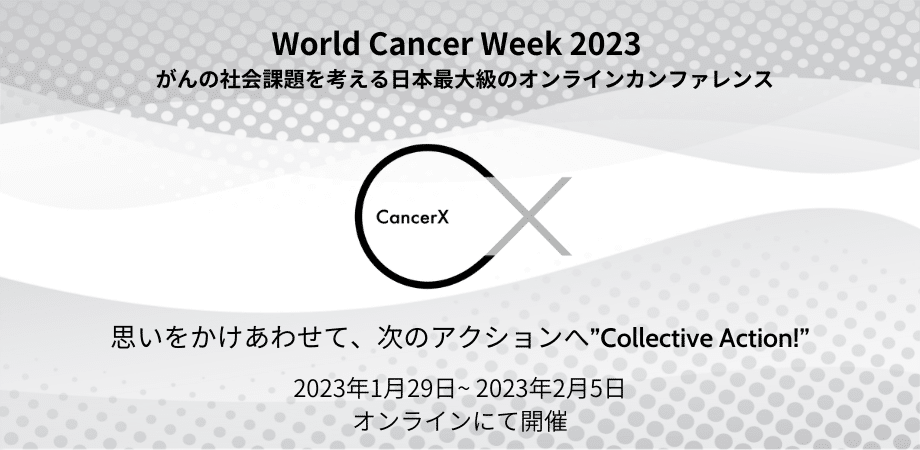
詳しくはこちらをクリック
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
