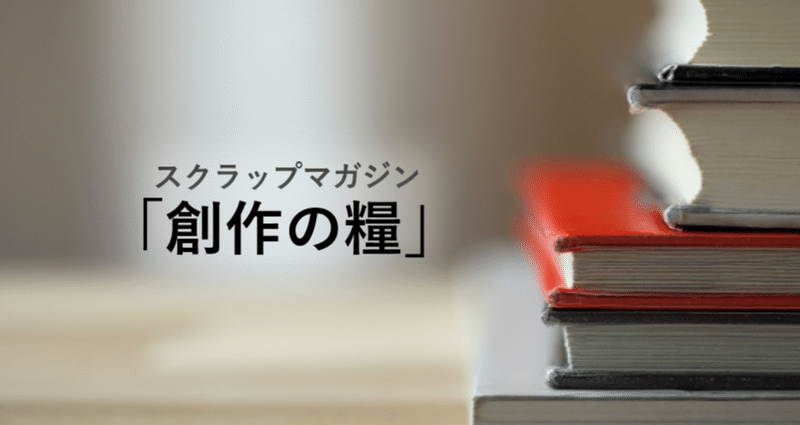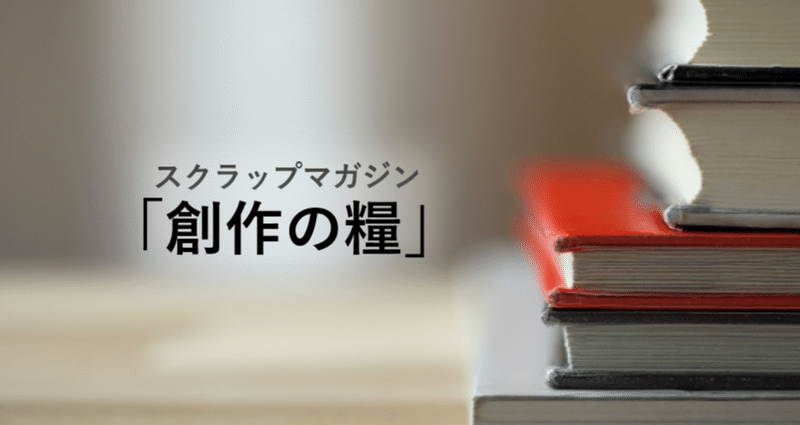俳の森-俳論風エッセイ第19週
百二十七、共振語についてーことばの実体化これまでにも、共振語について何度も述べてきましたが、共振語とは何か纏めて見たいと思います。そもそも俳句は、作者が季節に感動して生まれるものだとわたしは考えています。ある季節(季語)に、作者が出会うことがその引き金になります。
例えば、啓蟄という季語があります。二十四節気のなかでもニュースなどでよく取り上げられることばです。
陽暦では三月五日頃ですが、立春からひと月ほど経って、次第に陽気も落ち着いてくる頃です。子どもが幼稚園児の頃のこと