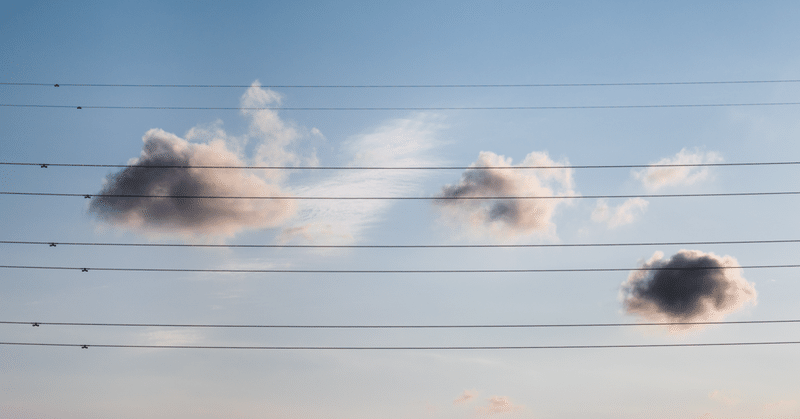
【写真について知っているいくつかのこと Vol.14】アナログプロセスとデジタルプロセス by KISHI Takeshi
カロワークスのKISHI Takeshiです。写真やカメラに関する技術・歴史や、写真業界の出来事などを月イチで綴るシリーズの第14回です。
今回は写真のアナログとデジタルのプロセスについて考えてみます。
*****
さて、まずはおさらい…。
アナログとは連続的に変化する量を、別の連続的に変化する量であらわすものです。例えばアナログ時計であれば時間の変化を針の角度の変化であらわしますが、このとき両者は類比的(analogy)な関係にあります。
一方、デジタルとは連続的に変化する量を、離散的な値(非連続的な飛び飛びの値)によってあらわすものです。デジタル時計は時・分・秒をそれぞれ数字であらわすように、digitalとは数値、またはそれらを表現する方法に関連する言葉です。
さて、このアナログとデジタル、それぞれ以下のような特徴があります。

(*みっ、見づらい…。noteに表作成機能がほしい…。)
アナログ的な情報の最大の利点は、人間の視覚や聴覚などで、感覚的に理解しやすいという点でしょうか。しかし、本来の情報には含まれていない雑音(ノイズ)の影響を受けて変化しやすく、情報それ自体をコンピュータで扱うことが難しいという欠点もあります。
デジタル的な情報は “計算機”であるところのコンピュータとの親和性が高く、規則的な数値によって情報を扱うので、何らかの欠落があった場合にも修復が容易です。
例えば「1,2,3,4、5…」と変化する情報のうち、一部が欠落して
「1,2,×,4、5…」となっても、周囲の数値をもとに欠けた情報を補間できます。
また、ノイズや減衰の影響を受けずに、劣化の無い複製を簡単に作成できる点も大きな利点です。
続けて写真におけるアナログ、デジタルのプロセスの違いを見てみましょう。


アナログプロセス、デジタルプロセスともに「光のエネルギーを用いて像をつくる」という点は共通しています。この光は勿論、アナログ的な情報です。
アナログプロセスではフィルムなどの感光材料に光が当たると、化学反応によって「潜像」が形成され、さらに露光後の材料を「現像」処理することによって、像は目に見える形としてあらわれます。
このとき、光のエネルギーの強弱に応じて、像の濃淡は連続的に変化するので、両者はまさに類比的(アナログ)な関係です。
一方、デジタルプロセスではフィルムの代わりにイメージセンサを用いて光をとらえます。センサ上のフォトダイオードは照射された光の強弱の情報を電気信号(アナログ信号)に変換、さらに電気信号をデジタル信号に変換・信号処理することで、光の情報を数値に置き換えて記録メディアに保存します。
*****
両者の大きな違いは、アナログでは、撮影~記録~表示~保存が同一の媒体(フィルムや印画紙)で行われるのに対して、デジタルでは、各工程でイメージセンサ、記録メディア、ディスプレイ・プリンタなど物理的に異なる媒体を用いる点です。
アナログプロセスでは、像を可視化するためには現像処理が必須となりますが、現像後のフィルムや印画紙、それ自体を見るのにあたっては特別な機器は必要ありません。大量の写真の内容を確認しながら、並び替えて整理・保存するといった作業は、紙焼きのプリントの方が感覚的に素早く楽に行える…という経験もあるのではないでしょうか。
ただし、それらをハンドリングする中では、折れ・傷、変退色やカビなど様々な劣化を受けて、画像の一部が欠落したり、不要なノイズ成分が発生するなどの影響を受けやすいものでもあります。
かたや、デジタルプロセスでは、デジタルカメラやスキャナなどの入力機器を用いて、アナログの情報(光)をデジタル情報(数値)に変換します。こうして得られたデジタル情報は、ネットワークを介して遠く離れた場所に送信することも容易です。
しかし、デジタル情報そのものは数値のデータであるため、そのままでは写された図像を目で見て確認したり、手で触ったり…ということは出来ません。
そのため、もう一度デジタル情報を目に見える形にするため、ディスプレイやプリンタなどの出力機器を用いて、デジタル(数値)からアナログ(光など)の情報に変換する必要があります。
しかし、この出力機器には固有の特性があり、たとえ同一のデータであっても、機器の原理や設定、視環境などによって、諧調や色の異なる画像が出力される…という点はデジタルプロセスの問題といえるでしょう。(オリジナルとなる画像はどれ?という疑問)
*****
こうして見てみると、いずれのプロセスも、最初に「光」というアナログの情報があり、それを、目に見える別の「光」(印画紙やインクジェットプリントの濃淡も光の反射・吸収によって生じる)に置き換えていることが判ります。
その中間工程での情報の処理・保存の方式にアナログかデジタルか、という差異はあれど、私たちの視覚に働きかけるのは、最終的な光に他なりません。
私たちが、SFで描かれるような、脳に直接デジタルデータを送って情報をやりとりする機構を内蔵するまでは、この「光」をどのように扱うかという点は写真にとっても重要なテーマといえるでしょう。
さて、次回もこのnoteでお会いしましょう~。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
