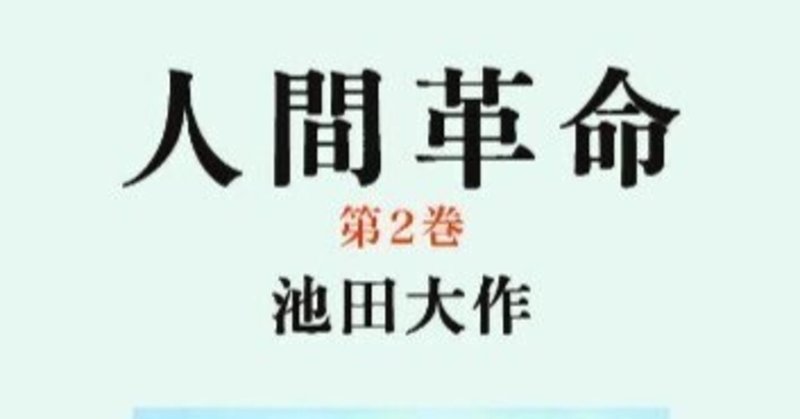
小説「人間革命2巻」⑤~地涌~
人間革命2巻の地涌は、初めて山本伸一が登場する。そして、戸田城聖と出会う。この出会いから、創価学会は本当の意味で大きな船出をし始める。
人をつくることを忘れて、社会の確かな未来はない。教育は、その根幹となるものであるはずだ。 教育者であった初代会長・牧口常三郎は、未来の宝である「子どもの幸福」こそ、教育の第一義の目的とすべきであると、力説してやまなかった。
「人間」が「人間」として、自らを作り上げていくーそのためにこそ、教育はあるはずである。その教育に、社会を挙げて取り組むことこそ肝要だろう。
「創価学会は人材を持って城となす」と言われている。その根底は、組織が小さかろう、大きかろう変わらない。最後は「人」なのである。
他教団の本部へ乗り込んで、英雄気取りで論争したことを、戸田に厳しくたしなめられて以来、二人は、かつての同級生を探し出し、着実に折伏を始めた。
前章での教団での論争対決から、地道な折伏に足を運ぶようになる。その足を運ぶ友人の一人が「山本伸一」なのであった。
彼(山本伸一)もまた、一つの確立した哲学はもてず、観念の遊戯をしていた平凡な青年であったことには、間違えなかった。
当時の青年は、知識をどん欲に吸収していく意欲がすごい。しかしながら、何か虚無的であり、知的作業と生活とが乖離している状態だったのではないだろうか。
当時の青年たちの唯一の憩いの場であり、また知力の研鑽や、人間形成の場でもあった。どこの家庭でも、生活の困窮は似たり寄ったりであったし、青年たちは、社会の暗い憂鬱な空気に、息が詰まりそうであった。耐えられなかったともいえる。それが、ひとたび同年配の青年たちが顔を合わせると、時代のよどんだ空気を忘れることができた。そして、いつか建設的な面を互いに引き出していたのである。
(中略)
彼らは、毎夜、集まっては、高い知識を求めているようであったが、その積み重ねが、単なる遊戯であっては、自身の人生問題を、何一つ具体的に解決できないことにも気づき始めていた。山本自身も人生に対する強い確信をもち、人生観を深く確立したいという心が動いてきていたのである。
(中略)
彼らは、真面目な青年であった。それゆえにこそ、善悪の基準と愛国心の二つの疑問を軸として、苦しんでいたともいえる。”もしも、この疑問に完全な回答を与えることのできる人がいたら、その人こそ自分たちの師父である。その時は、一切をなげうって、その人にどこまでも、ついていこうではないか”と、彼らは、時に夢見るような思いで相談し合っていた。
青年たちは正しき人生の哲学を求めていたに違いない。
しかし、そのどれが正しいのかが分からないでいた。知的領域だけでは決められなかったのではないだろうか。
酒井たちは、伸一だけでも誘い出そうとしたが、彼は頑強に動かなかった。二人の友人が姿を見せないことよりも、夕刻から始まった胸部疾患による発熱で、体が疲れてならなかったからである。伸一は、軽い咳をしながら、だるい体に耐えていた。彼は、律義に二人の友人を待っていたが、その心の中では、今日は中止にしたいとも望んでいた。
ところが、一時間も遅れて二人の友人が来てしまうと、彼は、熱っぽい体を立ち上がらせた。
この部分は、赤裸々に書かれていて面白い。山本伸一は、のちの創価学会の三代会長になる人間であり、著者自身のことである。もしも仮に、ここで山本伸一がこの会合に出席しなかったとしたら、創価学会の発展はなかったかもしれない。仏法の眼からすれば、この時の胸部疾患は、広宣流布を妨げようとする魔だったと見ることができる。
私自身も経験としてあるが、学会活動の中の会合や打ち合わせなど、物凄く行きたくない時がある。しかし、そんな時、重い腰をあげて参加すると、自分にとって大きな転換点となる会合になることがある。この不思議な運命的な力を感じるか否かが、信仰の力なのではないだろうか。
(戸田)「今日は、ここまでにしておこう。今日、講義した『立正安国論』の、わずか数行を拝しても、大聖人の偉大な御確信が伝わってきます。大聖人は、仏法哲理の真髄を、ただ御一人、ご存じであるがゆえに、すごいのです。
七百年前に、お書きになったものが、まるで敗戦後のわれわれのために、お書き残しくださったかのようだといってよい。個人であれ、一家であれ、一国であれ、この仏法哲理をもって、根本から解決しない限り、一切のことは始まらないのです。
御本尊様を、ひとたび受持した以上、個人としての成仏の問題は解決する。しかし、一家のことを、一国のことを、さらに動乱の二十世紀の世界を考えた時、私は、この世から一切の不幸と悲惨をなくしたいのです。
これを広宣流布という。どうだ、一緒にやるか!」
「この世から一切の不幸と悲惨をなくしたい」これこそが、戸田自身の想いである。そして、全世界の誰もが感じている願いが達成できる思想こそが、創価哲学であり日蓮大聖人の仏法なのである。
「山本君は、いくつになったね?」
戸田は、「幾つだ」とは聞かなかった。「幾つになったね」と聞いたのである。初対面であったが、旧知に対しての言葉であった。
戸田は山本伸一に対して、何とも言えない親近感を感じていたのだろう。人は、時に会ったその日、その場で仲良くなる人がいる。それは過去世に巡り合っていたのではないかと思うぐらいである。そういう友人とは、意外と最初の出会いを覚えていないことが多い。生命というものが過去世、現世、未来世と続き、宿縁で巡り合っているのではないかと感じる瞬間である。
そして、山本伸一は戸田に自身の悩んでいた質問を聞いてみる。ここでは少々長いが、戸田の回答をまとめてみた。
(山本)「先生、正しい人生とは、いったい、どういう人生を言うをいうのでしょうか。考えれば考えるほど、わからなくなるのです」
(中略)
(戸田)「この質問に正しく答えられる人は、今の時代には一人もいないと思う。しかし、ぼくには答えることができる。なぜならば、ぼくは福運あって、日蓮大聖人の仏法の大生命哲理を、いささかでも、身で読むことができたからです」
(中略)
「人間の長い一生には、いろいろな難問題が起きてくる。戦争もそうでしょう。現下の食糧難、住宅難もそうでしょう。また、生活苦、経済苦、あるいは恋愛問題、病気、家庭問題など、何が起きてくるか、わからんのが人生です。
そのたびに、人は命を削るような思いをして、苦しむ。それは、なんとか解決したいからだ。しかし、これらの悩みは、水面の波のようなもので、まだまだ、やさしいともいえる。どう解決しようもない、根本的な悩みというものがある。
人間、生きるためには、生死の問題を、どう解決したらいいかーこれだ。
仏法では、生老病死と言っているが、これが正しく理解されなければ、真の正しい人生なんか、わかるはずはありません。
生まれて悪うございました、と言ったって、厳然と生まれてきた自分をどうしようもない」
(中略)
「いつまでも、十九の娘でいたい、年は絶対に取りたくないと、いくら思ったって、四、五十年たてば、お婆さんになってしまう。
私は、病気は絶対にごめんだと言ったって、生身の体だもの、年を取れば、ガタガタになってしまう。これも避けるわけにはいかない。それから最後に、死ぬということーこれは厳しい。
みんな、いつまでも生きられると思っているが、今、ここにいる誰だって、せいぜい、六、七十年たてば、誰もこの世に居なくなる。”死ぬのは、いやだ”と言ったって、だめだ。どんなに地位があろうが、財産があろうが、どうすることもできない。
こうした人生の根本にある問題は、いくら信念が強固だと言ったって、どうにもならない悲しい事実です。人生にとって重大な、こうした問題を、正しく、見事に、さらに具体的に解決した哲学は、これまでになかったといっていい。
だから、正しい人生を送りたいと願っても、実際には、誰もどうしようもなかった。突き詰めて考えてもわからないから、『人生不可解なり』などと、自殺する者も出てくる。厭世的になるか、刹那的になるか、あるいは、あきらめて人生を送るしかにない。
ところが、日蓮大聖人は、この人生の難問題、すなわち生命の本質を解決してくださっているんです。しかも、どんな凡夫でも、必ずそのような解決の境涯にいけるように、具体的に指南してくださっている。これほどの大哲学が、いったいどこにありますか」
(中略)
「正しい人生とは何ぞや、と考えるのもよい。しかし、考える暇に、大聖人の仏法を実践してごらんなさい。青年じゃありませんか。必ずいつか、自然に、自分が正しい人生を歩んでいることを、いやでも発見するでしょう。
私は、これだけは間違いないと言えます」
この箇所は、私たち創価学会員が信心をするすべての根幹であると言えるだろう。また、信仰をするということ、宗教を信じるということは、この難問を解決するため言ってよいだろう。そして、それは理論や観念で分かるものではいない。体験するしかないからこそ、戸田は「大聖人の仏法を実践してごらんなさい」と喝破されているのである。
(山本)「もう一つ、お願いします。本当の愛国者というのは、どういう人を言いますか」
(中略)
(戸田)「これは簡単だ。楠木正成も愛国者でしょう。吉田松陰も愛国者でしょう。乃木大将も愛国者でしょう。確かにそうですね。しかし、これからもわかるように、愛国者という概念は、時代によって変わってしまう。
国家や、民族に忠実である人が愛国者ですが、その国家、民族自体、時代の流れでずいぶん変化するものです。したがって、愛国者という人間像も変わる。
時代を超越した、真の愛国者があるとするならば、それは、この妙法の実践者という結論になります。その理由は、妙法の実践者こそが、一人の尊い人間を永遠に救いきり、さらに、今の不幸な国家を救う源泉となり、崩れない真の幸福社会を築く基礎となるからです。
世界最高の正法を信じ、行ずる者が、最高の愛国者たる資格をもつのは当然です。これは観念論では決してない。妙法を根底にした国家社会が、必ず現出するのです。歴史、思想、民族の流れから見ても、それ以外に絶対ない。いや、なくなってくるだろう。
それまで、多くの人は信じないかもしれない。現出してきた姿を見て、初めて”あっ”と驚くのです。それだけの力が、大聖人様の仏法、南無妙法蓮華経には、確かにある。後世、百年、二百年たった時、歴史家は必ず認めることと思う」
(山本)「先生は、天皇をどうお考えですか」
(中略)
(戸田)「仏法から見て、天皇や、天皇制の問題は、特に規定すべきことはない。代々、続いてきた日本の天皇家としての存在を、破壊する必要もないし、だからといって、特別に扱う必要もない。どちらの立場も気の毒だと思う。
天皇も、仏様から見るならば、同じ人間です。凡夫です。どこか違うところでもあるだろうか。そんなこともないだろう。
具体的に言うなら、今日、天皇の存在は、日本民族の幸・不幸にとって、それほど重要な要因ではない。時代は、大きく転換してしまっている。今度の新憲法を見てもわかるように、主権在民となって、天皇は象徴という立場になっているが、私はそれでよいと思っている。
今、問題なのは、天皇をも含めて、わが日本民族が、この敗戦の苦悩から、一日も早く立ち上がり、いかにして安穏な、平和な文化国家を建設するかということではなかろうか。姑息な考えでは、日本民族の興隆はできない。世界人類のために貢献する国には、なれなくなってしまう。どうだろう!」
「正しい人生とは」に続き、「愛国者とは」「天皇とは」について聞いている。そして、山本伸一は、戸田に対して以下のように思う。
山本伸一は、戸田の顔をじっと見つめていた。彼に、決定的瞬間がやってきたのは、この時である
”なんと、話の早い人であろう。しかも、少しの迷いもない。この人の指導なら、自分は信じられそうだ”
この時の山本伸一は、まだ仏法、そして三世の生命観をしらない。しかし、言葉に表しつくせない戸田への魅力を感じ取っているのである。そして、この人ならば付いていけるかもしれないと思うのである。
伸一にとっても、入会とは、何かに束縛されるような、いまだ見たこともない別世界に行くような感じであった。お先真っ暗な、不安の入り混じった複雑な気持ちでもあった。しかし、今夜の衝撃は、どうしようもなかったのである。
もう、入会の手続きなど、どっちでもよかった。ベルクソンのことも、遠い淡い観念の世界になっていった。戸田城聖という人ーそれが彼によって、実に不思議に、懐かしく思えてならなかったのである。
(中略)
物事を、真面目に、真剣に考える彼によって、自分の体のことが気がかりであった。彼の体は、決して強靭とはいえない。むしろ、病と闘わなければならない日常であった。彼が、一生涯、宗教革命に、仏法の実践に活躍しきっていけるかどうかは、自分でも分からなかったにちがいない。
人はともすれば、「この人のためなら自分の人生をささげたい」と思える人と出会えることは稀かもしれない。そんな人に出会えることほど、最高の人生であると言えるのではないだろうか。
一方で、創価学会へ入会することを束縛と感じ不安と捉えている。また自身の体調を危惧している。しかし、ここで気づくのは、伸一は自身の生活を良くしようとか、自身の病を治そうということで、創価学会に入会したわけではないという点だ。「入会の手続きなど、どっちでもよかった。」とあるように、すべては戸田城聖の魅力であったに違いない。入会して束縛を感じるよりも、戸田という人物への想いが勝っていたのである。
電車に乗って、自分の青春時代に、さまざまな想いをめぐらした時、牧口常三郎の面影が、ありありと蘇ってきた。そして、その時、牧口が四十八歳であったことに思いいたって、彼は愕然とした。
”俺は今、四十七歳だ。山本伸一は十九歳と言った。ともに、ほぼ同じ年の開きである……”
(中略)
”十九歳の青年は、いくらでもいる。しかし、牧口先生との出会いの時を、まざまざと思い蘇らせたのは、今日の、一人の青年ではなかったか……”
伸一と同じように、戸田も同様にその宿縁を感じていたのである。
今、牧口の偉業を彼と分かつ一人の青年が、四十七歳の彼の前に、出現したのである。仏法がまことであるならば、人類史上、未曽有の宗教革命を断行する人と人との間に、必ず師弟の宿縁が、存在するはずである。
法華経化城喩品第7には、「在在諸仏土常与師俱生」とある。聖教新聞の用語解説では、「在在[いたるところ]の諸仏の土に|常に師と俱に生ず」(法華経317㌻)と読み下す。最初に法を説いて下種した師匠と、下種を受けて結縁した弟子は、あらゆる仏国土にあっていつも一緒に生まれると説かれる。
この戸田と伸一の出会いは、法華経に明確に説かれているように、我々と、我々の師である池田先生とが巡り合うことは、決して偶然ではなく必然であるのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
