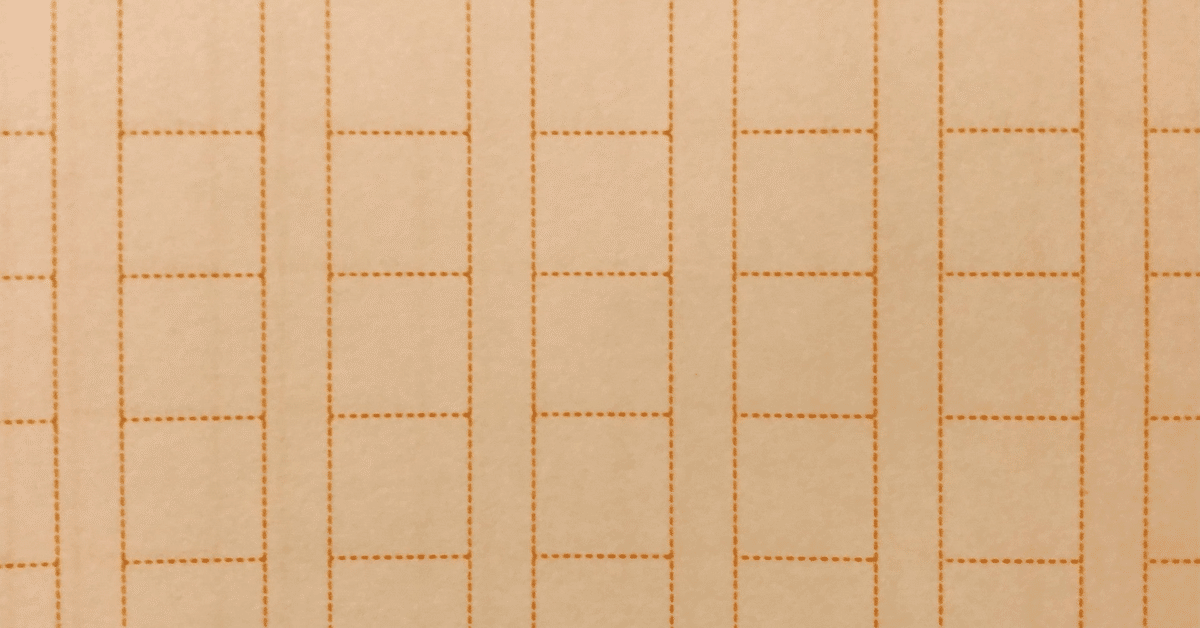
現役接客スタッフが思う、「現国」の大切さ
私は幼少期よりずっと読書が好きな方だったが、学生時代は思いのほか現国で点が取れずに苦労した。
なぜなんだろうかと思っていたが、そのものズバリ同じ疑問に、平野さんがご著書の中で応えてくださっていた。
仮に、どうも、設問者の小林秀雄の解釈が間違っているように感じたとしても、自分が正しいと思う小林秀雄の解釈を答案で書いてみたところで仕方ない。×をもらうのがオチだ。国語のテストとは、そういう性格のものではないのである。あくまで、問題制作者の理解がどういうものであるかを考える。それでは鬱憤が溜まるじゃないかと思われるかもしれないが、これも一つの訓練である。
ナルホドねー。
ほんと、鬱憤が溜まってたよ、学生時代の現国。
私が思うに、授業の現国がああもつまらない理由は上記の理由が大きい。そして、「自分が読みたいものを読みたいときに読みたいように読ませてくれない」ところにもあると思う。自由度が低すぎるんだよな。
ただ、つまらないからといって、侮ってはいけない。とても大事な授業なんだよ、現国は。社会人になってからつくづく思う。
私は、今、接客業をしている。
依然として、義務教育から社畜へ「おりからおりへはしごして 自分をとじこめている」(B'zの楽曲『Hi』の歌詞)。
なぜかこれしか選択肢がないと思い込んだ20代からこっち、40代の今も粛々と接客業で社畜人生を送っているが、社畜が義務教育と比べてまだマシなのは、一畜生として飼い主に仕えている間は、お給金の範囲内で自由意思で本を買うことができ、読むことができるという一点である。
自由というのは諸刃のつるぎ
だけど、自由というのは諸刃のつるぎ。自由に選ぶ、その前段階として、「どれだけ脳が柔らかい若い時代に良質のものを吸収できていたか」がとても大事になる。それ以降の自身の選択が、その吸収度合いに大きく左右されるからである。
私、マンガは好きだし、今や世界に誇る日本のマンガ文化をオトす意図は毛頭ない。
しかし、やはり『少年ジャンプ』(『SPY×FAMILY』新刊が超楽しみ!)や『ちゃお』ばっかりを「読書」と心得て、『こころ』・『高瀬舟』あたりを「つまんねー。読むだけ時間のムダ」って避けて育つのは良くないと思う。それでは、良質な日本語を育てる土壌が、そもそも育たないと思う。
土壌がスッカスカの状態で、社会人になるとどうなるか
接客業として言わせてもらうと、「使えない」人になる。敬語の使い方とかそういうことにとどまらない。お客様の使われている言葉や慣用句や言い回しを理解して、かつ自分から合わせていけない方は、一見のお客様はなんとかなってもリピーター獲得に至らない。そういう意味で使えないと言っている。
尚、この場合、学歴は、まったく関係ない。
言いすぎとわかって書くけど、東大出といえど、「他人のウワサ話」「著名人がああ言ったこう言った」「政治家の悪口」この3点セット「しか」喋ることがない人は、自分の中に言葉と思想の土壌がない。だからいわば根なし草のようなもの。常に「だれだれがこういった」と言っているだけで、自分の意見は?と聞くと答えられない。そういうときどうするかというと、話を逸らす。逸らしに逸らして本題が何だったか煙に巻く。腹立ただしいことに、この煙に巻くのだけ非常に上手である。わりと自分はばかで、とか思っている謙遜タイプには少なく、自分は賢いと思っている自信家タイプにこういうのが多い。これにつきあわされるほうはいい迷惑なんだが、おかまいなしである。
別にお客様より常に知的に上回る必要はない
話がそれたので、戻すと、別にお客様より常に知的に上回る必要はない。ときにはお客様よりバカである(バカの振りをする)必要もある。まったくもって腹ただしいことだが、話し手が女性で相手方が男性の場合、特にそのほうが好感度がグンバツに上がる。「そうなんですか」「知らなかったです」「教えてください」って衒いもなく聞くだけで、相手はめっちゃ喜ぶ。すごく粗い言い方すると、ちょいと昔の「Dumb Blonde」モテテクみたいなものである(フェミニストの私としては、あんなモテテク、滅びればいいと思うけど。あ、「Dumb Blonde」の意味は「アヴリル・ラヴィーン・洋楽和訳・Dumb Blonde」で検索ください)。
だけど、同じバカと言っても、言い回しがそれだと本当に致命的。外面、同じジャパニーズピーポーでも、「ちょうすてきですよね!」「あ、なんかぁおにおにおにむかつく!」みたいな表現ともいえない表現を延々されると、「この程度の日本語しか喋れないのなら、オマエ、ホモサピエンスとみせかけて、さてはサルだな」とみなされても仕方ない。(友達だったら好きにすりゃいいんですよ。対お客様としてです、あくまで)
あと、お客様のお名前でときどきとっても難しい漢字の方とかいらっしゃって、実際に書いてくれればいいのに、言葉で「へんが~で、つくりが~」と説明される場合がある。(「へん」ってなに?「つくり」ってなに?)って考えていたら、その時点で試合終了なのである。
以上、話が逸れついでに、いろいろ書いたが、言いたいのは「ある程度以上の知的レベルをお持ちのお客様」をコアな顧客としてお迎えしたい場合、それなりに自分も上げておかないといけないということだ。「類友の法則」ってやつだ(ただ、お客様は友達ではないので、そこだけは肝に銘じて毎回接客します、私は)。
結論:自由がないからこそ、現国の授業は、もんのすごくもんのすごく大切
自分の知的レベルを上げるためには基礎がなければ上げようがない。その基礎の土壌作りという意味で、現国の授業は、もんのすごくもんのすごく大切なんだ。だって、読みたくもなかった本でも、授業では先生に当てられるから、しょうがなしに読むだろう。脳みそがまだイキイキハッスルの小学生時代は、しょうがなしに読んだことでも頭に入っている。語彙も言い回しも。それが素晴らしいことだと思う。
仏教関係で多数の著作をお持ちのスマサラーナ大先生がおっしゃるには
こどもとおとなでは、時間の流れ方がそもそも違うそうである。
子どもたちの時間感覚は、大人たちのものとは異なるので、新しい環境への適応が早い。それに比べれば、高齢者になればなるほど、保守的になり、新しい環境に適応できない人の割合が増えていくのです。
なので、この若々しいローティーンと円熟味溢れるアラフィフでは、吸収速度も物事の味わい方も異なって当然なのだ。円熟味溢れる期間は、それなりに円熟した文学作品を味わうにもってこいの期間。ただそのうまみをいただくには、ローティーンのときにどれだけ日本語の素養を積んでいるかに尽きる。
以上、ああもう少しちゃんと現国の授業受けておけばよかったという自戒を込めて。
こんなにえらそげに長々書いたけど、学生時代、授業中は先生の悪口を嬉々として便箋に書いて、ちっちゃくちっちゃくして友達に回しあうことに必死のお馬鹿さんだった。便箋をいかに小さくきれいに折れるか苦心しているヒマがあったら、ちゃんときれいな声に出したい日本語を読んでおくべきだったのに。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
