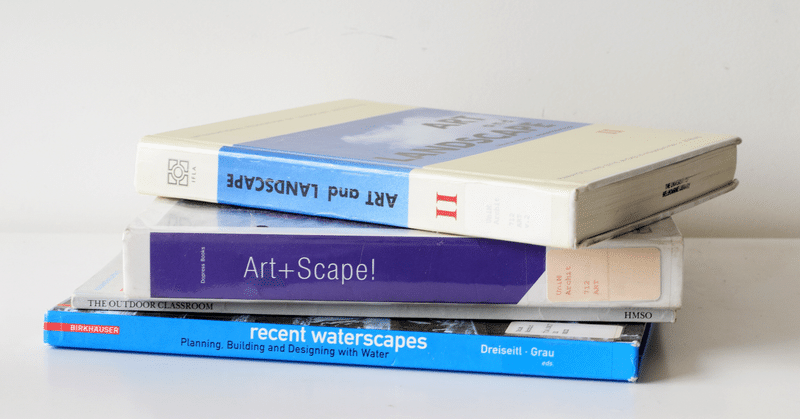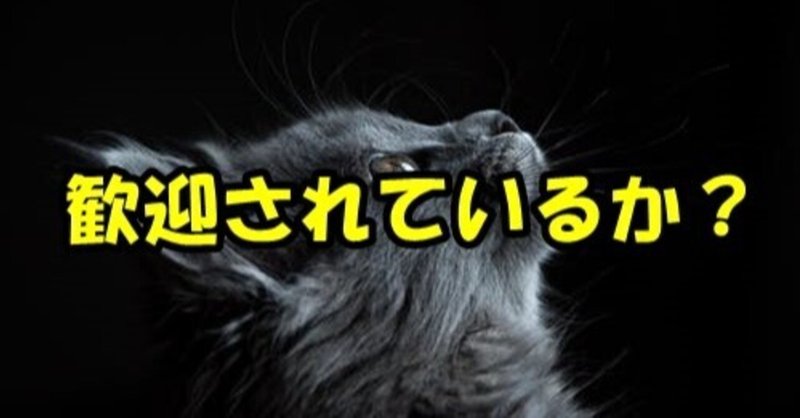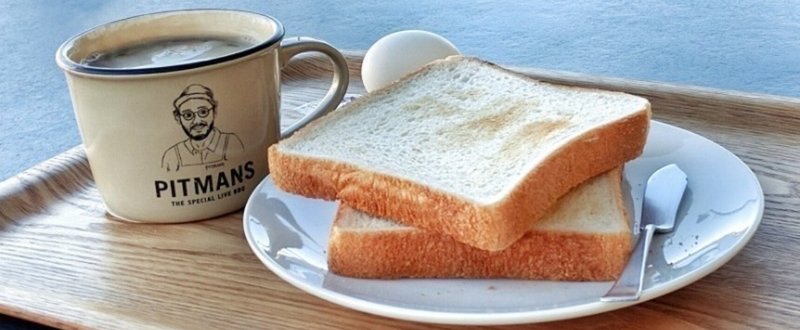#コラム

「noteって、どうやって運営していったらいいんでしょう?」 企業の担当者さんに相談されたとき私がいつも答えていること
長年noteを使い、noteのプロデューサーを務めていたこともあって、noteをはじめたい企業の担当者さんから相談を受けることが多々あります。企業側がやりたいこととnoteでできることをすり合わせた結果、「こんなにいろんな使い方ができるんですね」と驚かれることもしばしば。 特にフォロワーやスキを増やすためのノウハウではなく、これまでの公式の情報発信では拾いきれていなかった舞台裏を伝えファンとつながる場を作り上げるためのアイデアを話していると、担当の方自身の熱量が高まり「やら
¥200